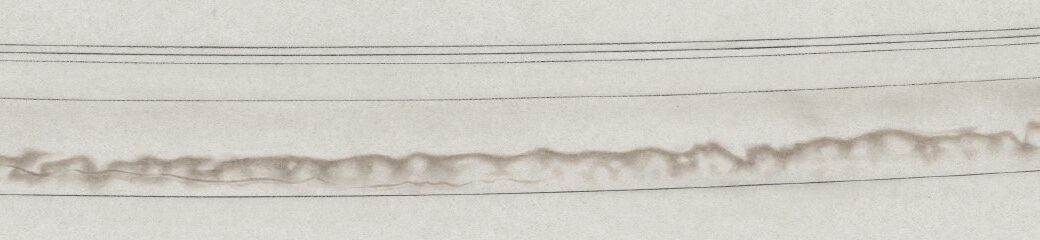
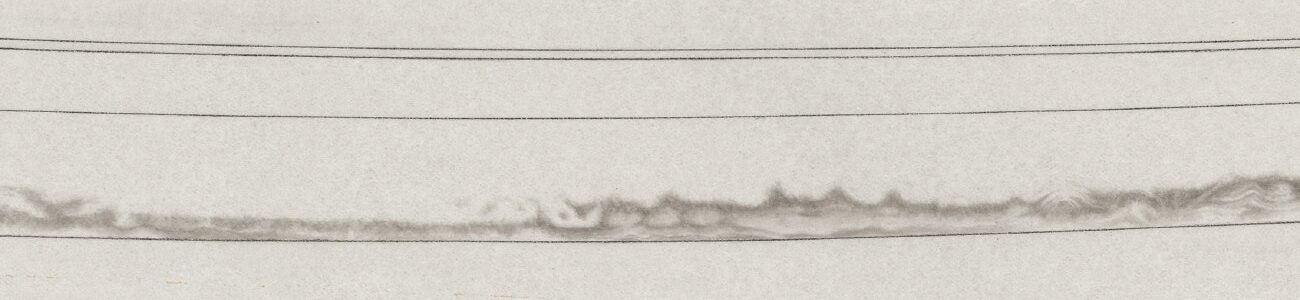
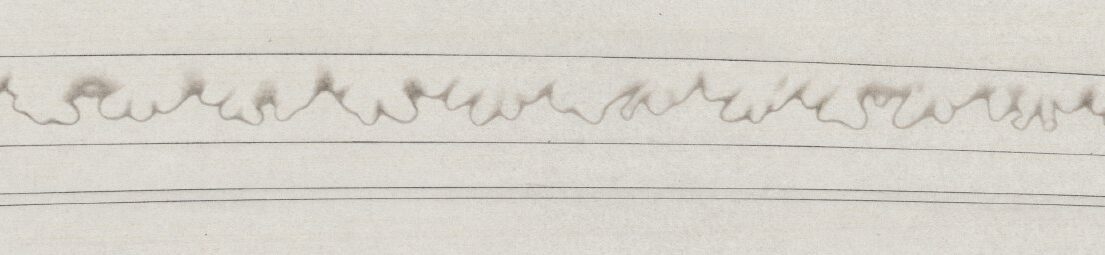
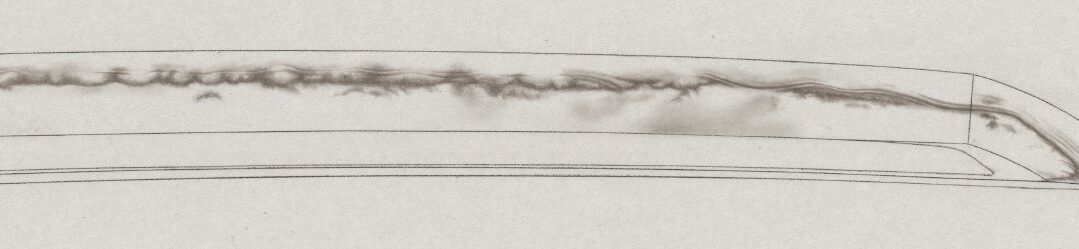
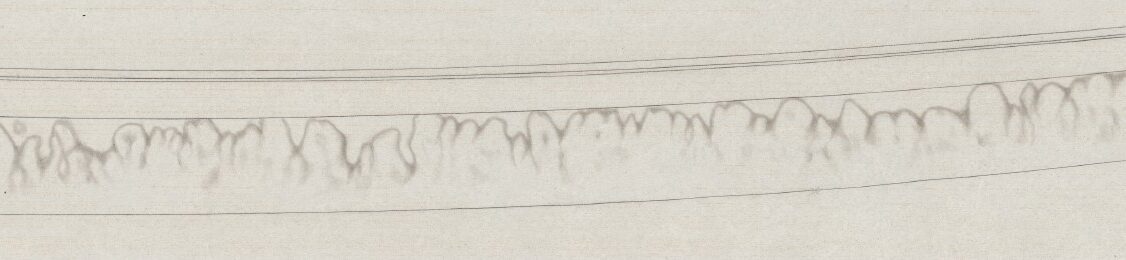
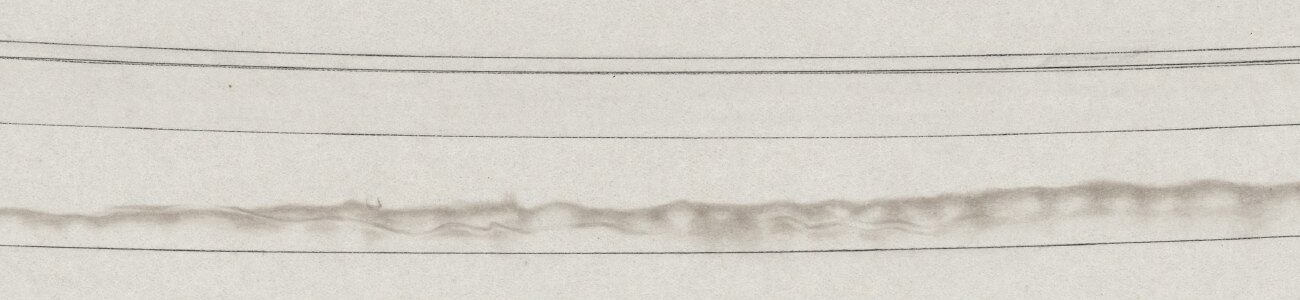
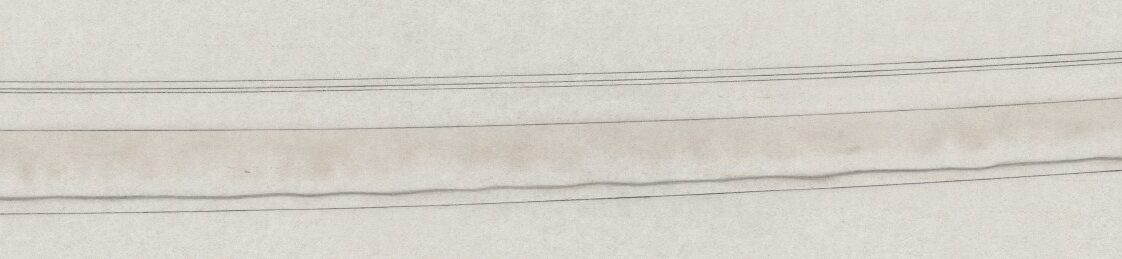
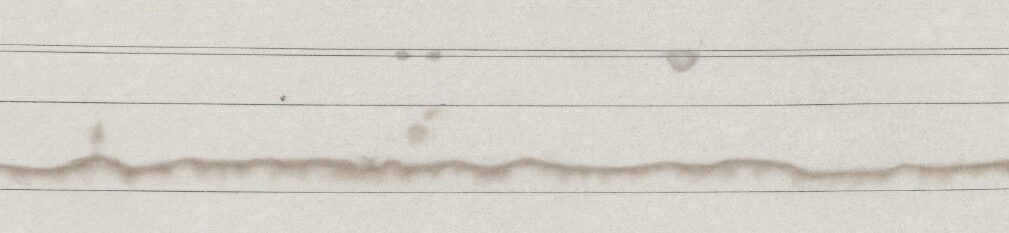
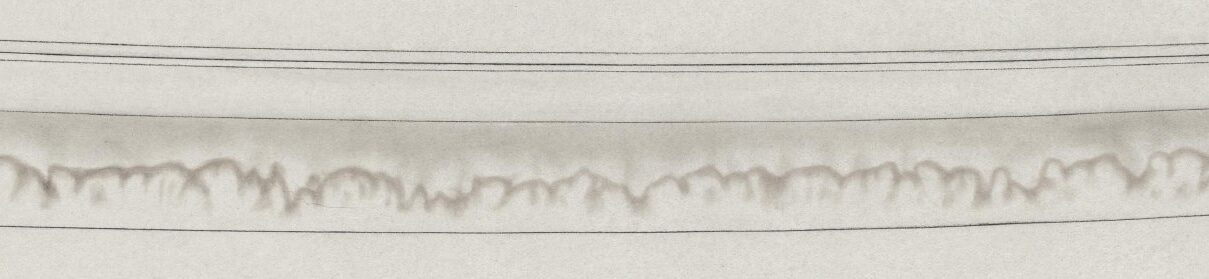
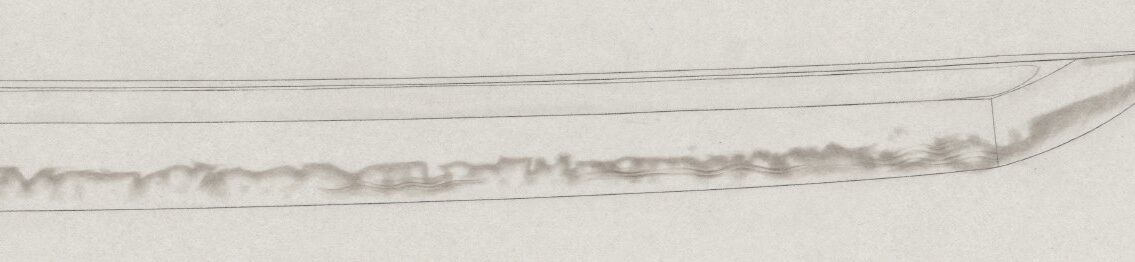
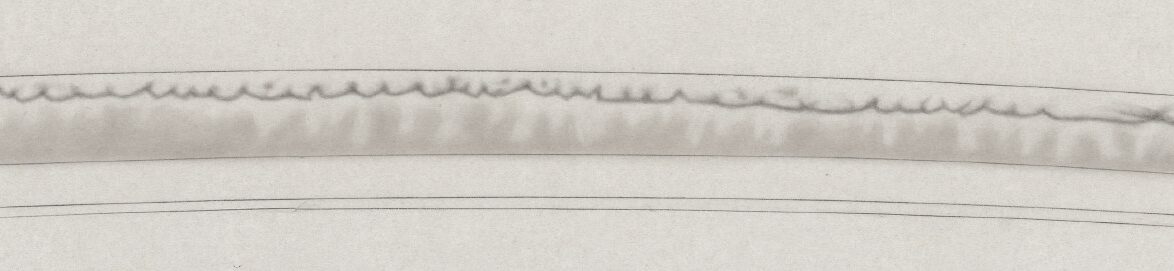
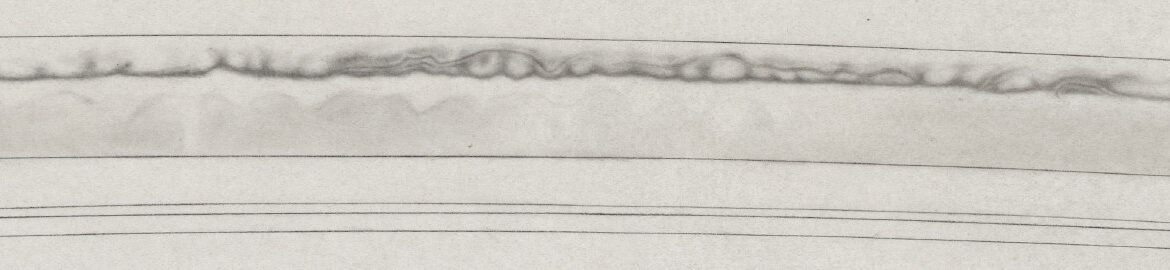
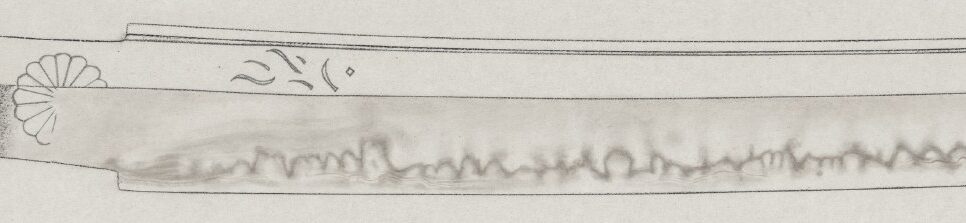
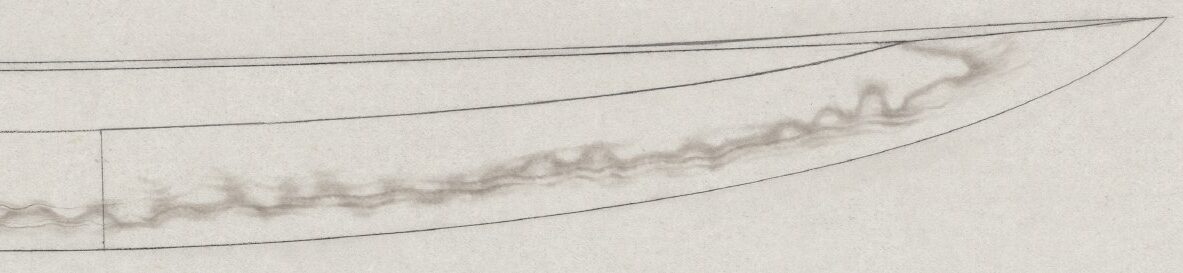
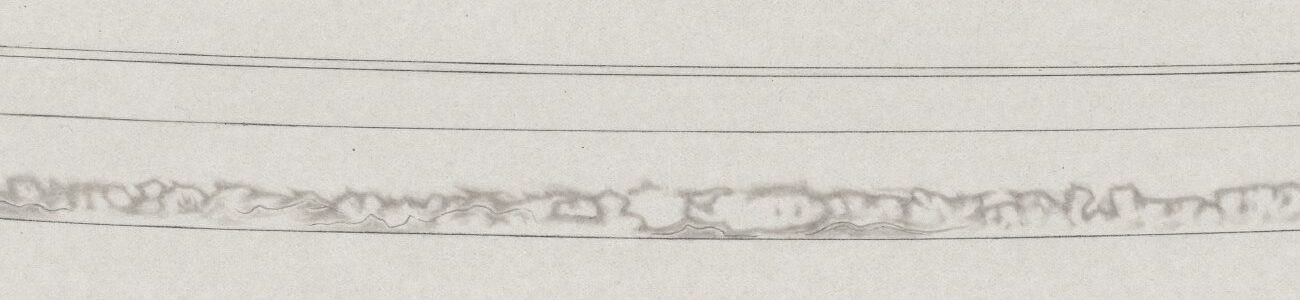
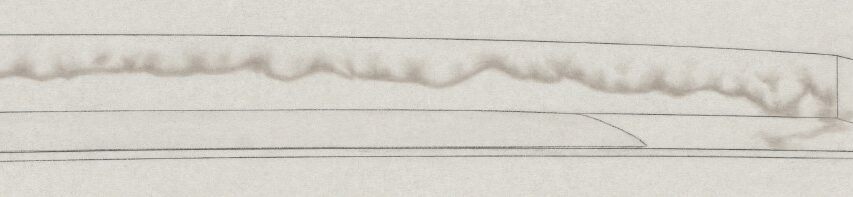
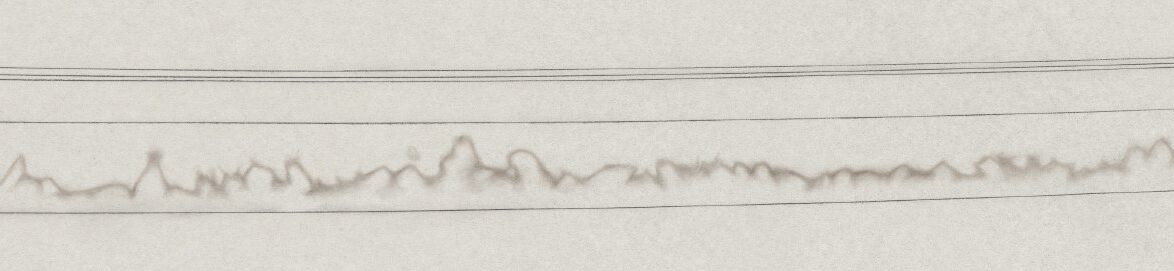

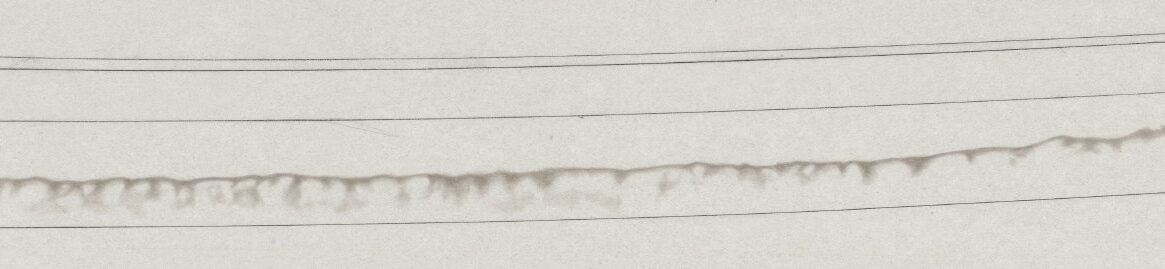
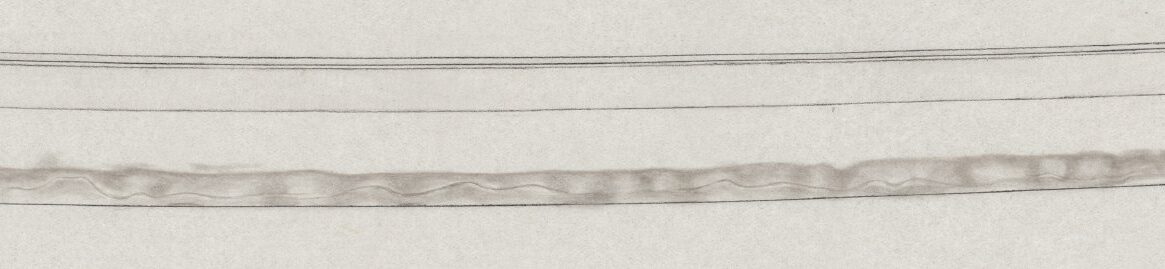
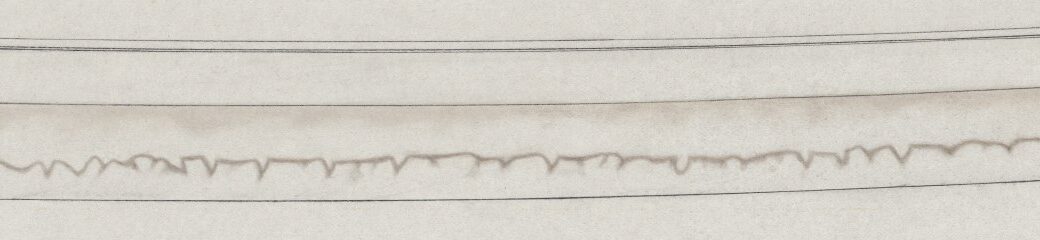
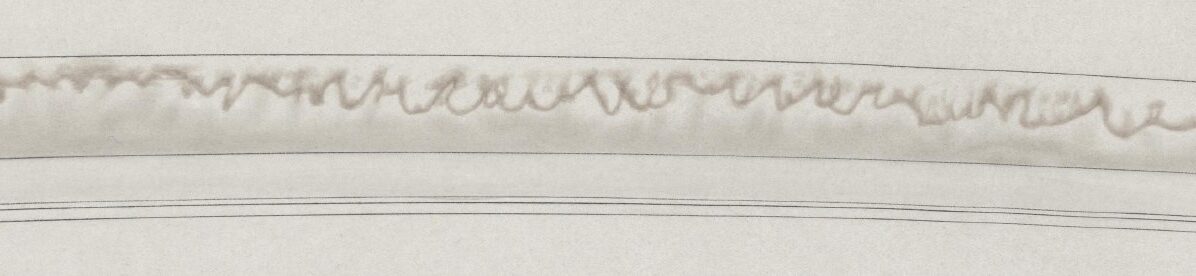
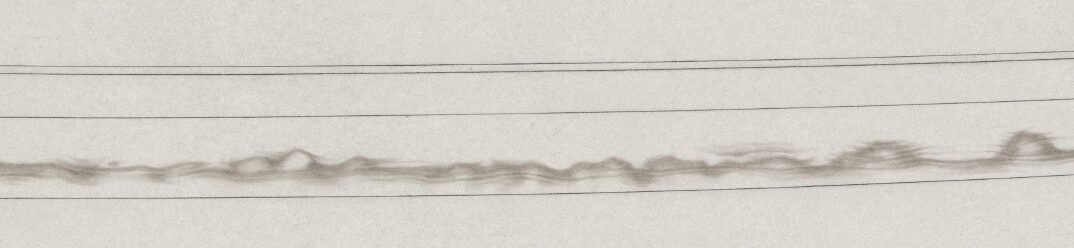
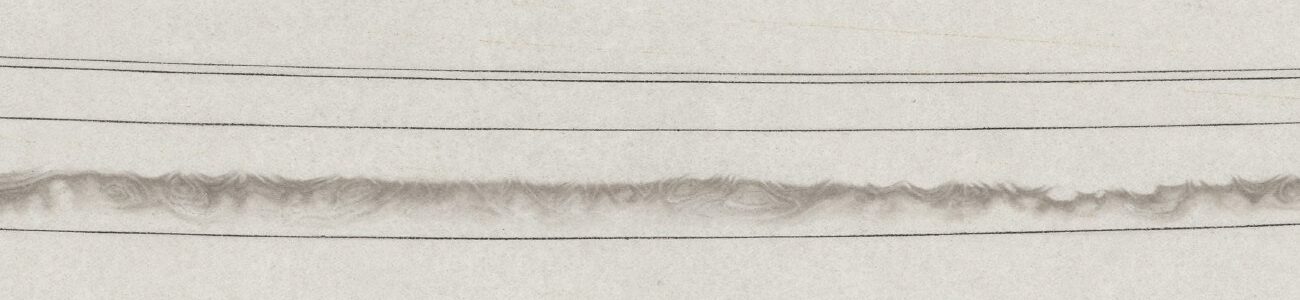
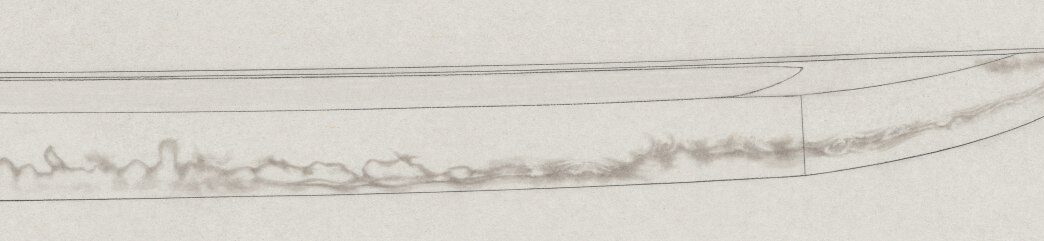
Õ£©ķŖśŃü«µØźŃéÆõ║īŃüżµÄĪµŗōŃĆéńø┤ÕłāŃü«µ¢╣ŃĆüõ╗«Ńü½Õģźµ£ŁķææÕ«ÜŃü¬ŃéēŃü░’╝æµ£Łńø«Ńü½µ¢░ĶŚżõ║öŃü«µ£ŁŃüīÕżÜŃüÅÕģźŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéŃüōŃéōŃü¬Õ£░ķēäŃü«µØźŃééµ£ēŃéŗŃéōŃü¦ŃüÖŃüŁŃüćŃĆéŃüōŃü«Õ£░ķēäŃĆüńĀöŃüÄŃüīķĀŚŃéŗõĖŖµēŗŃüäõ║ŗŃééĶ”üÕøĀŃü«õĖĆŃüżŃĆéµ╣┐µĮżŃü½µŖæŃüłŃüżŃüżÕ░ÅĶéīŃéÆÕŹüÕłåÕ╝ĢŃüŹń½ŗŃü¤ŃüøŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ¦śŃü¬ńĀöŃüÄŃéÆŃüÖ […]
NHKŃé╣ŃāÜŃéĘŃāŻŃā½Ńü¦ŃĆĵ¢░ŃéĖŃāŻŃāØŃāŗŃé║ŃāĀ ń¼¼7ķøå µÖéõ╗ŻÕŖć õĖ¢ńĢīŃéÆķŁģõ║åŃüÖŃéŗŃé┐ŃéżŃāĀŃāłŃā®ŃāÖŃā½ŃĆÅŃéÆŃü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõ╗źÕēŹŃā¢ŃāŁŃé░Ńü¦ŃüōŃéōŃü¬õ║ŗŃéƵøĖŃüäŃü¤õ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃā╗µÖéõ╗ŻÕŖćŃüŗŃéē | ńÄēńĮ«ńŠÄĶĪōÕłĆÕēŻńĀöńŻ©Õć”’Į£õ║¼ķāĮŃā╗ÕĘ”õ║¼Õī║Ńā¢ŃāŁŃé░ÕåģŃü«Ńā¬Ńā│Ńé»ÕģłŃüīÕłćŃéīŃü”ŃüäŃüŠ […]
õ╗Ŗµ£Øõ║¼ķāĮķ¦ģŃü¦ńö©õ║ŗŃüżŃüäŃü¦Ńü½ķüŗÕŗĢŃü«Ńü¤ŃéüÕż¦ķÜĵ«ĄŃéÆńÖ╗ŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ŃéēŃĆüķĘ╣ÕīĀŃüīķĘ╣’╝łÕżÜÕłåŃāÅŃā¬Ńé╣ŃāøŃā╝Ńé»’╝ēŃéÆķŻøŃü░ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé Õģ©ńäČń¤źŃéēŃüÜÕüČńäČĶ”ŗŃü¤Ńü«Ńü¦ķ®ÜŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃü¤ŃüČŃéōķ│®ŃéłŃüæŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéŃüÜŃüŻŃü©Ķ”ŗŃü”ŃüäŃü¤ŃüŗŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīµÖéķ¢ōŃééŃü¬ŃüÅŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆé Ńü©ŃüōŃéŹŃü¦ […]
µ£¼Õ╣┤ŃééŃéłŃéŹŃüŚŃüÅŃüŖķĪśŃüäŃüäŃü¤ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé Õ╣┤µ£½ŃüŗŃéēŃüÜŃüŻŃü©µŖ╝ÕĮóŃéÆŃéäŃüŻŃü”ŃüŠŃüÖŃĆéµ¢░Õ╣┤Ńü»µØźńē®ŃüŗŃéēŃĆéŃüōŃü«õ║║Ńü«ńÅŠÕŁśõĮ£Ńü»Õ░æŃü¬ŃüÅŃĆüµØ▒ÕŹÜŃé䵤ÉÕŠĪÕ««µ¦śŃü½µ«ŗŃéŗńē®Ńü»ń¤źŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõ╗¢Ńü»Ńü╗Ńü╝ńäĪŃüŚŃĆ鵜©Õ╣┤ŃĆüŃüŠŃü¤ÕłźŃü«ÕŠĪÕ««µ¦śŃü½ÕåŹÕłāŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīÕ£©ķŖśŃü«ÕōüŃüīµ«ŗŃüĢŃéīŃü” […]
ŃĆÄÕłĆÕēŻńŠÄĶĪōŃĆÅŃü½Ńü»ÕłĆÕēŻŃéäÕłĆĶŻģÕģĘńŁēŃü«ńøŚÕōüµāģÕĀ▒ŃüīµÄ▓Ķ╝ēŃüĢŃéīŃéŗõ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░µ│Ģõ║║Ķ¦ŻµĢŻŃü½õ╝┤Ńüäõ╗żÕÆī’╝ŚÕ╣┤’╝śµ£łŃü½ķż©Ńü«ķüŗÕ¢ČŃéÆńĄéõ║åŃüŚŃü¤Ķ¤╣õ╗Öµ┤×Ńü«ńøŚķøŻõ║ŗõ╗ČŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆéŃüōŃü«õ║ŗõ╗ČŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»Õ╣│µłÉ’╝ōÕ╣┤ŃĆüŃĆÄÕłĆÕēŻńŠÄĶĪōŃĆÅ’╝ö’╝æ’╝öÕÅĘŃü½õ╗źõĖŗ’╝æ’╝ÆÕÅŻŃü«ńøŚķøŻÕłĆÕēŻµāģÕĀ▒ŃüīµÄ▓ […]
Õż¦ńŻ©õĖŖŃüÆŃĆüµ£▒µøĖŃü«Õ░╗µćĖÕēćķĢĘŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆÕłČõĮ£’╝łķĆöõĖŁ’╝ēŃĆé Ńü¤ŃüŠŃü¤ŃüŠõ╗ŖµØæÕłźÕĮ╣ÕłĆÕēŻĶ¼øĶ®▒ŃéÆĶ¬ŁŃéōŃü¦ŃüäŃü”ŃĆüÕłźÕĮ╣µłÉńŠ®ŃüīÕ░╗µćĖŃü½ŃüżŃüäŃü”õ╗źõĖŗŃü«µ¦śŃü½ŃĆéŃĆÄÕēćķĢĘŃü»Õż¦ÕÆīńē®õĖŁÕ£░ķēäŃééÕ░æŃüŚŃüÅÕŖŻŃéŖŃĆüŃüŗŃüżŃü¢ŃéōŃüÉŃéŖŃü©ŃüŚŃü”Õ£░ĶŹÆŃéīŃü«ÕżÜŃüäŃééŃü«ŃüīŃéłŃüÅŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃéåŃüłŃü½õĮŹÕłŚŃéé […]
ķÄīÕĆēµ£½µ£¤õ┐صśīÕ£©ķŖśń¤ŁÕłĆ Õż¦ńŻ©õĖŖŃüÆńäĪķŖśÕłĆŃĆĆÕŹāµēŗķÖó ŃéäŃü»ŃéŖń¦üŃü»Õż¦ÕÆīńē®ŃüīÕ£¦ÕĆÆńÜäŃü½ÕźĮŃüŹŃü¬Ńü«ŃüĀŃü©ÕåŹĶ¬ŹĶŁśŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüØŃü«ńÉåńö▒Ńü«Ķ©ĆĶ¬×Õī¢Ńü»ķøŻŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéÕźĮŃü┐Ńü©Ķ©ĆŃüłŃü░ŃüØŃéīŃüŠŃü¦Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆéÕģłµŚźµ¤ÉÕłĆÕīĀŃüĢŃéōŃü½µĢÖŃüłŃü”ŃééŃéēŃüŻŃü¤ńÉåńö▒Ńü¬Ńü«ŃüŗŃééŃü©ŃĆüŃüĪŃéćŃüŻŃü©µ£¼µ░ŚŃü¦ […]
Ńé┐ŃéżŃāłŃā½Ńü½ŃüÖŃéŗŃü©Ńü¬ŃéōŃüĀŃüŗÕż¦ķó©ÕæéµĢĘķüÄŃüÄŃüŠŃüÖŃüīŃĆéŃĆéŃüĪŃéćŃüŻŃü©õ╣ģŃĆģŃü«µŖ╝ÕĮóŃü¦Õ«żńö║µÖéõ╗ŻÕ£©ķŖśÕż¦ÕÆīńē®Ńü«ÕłĆŃü«µŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōŃéÆńĄéŃüłŃĆüÕ«żńö║õĖŁµ£¤Õ£©ķŖśÕ▒▒Õ¤ÄÕłĆŃü«µÄĪµŗōŃéÆķ¢ŗÕ¦ŗŃĆé Õ£░Õ¤¤Ńé鵥üµ┤ŠŃééõĮĢŃééŃüŗŃééķüĢŃüåŃü«Ńü½ŃĆüÕģ©ÕøĮŃü¦Ńü╗Ńü╝ÕÉīµÖéŃü½ÕłĆŃü«ń®║µ░Śµä¤ŃüīÕÉīµ¢╣ÕÉæŃü½ÕżēÕī¢ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü« […]
õ╗Ŗµ£łŃü»Ķ¼øÕĖ½ÕĮōńĢ¬Ńü¦ŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüķææÕ«ÜÕłĆ’╝ĢÕÅŻŃü½ÕŖĀŃüłŃĆüķææĶ│×ÕłĆŃéÆ’╝ōÕÅŻŃü©Õ╣ŠŃüżŃüŗŃü«ÕÅéĶĆāµŖ╝ÕĮóŃéÆŃüöńö©µäÅŃüĢŃüøŃü”ŃüäŃü¤ŃüĀŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ķææÕ«ÜÕłĆ ŃĆĆ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕ«łķ插╝łńĢĀńö░’╝ēŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆķćŹĶ”üÕłĆÕēŻŃĆĆ’╝ÆÕÅĘŃĆĆĶäćµīćŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕéÖÕĘ×ķĢĘĶł╣Õģ╝ÕģēŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆķćŹĶ”üÕłĆÕēŻŃĆĆ […]
ńÅŠÕ£©ŃĆüõĖĪÕøĮŃü«ÕłĆÕēŻÕŹÜńē®ķż©Ńü½Ńü”ŃĆÄÕÅŚĶ┤łĶ©śÕ┐ĄŃĆĆÕÅŚŃüæńČÖŃüīŃéīŃéŗµŚźµ£¼ÕłĆŃĆĆŌĆĢķł┤µ£©ĶÄŖõĖĆŃé│Ńā¼Ńé»ŃéĘŃā¦Ńā│ŃéÆõĖŁÕ┐āŃü½ŌĆĢŃĆÅŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕÅŚŃüæńČÖŃüīŃéīŃéŗµŚźµ£¼ÕłĆŌĆĢķł┤µ£©ĶÄŖõĖĆŃé│Ńā¼Ńé»ŃéĘŃā¦Ńā│ŃéÆõĖŁÕ┐āŃü½ŌĆĢŃĆĆÕ▒ĢĶ”¦õ╝Ü | ÕłĆÕēŻÕŹÜńē®ķż©Õ▒Ģńż║Ńā¬Ńé╣ŃāłŃĆĆ2025ÕÅŚĶ┤łÕ▒Ģńø«ķī▓10 […]
µ£¼ĶāĮÕ»║Õż¦Õ»Čµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü¦ķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü«ŃĆīµŁ”ÕŻ½Ńü«ĶĪ©ķüōÕģĘŃü©ŃüØŃü«õŠĪÕĆżÕ▒ĢŃĆŹŃü½Õć║ķÖ│õĖŁŃü«ÕłĆŃéÆŃüöń┤╣õ╗ŗŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé’╝łĶ¬┐µøĖŃü»ŃüäŃüżŃééŃā¢ŃāŁŃé░Ńü½µøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗÕģźµ£ŁķææÕ«ÜĶ©śńÜäŃü¬ŃééŃü«Ńü¦ŃĆüĶ”ÅÕēćµĆ¦ŃüīõĮÄŃüÅĶ¬ŁŃü┐ķøŻŃüÅŃü”ŃüÖŃü┐ŃüŠŃüøŃéōŃĆé( )ÕåģŃü«µĢ░ÕĆżŃü»ŃĆüÕģāÕ╣ģŃā╗ÕģłÕ╣ģŃüīÕ║ĄķĀéńé╣Ķ©łµĖ¼ÕĆżŃĆüÕģāķćŹ […]
õ║¼ķāĮŃü«õĖŖķćÄիŵ©╣ŃüĢŃéōŃĆéńĀöŃüÄŃééÕż¦µ”éŃéäŃüæŃü®ńÖĮķŖĆŃééńøĖÕĮōŃéäŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆé(ķ¢óĶź┐Õ£Åõ╗źÕż¢Ńü«µ¢╣Ńü«Ńü¤ŃéüŃü½ĶŻ£ĶČ│ŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüŃééŃüĪŃéŹŃéōĶē»ŃüäµäÅÕæ│Ńü¦µøĖŃüäŃü”ŃüŠŃüÖ) µēŗõ╗Ģõ║ŗŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃĆüÕłźŃü«ÕłåķćÄŃü¦Ńééńē®ŃéÆĶ”ŗŃéīŃü░ŃüØŃü«ÕćäŃüĢŃü»ŃüéŃéŗń©ŗÕ║”ÕłåŃüŗŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüõĖ¢Ńü«õĖŁŃüØŃüåŃüäŃüåŃü«Ńüī […]
’╝æ’╝ÉÕ╣┤µī»ŃéŖŃü½µ│ĢķÜåÕ»║ŃĆé ķćæÕĀéŃü½ÕłØŃéüŃü”ÕģźŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµ¦ŹķēŗŃü«ĶĘĪŃüīńŠÄŃüŚŃüäõĖƵ×ܵØ┐Ńü«ÕĘ©Õż¦Ńü¬µēēŃüīÕżÜµĢ░ŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕĮōÕłØŃü«µēēŃü»µśŁÕÆīŃü«ńü½ńüĮŃü¦ńä╝Õż▒ŃĆüõ╗ŖŃü«ŃééŃü«Ńü»ŃüØŃü«ÕŠīŃü«õ┐«ńÉåŃü¦Ńü«ÕŠ®ÕģāŃüĀŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«Õż¦ŃüŹŃüĢŃü«µØ┐Ńü»ÕøĮÕåģńöŻŃü¦Ńü»ńäĪńÉåŃüĀŃéŹŃüåŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ŃéēŃĆü […]
SNSŃü¦Ķ”ŗŃüŗŃüæŃĆüŃüŖÕ║ŚŃü½ķø╗Ķ®▒ŃüŚŃü”ŃüŠŃüĀµ£ēŃéŗõ║ŗŃéÆńó║Ķ¬ŹŃĆüµ¢░Õ╣╣ńĘÜŃü½ķŻøŃü│õ╣ŚŃüŻŃü”ŃĆüń¤ŁÕłĆŃéÆĶ▓ĘŃüŻŃü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕłĆÕ▒ŗŃüĢŃéōŃü¦ń¤ŁÕłĆŃéÆĶ▓ĘŃüŻŃü¤Ńü«Ńü»ÕłØŃéüŃü”Ńü¦ŃüÖŃĆéÕÉłÕÅŻµŗĄõ╗śŃüŹŃü«Õ░ÅŃüĢŃü¬ń¤ŁÕłĆŃĆéĶŻĮõĮ£ÕĮōÕłØŃéłŃéŖķćŹŃüŁŃü»õĮĢŃā¤Ńā¬µĖøŃüŻŃü”ŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃüŗŃü¬ŃéŖµĖøŃüŻŃü”ŃüäŃü”ŃĆüńø┤ŃüÉ […]
õ╗ŖÕ╣┤Ńü«ń¦ŗŃü«µö»ķā©µŚģĶĪīŃü»µ×ŚÕĤńŠÄĶĪōķż©Ńā╗Õ▓ĪÕ▒▒Õ¤ÄŃā╗Õ▓ĪÕ▒▒ń£īń½ŗÕŹÜńē®ķż©Ńü«’╝ōķż©ķĆŻµÉ║Õ▒Ģńż║ŃĆīķø▓Ńü«µŚģŃĆŹŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéŌĆØķø▓Ńü«µŚģŌĆØŃüŻŃü”ń┤ĀµĢĄŃü¬ŃāŹŃā╝Ńā¤Ńā│Ńé░Ńü¦ŃüÖŃĆéķø▓µ¼ĪŃü»ńĀöńŻ©ŃéäµŗØĶ”ŗŃü«µ®¤õ╝ÜŃééÕ║”ŃĆģŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüķø▓ńö¤Ńü»Õ░æŃü¬ŃüÅŃĆüķø▓ķćŹŃü»µēŗŃü½ÕÅ¢ŃüŻŃü¤õ║ŗŃééŃü¬ŃüäńäĪŃüäŃüŗŃééŃüŚŃéīŃüŠŃüøŃéōŃĆé […]
Õć║ÕģłŃü½Ńü”Õ«żńö║ÕēŹµ£¤Ńü«Õż¦ÕÆīŃü«Õ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃü©Õć║ķĆóŃüåŃĆéõ╗źÕēŹķĢĘŃüäńē®Ńü¦ŃüōŃü«ķŖśŃéÆĶ”ŗŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃééŃüŚŃüŗŃüŚŃü”õĖ¢Ńü½ŃüōŃéī’╝æŃüżŃüŚŃüŗńäĪŃüäŃüŗŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ŃüīŃĆüĶ¬┐Ńü╣ŃéŗŃü©ŃééŃüå’╝æÕÅŻÕ£©Ńéŗõ║ŗŃüīÕłżµśÄŃĆéŃüØŃéīŃüīõ╗ŖÕø×Ńü«ń¤ŁÕłĆŃĆéõ┐ØÕŁśŃā╗ńē╣õ┐ØĶ│ćµ¢ÖŃüīń░ĪÕŹśŃü½ķ¢▓Ķ”¦Õć║µØźŃéŗÕĀ┤µēĆŃüīŃüéŃéīŃü░ŃĆüŃééŃüåŃüØ […]
ŃĆīŃüäŃüäÕŹŚń┤Ć’╝łķćŹÕøĮ’╝ēŃüéŃéŗŃéłŃĆüĶ”ŗŃü½ŃüŖŃüäŃü¦’Į×ŃĆŹŃü©ŃüŖÕŻ░ŃüīŃüæŃüäŃü¤ŃüĀŃüŹŃĆüń┤ĆÕĘ×ŃüĖŃĆéķלŃéƵēĢŃüåŃü©ŃĆüÕłĆĶ║½ĶĪ©ķØóŃü«ń©ŗŃéłŃüäńĪ¼Õ║”Ńü©ńÜäńó║Ńü¬ńĀöńŻ©Ńüīńö¤Ńü┐Õć║ŃüÖŃĆüÕÉŹÕōüńē╣µ£ēŃü«ÕģēÕĮ®Ńüīńø«Ńü½µśĀŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«Ķ╝ØŃéŖµ¢╣Ńü»µĮżŃüäŃü©ŃééŃü®ŃüōŃüŗńĢ░Ńü¬ŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃĆüķÄīÕĆēµ£¤Ńü«ÕłĆŃéÆÕɽŃéüŃü”ŃééµĢ░Õ╣┤Ńü½ […]
ŃüŠŃü¤õĮĢÕÅŻŃüŗÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµ¢░ŃĆģÕłĆŃéƵ╗ģÕżÜŃü½Ńü©ŃéēŃü¬ŃüäŃü«Ńü¦õ╣ģŃĆģŃü½ŃĆé ķØÆķŠŹĶ╗Æńøøõ┐ŖŃü«ŃüŖŃüØŃéēŃüÅķĆĀŃĆéķüÄÕÄ╗Ńü½ŃüŖŃüØŃéēŃüÅķĆĀŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü»µĖģķ║┐Ńü©Õ«ŚµśīĶ”¬ŃüĢŃéōŃüŚŃüŗµÄĪµŗōŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ŃüŗŃééń¤źŃéīŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüŖŃüØŃéēŃüÅķĆĀŃü©ŃüäŃüŻŃü”ŃééÕ«¤Ńü»Õ¦┐Ńü»µ¦śŃĆģŃü¦ŃüÖŃüī […]
µŁŻÕĆēķÖóŃü«ĶŖ▒ķ╣┐ŃüīŃü¬ŃéōŃü©ŃééµäøŃéēŃüŚŃüäŃāĢŃé®Ńā½ŃāĀŃü¦Õż¦ÕźĮŃüŹŃü¦ŃĆüŃü«Ńéōµ░ŚŃü½ĶŖ▒ķ╣┐Ńü«õ║ŗŃéÆĶĆāŃüłŃü”ŃĆéŃĆéÕ«ČŃü«ÕēŹŃü«Õ▒▒Ńü½Ńü»ķ╣┐ŃüīŃéłŃüÅµØźŃü”ń¼╣Ńü¬Ńü®ŃéÆķŻ¤Ńü╣Ńü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüĶŖ▒ķ╣┐ŃüīõĮÅŃéōŃü¦Ńü¤ŃéēŃüäŃüäŃü«Ńü½ŃĆéõ╗źÕēŹŃü»ńī┐Ńü«ńŠżŃéīŃüīÕ║”ŃĆģµØźŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤Ńüīµś©Õ╣┤Ńü»’╝æÕ║”ŃüĀŃüæŃĆéŃéŁŃāäŃāŹŃü»’╝ÆÕ║”Ńü╗Ńü® […]
ń┤ģĶæēŃü«ÕŁŻń»ĆŃü¦ŃüÖŃĆéÕżÜµŁ”Õ│░Ńü«Ķ½ćÕ▒▒ńź×ńżŠŃüĢŃéōŃü¦ķ揵¢ćÕÉēÕ╣│Ńü«Õ░ÅÕż¬ÕłĆŃüīÕ▒Ģńż║ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ŃĆÉÕģ¼Õ╝ÅŃĆæĶ½ćÕ▒▒ńź×ńżŠ’Į£Õż¦ÕÆīÕżÜµŁ”Õ│░ķÄ«Õ║¦
’╝æÕÅĘŃĆĆÕłĆÕÅŹŃéŖµĄģŃüÅõĖŁķŗÆŃĆüńŗ¼ńē╣Ńü«ĶéīÕÉłŃüäŃĆüõĮÄŃüäµ╣ŠŃéīŃü½õ║ÆŃü«ńø«ŃéÆõ║żŃüłŃĆüńē®µēōõ╗śĶ┐æńä╝ŃüŹõĖŖŃüīŃéŗŃĆéÕĮ½ŃüéŃéŖŃĆé ’╝ÆÕÅĘŃĆĆĶ¢ÖÕłĆŃüōŃü«ÕøĮńŗ¼ńē╣Ńü«ĶéīÕÉłŃüäŃü½ÕīéŃüäÕÅŻńĘĀŃüŠŃéŗńø┤ÕłāŃĆüÕĮ½ńē®ŃĆé ’╝ōÕÅĘŃĆĆĶäćÕĘ«ńēćÕłćÕłāķĆĀŃĆéĶ║½Õ╣ģÕ║āŃüÅÕÅŹŃéŖÕ╝ĘŃüäŃĆéĶ®░ŃéĆÕ£░ķēäŃĆüµ╣ŠŃéīõ║ÆŃü«ńø«ŃĆé ’╝öÕÅĘŃĆĆń¤ŁÕłĆķćŹ […]
11µ£ł’╝æ’╝Ģ’Į×’╝æ’╝śµŚźŃüŠŃü¦ŃĆüµĖēµłÉÕ£ÆŃü½Ńü”ŃĆīÕĘź’╝ŗĶŚØŃĆŹõ║¼ķāĮ2025Ńüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé µØ▒õ║¼ńŠÄĶĪōÕĆȵźĮķā©Ńü»µŚźµ£¼Ńü«õ╝ØńĄ▒ŃĆüķó©Õ£¤ŃĆüńŠÄµäÅĶŁśŃü½µĀ╣ÕĘ«ŃüŚŃü”ńČÖµē┐ŃüĢŃéīŃĆüŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬ĶĪ©ńÅŠŃü©µīæµł”ŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕĘźĶŖĖŃü½ńä”ńé╣ŃéÆŃüéŃü”ŃĆü2024Õ╣┤ŃéłŃéŖŃĆīŃé©’╝ŗĶŚØŃĆŹKO+GE […]
µÖéõ╗ŻŃü»ķÄīÕĆēµ£½µ£¤ķĀāŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆüÕÅżŃüäÕż¦ÕÆīńē®Ńü«Õģ©Ķ║½Ńü»ŃüĪŃéćŃüŻŃü©õ╣ģŃĆģŃĆéŃüōŃü«µÖéõ╗ŻŃü«Õż¦ÕÆīńē®Ńü«µŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōŃü»µźĮŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃü«ÕłĆŃĆüõĖĪŃāüŃā¬Ńü«µŻÆµ©ŗŃü½µĘ╗µ©ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃüōŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕłāŃĆüµĘ╗Ńüłµ©ŗŃü«Ķ¦Æ’╝Ƶ£¼ŃĆüķļńŁŗŃĆüµŻÆµ©ŗŃü«Ķ¦Æ’╝Ƶ£¼ŃĆüµŻ¤Ķ¦ÆŃĆüÕ║ĄŃü©ŃĆüÕāģŃüŗ’╝ōcmÕ╣ģŃü«Õż¢ÕĮó […]
’╝ōÕ░║’╝¢ÕłåŃü«µ¢░õĮ£Ńü«ÕēŻŃü«ÕåģµøćŃéŖŃĆéõĖŗÕ£░ÕŠīŃüŗŃü¬ŃéŖµ£¤ķ¢ōŃüīń®║ŃüŹŃĆüŃüØŃü«Ķŗ”ÕŖ┤Ńü»Ńü╗Ńü╝Ķ©śµåČŃü½Ńü¬ŃüÅŃĆéŃĆéĶ”ÜŃüłŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃü«Ńü»µÖéķ¢ōŃü«ŃüøŃüäŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüĶŗ”ÕŖ┤Ńü»Ķ©śµåČŃü½µ«ŗŃéēŃüÜŃü¤ŃüĀńĄīķ©ōŃü©ŃüŚŃü”Ķ║½õĮōŃü½Õł╗ŃüŠŃéīŃéŗŃüĀŃüæŃü©ŃüäŃüåńĀöÕĖ½Ńü©ŃüŚŃü”Ńü»Õż¦ÕżēķāĮÕÉłŃü«Ķē»ŃüäõĮōĶ│¬Ńü«ŃüŖŃüŗŃüÆŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü« […]
µŖ╝ÕĮóŃü«Ńé╣ŃéŁŃāŻŃā│Ńü½õĮ┐ŃüŻŃü”ŃüäŃü¤A3Ńé╣ŃéŁŃāŻŃāŖŃā╝Ńü«ÕģĘÕÉłŃüīµé¬ŃüÅŃĆéÕÅ¢ŃéŖĶŠ╝ŃéōŃüĀńö╗ÕāÅŃü«õĖĪŃéĄŃéżŃāēŃü«Ķē▓ŃüīµÜŚŃüÅŃü¬ŃéŖŃĆüÕłåÕē▓ńö╗ÕāÅŃüīń╣ŗŃüīŃéēŃüÜĶē▓Ķ¬┐µĢ┤Ńü½µÄøŃüŗŃéŗµÖéķ¢ōŃüīķģĘŃüäŃĆéŃāĢŃé®ŃāłŃéĘŃā¦Ńé╣ŃéŁŃā½Ńüīķ½śŃüæŃéīŃü░ŃüōŃéōŃü¬õĮ£µźŁŃü»ń░ĪÕŹśŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüīŃĆéŃĆéµ£¼ĶāĮÕ»║Õ«Øńē®ķż©Ńü½Õ▒Ģńż║õĖŁŃü« […]
µ£ĆĶ┐æµÄĪµŗōŃüŚŃü¤Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃĆüÕ▒▒Õ¤Äńē®ńö¤ŃüČÕ£©ķŖśķÄīÕĆēõĖŁµ£¤Õż¬ÕłĆŃĆüÕ▒▒Õ¤Äńē®ķÄīÕĆēµ£½µ£¤Õ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃĆüĶČŖõĖŁńē®ńäĪķŖśÕłĆ’╝łķćæĶ▒ĪÕĄī’╝ēŃĆüĶČŖõĖŁńē®Õ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃĆüÕÅżÕéÖÕēŹµŖśĶ┐öķŖśÕż¬ÕłĆŃĆüńäĪķŖśķØƵ▒¤ŃĆüÕ╣┤ń┤ĆÕģźÕĆ½ÕģēŃĆüµ£½µēŗµÄ╗Õ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃĆüµ¢░ÕłĆńä╝ŃüæĶ║½Ńü«ńĀöŃüÄĶ║½ŃĆüÕÉēÕ▓ĪõĖƵ¢ćÕŁŚÕłĆŃĆé’╝łķ揵¢ć’╝ō’╝īķćŹńŠÄ’╝æ […]
ŃüŚŃü░ŃéēŃüÅÕēŹŃü½ÕÅżńĀöŃüÄŃü¦ķīåŃüīÕÉäµēĆŃü½ńÖ║ńö¤ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕłĆŃéÆ’╝ÆÕÅŻŃĆüÕż¬ÕłĆ’╝æÕÅŻŃéÆńĀöŃüīŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé’╝łÕ«żńö║µ£½µ£¤ŃĆüÕ«żńö║õĖŁµ£¤ŃĆüķÄīÕĆēµ£½µ£¤’╝ēŃüØŃü«ńĀöŃüÄŃüīń¦üŃü«Õż¦ÕĖ½ÕīĀŃü¦µ░ĖÕ▒▒ńĀöõ┐«µēĆÕć║Ķ║½Ńü«ÕåģÕ▒▒õĖĆÕż½Õģłńö¤Ńü«ńĀöŃüÄŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤õ║ŗŃüīÕłżµśÄŃĆéÕåģÕ▒▒Õģłńö¤Ńü»ÕźłĶē»ń£īŃü«ńäĪÕĮóµ¢ćÕī¢Ķ▓Īõ┐صīü […]
õ║ÆŃü«ńø«Ńü«ńÅŠõ╗ŻÕłĆŃü©õĖŁµ▓│ÕåģŃéÆÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐ńĀöŃüÄŃü¦õ╗ĢõĖŖŃüÆŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃü®ŃüĪŃéēŃééŃüŗŃü¬ŃéŖńĪ¼ŃüäÕłĆŃĆéńÅŠõ╗ŻÕłĆŃü«µ¢╣Ńü»ÕłāŃü½ÕåģµøćŃéŖŃüīÕŖ╣ŃüŹŃüźŃéēŃüäŃĆéõĖŁµ▓│ÕåģŃü«µ¢╣Ńü»ŃüŠŃü¤ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ķüĢŃüåĶ│¬Ńü¦ŃüÖŃüīńĪ¼ŃüĢŃü»ÕÉīńŁēŃĆéń¦üŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃüōŃüåŃüäŃüåńĪ¼ŃüäÕłĆŃü«µ¢╣ŃüīÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐Ńü»õĖŖµēŗŃüÅõ╗ĢõĖŖŃüīŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüØŃü«ÕŠīŃüĢŃéēŃü½’╝ō’╝ÉõĖüŃĆüŃüĢŃéēŃü½’╝Ģ’╝ÉõĖüŃü╗Ńü®Ķ®”ŃüŚŃéÆŃĆéńĄÉÕ▒Ćńø«ÕĮōŃü”Ńü«ńĀöŃüÄÕæ│Ńü«ń¤│Ńü»Ķ”ŗŃüżŃüŗŃéēŃüÜńĄéŃéÅŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüøŃüŻŃüŗŃüÅŃü¬Ńü«Ńü¦ŃééŃüåõĮĢÕŹüÕ╣┤Ńééµ░ŚŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗń┤░ÕÉŹÕĆēŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃééŃĆé’╝Æ’╝Éõ╗ŻŃü«ķĀāŃü»õĖŁÕÉŹÕĆēŃü©ń┤░ÕÉŹÕĆēŃü»Õż®ńäČŃéÆõĮ┐ńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüäŃüżķĀāŃüŗŃéēŃüŗõ║║ […]
ń¦üŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃü¦ŃüÖŃüīÕłĆķ¢óķĆŻµøĖń▒ŹŃü¦õĖĆńĢ¬ŃéłŃüÅõĮ┐ŃüåŃü«Ńü»ŃĆüķćŹÕłĆŃā╗ńē╣ķćŹÕø│ĶŁ£ŃĆüÕłĆÕēŻńŠÄĶĪōŃĆüŃüØŃüŚŃü”µŚźµ£¼ÕłĆķŖśķææŃü¦ŃüÖŃĆéķćŹÕłĆÕø│ĶŁ£ŃéäÕłĆńŠÄŃü»õĮĢŃüŗŃü«Ķ¬┐Ńü╣ńē®Ńü¦Ńü▓Ńü¤ŃüÖŃéēµÄóŃüŚŃü”ŃéČŃā╝ŃāāŃü©Ķ”ŗŃéŗŃüĀŃüæŃü«õ║ŗŃüīÕżÜŃüäŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüķŖśķææŃü»ķ¢ŗŃüÅŃü©µÖéķ¢ōŃéÆÕ┐śŃéīŃüĪŃéāŃüäŃüŠŃüÖŃüŁŃĆ鵌źµ£¼ÕłĆķŖśķææ | […]
ÕĆēÕ║½ŃüŗŃéēµīüŃüŻŃü”µØźŃü¤ŃüØŃéīŃéēŃüŚŃüäń¤│Ńü»Õģ©ķā©ŃüĀŃéüŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗ŖÕø×Ńü»µŻÜŃü«ŃééÕɽŃéü’╝¢’╝ÉõĖüŃü╗Ńü®Ķ®”ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīÕģ©ķā©ķüĢŃüåŃĆé ŃüØŃéŖŃéāŃüØŃüåŃü¬ŃéōŃü¦ŃüÖŃĆéĶ”ŗŃü¤ńø«ŃééÕ╝ĢŃüŹÕæ│ŃééŃĆüŃüÜŃüŻŃü©ķü┐ŃüæŃü”µØźŃü¤ń¤│ŃéƵÄóŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃéÅŃüæŃü¬Ńü«Ńü¦ŃĆéÕģāŃĆģŃü¬ŃéōŃü¦ŃééõĮ┐ŃüŻŃü”Ńü┐ŃéŗŃé┐ŃéżŃāŚŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüķś┐ķā© […]
ŃüĪŃéćŃüŻŃü©õ╣ģŃĆģŃü½ÕĆēÕ║½ŃéÆŃé¼ŃéĄŃé¼ŃéĄŃĆéŃüöĶ┐æµēĆŃüĢŃéōŃü«Õż¦ķ¢ĆńĀöÕĖ½Ńü½µĢÖŃüłŃü”ŃééŃéēŃüŻŃü¤ńĀźń¤│ŃüīńäĪŃüäŃüŗµÄóŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé ’╝ÖÕē▓õ╗źõĖŖŃüīµśöĶ▓ĘŃüŻŃü¤ńē®Ńü¦ŃüÖŃüīĶ┐æÕ╣┤Ńü«ń¤│Ńéé’╝ōŃĆü’╝ö’╝ÉŃéŁŃāŁń©ŗÕ║”ŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüØŃéīŃüŻŃüĮŃüäńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ¦śŃü½Ķ®”ŃüÖŃü«Ńü»õ╣ģŃĆģŃĆéŃüōŃéōŃü¬Õł║µ┐ĆŃéÆŃééŃéē […]
µ£¼ķā©ŃüŗŃéēŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆ’╝łÕłĆ’╝¤’╝ēÕ░æŃüŚń┤░Ķ║½ŃĆéÕ░æŃüŚÕÅŹŃéŗŃĆ鵯¤Õģł’╝ÆÕ»ĖŃü╗Ńü╝ńø┤ńĘÜŃĆüÕģł’╝æÕ»ĖµŻ¤Ķ¦ÆÕāģŃüŗŃü½ÕåģŃĆéÕż¦Õż¦µØ┐ńø«ŃĆéķīĄŃüīÕ╝ĘŃüäńø┤ŃüÉĶ¬┐Ńü«ÕłāŃü¦Õż¦µØ┐ńø«ŃüīÕłāŃü½ÕģźŃéŖÕłāĶéīŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüķīĄńŁŗńŁēĶżćķøæŃü½ÕāŹŃüÅŃĆéĶģ░ŃéÆŃüŗŃü¬ŃéŖķĢĘŃéüŃü½ńä╝ŃüŹĶÉĮŃü©ŃüÖŃééńå▒Ńü½ŃéłŃéŗÕŠīÕż®ńÜäŃü¬ńē®Ńü½Ķ”ŗŃüłŃéŗŃĆé […]
Õż£ķüģŃüÅŃü½õĖĆÕ║”ŃüŚŃüŗõĖŖµśĀŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüµĄüń¤│Ńü½ĶĪīŃüŗŃü¬ŃüäŃü©ŃĆéIMAXŃüīÕćäŃüäŃü©Ńü«õ║ŗŃü¦ńó║ŃüŗŃü½ŃüØŃüåŃü¬ŃéōŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüµłæŃĆģõĖ¢õ╗ŻŃü«ńö░ĶłÄõ║║Ńü»ŃāćŃé½ŃüäŃé╣ŃāöŃā╝Ńé½Ńā╝Ńü«ķ¤│Õ£¦ŃéƵä¤ŃüśŃü”Ķé▓ŃüŻŃü”ŃüäŃü”ŃĆüŃéżŃāżŃāøŃā│õĖ¢õ╗ŻŃü«õ║║Ńü©Ńü»ķüĢŃüåµä¤µā│ŃüŗŃééŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃééÕćäŃüäŃü¦ŃüÖIMAX […]
Õ£©ķŖśŃü«µ£½µēŗµÄ╗ń¤ŁÕłĆŃü©ÕéÖÕēŹĶ▓×µ▓╗Õ╣┤ń┤ĆÕ»ĖÕ╗ČŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆéõ╗źõĖŗµ£½µēŗµÄ╗Ńü«ń░ĪÕŹśŃü¬Ķ¬┐µøĖŃĆé ÕłāķĢĘ27.1ŃÄØÕåģÕÅŹŃéŖÕģāÕ╣ģ20.9(22.4)mmÕģāķćŹ6.3mmĶīĵ£ĆÕÄÜ7.0mm Õ╣│ķĆĀŃéŖŃĆüõĖēŃā䵯¤(õĖŁńŁŗń┤░Ńüä)ŃĆéÕ»ĖŃü«Õē▓Ńü½Ķ║½Õ╣ģńŗŁŃüÅŃĆüķćŹŃüŁÕÄÜŃüÅŃĆüÕģ©õĮōŃü½ […]
µ£¼µŚźŃü»Õć║ÕģłŃü½Ńü”ńøĖõ╝ص¤Éõ║½õ┐ØÕÉŹńē®Ńü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕć║ÕģłŃü¦Ńü«µÄĪµŗōŃü»Õż▒µĢŚŃüīĶ©▒ŃüĢŃéīŃüÜŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüõĖćõĖĆŃü½ÕéÖŃüłń┤ÖŃü»õĮĢµ×ÜŃüŗµ║¢ÕéÖŃüŚŃü”ĶĪīŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéõ╗ŖÕø×Ńü»Õģ©ķĢĘńŁēµĢ░ÕĆżŃāćŃā╝Ńé┐ŃüīŃüéŃéŖõĮŹńĮ«µ▒║ŃéüŃééõ║ŗÕēŹŃü½Õć║µØźŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦ńÅŠÕĀ┤Ńü¦Ńü«õĮ£µźŁŃééŃé╣ŃāĀŃā╝Ńé║Ńü½ŃĆéÕģłµŚźµØźĶżćķøæ […]
ŃüŠŃü¤µŖ╝ÕĮóŃü¦ŃüÖŃüīŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆéń¦üŃü»µśöŃüŖµĢÖŃüłķĀéŃüäŃü¤ŃéäŃéŖµ¢╣Ńü¦ŃĆüÕ║ĄŃü«ķĀéńé╣Ńü«ńĘÜŃü»µŻ¤Ķ¦ÆŃü¦Ńü©ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«ńĘÜŃéÆÕī║ŃüŗŃéēµ©¬µēŗõ╗śĶ┐æŃüŠŃü¦Ńü©ŃüŻŃü”õĖƵŚ”ń┤ÖŃéÆÕż¢ŃüŚŃĆüõĖŖõĖŗķĆåŃü½ŃüŚŃü”ŃüŠŃü¤µŻ¤Ķ¦ÆŃü½ÕĮōŃü”Õģłń½»Ńü½ńĄÉŃüČŃĆüŃüØŃü«ŃéäŃéŖµ¢╣Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéÆń¤ŁÕłĆŃü¦ŃééÕÉīŃüśµ¦śŃü½ĶĪīŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü […]
µ£¼ĶāĮÕ»║Õż¦Õ»Čµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü½Ńü”ķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü«ŃĆīµŁ”ÕŻ½Ńü«ĶĪ©ķüōÕģĘŃü©ŃüØŃü«õŠĪÕĆżÕ▒ĢŃĆŹŃĆéÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü«Õ▒Ģńż║Ńü½ÕÉēńö░µŁŻõ╣¤ÕłĆÕīĀŃü«ŃĆīÕż¬ÕłĆŃĆĆķŖśŃĆƵŁŻõ╣¤ŃĆĆõ╗żÕÆīõĖāÕ╣┤µśź’╝łÕ▒▒ķ│źµ»øÕåÖ’╝ēŃĆŹŃéÆõĮ┐ńö©ŃüĢŃüøŃü”ŃüäŃü¤ŃüĀŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃĆīÕ▒▒ķ│źµ»øÕåÖŃüŚŃĆŹŃü©Õæ╝ŃéōŃü¦ŃéłŃüäŃü«ŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃĆüŃüöµ£¼õ║║Ńü½ńó║Ķ¬ŹŃüŚŃü”ŃüäŃüŠ […]
µ¤Éõ║½õ┐ØÕÉŹńē®Ńü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆéÕć║ÕģłŃü¦Ńü©ŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüµēĆĶ╝ēÕōüŃü¬Ńü®Ńü»õ║ŗÕēŹŃü½ńĘ┤ń┐ÆŃüŚŃü”ŃüŗŃéēĶć©ŃéĆõ║ŗŃééÕ║”ŃĆģŃü¦ŃüÖŃĆé Õ▒▒ķ│źµ»øŃü«µÖéŃü»ķü®ÕĮōŃü¬ÕłĆŃü¦Õż¢ÕĮóŃéÆŃüżŃüÅŃéŖŃĆüķüÄÕÄ╗Ńü«µŖ╝ÕĮóŃéÆÕÅéĶĆāŃü½Õ╣ŠŃüżŃüŗŃü«ŃāÉŃā╝ŃéĖŃā¦Ńā│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃüōŃéīŃĆüŃé╝ŃāŁńŖȵģŗŃü¦Ķć©ŃéĆŃéłŃéŖŃü»ÕżÜÕ░æµģŻŃéī […]
ÕÅżÕéÖÕēŹŃü«Õ£©ķŖśŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōŃĆéĶČŖõĖŁńē®ń¤ŁÕłĆÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóõĖŗµøĖŃüŹŃĆéµÖ«µ«ĄŃü»õĖŗµøĖŃüŹńäĪŃüŚŃü¦ŃüäŃüŹŃü¬ŃéŖÕó©ÕģźŃéīŃüīÕżÜŃüäŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü»ń¤ŁÕłĆńēćķØóŃü«õĖŗµøĖŃüŹŃü¦õ║īµŚźŃüŗŃüæŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤ŃĆéŃüöĶ┐æµēĆŃüĢŃéōŃü«Õż¦ķ¢ĆńĀöÕĖ½Ńü½Õ£░ńĀźŃéÆŃüŖÕƤŃéŖŃüŚŃü”Õ╝ĢŃüÅŃĆéń¦üŃü»ńĄÉµ¦ŗĶē▓ŃĆģĶ®”ŃüÖŃé┐ŃéżŃāŚŃü«ńĀöÕĖ½ŃüĀ […]
µ£¼ĶāĮÕ»║Õż¦Õ»│µ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü¦ķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü«ŃĆīµŁ”ÕŻ½Ńü«ĶĪ©ķüōÕģĘŃü©ŃüØŃü«õŠĪÕĆżÕ▒ĢŃĆŹŃĆéõĖ╗Ńü¬Õ▒Ģńż║ÕłĆ10ÕÅŻÕłåŃü½ŃüżŃüŹŃüŠŃüŚŃü”ŃĆüÕłĆÕēŻŃü©ÕÉłŃéÅŃüøŃĆüĶ”ŗŃü®ŃüōŃéŹĶ¦ŻĶ¬¼õ╗śŃüŹÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃāæŃāŹŃā½ŃéÆĶ©ŁńĮ«ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ŃĆĆÕ▒Ģńż║õŠŗ Ńā╗Õż¬ÕłĆŃĆĆķŖśŃĆĆń¤│ÕĘ×Õć║ńŠĮõĮÅńø┤ńČ▒õĮ£(ķćŹĶ”üńŠÄĶĪōÕōü)ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ […]
’╝Öµ£ł’╝¢µŚźŃéłŃéŖŃĆüµ£¼ĶāĮÕ»║Õż¦Õ»Čµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü½Ńü”ŃĆīµŁ”ÕŻ½Ńü«ĶĪ©ķüōÕģĘŃü©ŃüØŃü«õŠĪÕĆżÕ▒ĢŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé Õ▒Ģńż║ÕłĆŃü»õ╗źõĖŗŃü«ķĆÜŃéŖŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆń¤│ÕĘ×Õć║ńŠĮõĮÅńø┤ńČ▒õĮ£’╝łķćŹĶ”üńŠÄĶĪōÕōü’╝ē Õ░ÅÕż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕøĮĶĪī’╝łµØź’╝ē ŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆńäĪķŖśŃĆĆÕ╗ČÕ»┐’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ē […]
õ╗ŻŃéÆķćŹŃüŁŃéŗµ¤ÉÕĘźŃü«ńÅŠÕŁśÕōüõĖŁµ£ĆŃééÕÅżŃüäµÖéõ╗ŻŃü«Õż¬ÕłĆŃüīŃüéŃüŻŃü¤ŃĆéÕćäķüÄŃüÄŃü¤ŃĆé
ÕåŹÕłāŃü«ķćŹÕłĆŃééĶżćµĢ░ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃü¢ŃüŻŃü©µÄóŃüÖŃü©õ╗źõĖŗŃü«ńē®ŃüīŃĆé’╝łÕģ©Ńü”ŃĆīÕåŹÕłāŃĆŹŃü©ŃüŚŃü¤ŃüåŃüłŃü¦Ńü«ķćŹÕłĆµīćÕ«ÜŃü¦ŃüÖ’╝ē ŃĆĆń¼¼’╝Æ’╝ÉÕø×ŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕéÖÕēŹÕøĮķĢĘĶł╣õĮÅÕĘ”Ķ┐æÕ░åńøŻķĢĘÕģēķĆĀŃĆƵŁŻÕ┐£õ║īÕ╣┤ÕĘ│õĖæÕ╣┤ÕģŁµ£łµŚź’╝łķøåÕÅżµŗŠń©«µēĆĶ╝ē’╝ēŃĆĆń¼¼’╝Æ’╝æÕø×ŃĆĆń¤ŁÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆĶĪīÕģē’╝łõ║½õ┐ØÕÉŹńē® […]
ŃüØŃüåŃüäŃüłŃü░ÕģłµŚźŃĆüÕŹŚÕīŚµ£Øµ£¤Õ£©ķŖśÕ»ĖÕ╗ČŃü¦ÕåŹÕłāŃü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗŃééŃü«Ńü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗źõĖŗń░ĪÕŹśŃü¬Ķ¬┐µøĖŃĆé ÕłāķĢĘ34.3ŃÄØÕÅŹŃéŖ0.6ŃÄØÕģāÕ╣ģ31.0(31.5)mmÕģāķćŹ6.0mmĶīĵ£ĆÕÄÜ6.6mm Õ╣│ķĆĀŃéŖŃĆüõĖĖµŻ¤ŃĆüĶ║½Õ╣ģÕ║āŃüÅŃĆüÕÅŹŃéŖõ╗śŃüÅŃĆéńø«ķćś […]
ŃüØŃüåŃüäŃüłŃü░Ńā×Ńā╝ŃāåŃéŻŃā│ŃüīŃĆüŃā©Ńā╝ŃāŁŃāāŃāæŃü½Ńü»ÕåŹÕłāŃü«µŚźµ£¼ÕłĆŃüīķØ×ÕĖĖŃü½ÕżÜŃüäŃü©ŃüäŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕĮ╝ŃüīŃüäŃüåŃü½Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼ÕøĮÕåģŃü¦Ńü»ÕŻ▓ŃéŖķøŻŃüäÕåŹÕłāÕłĆŃéÆŃā©Ńā╝ŃāŁŃāāŃāæŃü½Õć║ŃüŚŃü¤µÖéõ╗ŻŃüīŃüéŃüŻŃü¤Ńü«ŃüĀŃüØŃüåŃü¦ŃĆéŃüØŃüåŃüäŃüåõ║ŗŃééŃüéŃüŻŃü¤Ńü«ŃüŗŃééŃü¦ŃüÖŃüŁŃüćŃĆéŃĆéŃüŖŃüŗŃüÆŃü¦ÕĮ╝Ńü«ÕåŹÕłāŃéÆĶ”ŗ […]
õ╗ŖŃüŠŃü¦õĮĢµ£¼Ńü«ÕåŹÕłāŃü½Õć║õ╝ÜŃüŻŃü”µØźŃü¤Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé’╝Æ’╝ɵ£¼Ńéä’╝ō’╝ɵ£¼Ńü¦Ńü»Ńü¬Ńüäõ║ŗŃü»ńó║ŃüŗŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüõĮĢµ£¼ŃüŗŃü»õĖŹµśÄŃü¦ŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ÕåŹÕłāŃü©Ķ¬ŹĶŁśŃüøŃüÜŃü½Õć║õ╝ÜŃüŻŃü¤ÕåŹÕłāÕłĆŃééŃüŗŃü¬ŃéŖŃü«µĢ░Ńü½Ńü«Ńü╝ŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéŃééŃüŚŃüŗŃüŚŃü¤ŃéēŃüØŃüĪŃéēŃü«µ¢╣ŃüīÕżÜŃüäŃü«ŃüŗŃééń¤źŃéīŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃĆé µś©µŚźŃü« […]
ÕżÜÕłå’╝æ’╝ĢÕ╣┤õ╗źõĖŖÕēŹŃĆüµŗĄÕģźŃéŖń¤ŁÕłĆŃéÆÕåŹÕłāŃüŚŃü”ŃééŃéēŃüŻŃü¤õ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńĄÉµ×£Ńü»ÕłćŃüŻÕģłõ╗śĶ┐æŃü«ķēäŃüīµé¬ŃüÅŃĆüŃüØŃü«ķā©ÕłåŃü»ńä╝ŃüŹŃüīÕģźŃéēŃüÜŃĆéŃüØŃüŚŃü”ÕÅŹŃéŖŃüīÕżēŃéÅŃüŻŃü¤Ńü¤ŃéüŃĆüÕłĆĶ║½Ńü«õĖēÕłåŃü«õ║īń©ŗÕ║”ŃüŠŃü¦ŃüŚŃüŗķלŃü½ÕģźŃéēŃü¬ŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕåŹÕłāŃüŚŃü¤ŃéēŃü®ŃéōŃü¬Õ£░ÕłāŃü½Ńü¬ŃéŗŃüŗŃéÆ […]
ńäĪķŖśŃü«Õ╣│ķĆĀŃéŖĶäćÕĘ«Ńü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆé ÕłāķĢĘ33.95ŃÄØÕÅŹŃéŖ0.5ŃÄØÕģāÕ╣ģ31.8(32.8)ŃÄ£ÕģāķćŹ4.8ŃÄ£Ķīĵ£ĆÕÄÜ5.4ŃÄ£248gÕ╣│ķĆĀŃĆüõĖēŃüżµŻ¤ŃĆéķćŹŃüŁĶ¢äŃüÅŃĆüĶ║½Õ╣ģÕ║āŃüÅŃĆüÕ»ĖŃüīÕ╗ČŃü│ŃĆüÕ░æŃüŚÕÅŹŃéŖŃĆüŃüĄŃüÅŃéēÕģłµ×»ŃéīŃü”ķŗŁŃüäŃĆéńö¤ŃüČĶīÄŃĆüĶīĵźĄń¤ŁŃüÅŃĆüÕģāµØź […]
ÕåŹÕłāŃü©ÕłżÕ«ÜŃüĢŃéīŃéŗÕłĆŃü»µĖøŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃü©µä¤ŃüśŃüŠŃüÖŃĆ鵜öŃü«ÕłżÕ«ÜŃü»ÕÄ│ŃüŚŃüŗŃüŻŃü¤ŃĆéŃĆ鵜öŃü»Ķē»ŃüŗŃüŻŃü¤Ńü©ŃüŗĶŗ”ÕŖ┤Ķ欵ģóŃü©ŃüŗŃüØŃü«ķĪ×Ńü«õ║ŗŃéÆĶ©ĆŃüåŃüżŃééŃéŖŃü»Ńü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüµśöŃü»ÕÄ│ŃüŚŃüŗŃüŻŃü¤ŃĆé õ╗źÕēŹµ¤ÉµēĆŃü¦µśŁÕÆīŃü½ÕåŹÕłāŃü©ÕłżÕ«ÜŃüĢŃéīŃü¤Õ£©ķŖśŃü«Õż¬ÕłĆŃéÆĶ”ŗŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüīŃĆüń¦üŃü½Ńü»ÕåŹÕłāŃü½Ķ”ŗ […]
ĶŚżÕ│ČÕłĆÕĘźŃéÆķŖśķææŃü¦Ńü┐ŃéŗŃü©õ╗źõĖŗŃü«ķĆÜŃéŖŃĆéńĄÉµ¦ŗÕ▒ģŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń¦üŃüīĶŚżÕ│ČŃü©Ķ¬ŹĶŁśŃüŚŃü”Ķ”ŗŃü¤õ║ŗŃüīŃüéŃéŗŃü«Ńü»ÕÅŗķćŹŃüĀŃüæŃüŗŃééń¤źŃéīŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃĆīĶŚżÕ│ČŃĆŹŃü©Ńü«Ńü┐ÕłćŃéŗńē®ŃééńøĖÕĮōµĢ░ÕŁśÕ£©ŃüŚŃĆüŃüØŃéīŃü»ŃéłŃüÅĶ”ŗŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤Õ«¤ķÜøŃü«ÕłćķŖśŃü»ŃĆīĶŚżÕČŗŃĆŹŃü¦ŃĆüÕŹöõ╝ÜŃééõ╗źÕēŹŃü»ŃĆīÕČŗŃĆŹŃü©ŃĆīÕ│ČŃĆŹŃü«õĮ┐Ńüä […]
ÕÅżÕłĆµ£¤Ńü«ÕŖĀĶ│ĆÕøĮŃü½Ńü»ĶŚżÕ│ČõĖƵ┤ŠŃüīÕ▒ģŃüŠŃüÖŃĆéõĖƵ┤ŠŃü©Ńü»Ķ©ĆŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃü¦Ńü»Ķ¬░ŃüīŃüäŃéŗ’╝¤Ńü©ĶĆāŃüłŃü”ŃééŃāæŃāāŃü©Õć║Ńü”ŃüÅŃéŗŃü«Ńü»ÕÅŗķćŹŃü░ŃüŗŃéŖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚÕģłŃü╗Ńü®ķŖśķææŃü¦Ķ”ŗŃéŗŃü©ÕÅŗķćŹõ╗źÕż¢Ńü½ŃééŃüŗŃü¬ŃéŖŃü«µÄ▓Ķ╝ēŃüīŃüéŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüŃüØŃéīŃü»ŃüŠŃü¤ÕŠīµŚźŃĆé ŃüĢŃü”ŃüØŃü«ĶŚżÕ│ČŃü«ÕłĆŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüń¦üŃü»Ńéä […]
Ńüīńē╣Ńü½Ńü®ŃüåŃüŚŃü¤Ńü©ŃüäŃüåĶ©│Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüõ┐صśīŃü©ńøĖÕĘ×ńö¤ŃüČÕ£©ķŖśÕŹŚÕīŚÕ╣┤ń┤ĆŃü©ŃĆüÕ║āÕģēÕ»ĖÕ╗ČŃü│Ńü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆéÕŹŚÕīŚÕ╣┤ń┤ĆŃü«ńē®Ńü»Õ░ÅÕż¬ÕłĆŃĆéŃüŠŃüĀµÄĪµŗōõĖŁŃü¦ńēćķØóŃü«’╝ĢÕē▓ń©ŗÕ║”ŃĆéŃüŗŃü¬ŃéŖµ┐ĆŃüŚŃüäńÜåńä╝Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃĆīÕ¤║Ķ¬┐Ńü»Õż¦ÕĆČÕł®õ╝ĮńŠģÕ║āÕģēŃü½õ╝╝Ńü”ŃüäŃéŗŃüŗŃééŃĆŹŃü©Õż¦ÕĆČÕł®õ╝Į […]
ŃüŠŃü¤µ░ŚŃü½Ńü¬ŃéŖŃĆüõ╗Ŗµ£Øµö╣ŃéüŃü”Ķ¬┐Ńü╣ŃéŗŃü©ń░ĪÕŹśŃü½Ķ”ŗŃüżŃüŗŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗źÕēŹŃééŃāćŃéĖŃé│Ńā¼Ķ”ŗŃü”Ńü¤Ńü»ŃüÜŃü¬ŃéōŃü¦ŃüÖŃüīŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆé MUSEUM’╝æ’╝ō’╝¢Ńü½Õ»ÆÕ▒▒Õģłńö¤Ńü½ŃéłŃéŗĶ®│ń┤░ŃüīŃĆéŃĆÄķĢĘŃüĢ’╝ś’╝śŃÄØŃĆüÕÅŹŃéŖ’╝Æ.’╝ÖŃÄØŃĆüÕģāÕ╣ģ’╝ō.’╝Æ’╝śŃÄØŃĆüÕģłÕ╣ģ’╝Æ.’╝Æ’╝śŃÄØŃĆüķŗÆķĢĘ’╝Ģ.’╝Ś’╝ĢŃÄØĶīÄķĢĘ’╝Æ […]
ÕģłµŚźÕ£©ķŖśķĢĘĶ░Ęķā©µ¤Éń¤ŁÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆéŃüäŃüżŃééŃü«ķĢĘĶ░Ęķā©ŃéēŃüŚŃüäńÖĮŃüÅĶéīń½ŗŃüżÕ£░ĶéīŃü¦ŃüÖŃĆéńÖĮńå▒ńü»Ńü¦Ķ”ŗŃü¬ŃüīŃéēŃĆüÕĘ«ŃüŚĶĪ©Ńü»ÕłāµŻ¤Ńüīµ¤ŠŃüīŃüŗŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅÕ«īÕģ©Ńü¬µ¤ŠŃü¬Ńü«Ńü¦Õ░æŃüŚń¢æÕĢÅŃü½µĆØŃüäŃü¬ŃüīŃéēŃééŃĆüµÖéķ¢ōŃééńäĪŃüäõ║ŗŃüĀŃüŚŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃüōŃéīŃééµ£ēŃéŖŃüŗŃü©ŃüØŃü«ŃüŠŃüŠķĆ▓ŃéüŃüŠŃüŚŃü¤ […]
ĶéźÕēŹÕ┐ĀÕ║āńī«õĖŖķŖśµŗØĶ”ŗŃĆéńī«õĖŖķŖśŃü»ŃüĪŃéćŃüŻŃü©õ╣ģŃĆģŃĆ鵟Ąń½»Ńü½Ńé┐Ńé¼ŃāŹŃüīÕż¬ŃüäŃé┐ŃéżŃāŚŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃüīŃĆüÕøĮŃü«ÕÅ│ŃĆüĶŚżŃü«õĖēµ£¼ńĘÜŃĆüÕ║āŃü«ĶÅ▒ńé╣Ńü¬Ńü®ÕłØõ╗Żńī«õĖŖķŖśŃü«ÕģĖÕ×ŗŃü¦ŃüÖŃĆéĶéźÕēŹÕłĆŃü»õ╗ŖŃüŠŃü¦õĖĆõĮōõĮĢµ£¼µŗØĶ”ŗŃüŚŃü”ŃüŹŃü¤Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéńĀöńŻ©ŃüĀŃüæŃü¦ŃééŃüŗŃü¬ŃéŖŃü«µ£¼µĢ░Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüµēŗŃü½ […]
õ╣ģŃĆģŃü½µ£▒ŃéÆŃüÖŃéŖµŖ╝ÕĮóŃü½µ£▒µøĖŃéÆÕģźŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ£▒µøĖŃüŹŃü»ŃüØŃéīń©ŗÕżÜŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃééŃü¬ŃüÅŃĆüµŖ╝ÕĮóŃü½ÕģźŃéīŃéŗõ║ŗŃééÕ░æŃü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéµ£▒Ńü¦µ¢ćÕŁŚŃéƵøĖŃüÅŃü©õĖŗµēŗÕŁŚŃü¦ŃééńĄÉµ¦ŗõĖŖµēŗŃüÅķī»Ķ”ÜÕć║µØźŃéŗŃü«Ńü¦µźĮŃüŚŃüÅŃü”ŃĆéŃü¦õ╗ŖÕø×Ńü»ńÅŹŃüŚŃüÅĶ╗ĖĶŻģÕēŹµÅÉŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüĶ¬żŃüŻŃü”ŃüäŃüżŃééŃü«µ░┤µĆ¦Ķē▓ķēøńŁåŃü¦Ķ╝¬ […]
’╝æÕÅĘŃĆĆÕłĆÕ░æŃüŚń¤ŁŃéüŃü«ÕłĆŃĆéÕÅŹŃéŖķĀāÕÉłŃüäŃü½ķćŹŃüŁĶ¢äŃéüŃü¦µēŗµīüŃüĪĶ╗ĮŃüäŃĆéÕ£░ķēäŃü»Ķ®░ŃéĆŃééÕ░æŃĆģĶéīń½ŗŃüĪŃüéŃéŖŃĆéµŻÆµśĀŃéŖńŖČŃü«ń«ćµēĆŃüīŃüéŃéŗŃééńÖĮŃüæŃüīÕ╝ĘŃüÅŃĆüĶģ░ÕģāÕ╣│Õ£░Ńü½Õ£¤ĶÉĮŃüĪķó©Ńü¦õĖŹĶ”ÅÕēćŃü¬ķŻøŃü│ńä╝ŃüŹŃü©µśĀŃéŖµ░ŚŃĆéÕłāµ¢ćŃü»ńä╝ŃüŹķĀŁŃüīµÅāŃüäµ░ŚÕæ│Ńü«õ║ÆŃü«ńø«ŃĆéÕĮóńŖČŃü»õĖŹĶ”ÅÕēćŃü¦ÕÉēõ║ĢŃü╗Ńü®µĢ┤ […]
ŌĆØÕŠīŃü«ńźŁŃéŖŌĆØŃüśŃéāŃü¬ŃüÅŌĆØńźćÕ£ÆÕŠīńźŁŌĆØŃü«õ║ŗŃü¦ŃüÖŃĆéŃüÜŃüŻŃü©Õ┐ÖŃüŚŃüÅŃāÉŃé┐ŃāÉŃé┐Ńü¦ŃĆüõ╗ŖÕ╣┤Ńü»Õ«ĄÕ▒▒ŃéäÕ▒▒ķēŠÕĘĪĶĪīŃü¬Ńü®Ńü«ŃāŗŃāźŃā╝Ńé╣ŃéäŃāŹŃāāŃāłµśĀÕāÅŃüÖŃéēĶ”ŗŃü”ŃüäŃü¬ŃüÅŃü”ŃĆéµ░ŚŃüīõ╗śŃüæŃü░ŃĆüŃééŃüåÕŠīńźŁŃü«ÕĘĪĶĪīķ¢ōķÜøŃĆ鵦śŃĆģÕĮ╣Õē▓ŃééÕóŚŃüłÕ┐ÖŃüŚŃüÅŃü¬ŃéŗÕ╣┤ķĮóŃü¦ŃĆüŃüōŃüōµĢ░Õ╣┤Ńü»ńĀöńŻ©Ńü½õĮ┐ŃüłŃéŗµÖéķ¢ō […]
ÕģłŃü╗Ńü®UPŃüŚŃü¤Õ»ĖÕ░║ÕżēµÅøŃāÜŃā╝ŃéĖŃĆéĶ©łń«Śµ®¤ŃüĀŃü©õŠŗŃüłŃü░’╝ÆÕ░║’╝ōÕ»Ė’╝ĢÕłåŃéÆŃÄØŃü½ńø┤ŃüÖÕĀ┤ÕÉł’╝æ’╝ÉÕø×Ńé┐ŃāāŃāŚŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕżēµÅøŃāÜŃā╝ŃéĖŃüĀŃü©’╝ĢŃé┐ŃāāŃāŚŃü¦µĖłŃü┐ŃüŠŃüÖŃĆéŃéóŃāŚŃā¬ŃééµĪłÕż¢ķØóÕĆÆŃüĀŃüŚŃĆüµ▓óÕ▒▒ÕżēµÅøŃüÖŃéŗµ¢╣Ńü»Ńā¢ŃāāŃé»Ńā×Ńā╝Ńé»ŃüŚŃü”õĮ┐ŃüŻŃü”õĖŗŃüĢŃüäŃĆé
Õ»Ė’╝łÕÉłĶ©ł’╝ēŌåÆ Ńé╗Ńā│Ńāü ÕżēµÅø Ńé╗Ńā│Ńāü ŌåÆ Õ»ĖÕ░║ ÕżēµÅø
ÕÅżŃüäÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐ńĀöŃüÄŃü«ÕłĆŃüīÕć║Ńü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕÉäµØĪõ╗ČŃüŗŃéēÕ╣Ģµ£½ŃĆüµśÄµ▓╗Ńā╗Õż¦µŁŻŃā╗µśŁÕÆīÕłØµ£¤ķĀāŃü«ÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐Ńü©µĆØŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃüīõ┐ØÕŁśŃüīĶē»ŃüÅŃĆüµēōŃüĪń▓ēńŁēŃü«ŃāÆŃé▒ŃééÕ░æŃü¬ŃüÅńŖȵģŗĶē»ÕźĮŃĆéńēćķØóŃéƵ«ŗŃüŚŃü¤ŃüŠŃüŠÕÅŹÕ»ŠķØóŃü¦µ¦śŃĆģÕ«¤ķ©ōŃéÆŃĆéĶĆāŃüłŃéēŃéīŃéŗõ║ŗŃü»ŃéäŃéŖÕ░ĮŃüÅŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīÕåŹńÅŠÕć║µØźŃüÜ […]
õ╗ŖÕø×Ńü»µ£¼ķā©ŃüŗŃéēŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆķĢĘÕ»ĖŃĆüµØ┐ńø«Ńü¦Ķéīńø«ńø«ń½ŗŃüżŃĆéÕāŹŃüÅńČ║ķ║ŚŃü¬ńø┤ŃüÉĶ¬┐ÕłāŃĆüĶģ░ÕģāŃü«ÕłāŃü½µĮżŃü┐ŃĆéÕÅżŃüäŃü©ŃüōŃéŹŃü½Õģźµ£ŁŃĆé ’╝ÆÕÅĘŃĆĆń¤ŁÕłĆŃĆĆÕāģŃüŗŃü½ÕÅŹŃéŖŃĆéńē╣ÕŠ┤ńÜäŃü¬µśĀŃéŖŃĆüķīĄŃéŗÕłāŃĆéķÄīÕĆēµÖéõ╗Żµ£½µ£¤µ¤ÉÕĘźŃü½Õģźµ£ŁŃĆé ’╝ōÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆõĖŁķŗÆŃĆüÕģ©Ķ║½µśĀŃéŖŃĆüńø┤ŃüÉĶ¬┐Ńü½ńē╣ […]
õ║łÕ«ÜŃü«’╝æ’╝ɵ×ÜŃü«ÕåģŃĆü’╝śÕÅŻÕłåŃüŠŃü¦Õ«īõ║åŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤’╝ł’╝æµ×ÜŃü»ńÅŠÕ£©µ£¼ĶāĮÕ»║Õ«Øńē®ķż©Ńü½Ńü”Õ▒Ģńż║õĖŁ’╝ēŃĆéŃüéŃü©’╝ÆÕÅŻŃü»Ńü®ŃéōŃü¬ÕŠĪÕłĆŃüŗŃüŠŃüĀÕłåŃüŗŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüŃü©ŃéŖŃüéŃüłŃüÜŃüōŃéīŃüīńĄéŃéÅŃüŻŃü”Õ»éŃüŚŃüäŃü«Ńü¦µ¼ĪŃéƵźĮŃüŚŃü┐Ńü½ÕŠģŃüĪŃüŠŃüÖŃĆé Ńü©ŃüōŃéŹŃü¦ŃĆüń┤ÖŃüīńäĪŃüäŃĆéńÅŠÕ£©õĮ┐ńö©õĖŁŃü«ń┤ÖŃü»ŃĆü […]
ŃüØŃü«ÕŠīŃééÕż£õĖŁŃü½ŃüøŃüŻŃüøŃüōŃüøŃüŻŃüøŃüōµŖ╝ÕĮóŃéƵÅÅŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕłāŃü«ÕāŹŃüŹŃééńī¬ķ”¢ķó©ķŗÆŃééÕĖĮÕŁÉŃééŃé½ŃāāŃé│ŃüäŃüäŃĆé
µś©µŚźŃü«ÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü»Õ«īµłÉŃĆéÕłźŃü¦µĢ░µŚźķ¢ōķĆ▓ŃéüŃü”ŃüäŃü¤Õģ©Ķ║½Ńü»õ╣ģŃĆģŃü½Õż▒µĢŚŃüŚŃĆüŃé╝ŃāŁŃüŗŃéēŃéäŃéŖńø┤ŃüŚŃü¦ŃüÖŃĆéµĢ░Õ╣┤Ńü½õĖĆÕ║”ŃĆüŃü®ŃüåŃü½ŃééŃü¬ŃéēŃü¬ŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃéäŃéŖńø┤ŃüÖõ║ŗŃüīŃĆé’╝æ’╝ɵ×ÜÕģ©ķā©µ┐āŃüäńö╗ķó©Ńü¦µÅāŃüłŃéłŃüåŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃéäŃü»ŃéŖÕ┐āķģŹŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ķĆÜŃéŖŃāĆŃāĪŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé […]
µŖ╝ÕĮóŃü«õ║ŗŃü░ŃüŗŃéŖŃü¦ŃüÖŃüīŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆéÕģłµŚźŃü«Ńā¢ŃāŁŃé░Ńü½µøĖŃüäŃü¤’╝æ’╝ɵ×ÜŃü©Ńü»ÕłźŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆķćŹŃéŖŃéƵĖøŃéēŃüŚŃü”µÄĪµŗōŃĆéĶ┐æÕ╣┤ŃĆüõĖŗŃü«ńö╗ÕāÅŃü«µ¦śŃü½ÕżÜµĢ░Ńü«ķćŹŃéŖŃéÆõĮ┐ŃüŻŃü”µÄĪµŗōŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüØŃéīŃüīĶē»ŃüäŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ŃéÅŃüæŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüŃüéŃüÅŃüŠŃü¦ŌĆصĄüŃéīŌĆØŃü¦ŃéäŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ […]
Ķ©│ŃüéŃüŻŃü”’╝æ’╝ɵ×ÜÕłČõĮ£ŃüÖŃéŗõ║ŗŃü½Ńü¬ŃüŻŃü¤Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü»ŃüŗŃü¬ŃéŖµ┐āŃüŵÅÅŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃü¤ŃüĀŃüōŃü«ÕŠīŃü«’╝Ƶ×ÜŃüīŃüōŃü«µ┐āŃüĢŃüĀŃü©Ńü®ŃüåŃü¬ŃéŗŃüŗõĖŹµśÄŃü«õĮ£ķó©Ńü¦ŃĆéµ£¼µØźŃĆüµśÄŃéŗŃüäÕłāŃü»µ┐āŃüŵÅÅŃüŹµ▓łŃéĆÕłāŃü»Ķ¢äŃüŵÅÅŃüÅŃü«ŃüīµŁŻŃüŚŃüäŃü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüīŃĆüŃüØŃéīŃü░ŃüŗŃéŖŃü¦ŃééŃü¬ŃüäŃü«ŃüīµŖ╝ÕĮóŃüĀ […]
õ╗ŖÕø×Ńü»ÕĮōńĢ¬Ńü¦ÕłżĶĆģŃü©Ķ¦ŻĶ¬¼Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆƵĖģńČ▒’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ē’╝ÆÕÅĘŃĆĆń¤ŁÕłĆŃĆĆńäĪķŖśŃĆĆĶĪīÕģē’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ē’╝ōÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆĶéźÕēŹõĮÉĶ│ĆõĮÅÕøĮÕ║ā’╝öÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆƵŁŻÕł®’╝łÕØéÕĆēķ¢ó’╝ē’╝ĢÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆńäĪķŖśŃĆĆÕ╗ČÕ»┐’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ē ’╝æÕÅʵĖģńČ▒Õż¬ÕłĆ ’╝ÆÕÅĘĶĪī […]
ŃüéŃü╣Ńü«ŃāÅŃā½Ńé½Ńé╣Ķ┐æķēäµ£¼Õ║Ś11ķÜÄŃĆüńŠÄĶĪōńö╗Õ╗ŖŃü½Ńü”ÕĘØ’©æµÖČÕ╣│ÕłĆÕīĀŃü«ÕĆŗÕ▒ĢŃĆīķīĄŃü«Õ«ÖŃĆĆÕłĆķŹøÕåČ µÖČÕ╣│Ńü«õĖ¢ńĢīŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé Ńā╗õ╝ܵ£¤ŃĆĆõ╗żÕÆī7Õ╣┤5µ£ł14(µ░┤)ŃĆ£20µŚź(ńü½)Ńā╗Ńé«ŃāŻŃā®Ńā¬Ńā╝ŃāłŃā╝Ńé»ŃĆĆ5µ£ł17ŃĆü18µŚźŃĆĆÕŹłÕŠī1µÖé’Į× ŃüéŃü╣Ńü«ŃāÅŃā½Ńé½Ńé╣Ķ┐æķēä […]
ÕĖéÕĮ╣µēĆÕēŹŃü½ńö©õ║ŗŃü¦ĶĪīŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüĪŃéćŃüōŃüŻŃü©µ£¼ĶāĮÕ»║ŃüĢŃéōŃü½ŃüŖķé¬ķŁöŃüŚŃü”ŃĆüµŖ╝ÕĮóŃéÆĶ”ŗŃü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃéäŃü»ŃéŖń¦üŃü»µŖ╝ÕĮóŃüīÕż¦ÕłåÕźĮŃüŹŃü¦ŃĆéµÖ«µ«ĄµŖ╝ÕĮóŃéÆĶżćµĢ░õĖ”Ńü╣Ńü”Ķ”ŗŃéŗõ║ŗŃééŃü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃüŚŃĆüÕŹüµĢ░µ×ÜŃüīµĢ┤ńäČŃü©õĖ”Ńüȵ¦śŃü»ŃĆīńČ║ķ║ŚŃéäŃü¬ŃüüŃā╗Ńā╗ŃĆŹŃü©ŃĆüŃüÜŃüŻŃü©Ķ”ŗŃü”ŃüäŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéĶć¬ÕłåŃü¦ […]
µ¢░ÕłĆõĖüÕŁÉÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆé µ┐āŃüÅŃüøŃüÜŃüŚŃéāŃéŖŃéŖŃü©µÅÅŃüÅŃü©ŃüØŃéīŃü¬ŃéŖŃü½µŚ®ŃüŵÅÅŃüæŃéŗŃü«Ńü¦Õłāµ¢ćŃü»ĶĪ©ĶŻÅŃéÆõĖĖ’╝æµŚźŃü¦Õ«īµłÉŃĆé’╝łĶīÄŃü©Õģ©Ķ║½Ķ╝¬ķāŁŃü»ÕēŹÕż£’╝ēŃüōŃü«ķƤÕ║”Ńü¦µÄĪµŗōÕć║µØźŃéīŃü░Õć║ÕģłŃü¦õĖƵ¢ćÕŁŚńŁēŃü¦ŃééŃü¬ŃéōŃü©ŃüŗŃĆé ńĀöŃüÄÕĀ┤Ńü½Ńü”ķÄīÕĆēµ£½µ£¤ńö¤ŃüČĶīÄÕż¬ÕłĆŃéÆ’╝ÆÕÅŻµŗØĶ”ŗŃĆéõĖĆŃüżŃü» […]
õ╗ŖÕø×Ńü»ńåŖĶ░ĘÕÆīÕ╣│Õģłńö¤ŃĆéÕģ©ķā©ķļķĆĀĶäćÕĘ«’╝¢ÕÅŻŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆĶäćÕĘ«’╝æÕ░║’╝ŚÕ»Ėń©ŗÕ║”ŃüŗŃĆéÕÅŹŃéŖÕ░ŗÕĖĖŃĆéµ¢░ÕłĆõ║ÆŃü«ńø«õ╣▒ŃéīŃĆéÕŹŖõĖĖÕĮóŃĆéĶģ░ķ¢ŗŃüŗŃüÜŃā¬Ńé║ŃāĀŃüéŃéŖŃĆéÕ£░ķēäÕ░æŃĆģÕ╝▒ŃéüŃĆéńø┤ŃüÉŃü½Õ░ÅõĖĖŃĆéÕŠ«Õ”ÖŃü½Õø║ŃüŵŁóŃüŠŃéŗŃĆé ÕłåŃüŗŃéēŃéōŃü«Ńü¦µ┤źńö░ÕŖ®Õ║āÕłØµ£¤ķŖśŃü©Õģźµ£ŁŃĆé ’╝ÆÕÅĘŃĆĆĶäćÕĘ«ÕÉīÕ»Ėń©ŗÕ║” […]
ŃüäŃüżŃééÕåÖń£¤ŃéƵƫŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ŃüĀŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃĆüÕåÖń£¤Õ«ČŃü«ķĢĘĶ░ĘÕĘØõĮ│µ▒¤ŃüĢŃéōŃü«ÕåÖń£¤Õ▒ĢŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéµ»ÄÕ║”µ»ÄÕ║”ŃĆüÕŗĢŃüŹŃééÕŹśĶ¬┐Ńü¦ÕÉīŃüśõĮ£µźŁŃü½ŃüŚŃüŗĶ”ŗŃüłŃü¬ŃüäŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŚŃĆüńö│ŃüŚĶ©│Ńü¬ŃüäŃü¬ŃüüŃü©µĆØŃüäŃüżŃüżŃĆéŃĆéŃüØŃéīŃü¦Ńé鵳æŃĆģĶüĘõ║║Ńü«õĖĆń×¼ŃéÆÕåÖŃüŚÕć║ŃüŚŃĆüÕĮóŃü½ŃüŚŃü”ŃüÅŃüĀŃüĢŃüŻŃü”ŃüäŃüŠ […]
ķÄīÕĆēµÖéõ╗Żµ£½µ£¤Ńü«Õż¦ńŻ©õĖŖŃüÆńäĪķŖśÕłĆŃĆéńäĪķŖśŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüķü®Õ║”Ńü¬ńĪ¼ŃüĢŃü«ń¤│ĶÅ»Õó©Ńü¦ķæóńø«ŃéÆŃü¬ŃéŗŃü╣ŃüŵĮ░ŃüĢŃü¼ŃéłŃüåŃĆüµ£ĮŃüĪĶŠ╝Ńü┐ŃéÆÕ¤ŗŃéüķüÄŃüÄŃü¼ŃéłŃüåŃĆüµÖéķ¢ōŃéÆŃüŗŃüæŃü”õĖüÕ»¦Ńü½µō”ŃéŖŃüĀŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŻŃüŗŃéŖŃü©µÖéķ¢ōŃéÆŃüŗŃüæŃéŗõ║ŗŃü¦ń┤ÖŃü½Õó©ŃüīŃü¤ŃüŻŃüĘŃéŖŃü©Ńü«ŃéŖŃĆüµĘ▒Ńüäķ╗ÆÕæ│Ńü©ĶēČŃüīńö¤ŃüŠŃéīŃüŠŃüÖ […]
µ¢░õĮ£õĖüÕŁÉŃü«Õż¬ÕłĆŃĆüÕ▒▒ķÖĮķüōķÄīÕĆēµ£½µ£¤ńö¤ŃüČÕ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃĆüńö¤ŃüČÕ£©ķŖśµØźÕøĮĶĪīÕż¬ÕłĆŃĆüńö¤ŃüČÕ£©ķŖśµØźÕøĮõ┐ŖÕż¬ÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆéÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü¦ŃééŃéäŃü»ŃéŖńö¤ŃüČÕż¬ÕłĆŃü»µĀ╝ÕłźŃü¦ÕźĮŃüŹķüÄŃüÄŃéŗŃĆéµ£©Õ▒ŗµŖ╝ÕĮóŃéƵ«ŗŃüŚŃü¤ńĀöÕĖ½ķüöŃééÕ┐ģŃüÜÕÉīŃüśµ░ŚµīüŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤ŃéŹŃüåŃĆé
µ£¼ĶāĮÕ»║Õż¦Õ»Čµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü½Ńü”ŃĆīµŁ┤ÕÅ▓Ńü©ÕŁ”ŃüȵŚźµ£¼ÕłĆÕ▒ĢŃĆŹŃüīÕ¦ŗŃüŠŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĖŖÕÅżÕłĆŃüŗŃéēńÅŠõ╗ŻÕłĆŃüŠŃü¦Ńü«ÕÉŹÕłĆŃüīõĖ”Ńü│ŃüŠŃüÖŃĆéÕłĆĶŻģÕģĘŃü¦Ńü»µŖśń┤Öõ╗śŃü«ÕÉŹÕōüŃéäÕć║Õ£¤Ńü«ÕĆÆÕŹĄÕĮóķÉöŃééÕ▒Ģńż║ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé Ńā╗õĖŖÕÅżÕłĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ’╝łÕźłĶē»µÖéõ╗Ż’╝ē Ńā╗Õż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆƵŁŻµüÆ […]
ÕģłµŚźŃü«µö»ķā©ķææÕ«ÜŃü¦ķćæĶ▒ĪÕĄīķŖśŃü«Õ╗ČÕ»┐ÕøĮµÖé’╝łķćŹÕłĆ’╝ēŃüīÕć║ķĪīŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé3µ£łõ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©Õģźµ£ŁķææÕ«Ü | ńÄēńĮ«ńŠÄĶĪōÕłĆÕēŻńĀöńŻ©Õć”’Į£õ║¼ķāĮŃā╗ÕĘ”õ║¼Õī║ ŃĆī’╝æÕÅĘÕłĆŃĆüĶ║½Õ╣ģÕ║āŃéüŃĆüķćŹŃüŁÕ░ŗÕĖĖŃĆéõĖŁķŗÆŃĆéķÄīÕĆēµ£½µ£¤ŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚŃü«ķĆĀŃéŖĶŠ╝Ńü┐ŃĆéÕ£░ķēäĶ®░Ńü┐µ░ŚÕæ│ŃĆéķļջäŃéŖµśĀŃéŖµ░ŚŃĆéÕģ©õĮōŃü½ […]
ń¼¼’╝¢’╝ŚÕø×ķĀāŃüŠŃü¦Ńü«Õ╗ČÕ»┐µ┤ŠķćŹÕłĆŃā╗ńē╣ķ揵īćÕ«ÜÕōüõĖŁ’╝łõĖĆķā©ķ揵¢ćķćŹńŠÄÕɽŃéĆ’╝ēŃĆüÕłĆŃā╗Õż¬ÕłĆŃü«ÕĖĮÕŁÉŃü«Ķ¬┐µøĖŃĆé’╝łńäĪķŖśŃü»õ╝ØÕɽŃéĆ’╝ē ńäĪķŖśÕ╗ČÕ»┐ Ńā╗ńä╝ŃüŹµĘ▒ŃüÅĶĪ©Ńü»õ╣▒ŃéīŃüöŃüōŃéŹŃĆüĶŻÅŃü»ńø┤ŃüÉĶ¬┐Ńü©Ńü¬ŃéŖÕģ▒Ńü½ÕģłÕ░ÅõĖĖŃā╗Õż¦õĖĖŃüöŃüōŃéŹŃü½Ķ┐öŃéŖµĄģŃüäŃā╗ńø┤ŃüÉŃü½Õż¦õĖĖĶ┐öŃéŖµĄģŃüäŃā╗ńø┤ŃüÉŃü½Õ░ÅõĖĖÕģł […]
Õż¦ķś¬µŁ┤ÕÅ▓ÕŹÜńē®ķż©Ńü¦ķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃéŗŃĆÄńē╣ÕłźÕ▒ĢŃĆī’╝ŹÕģ©µŚźµ£¼ÕłĆÕīĀõ╝Ü50Õæ©Õ╣┤Ķ©śÕ┐Ą’╝ŹµŚźµ£¼ÕłĆ1000Õ╣┤Ńü«Ķ╗īĶĘĪŃĆŹŃĆÅŃĆéŃüäŃéłŃüäŃéłµśÄµŚź’╝öµ£ł’╝öµŚźŃüŗŃéēŃü¦ŃüÖ’╝ü ÕłĆÕīĀõ╝ÜYouTubeŃāüŃāŻŃā│ŃāŹŃā½Ńü½Ńü”ŃĆüÕÉäÕłĆÕīĀŃüĢŃéōŃü«ń┤╣õ╗ŗÕŗĢńö╗ŃüīUPŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé Õģ©µŚźµ£¼ÕłĆÕīĀõ╝ÜYou […]
’╝æÕÅĘŃüŗŃéēÕÅżŃüäńē®ķĀåŃü©Ńü«ŃüōŃü©ŃĆé’╝æÕÅĘŃü»Õż¦ńŻ©õĖŖŃüÆķćŹÕłĆŃĆéŃüéŃü©Ńü»Õ£©ķŖśŃü¦’╝ĢŃééķćŹÕłĆŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕłĆĶ║½Õ╣ģÕ║āŃéüŃĆüķćŹŃüŁÕ░ŗÕĖĖŃĆéõĖŁķŗÆŃĆéķÄīÕĆēµ£½µ£¤ŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚŃü«ķĆĀŃéŖĶŠ╝Ńü┐ŃĆéÕ£░ķēäĶ®░Ńü┐µ░ŚÕæ│ŃĆéķļջäŃéŖµśĀŃéŖµ░ŚŃĆéÕģ©õĮōŃü½ńÖĮŃüæŃéŗµä¤ŃĆéńø┤ŃüÉÕ░ŵ╣ŠŃéīŃĆüÕ░ÅķīĄŃĆéķŻ¤ŃüäķüĢŃüäŃĆéõ║īķćŹÕłāŃüīŃüŗŃéŗń«ćµēĆ […]
Õż¦ķś¬µŁ┤ÕÅ▓ÕŹÜńē®ķż©Ńü¦ķ¢ŗÕé¼Ńü«ŃĆÄńē╣ÕłźÕ▒ĢŃĆī’╝ŹÕģ©µŚźµ£¼ÕłĆÕīĀõ╝Ü50Õæ©Õ╣┤Ķ©śÕ┐Ą’╝ŹµŚźµ£¼ÕłĆ1000Õ╣┤Ńü«Ķ╗īĶĘĪŃĆŹŃĆÅŃü«Õ▒Ģńż║ÕōüŃüīńÖ║ĶĪ©ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤’╝ü ńē╣ÕłźÕ▒ĢŃĆī’╝ŹÕģ©µŚźµ£¼ÕłĆÕīĀõ╝Ü50Õæ©Õ╣┤Ķ©śÕ┐Ą’╝ŹµŚźµ£¼ÕłĆ1000Õ╣┤Ńü«Ķ╗īĶĘĪŃĆŹÕć║ÕōüõĖĆĶ”¦Ńā╗Õ▒Ģńż║µø┐Ńā¬Ńé╣Ńāł ŃüōŃéōŃü¬Ńü½ÕżÜµĢ░Ńü«ńÅŠõ╗ŻÕłĆÕīĀ […]
’╝öµ£ł’╝æ’╝ÖµŚźŃĆüKKRŃāøŃāåŃā½Õż¦ķś¬Ńü¦ķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃéŗńźØĶ│Ćõ╝ÜŃü½ŃüŠŃüĀń®║ŃüŹŃüīŃüéŃéŗŃüØŃüåŃü¦ŃüÖ’╝üÕżĢµ¢╣’╝ĢµÖéÕŹŖŃüŗŃéēķ¢ŗÕé¼ŃĆéÕģ©ÕøĮŃü«ÕłĆķŹøÕåČŃüĢŃéōŃéäÕÉäĶüʵ¢╣Ńü©ń½ŗķŻ¤ŃāæŃā╝ŃāåŃéŻŃā╝Ńü¦Ńü«õ║żµĄüõ╝ÜŃü¦ŃüÖŃĆéń¦üŃééÕÅéÕŖĀŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃüöÕ┐£Õŗ¤ŃéłŃéŹŃüŚŃüÅŃüŖķĪśŃüäŃüäŃü¤ŃüŚŃüŠŃüÖ’╝ü’╝ü µŚźµÖé : õ╗ż […]
ŃĆÄÕż¦ķś¬µŁ┤ÕÅ▓ÕŹÜńē®ķż©Ńü¦Ńü»ŃĆüõ╗żÕÆī7Õ╣┤’╝ł2025’╝ē4µ£ł4µŚź’╝łķćæ’╝ēŃüŗŃéē5µ£ł26µŚź’╝łµ£ł’╝ēŃüŠŃü¦ŃĆü6ķÜÄńē╣ÕłźÕ▒Ģńż║Õ«żŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüńē╣ÕłźÕ▒ĢŃĆī’╝ŹÕģ©µŚźµ£¼ÕłĆÕīĀõ╝Ü50Õæ©Õ╣┤Ķ©śÕ┐Ą’╝ŹµŚźµ£¼ÕłĆ1000Õ╣┤Ńü«Ķ╗īĶĘĪŃĆŹŃéÆķ¢ŗÕé¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé ķļķĆĀŃüŚŃü«ŃüÄŃüźŃüÅŃéŖŃü¦ÕÅŹŃüØŃéŖŃü«ŃüéŃéŗńŠÄŃüŚŃü䵌ź […]
õ╗źÕēŹµŗØĶ”ŗŃüŚŃü¤ŃéŖńĀöńŻ©ŃüŚŃü¤ÕłĆŃü¦ŃüØŃü«ÕŠīķćŹÕłĆµīćÕ«ÜŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤µĢ░ÕÅŻŃĆ鵥üŃéīµĄüŃéīŃü”ÕüČńäČÕåŹõ╝ÜŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüÕĮōµÖéŃü»ńäĪŃüŗŃüŻŃü¤ķלµøĖŃüīŃüéŃéŗõ║ŗŃü½µ░Śõ╗śŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕłØĶ”ŗµÖ鵌óŃü½µĢģõ║║Ńü«ĶæŚÕÉŹŃü¬õ║║ńē®Ńü«ķלµøĖŃüŹŃüīķćŹÕłĆµīćÕ«ÜÕŠīŃü½µøĖŃüŗŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆü’╝æ’╝É’╝É’╝ģÕüĮķלµøĖŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüō […]
ÕĖ░ķāĘŃü½ŃüżŃüŹŃĆüõĖŖÕ╣│õĖ╗ń©ÄŃü«ÕóōµēĆŃéƵÄóŃüŚŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüōŃü«ķøåĶÉĮŃü«õĖŖµ¢╣Ńü«Õ▒▒õĖŁŃü½ŃüéŃéŗŃü»ŃüÜŃĆé’╝łŃā×Ńé”Ńé╣ŃéÆŃāēŃā®ŃāāŃé░ŃüÖŃéŗŃü©’╝ō’╝¢’╝ÉÕ║”Ķ”ŗŃéēŃéīŃüŠŃüÖ’╝ēńĢæõ╗Ģõ║ŗŃéÆŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¤µ¢╣Ńü½Ńü¤ŃüÜŃüŁŃéŗŃü©Ķ”¬ÕłćŃü½Ķē▓ŃĆģµĢÖŃüłŃü”õĖŗŃüĢŃéŖŃĆéŃĆīõĖŁõ║ĢÕ║äõ║öķāÄŃüĢŃéōŃü«ŃüŖÕóōŃü»ŃüéŃéŗŃüīŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆŹŃü©ŃĆü […]
µ£ĆĶ┐æŃü«ŃüŖõ╗Ģõ║ŗŃü¦Ķ©śķī▓ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ńē®ŃéÆÕ╣ŠŃüżŃüŗŃĆé’╝łµŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōŃüĀŃüæŃü«ńē®ŃééõĖĆńé╣’╝ē ķÄīÕĆēµ£½µ£¤ÕłĆŃĆüķćŹŃüŁŃüīÕż¦ÕżēÕÄÜŃüÅķēäÕæ│Ńü«ŃéłŃüäĶīÄŃĆé Ķē»ÕłĆŃĆéķŁģÕŖøńÜäŃü¬Õ£░ķēäŃü»ÕāŹŃüŹĶ▒ŖÕ»īŃü½Ńü¬ŃéŗŃĆé ķÄīÕĆēÕēŹµ£¤Õż¬ÕłĆŃĆéÕ░ÅķīĄŃĆé ķÄīÕĆēµ£½µ£¤ńö¤ŃüČĶīÄÕż¬ÕłĆŃĆé ńä╝ŃüŹŃü«ķ½śŃüäõĖüÕŁÉÕż¬ÕłĆŃĆé Õ░æŃĆģĶżćķøæ […]
ńö¤ŃüČĶīÄÕ£©ķŖśŃü«µØźÕøĮõ┐ŖŃĆéÕÅżŃüäńĀöŃüÄŃü«ŃüŠŃüŠµ¢░Ńü¤Ńü½ńÖ║Ķ”ŗŃüĢŃéīŃü¤ŃééŃü«ŃĆéõ║īÕ░║ÕģŁÕ»ĖŃĆéĶīÄŃü«ÕÅŹŃéŖŃééŃüØŃü«ŃüŠŃüŠŃü¦Õż¦ÕżēĶ▓┤ķćŹŃĆéÕøĮĶĪīÕż¬ÕłĆŃĆéµØźŃĆéĶīÄŃü«õ┐ØÕŁśńŖȵģŗŃüīµ£ĆĶē»Ńü¦ķŖśÕŁŚķ««µśÄŃĆéŃüōŃü«µ£¤Ńü«Õż¬ÕłĆŃü»ķćŹÕÄܵä¤ŃüīÕćäŃüäŃĆéÕéÖÕēŹÕøĮķĢĘĶł╣õĮÅÕĘ”Ķ┐æÕ░åńøŻķĢĘÕģēŌ¢ĪŃĆüµŁŻÕ«ēÕ╣┤ń┤ĆŃü«Õ░ÅÕż¬ÕłĆŃĆéõ║īõ╗ŻķĢĘ […]
µ£¼ĶāĮÕ»║Õż¦Õ»Čµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü¦ķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü«ŃĆīõ┐ĪķĢĘŃüīµäøŃüŚŃü¤ÕłĆŃü©ŃüØŃü«µÖéõ╗ŻŃü«ÕłĆÕēŻÕ▒ĢŃĆŹŃü«Õ▒Ģńż║ÕōüŃéÆÕ╣ŠŃüżŃüŗŃüöń┤╣õ╗ŗŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé ÕłĆŃĆĆķŖśŃĆĆĶ¢¼ńÄŗÕ»║’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ēµ░Ėõ║½ķĀāŃĆüõĖēµ▓│Ńü«Ķ¢¼ńÄŗÕ»║õĖƵ┤ŠŃü«õĮ£ÕōüŃü¦ŃüÖŃĆéĶ¢¼ńÄŗÕ»║µ┤ŠŃü«õĮ£ÕōüŃü»ńÅŠÕŁśµĢ░ŃüīÕ░æŃü¬ŃüÅń¦üŃééńĀöńŻ©ŃüŚŃü¤õ║ŗŃü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéÕÉīµ┤Š […]
õ╗ŖÕø×Ńü»µ£¼ķā©ŃüŗŃéēŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆƵŚźµ£¼µĄĘÕü┤Ńü¦ÕÅżŃüäµēĆŃüĀŃü©µĆØŃüåŃĆéŃüäŃüżŃééŃü«ŃéżŃāĪŃā╝ŃéĖŃéłŃéŖŃé╣Ńā×Ńā╝ŃāłŃĆé ’╝ÆÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆÕżÜÕłå’╝æ’╝ĢÕ╣┤Ńü╗Ńü®ÕēŹŃü½µ£¼ķā©ŃüŗŃéēµØźŃü¤Õż¬ÕłĆŃüĀŃü©µĆØŃüåŃĆé ’╝ōÕÅĘŃĆĆÕłĆŃĆĆÕÅŹŃéŖÕ╝ĘŃéüŃü«µ£½ÕÅżÕłĆŃĆéÕłāńĖüŃüīÕāŹŃüÅõĖŁńø┤ÕłāŃĆéÕż¦ÕżēĶē»ŃüäÕ£░ķēäŃüĀŃüīĶéīŃéÆĶŹÆŃüÅńĀöŃüä […]
ÕģłµŚźõĖŖķćÄŃü«ÕŹÜńē®ķż©Ńü¦Õ░Åń½£µÖ»ÕģēŃéÆĶ”ŗŃü”µä¤ÕŗĢŃüŚŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüŃüØŃü«ÕŠīµÖ»ÕģēŃéÆĶ¬┐Ńü╣Ńü”Ńü┐Ńü¤ŃéŖŃé┤ŃéĮŃé┤ŃéĮŃü©ŃĆéµÖ»ÕģēÕż¬ÕłĆŃü»ķ揵¢ćõ╗¢µēŗµīüŃüĪŃüīŃé║ŃéĘŃā¬Ńü©ķćŹŃüäÕÉŹÕōüŃéÆÕ╣ŠŃüżŃüŗńĀöńŻ©ŃüŚŃü¤ŃéŖµŗØĶ”ŗŃüŚŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüōŃü«ÕÉŹÕōüÕłĆńĄĄÕø│ĶüܵłÉŃü«Õ░Åń½£µÖ»ÕģēŃü«Ķ¦ŻĶ¬¼Ńü«ķĆÜŃéŖŃüĀŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖ […]
Ķ½ĖŃĆģŃü«ńö©õ║ŗŃü¦ń¦╗ÕŗĢŃĆé õ╣ģŃĆģŃü½ÕøĮÕ«ØÕ░ÅķŠŹµÖ»ÕģēŃéÆĶ”ŗŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗ŖŃüŠŃü¦Ńü¦µ¢ŁńäČŃĆüõ╗ŖÕø×ŃüīõĖĆńĢ¬ŃéłŃüŗŃüŻŃü¤ŃĆéŃüōŃéōŃü¬Ńü½ŃééŃāæŃā»Ńā╝ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃüŗŃĆéÕćäŃüäµÖ»ÕģēŃü»Õ╣ŠÕÅŻŃüŗµŗØĶ”ŗŃüŚŃü¤ŃéŖńĀöńŻ©ŃéÆŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŵ®¤õ╝ÜŃééÕ║”ŃĆģŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüōŃéīŃü»Õłźµ¼ĪÕģāŃü«ÕŁśÕ£©Ńü¦ŃüÖŃĆéÕÉäµøĖŃü¦Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬Ķ¦Ż […]
µ¢░Õ╣┤Ńü«Õģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝ÜŃü»µ¢░Õ╣┤õ╝ÜŃééÕģ╝ŃüŁŃü”ŃüŖŃéŖµÖéķ¢ōŃü«ķāĮÕÉłŃééŃüéŃüŻŃü”ŃĆü’╝æµ£¼Õģźµ£ŁŃü¦ĶĪīŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃü¤ŃüĀÕłØÕ┐āĶĆģŃüĢŃéōŃü½Ńü»ķĆÜÕĖĖŃü«’╝æµ£¼Õģźµ£ŁŃü¦Ńü»ŃāÅŃā╝ŃāēŃā½Ńüīķ½śķüÄŃüÄŃéŗŃü¤ŃéüŃĆü’╝æ’Į×’╝ĢÕÅĘÕłĆŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü½’╝ōÕĘźŃüźŃüżĶ©śÕģźŃüŚŃĆüµÅÉÕć║Ńü»õĖĆÕ║”Ńü«Ńü┐Ńü©ŃüäŃüåµēŗµ│ĢŃü¦ŃĆéµÖ«µ«ĄŃü©Ńü»ķüĢŃüåµĆØĶĆāŃü©Ńāå […]
õ║¼ķāĮÕøĮń½ŗÕŹÜńē®ķż©Ńü¦Ńü»ńÅŠÕ£©ŃĆīńē╣ķøåÕ▒Ģńż║ŃĆƵ¢░µÖéõ╗ŻŃü«Õ▒▒Õ¤ÄķŹøÕåČŌĆĢõĖēÕōüµ┤ŠŃü©ÕĀĆÕĘص┤ŠŌĆĢŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü¦ŃüÖŃĆéÕĀĆÕĘØńē®Ńü©õĖēÕōüµ┤ŠõĮ£ÕōüŃüīõĖ╗Ńü¬Õ▒Ģńż║Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ńĀöńŻ©ŃéÆŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü¤ŃééŃü«ŃééÕżÜµĢ░Õć║ķÖ│ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕ»║ńżŠÕŠĪµēĆĶöĄŃü«ŃééŃü«ŃéÆķÖżŃüŹµēŗÕģāŃü½µŖ╝ÕĮóĶ©śķī▓ŃüīŃüéŃéŗ […]
ŃüŖµŁŻµ£łŃü¬Ńü«Ńü¦µÖ«µ«ĄõĮ┐ŃüäŃü«Õłāńē®Ńü©ŃüŚŃü”ŃāŖŃéżŃāĢŃéÆĶ▓ĘŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüäŃüŻŃü¤ŃüäÕ╣┤ķ¢ōÕ╣ŠŃüżŃü«ĶŹĘńē®ŃéÆŃāŖŃéżŃāĢŃü¦ķ¢ŗÕ░üŃüÖŃéŗŃüŗÕłåŃüŗŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüŃüŗŃü¬ŃéŖķĀ╗ń╣üŃü¦ŃüÖŃĆéńĀöŃüÄŃü«ķüōÕģĘŃéÆõĮ£ŃüŻŃü¤ŃéŖõĮĢŃüŗŃéÆÕēŖŃü¤ŃéŖŃĆüµŚźŃĆģÕłāńē®ŃéÆõĮ┐ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕłāĶēČŃéÆÕłćŃéŗńö©Ńü«Õ░ÅÕłĆŃéÆõĮ┐Ńüåõ║ŗŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆü […]
ŃüéŃüæŃüŠŃüŚŃü”ŃüŖŃéüŃü¦Ńü©ŃüåŃüöŃü¢ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµ£¼Õ╣┤ŃééŃü®ŃüåŃü×ŃéłŃéŹŃüŚŃüÅŃüŖķĪśŃüäŃüäŃü¤ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé µ¢░Õ╣┤’╝æµ£ł’╝ŚµŚźŃüŗŃéēŃĆüµ£¼ĶāĮÕ»║Õż¦Ķ│ōµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü½ŃüŖŃüŹŃüŠŃüŚŃü”ŃĆīõ┐ĪķĢĘŃü«µäøŃüŚŃü¤ÕłĆŃü©ŃüØŃü«µÖéõ╗ŻŃü«ÕłĆÕēŻÕ▒ĢŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕ▒Ģńż║ÕłĆÕēŻŃü»õĖŗĶ©śŃü¬Ńü®Ńü¦ŃüÖŃĆé ŃĆĆÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆƵŚźÕĘ×ÕÅżÕ▒ŗõ╣ŗ […]
õ╗ŖÕ╣┤ŃééŃĆüÕåŹÕłāŃü«ÕłĆŃĆüµł¢ŃüäŃü»ÕåŹÕłāŃü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗÕłĆŃĆüÕåŹÕłāŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃüīÕĆŗõ║║ńÜäŃü½ńĄČÕ»ŠÕåŹÕłāŃüĀŃü©µĆØŃüåÕłĆŃĆüŃüŠŃü¤ŃĆüÕåŹÕłāŃü©ŃüäŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüīÕĆŗõ║║ńÜäŃü½Ńü»ÕåŹÕłāŃü¦Ńü»ńäĪŃüäÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃéƵä¤ŃüśŃéŗÕłĆŃü¬Ńü®Ķē▓ŃĆģĶ”ŗŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵜öŃü½µ»öŃü╣ÕåŹÕłāÕłżÕ«ÜŃü»µ¢ŁńäČńöśŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃü©µä¤ŃüśŃü”ŃüäŃüŠ […]
’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃā╗ÕłĆÕÅŹŃéŗŃĆéÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐ŃĆéÕ£░ķēäŃü»ÕÅżŃüÅĶ”ŗŃüłŃéŗŃĆéĶģ░Õ░æŃĆģĶŹÆŃéīŃĆ鵜ĀŃéŖÕ╝ĘŃüäŃĆéĶŗźÕ╣▓Ķ¦ÆŃü░Ńéŗõ║ÆŃü«ńø«ŃüīÕģ©õĮōŃü½ŃĆéńēćĶÉĮŃüĪķó©Ńü¦ŃééŃüéŃéŖŃĆüÕ░æŃĆģķĆåŃüīŃüŗŃéŗķó©ŃééŃĆéĶģ░Ńü«µł┐Ńü»ń┤░ŃüŗŃüÅõĖŁń©ŗŃü½ŃüŗŃüæŃü”Õż¦ŃüŹŃüÅŃü¬ŃéŗŃĆ鵤Šµ░ŚńäĪŃüŚŃĆ鵜ĀŃéŖŃü»ńä╝ŃüŹķĀŁŃüŗŃéēõĖŖŃüīŃéŗŃĆéÕÅżŃüÅĶ”ŗŃüłŃéŗŃüīŃĆüÕĘ« […]
ÕéÖÕēŹńē®ŃĆüÕ┐£µ░ĖÕ╣┤ń┤ĆŃĆüńö¤ĶīÄŃü«Õż¬ÕłĆŃéƵŗØĶ”ŗŃĆéÕłāķĢĘõ║īÕ░║õĖēÕ»ĖõĖāÕłåŃĆüÕÅŹŃéŖõĖĆÕ»ĖõĖĆÕłåŃĆéķćŹŃüŁŃü»ń┤ä’╝śŃā¤Ńā¬ŃĆéŃü©Ńü½ŃüŗŃüŵĖøŃüŻŃü”ŃüäŃü¬ŃüäÕ«īńƦŃü¬Õż¬ÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆéõĖŖĶ║½Ńü»ŃééŃüĪŃéŹŃéōŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüĶīÄŃü«Ķē»ŃüĢŃü½ķ®ÜŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕéÖŃü«ńø┤ŃüÉõĖŖŃü½Õż¬ÕłĆķÉöŃü«ĶĘĪŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃéīõ╗źÕż¢Ńü»ķØ×ÕĖĖŃü½ńŖȵģŗ […]
Õ║”ŃĆģµøĖŃüäŃü¤õ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüµ£½ÕéÖÕēŹŃü½Ńü»ŃüéŃüŠŃéŖķ¢óÕ┐āŃüīŃü¬ŃüÅõ╗ŖŃüŠŃü¦µØźŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĮĢµĢģŃü©ŃüäŃüåńÉåńö▒Ńü»ÕłåŃüŗŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüŌĆØÕż¦ÕÆīńē®ŃüīÕźĮŃüŹŌĆØŃĆüŃü┐Ńü¤ŃüäŃü¬ŃééŃü«ŃüĀŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ńÉåńö▒Ńü»Ńü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéŃüéŃĆüõĖĆŃüżõĖŖŃüÆŃéŗŃü¬ŃéēŃü░ŃĆüµł”ÕøĮµŁ”Õ░åÕźĮŃüŹŃüśŃéāŃü¬ŃüäŃüŗŃéēŃüŗ […]
Ķē▓ŃéōŃü¬ńĄīńĘ»ŃüīŃüéŃüŻŃü”ŃĆüÕż¦ķś¬ÕŹŚÕĀƵ▒¤Ńü½ŃüéŃéŗŃĆīSTUDIO GIVEŃĆŹŃüĢŃéōŃü½ŃüŖķé¬ķŁöŃüŚŃü”ŃĆüŃé½ŃāĪŃā®Ńā×Ńā│Ńü«ķćÄńö░µŁŻµśÄŃüĢŃéōŃü½ŃéłŃéŗÕłĆŃü«µÆ«ÕĮ▒ŃéÆĶ”ŗÕŁ”ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶ®│ń┤░Ńü»µøĖŃüŹŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüŃéäŃü»ŃéŖŃāŚŃāŁŃü«ŌĆØŃüōŃüĀŃéÅŃéŗŌĆØõ╗Ģõ║ŗŃü»ÕćäŃüäŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆéŃü©Ńü½ŃüŗŃüÅõĮĢŃüŗŃéēõĮĢ […]
ÕÅżķØƵ▒¤Ńü«Õ«łµ¼Ī├Ś’╝Æ’╝īńé║µ¼ĪŃĆüĶ▓×µ¼ĪŃĆüÕīģµ¼ĪŃĆüĶĪīµ¼ĪŃĆüńäĪķŖśÕÅżķØƵ▒¤Ńü©Õ”╣Õ░ŠĶĪīÕøĮŃéÆķææĶ│×ŃĆéÕÅżķØƵ▒¤Ńü«Õ£░ķēäŃü»ńĖ«ńĘ¼ĶéīŃü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃéŗńŗ¼ńē╣Ńü«ķó©ÕÉłŃüäŃüīńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃĆüĶ¬īõĖŖķææÕ«ÜŃü¦Ńü»ŃĆīńŗ¼ńē╣Ńü«ĶéīÕÉłŃüäŃéÆÕæłŃüŚŃĆŹŃü¬Ńü®Ńü«µ¦śŃü½ŃĆüµÜŚŃü½ńĖ«ńĘ¼ĶéīŃü©ÕłåŃüŗŃéŗŃā»Ńā╝ŃāēŃü¦ÕÅżķØƵ▒¤ŃüĖŃü©Ķ¬śÕ░ÄŃüĢŃéīŃéŗŃü¤ŃéüŃĆü […]
Ķ┐æÕ╣┤µ¢░Ńü¤Ńü½Õć║ńÅŠŃüŚŃü¤Õģźķ╣┐ń¤ŁÕłĆŃü«µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃééŃüŚŃéäŃü©µĆØŃüäĶ¬┐Ńü╣Ńü”Ńü┐ŃéŗŃü©ÕģēÕ▒▒µŖ╝ÕĮóŃü½µÄ▓Ķ╝ēŃü«ÕŠĪÕōüŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéÕ░ŖŃüäŃĆé õ╗źõĖŗµēĆĶ”ŗŃĆé ń¤ŁÕłĆŃĆĆķŖśŃĆĆŌ¢Īķ╣┐õĮÅĶŚżÕĤջ”Ō¢Ī’╝łÕģźķ╣┐õĮÅĶŚżÕĤջ”ńČ▒’╝ÜÕģēÕ▒▒µŖ╝ÕĮóµēĆĶ╝ē)ÕłāķĢĘ 25.5ŃÄØ’╝łÕģ½Õ»ĖÕøøÕłåõ║īÕÄś’╝ēŃĆĆÕāģ […]
Õģźķ╣┐Õ║äŃüöÕć║Ķ║½Ńü«µ¢╣ŃüŗŃéēŃĆüń┤ĆÕĘ×ķē▒Õ▒▒Ńü¦µÄĪµÄśŃüĢŃéīŃü¤ķē▒ń¤│ŃéÆķĀ鵳┤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃü¬ŃéōŃü©ŃüŖńłČµ¦śŃüīń┤ĆÕĘ×ķē▒Õ▒▒Ńü«ĶüĘÕōĪŃéÆŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¤ŃüØŃüåŃü¦ŃĆéŃüōŃü«Õ£░Õ¤¤ŃüŗŃéēŃü»µ¦śŃĆģŃü¬ķē▒ńē®ŃüīµÄĪŃéīŃĆüń┤ĆÕĘ×ķē▒Õ▒▒Ńü¦Ńü»ķŖģķē▒ń¤│Ńü¬Ńü®ŃüīµÄĪµÄśŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¤ŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéÕģźķ╣┐ķŹøÕåČŃüīÕźĮŃüŹŃü¬ń¦üŃü»Õģźķ╣┐Ńü½µēĆńĖü […]
ŃĆīµ│ĢķÜåÕ»║Ķź┐Õ£ōÕĀéÕźēń┤ŹµŁ”ÕÖ©ŃĆŹŃü«Õø│ńēłŃü½Ķ╝ēŃéŗķ”¼µēŗÕĘ«µŗĄŃéƵĢ░ŃüłŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃéēŃĆüķלŃüĀŃüæŃü«ńē®Ńü©µŗĄÕģ©õĮōŃüīµ«ŗŃéŗŃééŃü«ŃéÆÕÉłŃéÅŃüøŃéŗŃü©’╝æ’╝śÕÅŻŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé’╝łĶź┐ÕååÕĀéŃü½µ«ŗŃüĢŃéīŃü¤ÕłĆÕēŻķĪ×Ńü»ńĘŵĢ░’╝¢’╝Ģ’╝É’╝ÉÕÅŻŃü©ŃééŃüäŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕø│ńēłŃü½Ķ╝ēŃéŗµŗĄ’╝łķלŃü«Ńü┐ÕɽŃéü’╝ēŃü»’╝ō’╝É’╝ÉŃü½µ║ĆŃü¤ […]
µ¤ÉÕłĆÕ▒ŗŃüĢŃéōŃü«ÕŗĢńö╗Ńü¦µ¤äµø▓ŃüīŃéŖ’╝łµī»Ķó¢ĶīÄ’╝ēŃü«ń¤ŁÕłĆŃéäķ”¼µēŗµīć’╝łÕÅ│µēŗµīć’╝ēŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«ÕåģÕ«╣ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéķ”¼µēŗµīćŃü©Ńü»ŃĆüõĮōŃü«ÕĘ”Õü┤Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅÕÅ│Ķģ░Ńü½ÕĘ«ŃüÖńē®Ńü©ŃüäŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃéŗĶģ░ÕłĆŃü«õĖĆŃüżŃü¦ŃüÖŃĆéķ”¼µēŗµīćµŗĄŃü«ńÅŠÕŁśÕōüŃü»Õ░æŃü¬ŃüÅŃĆüŃüØŃü«õĮ┐ńö©µ│ĢŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«Ķ©śķī▓ŃééÕ░æŃü¬ŃüäŃüōŃü© […]
õ╗ŖÕø×Ńü»ÕĮōńĢ¬Ńü¦ŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦õ╗źõĖŗŃü«ķææÕ«ÜÕłĆŃü½Ńü”Õģźµ£ŁķææÕ«ÜŃéÆĶĪīŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆńäĪķŖśŃĆĆńČŠÕ░ÅĶĘ»ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ē’╝ÆÕÅĘŃĆĆĶäćÕĘ«ŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆĶČŖõĖŁÕ«łµŁŻõ┐ŖŃĆĆŃĆĆŃĆĆ’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ēŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕ»øµ░ĖõĖēÕ╣┤Õģ½µ£łÕÉēµŚź’╝ōÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕĘ”ĶĪīń¦Ć’╝łĶŖ▒µŖ╝’╝ēŃĆĆ […]
õĮ┐ŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Õ«ÜĶ”ÅŃüīŃüéŃüŠŃéŖŃü½Ńü┐ŃüÖŃü╝ŃéēŃüŚŃüŗŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦µ¢░Ńü¤Ńü½õĮ£ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ÕłĆĶ║½Ńü½Õ«ÜĶ”ÅŃéÆĶ¦”ŃéīŃüĢŃüøŃüÜŃĆüÕłāµ¢ćŃü«ķ½śŃüĢŃéƵĖ¼ŃéŖŃü¬ŃüīŃéēÕÉīŃüśķ½śŃüĢŃü«Õłāµ¢ćŃéƵÅÅŃüÅŃüōŃü©ŃüīÕć║µØźŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤Õ«ÜĶ”ÅŃéƵ©¬Ńü½ÕŗĢŃüŗŃüŚŃü¬ŃüīŃéēõĮŹńĮ«µ▒║ŃéüŃüŚŃü”ĶĪīŃüÅŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüõ║ÆŃü«ńø«ŃéäĶ░ĘŃü«Õ╣ģŃü¬Ńü®ŃéƵŁŻńó║ […]
µ£ĆĶ┐æŃééµÖéķ¢ōŃéÆõĮ£ŃéŖŃĆüµŖ╝ÕĮóõĮ£µźŁŃü»ĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéĶ┐æŃüäŃü©ŃüōŃéŹŃü¦Ńü»ŃĆüÕż¦ķüōŃĆüÕ»┐ÕæĮÕ«ŚÕÉēŃĆüÕÅżķćæÕēøÕģĄĶĪøŃĆüÕøĮĶ▓×ń│╗Õż¦ķś¬µ¢░ÕłĆŃĆüĶČŖõĖŁŃĆüń╣üµģČŃĆüń┤ĆÕĘ×µ£½ÕÅżÕłĆŃĆüĶéźÕēŹÕÉēµł┐ŃĆüÕÅżķØƵ▒¤ĶĪīµ¼ĪŃĆüÕÅżÕéÖÕēŹõ┐ĪÕģēŃĆüÕīģµ░ĖŃĆüÕīģµĖģŃĆüÕĘ”µ¢ćÕŁŚŃü¬Ńü®ŃéÆŃĆéķĢĘÕ╣┤µŖ╝ÕĮóŃéƵÅÅŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü©Õłāµ¢ćŃü«Ķ¬┐ÕŁÉŃü© […]
µ¤ÉŃé│Ńā¼Ńé»ŃéĘŃā¦Ńā│Ńü«ń╣üµģČŃéÆńĀöńŻ©ŃĆéĶ┐æÕ╣┤Ńü¤ŃüŠŃü¤ŃüŠń╣üµģČŃéÆĶ”ŗŃéŗµ®¤õ╝ÜŃüīÕżÜŃüÅŃĆü’╝Ś’╝ī’╝śÕÅŻµŗØĶ”ŗŃüŚŃü¤Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéń╣üµģČŃü©ŃüäŃüåŃü©ÕēćķćŹŃü«µØŠńÜ«ĶéīŃü«µ¦śŃü¬Õż¦µØ┐ńø«Ķéīń½ŗŃüżŃéżŃāĪŃā╝ŃéĖŃéƵīüŃüżŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕ«¤ķÜøŃü»ŃüØŃéīŃü░ŃüŗŃéŖŃü¦Ńü»ńäĪŃü䵦śŃü¦ŃĆüĶ┐æÕ╣┤µŗØĶ”ŗŃüŚŃü¤ń╣üµģČŃü«ÕżÜŃüÅŃü»ŃéłŃüÅĶ®░Ńéō […]
µĢ░Õ╣┤ÕēŹ’╝ś’╝ĢµŁ│Ńü¦õ║ĪŃüÅŃü¬ŃüŻŃü¤õ╝»µ»ŹŃü»ĶŗźŃüäŃüōŃéŹÕź│Õä¬ŃüĢŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéń¦üŃüīń¤źŃéŗõ╝»µ»ŹŃü»ŃĆüŃü©Ńü½ŃüŗŃüÅĶÅ»ŃüīŃüéŃéŗŌĆصØ▒õ║¼Ńü«ŃüŖŃü░ŃüĢŃéōŌĆØŃĆéŃüäŃüżŃééń¤źńÜäŃü¦µśÄŃéŗŃüÅŃĆüÕåŚĶ½ćŃéÆĶ©ĆŃüŻŃü”Ńü»Ķ╗ĮŃüÅĶĖŖŃüŻŃü”Ķ”ŗŃüøŃü”ŃüÅŃéīŃéŗõ║║ŃĆéÕ░ÅŃüĢŃüäŃüōŃéŹŃüŗŃéēŌĆØõ╝»µ»ŹŃüĢŃéōŃü»Õź│Õä¬ŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ŌĆØŃü©Ńü»ń¤źŃüŻŃü”Ńüä […]
ńĪ¼Ńüäµ£½ÕÅżÕłĆŃü«õ╗ĢõĖŖŃüÆŃĆéŃü©Ńü½ŃüŗŃüÅŃü▓Ńü¤ŃüÖŃéēńĪ¼ŃüÅŃĆüÕåģµøćŃéŖŃüīÕŖ╣ŃüŹŃüźŃéēŃüäŃĆéŃüōŃüåŃüäŃüåÕłĆŃü»Õ£░ĶéīŃüīĶē»ŃüÅÕć║Ńéŗõ║ŗŃüīÕżÜŃüÅŃĆüõ╗ŖÕø×Ńééń┤░ŃüŗŃüÅÕ£░µ▓ĖŃüīõ╗śŃüŹŃĆüŃéĘŃāŻŃéŁŃāāŃü©ń░ĪÕŹśŃü½µÖ┤ŃéīŃéŗŃĆéŃü¤ŃüĀÕłāĶēČŃüīÕŖ╣ŃüŗŃü¬ŃüäŃü«Ńü¦ŃéłŃüÅķüĖŃü░Ńü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃüÜŃĆéÕłāµ¢ćŃééŃü©ŃéŖŃü©ŃéüŃü«Ńü¬ŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃĆü […]
Õ░æŃüŚÕēŹŃĆüķüÄÕÄ╗õĮĢÕ║”ŃüŗµŗØĶ”ŗŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕłĆŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐ńĀöŃüÄŃü¦µ£ēÕÉŹŃü¬ńĀöÕĖ½ŃüīńĀöŃüäŃüĀŃééŃü«ŃéÆõ╣ģŃĆģŃü½µŗØĶ”ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕÅżŃüäńĀöŃüÄŃĆéÕżÜÕ░æŃü«ŃāÆŃé▒ŃéäµøćŃéŖŃü»µ£ēŃéŗŃüīńŖȵģŗŃü»Ķē»ÕźĮŃĆéĶē▓ŃĆģĶĆāŃüłŃü¬ŃüīŃéēŃüśŃüŻŃüÅŃéŖŃü©õĮĢÕ║”ŃééµŗØĶ”ŗŃĆéŃü©Ńü½ŃüŗŃüÅõĖŖµēŗŃüäńĀöŃüÄŃü¦ŃĆüõ╗źÕēŹµŗØĶ”ŗŃüŚŃü¤Ńü©ŃüŹŃü« […]
ŃĆÄŃĆīµäøÕ«ĢÕ▒▒Ńü»ńĀźń¤│Õ▒▒ŃĆŹµäøÕ«ĢÕ▒▒ńĀźń¤│ŃéÆń¤źŃéŗõ║║ŃĆģŃü«Ķ©╝Ķ©ĆŃĆÅDVDŃéÆŃüŖķĆüŃéŖķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ铵Śźµ£¼ÕłĆ”Ńü»ŃĆüµäøÕ«ĢÕ▒▒Õæ©ĶŠ║ŃéÆÕ¦ŗŃéüŃü©ŃüÖŃéŗõ║¼ķāĮńöŻÕż®ńäČńĀźń¤│ŃüīńäĪŃüæŃéīŃü░Õ«īµłÉŃüŚŃüŠŃüøŃéōŃĆéńÅŠÕ£©µłæŃĆģŃüīÕłĆŃü«ńŠÄŃüŚŃüäÕ£░ĶéīŃéäÕłāµ¢ćŃéÆķææĶ│×Ńü¦ŃüŹŃéŗŃü«Ńü»ŃĆü […]
ŃüŚŃü░ŃéēŃüÅÕēŹŃĆüķīåĶ║½Ńü¦µźĄõĖĆķā©Ńü½ÕģēŃéŗń«ćµēĆŃéÆŃü┐ŃéŗÕłĆŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕāģŃüŗŃü½Ķ”ŚŃüÅÕ£░ÕłāŃüŗŃéēŃü»ķīĄŃü«µśÄŃéŗŃüäµ┐ĆŃüŚŃüäÕć║µØźŃüīńó║Ķ¬ŹŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéĶ║½Õ╣ģŃü»’╝öŃÄØõ╗źõĖŖŃüéŃéŖŃĆüķļŃüīķ½śŃüÅŃĆüķĢĘÕ»ĖŃĆüĶČģÕż¦ķŗÆŃü«Ķ▒¬ÕłĆŃĆéńäĪķŖśŃü¦ķĢĘŃüäĶīÄŃĆéĶīÄŃü«ķīåŃü»µĄģŃüÅŃüŠŃüĀÕģ©õĮōŃü½ķŖĆĶē▓Õæ│ŃéƵ«ŗŃüŚŃĆüµ¢░ŃĆģÕłĆŃü« […]
ŃüĪŃéćŃüŻŃü©õ╣ģŃĆģŃü½ńÄēńĮ«ńź×ńżŠŃü½ŃĆéÕåÖń£¤Ńü»ńÄēńĮ«Õ▒▒Ńü«ķüōõĖŁŃüŗŃéēŃĆéõĖ¢ńĢīķü║ńöŻŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”õ╗źķÖŹÕÅéµŗØĶĆģŃüīÕóŚŃüłŃĆüÕ▒▒ķüōŃü½µģŻŃéīŃü¬ŃüäķüŗĶ╗óĶĆģŃééÕżÜŃüÅÕ»ŠÕÉæĶ╗ŖŃü½µ│©µäÅŃüŚŃü¬ŃüäŃü©ÕŹ▒ķÖ║Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«µŚźŃééÕēŹÕŠīĶ╝¬Ńü©ŃééĶä▒Ķ╝¬ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗĶ╗ŖŃüīŃĆéŃĆé µ£ĆĶ┐æŃü»ŃĆīÕæ╝Ńü░ŃéīŃü¬ŃüæŃéīŃü░ĶŠ┐ŃéŖńØĆŃüæŃü¬Ńüäńź×ńżŠŃĆŹ […]
µ¢░ÕłĆµ£¤ŃĆüĶéźÕēŹÕłĆŃü«µĢ░Ńü»Õ£¦ÕĆÆńÜäŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«µ«åŃü®Ńü»Õ┐ĀÕÉēÕ┐ĀÕ║āŃĆüµŁŻÕ║āĶĪīÕ║āŃü¦ŃüÖŃĆéŃüØŃéīŃü½µ¼ĪŃüÉŃü«ŃüīÕ┐ĀÕøĮŃéäÕ«Śµ¼ĪŃü¬Ńü®Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéķüÄÕÄ╗Ńü½ÕÉēµł┐ŃéÆńĀöńŻ©ŃüŚŃü¤õ║ŗŃü»Ńü¬ŃüÅŃĆüµēŗŃü½ÕÅ¢ŃéŗŃü«ŃééÕłØŃéüŃü”ŃüĀŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕģāŃü»ķīåĶ║½ŃĆéĶéźÕēŹŃü«õĖüÕŁÉŃü¦ńÅŠÕ£©ÕåģµøćŃéŖŃĆéŃééŃüåÕÅżÕłĆŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆé […]
ķīåĶ║½Ńü«µ£½ÕÅżÕłĆÕ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃü«ń¬ōķ¢ŗŃüæŃĆéÕłāķĢĘ’╝¢Õ»Ė’╝öÕłåŃĆéÕģāķćŹ7.7mmŃĆéµ£½ÕÅżÕłĆŃü½ŃéłŃüÅŃüéŃéŗõĖŖĶ║½ŃüīÕ░ŵī»ŃéŖŃü¬Ńü«Ńü¦ĶīÄŃüīŃéäŃüæŃü½Õż¦ŃüŹŃüÅĶ”ŗŃüłŃéŗń¤ŁÕłĆŃĆé õĖĆĶł¼Ńü½ń¤ŁÕłĆŃéƵŖ╝ÕĮóŃü½ŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕłāÕī║Ńü½Õ»ŠŃüŚµŻ¤Õī║Õü┤ŃüīŃüŗŃü¬ŃéŖµĘ▒ŃüäµŖ╝ÕĮóŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃéīŃü»ŃĆüµŻ¤Õī║Ńü«µĘ▒ŃüĢŃü½ÕŖĀŃüł […]
ķÄīÕĆēµ£½µ£¤Ńü«ĶæŚÕÉŹÕĘźŃü«Õ╝¤ÕŁÉŃü©ŃüäŃéÅŃéīŃéŗÕłĆÕĘźŃü«ŃĆüµ¢░Õć║ńÅŠŃü«Õ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃéÆńĀöńŻ©ŃĆéÕ£©ķŖśŃü«ÕōüŃü»ÕāģŃüŗŃüŚŃüŗńó║Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéēŃüÜÕż¦ÕżēĶ▓┤ķćŹŃü¬ÕōüŃĆéÕźćĶĘĪńÜäŃü¬Ńā¼ŃāÖŃā½Ńü½ńĀöŃüĵĖøŃéŖŃüīÕ░æŃü¬ŃüäŃü¤ŃéüŃĆüÕłāÕī║µŻ¤Õī║Ńü©ŃééķØ×ÕĖĖŃü½µĘ▒ŃüäŃĆéõĖĆĶł¼Ńü½µĄüķĆÜŃüÖŃéŗÕÅżŃüäńē®Ńü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕ¤║µ£¼ńÜäŃü½Ńü»ńĀöŃüĵĖøŃüŻ […]
ķÄīÕĆēµÖéõ╗Żµ£½µ£¤Ńü«ÕéÖÕēŹńē®Õ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃü«ńĀöńŻ©ŃĆéõĖŁńø┤ÕłāŃü¦ŃüÖŃüīŃüØŃéīŃü¬ŃéŖŃü«ńĀöŃüĵĖøŃéŖŃüīŃüéŃéŖŃĆüĶģ░Ńü©ÕģłŃü«ÕłāÕ╣ģŃüīĶÉĮŃüĪŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕ£░ķēäŃü»ĶŻÅŃü«ÕģāÕģłõ╗źÕż¢ŃéäĶĪ©Ńü«ÕģłŃü½ńÜ«ķēäŃüīµ«ŗŃéŖŃĆüŃüØŃü«ķēäŃü»ŃéłŃüÅĶ®░ŃéōŃü¦Õ╝ĘŃüÅńŠÄŃüŚŃüäÕ£░ķēäŃü¦ŃüÖŃĆ鵫ŗÕ┐ĄŃü¬ŃüīŃéēŃüØŃéīõ╗źÕż¢Ńü«ÕżÜŃüÅŃü«ń«ćµēĆŃü»ńÖĮŃüäÕ░ÅÕéĘ […]
’╝Śµ£łŃü»µ£¼ķā©ŃüŗŃéēŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆķÖ░Ńü«Õż¬ÕłĆŃĆéµÖéõ╗ŻŃĆüÕøĮŃĆüµĄüµ┤ŠŃü½ńē╣ÕŠ┤ńÜäŃü¬ÕÅŹŃéŖŃĆéÕ£░µ¢æķó©Ńü½µśĀŃéŖŃĆéÕ░ÅķīĄÕć║µØźŃü¦ń┤░ńø«Ńü½ńä╝ŃüŹÕć║ŃüŚŃĆüõĖŖŃü»Õ£░ŃéłŃéŖÕłāÕ╣ģŃüīÕ║āŃüäŃĆéÕ░ÅŃüĢŃüÅĶ®░ŃüŠŃéŗķŗÆŃĆéÕĖĮÕŁÉµĘ▒ŃüäŃĆé ’╝ÆÕÅĘŃĆĆÕłĆÕ░æŃĆģķļķ½śŃĆéÕÅŹŃéŖµĄģŃéüŃĆéĶ║½Õ╣ģÕ║āŃüÅÕż¦ŃüŹŃüäÕłćŃüŻÕģłŃĆéńø┤ŃüÉĶ¬┐Ńü©õ║ÆŃü« […]
Ķ¢äķīåĶ║½Ńü«ŃüŠŃüŠķćŹÕłĆµīćÕ«ÜŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤Õģ½µ¢ćÕŁŚķĢĘńŠ®ŃéƵśöķćŹÕłĆµīćÕ«ÜÕ▒ĢŃü¦Ķ”ŗŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüéŃü«µÖéµöŠŃü¤ŃéīŃü”ŃüäŃü¤ńĢ░µ¦śŃü¬Ńé¬Ńā╝Ńā®ŃüīĶ©śµåČŃü½µ«ŗŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆ鵥ĘÕż¢Ńü½Õć║Ńü”ĶĪīŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüń½ŗµ┤ŠŃü¬ŃüŖĶĆāŃüłŃéÆŃüŖµīüŃüĪŃü«µ¢╣Ńü«ÕģāŃü¦Õż¦ÕłćŃü½ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃĆé’╝łÕŗĢńö╗Ńü»µŚźµ£¼Ķ¬×ÕŁŚÕ╣ĢŃü«Ķ©Ł […]
youtubeŃāüŃāŻŃā│ŃāŹŃā½ŃĆīµŚźµ£¼ÕłĆŃü«ńŠÄŃĆŹŃü½ŃĆüÕłĆŃü«õĖ¢ńĢīŃü«µ¦śŃĆģŃü¬Ńé©ŃāöŃéĮŃā╝ŃāēŃéÆĶē▓ŃéōŃü¬ńÜåŃüĢŃéōŃü½ŃüŖõ╝ØŃüłõĖŗŃüĢŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃĆüµ╝½ńö╗Õ«ČŃü«ŌĆØŃüŗŃüŠŃü¤ŃüŹŃü┐ŃüōÕģłńö¤ŌĆØŃüīÕć║µ╝öŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéń┤ĀµĢĄŃü¬ŃüŖĶ®▒Ńü¬Ńü«Ńü¦µś»ķØ×ŃüöĶ”¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüä’Į×ŃĆé ’╝Æ’╝É’╝æ’╝¢Õ╣┤ķĀāŃĆüipadŃü¦Ńü¦ŃüŚŃü¤ […]
ńå▒ńö░ńź×Õ««Ńü½Ńü”ŃĆīńå▒ńö░ńź×Õ««ÕłĆÕēŻõĖ”µŖĆĶĪōÕźēń┤ŹÕźēĶ│øõ╝ÜŃĆŹŃü½ŃéłŃéŗÕłĆÕēŻŃü«ĶŻĮõĮ£Õźēń┤ŹŃüīµ»ÄÕ╣┤ĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕ╣┤ŃééńäĪõ║ŗńä╝ŃüŹÕģźŃéīŃüīńĄéŃéÅŃüŻŃü¤ŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéõ╗ŖÕ╣┤Ńü«ńĢ¬ķŹøÕåČŃü»õĖŖńĢĀÕ«Śµ│░ÕłĆÕīĀŃĆéńå▒ńö░ńź×Õ««ÕóāÕåģŃü½ķŹøÕåČÕĀ┤ŃéÆĶ©ŁÕ¢ČŃüŚŃĆüÕ«īÕģ©ÕÅżÕ╝ÅķŹøķī¼Ńü¦ÕāģŃüŗõĖēµŚźķ¢ōŃü¦ķŹøķī¼ŃüŗŃéēńä╝ […]
ńö¤ŃüČĶīÄÕ£©ķŖśŃü«ÕÅżÕéÖÕēŹÕż¬ÕłĆŃĆéÕÅżÕéÖÕēŹÕłĆÕĘźõĖŁŃü«ń©ĆÕ░æķŖśŃĆéÕģ©õĮōŃü½ńĀöŃüÄń¢▓ŃéīŃü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕĮōÕłØŃü«ķø░Õø▓µ░ŚŃéƵ«ŗŃüÖÕ░Åõ╣▒ŃéīÕłāŃü«ń»äÕø▓ŃééÕ║āŃüäŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚõ╗źÕēŹńĀöńŻ©ŃüŚŃü¤ńĀöÕĖ½ŃüīŃüéŃüŠŃéŖŃü½ķģĘŃüÅŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆéŃü©ŃéŖŃüéŃüłŃüÜŃĆüÕåģµøćŃéŖŃĆüÕ£░ĶēČŃĆüµŗŁŃüäŃĆüÕłāÕÅ¢ŃéŖńŁēõĖĆķĆŻŃü«õ╗ĢõĖŖŃüÆŃéÆńĄīŃü”ŃüäŃéŗ […]
’╝łõ╗źõĖŗÕģ©µŚźµ£¼ÕłĆÕīĀõ╝ÜHPŃéłŃéŖĶ╗óĶ╝ē’╝ē ŃĆÉõ╝ܵ£¤ŃĆæ2024Õ╣┤7µ£ł10µŚź’Į×7µ£ł15µŚźŃĆÉõ╝ÜÕĀ┤ŃĆæõ║¼ķāĮķ½ÖÕ│ČÕ▒ŗS.C(ńÖŠĶ▓©Õ║Ś)6ķÜÄńŠÄĶĪōńö╗Õ╗ŖŃĆÉŃé«ŃāŻŃā®Ńā¬Ńā╝ŃāłŃā╝Ńé»ŃĆæ7µ£ł13µŚź(Õ£¤)15µÖé’Į× ŃĆƵ£łÕ▒▒ķŹøÕåČŃü»ķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻÕłØµ£¤Ńü«ķ¼╝ńÄŗõĖĖŃéÆńź¢Ńü©ŃüŚŃĆüÕźźÕĘ×µ£łÕ▒▒Ńü«ķ║ō […]
ķ׏ķ”¼ķ¢óŃü«ÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃüŚŃü”ŃüäŃü”ń¢▓ŃéīŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃĆüÕżĢµ¢╣ŃüŖµĢŻµŁ®Ńü½ŃĆéŃüøŃüŻŃüŗŃüÅŃü¬Ńü«Ńü¦ÕÅĪķø╗Ńü½õ╣ŚŃéŖķ׏ķ”¼Ńü½ĶĪīŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ķ׏ķ”¼Õ»║ŃĆéõĮĢÕ╣┤ŃüČŃéŖŃü¦ŃüŚŃéćŃüŗŃĆé ķØÆŃüäń┤ģĶæēŃüīńČ║ķ║ŚŃü¦ŃüÖŃĆéÕÅĪÕ▒▒ķø╗Ķ╗ŖŃü¦Ńü»ń¦ŗŃü«ń┤ģĶæēŃü«Ńā®ŃéżŃāłŃéóŃāāŃāŚŃüīń¤źŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüµ¢░ńĘæŃü«Ńā®ŃéżŃāł […]
ÕłĆŃĆĆķŖśŃĆĆõ┐Īµ┐āÕøĮń£¤ķøäõ┐ĪÕĘ×ĶĄżÕ▓®µØæŃü«ÕÉŹõĖ╗ŃĆüÕ▒▒µĄ”µ▓╗ÕÅ│ĶĪøķ¢ĆµśīÕÅŗŃü«ķĢĘńöĘŃü©ŃüŚŃü”ńö¤ŃüŠŃéīŃéŗŃĆ鵣ŻÕēćŃĆüÕ»┐Õ«łŃĆüÕ«īÕł®ŃĆüÕ»┐µśīŃĆüµŁŻķøäŃĆüń£¤ķøäŃĆüÕ»┐ķĢĘŃü¬Ńü®Ńü«ķŖśŃéÆÕłćŃéŖŃĆüÕ╝¤Ńü½µĖģķ║┐ŃüīŃüäŃéŗŃĆé Õ░ÅÕłĆŃĆĆķŖśŃĆĆõ┐ĪÕĘ×õĮÅń£¤ķøä ń¤ŁÕłĆŃĆĆķŖśŃĆƵĖģķ║┐ń£¤ķøäŃü«Õ╝¤ŃĆ鵣ŻĶĪīŃĆüńÆ░ŃĆüń¦ĆÕ»┐ŃĆüµĖģķ║┐Ńü«ķŖśŃéÆ […]
õ║¼ķāĮÕøĮń½ŗÕŹÜńē®ķż©ŃĆīķćæÕĘź 1F-5Õ▒Ģńż║Õ«żŃĆŹŃü½Ńü”ŃĆĵ¢ćÕī¢Ķ▓Īõ┐«ńÉåŃü«µ£ĆÕģłń½»ŃĆĆķćæÕ▒×ÕĘźĶŖĖŃĆÅŃüīķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü¦ŃüÖŃĆéõ╝ܵ£¤Ńü»2024Õ╣┤6µ£ł18µŚź’╝łńü½’╝ē’Į× 8µ£ł4µŚź’╝łµŚź’╝ē ÕłĆÕēŻÕ▒Ģńż║õĮ£ÕōüŃā¬Ńé╣Ńāł ŃĆĆÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆķĢʵøŠń”░ĶłłķćīÕģźķüōõ╣ĢÕŠ╣ ’╝łńĀöńŻ©ŃĆƵ£¼ķś┐ÕĮīµŚźµ┤▓/õ║║ķ¢ōÕøĮÕ«Ø […]
’╝æÕÅĘŃĆĆÕłĆĶĖÅŃéōÕ╝ĄŃéŖõ╗śŃüŹŃĆüĶģ░ÕÅŹŃéŖŃĆüÕģłŃééÕÅŹŃéŗŃĆéÕłāńĘÜÕ╝ĄŃéēŃüÜĶŗźÕ╣▓ń┤░ŃéüŃĆéķļķ½śŃüäŃĆéŃéłŃüÅĶ®░Ńü┐Ķē»ŃüäķēäŃĆéÕéÖÕēŹŃü«µśĀŃéŖŃĆéń©«ŃĆģŃü«õ║ÆŃü«ńø«ŃĆüÕ░æŃüŚĶģ░ķ¢ŗŃüÅŃĆéńĀ鵥üŃüŚńø«ń½ŗŃüżŃĆéÕĖĮÕŁÉõĖƵ×ÜŃü¦Ķ┐öŃéŖµĘ▒ŃüÅńä╝ŃüŹõĖŗŃüÆŃĆéĶĪ©ĶŻÅŃü«Ķģ░Ńü½µóĄÕŁŚŃü©Ķō«ÕÅ░ŃĆéÕć║µØźŃü«õ║ŗŃü»Ķ©śµåČŃü½ńäĪŃüäŃüīŃĆüŃüōŃü«ĶĪ©ĶŻÅŃü« […]
ÕģłµŚźŃü«ń£¤ķøäŃü«Õ░ÅÕłĆŃü½ńČÜŃüŹÕģ╝õ╣Ģń¤ŁÕłĆŃĆéĶ”¬ÕŁÉŃü¦ŃüÖŃĆé ń¤ŁÕłĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕŹćķŠŹĶ╗ÆÕģ╝õ╣ĢŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆƵ׮õ╗ŻĶćŻÕŹćķŠŹĶ╗ÆķŖśŃü»ķØ×ÕĖĖŃü½ńÅŹŃüŚŃüÅńÅŠÕŁśÕōüŃü»Ńü╗Ńü╝ńó║Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäĶ▓┤ķćŹķŖśŃüĀŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéķ¢óĶź┐Ńü½Õ▒ģŃéŗŃüŗŃéēŃüŗń¦üŃü«ńÆ░ÕóāŃüīŃüØŃüåŃü¬Ńü«ŃüŗŃĆüÕ▒▒µĄ”ń│╗Ńü«õĮ£ÕōüŃü½Õć║õ╝ÜŃüåŃüōŃü©Ńü»µ╗ģÕżÜŃü½Ńü¬ […]
ŃüōŃéīŃü¦Ķ½”ŃéüŃü¤ŃéēŃāĆŃāĪŃü¦ŃüŚŃéćŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃü¦’╝Ƶ×Üńø«ŃéƵÄĪµŗōŃĆéõ╣ģŃĆģŃü½Ńé½Ńā╝Ńā£Ńā│ŃéÆõĮ┐ŃüäÕåŹŃāüŃāŻŃā¼Ńā│ŃéĖŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé Ķē▓ŃéĆŃéēŃéƵŖæŃüłŃéŗŃü«ŃüīķøŻŃüŚŃüäŃü«Ńü©ķĢʵ£¤õ┐Øń«ĪŃü¦ÕżēĶē▓ŃüÖŃéŗõ║ŗŃééŃüéŃéŖŃĆüķĢĘŃéēŃüÅŃé½Ńā╝Ńā£Ńā│ń┤ÖŃü¦Ńü«µÄĪµŗōŃü»ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéÕÅ│Ńü«Ńé½Ńā╝Ńā£Ńā│Ńü«µ¢╣ŃüīķŖśŃüīµ¢ŁńäČ […]
Õ░ÅÕłĆŃü«µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃüÖŃéŗõ║ŗŃü½ŃĆéĶĆāŃüłŃü”Ńü┐ŃéīŃü░Õ░ÅÕłĆŃü»ÕłØŃéüŃü”Ńü¦ŃüÖŃĆéķćŹŃüŁŃüīńäĪŃüäŃü«Ńü¦ķĆÜÕĖĖŃü«µźöÕĮóŃü«ÕÅ░Ńü¦Ńü»Ķ╝¬ķāŁŃü«µÄĪµŗōŃü»ńäĪńÉåŃü©µĆØŃéÅŃéīŃĆüŃéĘŃā¬Ńé│Ńā│Ńü¦ÕłĆĶ║½Ńü½Õ«īÕģ©Ńü½ķÜĀŃéīŃéŗÕÅ░ŃéÆõĮ£ŃéŖÕłĆĶ║½ŃéƵĄ«ŃüŗŃüøŃüŠŃüÖŃĆé ńĀöŃüÄÕ┤®ŃéīŃü”ķļŃüīńäĪŃüÅķŖśŃééĶ¢äŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéń¤│ĶÅ»Õó©Ńü¦Ńü«µÄĪµŗōŃü¦Ńü» […]
Õ░æŃüŚÕēŹŃü¦ŃüÖŃüīķø▓µ×ŚķÖó’╝łŃüåŃüśŃüä’╝ēŃü«õĖĪÕłāń¤ŁÕłĆŃéƵŗØĶ”ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé’╝Æ’╝É’╝æ’╝ÆÕ╣┤Ńü«µö»ķā©ķææÕ«ÜŃü½ķø▓µ×ŚķÖóÕīģķĢĘŃü«õĖĪÕłāń¤ŁÕłĆŃüīÕć║Ńü¤õ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüØŃéīŃü©ÕÉīõĖĆŃüŗŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõ║ŗÕēŹŃü½ÕłāķĢĘŃéÆŃüŖĶü×ŃüŹŃüÖŃéŗŃü©’╝ŚÕ»Ėń©ŗŃü©Õ░ŵī»ŃéŖŃü©Ńü«õ║ŗŃĆéńó║ŃüŗķææÕ«ÜŃü½Õć║Ńü¤ÕīģķĢĘŃü»Õż¦µī»ŃéŖŃüĀŃüŻŃü¤ŃéżŃāĪ […]
Õ░æŃüŚÕēŹŃü½ńŠÄµ┐āńē®Ńü«ńÜåńä╝ÕłĆ’╝ÆÕÅŻŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüØŃü«ÕēŹÕŠīŃĆüńČŠÕ░ÅĶĘ»Õż¬ÕłĆŃĆüÕż¦ÕÆīķÄīÕĆēµ£¤Õ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃĆüÕż¦ÕÆīÕŹŚÕīŚµ£Øµ£¤Õ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃĆüÕż¦ÕÆīÕ┐£µ░ĖķĀāŃü«Õ£©ķŖśÕłĆŃĆüµĖģķ║┐ŃĆüÕēćķćŹŃü©Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆéµÅÅŃüŹµēŗŃü½ŃéłŃüŻŃü”µÅÅŃüŹŃéäŃüÖŃüäÕłĆŃĆüķøŻŃüŚŃüäÕłĆŃü©Ķē▓ŃĆģŃüéŃéŗŃü©µĆØŃüäŃüŠ […]
ŃüØŃééŃüØŃéé’╝æÕÅĘŃüŗŃéēÕÅżŃüäńē®ķĀåŃüĀŃü©ŃüŚŃü¤ŃéēŃĆü’╝ōÕÅĘŃü¦Õ¢äÕ«ÜŃü¬Ńü«Ńü¦’╝öÕÅĘŃü¦ķÄīÕĆē’Į×ÕŹŚÕīŚŃü«Õż¦ńŻ©õĖŖŃüÆŃü©ŃüäŃüåĶ”ŗµ¢╣Ńü»ńĀ┤ńČ╗ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüĶŗ”ŃüŚŃüäµÖéŃü»ŃüōŃüåŃüäŃüåõ║ŗŃüīĶĄĘŃüōŃéŖÕŠŚŃéŗŃü«ŃüīÕģźµ£ŁķææÕ«ÜŃü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃéé’╝ōÕÅĘÕ¢äÕ«ÜŃü¦ŃéżŃāżŃüĀŃüŻŃü¤ŃüŚŃĆéÕģ©Ńü”ń½ŗŃü”ńø┤ŃüŚŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé ’╝æ […]
õ╗ŖÕø×Ńü»ńåŖĶ░ĘÕÆīÕ╣│Õģłńö¤ŃüīĶ¼øÕĖ½Ńü½µØźŃü”ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕ╣│Ķ║½ŃĆéÕ»ĖÕ╗ČŃü│ŃĆéÕ╣ģÕ║āŃüÅķćŹŃüŁĶ¢äŃüäŃĆéõĖēŃüżµŻ¤ŃĆéńÜ«ķēäŃü»Ķ®░ŃéōŃü¦ŃāöŃāüŃāöŃāüń½ŗŃüĪńÖĮŃüäŃĆéÕłāµ¢ćŃü»ĶĪ©ĶŻÅµÅāŃüäµØæµŁŻķó©ŃĆéķćŹŃüŁŃü»ŃüŗŃü¬ŃéŖĶ¢äŃüäŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆé ’╝ÆÕÅĘŃĆĆń¤ŁÕłĆŃĆĆõĖēŃüżµŻ¤ŃüŗŃü¬ŃéŖķ½śŃüäŃĆéÕ«ÜÕ»ĖŃü╗Ńü®ŃĆéķćŹŃüŁŃü»ÕģłŃüŠ […]
ÕÉŹÕłĆÕ▒ĢŃü«ŃāüŃé▒ŃāāŃāłŃü»Õģ©Ńü”ÕĘ«ŃüŚõĖŖŃüÆŃéŗõ║ŗŃüīÕć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüöķĆŻńĄĪķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ńÜ嵦śŃĆüŃüéŃéŖŃüīŃü©ŃüåŃüöŃü¢ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µ£¼ĶāĮÕ»║ŃĆüÕż¦Ķ│ōµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü½Ńü”ķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü«ŃĆīÕÉŹÕłĆÕ▒ĢŃĆŹŃāüŃé▒ŃāāŃāłŃéÆķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüöÕĖīµ£øŃü«µ¢╣Ńü½ŃüĢŃüŚŃüéŃüÆŃüŠŃüÖŃĆéÕĮōŃāøŃā╝ŃāĀŃāÜŃā╝ŃéĖõĖŖķā©ŃāĪŃāŗŃāźŃā╝Ńü«ŃĆīŃüŖÕĢÅŃüäÕÉłŃüøŃĆŹŃü«ÕģźÕŖøŃāĢŃé®Ńā╝ŃāĀŃüŗŃéēŃüöķĆŻńĄĪķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃéēŃüŖķĆüŃéŖŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüŖķĆüŃéŖÕģłŃü«ŃüöõĮŵēĆŃü©ŃüŖÕÉŹÕēŹŃéÆŃüŖķĪśŃüäŃüäŃü¤ […]
ńŠÄµ┐āÕłĆÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü«ńČÜŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéÕłāµ¢ćµÅÅÕåÖŃü»ÕĘ«ŃüŚĶĪ©Ńü½ÕģźŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃüåŃüäŃüłŃü░ÕģłµŚźŃüöĶć¬Ķ║½ŃééµŖ╝ÕĮóŃéÆŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗµ¢╣Ńü½ŃĆīÕłāµ¢ćŃü»Ńü®ŃüōŃüŗŃéēµÅÅŃüŹÕ¦ŗŃéüŃüŠŃüÖŃüŗ’╝¤ŃĆŹŃü©Ńü¤ŃüÜŃüŁŃü¬ŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń¦üŃü»ÕĘ«ŃüŚĶŻÅŃü«ÕłĆĶ║½õĖŁÕż«ŃüŗŃéēµÅÅŃüÅõ║ŗŃüīÕżÜŃüäŃü«Ńü¦ŃüØŃü«µ¦śŃü½ŃüŖńŁöŃüłŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤Ńéēķ®ÜŃüŗ […]
ńŠÄµ┐āÕłĆŃü»ńÅŠÕŁśµĢ░ŃüīÕżÜŃüäŃéÅŃéŖŃü½ńĀöńŻ©ŃüÖŃéŗµ®¤õ╝ÜŃü»Õ░æŃü¬ŃüÅŃĆüµēŗÕģāŃü½µ«ŗŃéŗÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü½ŃééńŠÄµ┐āÕłĆŃü»µ«åŃü®ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéõ╗ŖÕø×Ńü»ńŠÄµ┐āŃü«ÕÉīõĖĆķŖśŃü«ÕłĆŃéÆÕÉīµÖéŃü½µÄĪµŗōŃĆéÕÉīõĖĆķŖśŃéÆķĆŻńČÜŃüŚŃü”µÄĪµŗōŃüÖŃéŗŃü«Ńü»õ╗źÕēŹµÄĪŃüŻŃü¤Õ┐ĀÕÉēÕż¦Õ░Åõ╗źµØźŃüĀŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆé õ╗ŖÕø×Ńü«ÕłĆŃĆüķŖśŃü»ÕÉīŃüśŃü¦ŃüÖŃüī […]
Õż¦Õż¬ÕłĆ’╝łķĢĘÕłĆ’╝ēń¤│ÕłćÕŖöń«Łńź×ńżŠĶöĄŃĆĆ’╝ł’╝Æ’╝É’╝Æ’╝ōÕ╣┤ŃĆüĶ¬┐µ¤╗Ķ©śķī▓Ńü«Ńü¤ŃéüÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗō’╝ēŃĆĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆķćæµł┐ÕĘ”Ķ┐æÕ░ēµö┐ķćŹõĮ£ŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕźēń┤ŹÕŠĪńź×ÕēŹÕŠĪÕż¬ÕłĆµ▓│ÕĘ×ÕÉīķāĪÕż¦µ▒¤µ£©ń®ŹńēøķĀŁÕż®ńÄŗÕŠĪÕ»│ÕēŹµśÄµÜ”ÕøøµłŖµłīÕż®µŁŻµ£łÕ╗┐õĖēµŚź µæéÕĘ×Õż¦ÕØéõĮÅõ║║ń½╣Õ▒ŗõ║öķāÄÕģĄĶĪøÕ░ēĶŚżÕĤµŁŻÕÉēµĢ¼ńÖĮŃĆĆÕłāķĢĘ […]
õ║¼ķāĮÕĖéÕåģŃéÆŃüŖµĢŻµŁ®ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃĆüŃüŖÕ£░ĶöĄŃüĢŃéōŃüīµ▓óÕ▒▒ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃéīŃüīŃüŠŃüüŃéäŃüæŃü½µ▓óÕ▒▒ŃüéŃüŻŃü”Õ░æŃüŚµŁ®ŃüÅÕ║”Ńü½µ¼ĪŃĆģńÅŠŃéīŃĆüÕĀ┤µēĆŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ńü»õĖĆÕ║”Ńü«ŃüŖµĢŻµŁ®Ńü¦õĮĢÕŹüõĮōŃü©µ©¬ÕłćŃéŗõ║ŗŃü½ŃĆéŃāŹŃāāŃāłŃü¦µż£ń┤óŃüŚŃü”Ńü┐Ńü¤ŃéēĶČŻÕæ│Ńü¦Ķ©śķī▓ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗµ¢╣ŃüīŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ║¼ķāĮŃü«ŃüŖÕ£░ĶöĄŃüĢŃéō […]
Õż¦Õż¬ÕłĆŃéäķĢĘÕłĆŃü½Õż¦Ķ¢ÖÕłĆŃü¬Ńü®ŃĆüÕłåÕē▓ŃüŚŃü”Ńé╣ŃéŁŃāŻŃā│ŃüŚŃü¤Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆPCŃü¦ń╣ŗŃüÆŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüµö╣ŃéüŃü”ĶĆāŃüłŃéŗŃü©ŃéłŃüÅŃüōŃéōŃü¬Õż¦ÕżēŃü¬µÄĪµŗōõĮ£µźŁŃéÆŃéäŃüŻŃü¤Ńü¬ŃüüŃü©ŃĆéŃĆé õ╗ŖŃüŠŃü¦µĘ▒ŃüÅĶĆāŃüłŃü”µØźŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüŖŃüØŃéēŃüÅķøåõĖŁŃüŚŃü”õĮĢŃüŗŃéÆŃéäŃüŻŃü”ŃüäŃéŗµÖéŃü«Ķ©śµåČŃü»Ńüé […]
Õ£©ķŖśÕż¦ÕÆīńē®Ńü«ÕÅżŃüäÕż¬ÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆ’╝ÆÕÅŻµÄĪµŗōŃĆéõ╗źÕēŹŃü»Õż¦ÕÆīńē®Ńü«µŖ╝ÕĮóŃü»µ»öĶ╝āńÜäń░ĪÕŹśŃüĀŃü©µä¤ŃüśŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü»’╝ÆÕÅŻŃü©ŃééķøŻŃüŚŃüäŃĆé ŃüåŃüĪ’╝æÕÅŻŃü«ńĀöńŻ©ŃüīķØ×ÕĖĖŃü½Ķē»ŃüäŃĆéŃüŖŃüØŃéēŃüŵ¤Éµ┤ŠŃü«ńĀöÕĖ½Ńü«ńĀöńŻ©ŃĆ鵜©Õ╣┤µØźŃüōŃü«ńĀöŃüÄŃéÆŃéäŃéŖŃü¤ŃüÅŃĆüĶē▓ŃĆģĶ®”ŃüŚŃü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤Ńüī […]
ķāĮÕÉłŃü½ŃéłŃéŖÕģźµ£ŁÕć║µØźŃüÜŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆń¤ŁÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆõ┐ĪÕøĮŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕ┐£µ░ĖõĖēÕ╣┤Õģ½µ£łµŚź’╝ÆÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆńäĪķŖśŃĆĆõ┐ĪÕøĮ’╝łÕŹŚÕīŚµ£ØÕŠīµ£¤’╝ē’╝ōÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕ╗ŻÕ╣Ė’╝łÕ╣│Õ«ēÕ¤ÄÕ╝śÕ╣Ė’╝ē’╝öÕÅĘŃĆĆĶäćÕĘ«ŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕ¤ÄÕĘ×õĮŵö┐ÕøĮ’╝ĢÕÅĘŃĆĆĶäćÕĘ«ŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆƵ¢╝Õż¦ÕØéÕÆīµ│ēÕ«łÕøĮĶ▓×õĮ£õ╣ŗ õ╗Ŗ […]
’╝æÕÅĘ’╝ōÕ░║ĶČģŃĆéÕ░æŃüŚń┤░Ķ║½Ńü¦ÕÅŹŃéŖµĄģŃüäŃĆéŃéłŃüÅĶ®░ŃéĆńČ║ķ║ŚŃü¬Õ£░ķćæŃĆéõ║ÆŃü«ńø«Ńü©µ╣ŠŃéīŃĆéÕ»øµ¢ćµ¢░ÕłĆŃü«Õ¦┐ŃéÆŃüØŃü«ŃüŠŃüŠŃé░Ńā│Ńü©Õ╗ČŃü░ŃüŚŃü¤µä¤ŃüśŃĆéŃüōŃéīŃĆüõ╗źÕēŹõĖ”ŃéōŃüĀõ║ŗŃüīŃĆé’╝łÕŠīŃü¦Ķ¬┐Ńü╣Ńü¤Ńéē’╝Æ’╝É’╝æ’╝ŚÕ╣┤Ńü½ķææĶ│×ÕłĆŃü©ŃüŚŃü”Õć║Ńü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤’╝ēŌĆØĶ”ÜŃüłŃü”ŃüäŃü”ŃéłŃüŗŃüŻŃü¤ŃüüŃĆüń¤źŃéēŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤Ńéē […]
µśÄµŚź’╝öµ£ł’╝æ’╝ÖµŚźŃéłŃéŖŃĆüµ£¼ĶāĮÕ»║ Õż¦Ķ│ōµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü½Ńü”ŃĆīÕÉŹÕłĆÕ▒ĢŃĆŹŃüīÕ¦ŗŃüŠŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõ╗źõĖŗÕć║ķÖ│ÕłĆÕēŻŃü«õĖĆķā©Ńü¦ŃüÖŃĆé Õż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕģēÕ┐Ā’╝łķćŹĶ”üńŠÄĶĪōÕōü’╝ēÕż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕīģÕ╣│’╝łńē╣ÕłźķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ēÕż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕøĮÕ«Ś’╝łńē╣ÕłźķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ēŃĆĆÕłĆŃĆĆńäĪķŖśŃĆĆĶ▓×Õ«Ś’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ēŃĆĆÕłĆ […]
µśÄÕŠīµŚźŃĆü’╝öµ£ł’╝æ’╝ÖµŚźŃéłŃéŖŃĆüµ£¼ĶāĮÕ»║ Õż¦Ķ│ōµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü½Ńü”ŃĆīÕÉŹÕłĆÕ▒ĢŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé Õ▒Ģńż║Ńā¬Ńé╣ŃāłŃü»ŃāüŃā®ŃéĘŃéÆŃüöĶ”¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
ÕéÖÕēŹÕŹŚÕīŚµ£Øµ£¤ŃĆéÕéÖÕēŹńē®Ńü«µŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōŃéƵĖøŃéēŃüØŃüåŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃéäŃü»ŃéŖµĢ░ŃüīÕ£¦ÕĆÆńÜäŃü½ÕżÜŃüÅŃüØŃüŚŃü”ÕÉŹÕōüŃü«ńÄćŃü»õ╗¢ÕøĮŃéÆÕż¦ŃüŹŃüÅõĖŖÕø×ŃéŗŃü«Ńü¦ŃĆüńĄÉÕ▒ƵŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōńÄćŃééõĖŖŃüīŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õ╗źÕēŹŃĆüµ¤┤ńö░µ×£Ńü«ĶéźÕēŹÕłĆĶ”│Ńü«õ║ŗŃéÆÕ░æŃüŚµøĖŃüäŃü¤ŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃĆƵ¤┤ńö░µ×£Ńü«ĶéźÕēŹÕłĆĶ”│µśŁÕÆī’╝Æ’╝¢Õ╣┤ŃĆüÕłĆńŠÄń¼¼’╝æ’╝É’╝ī’╝æ’╝Æ’╝ī’╝æ’╝ōÕÅĘŃĆüµ¤┤ńö░µ×£Ńü«ŃĆīÕłĆÕīĀŃü»µ¢»ŃüåĶĆāŃüĖŃéŗŃĆŹŃü«õĖĆń»ĆŃĆéŃĆÄń¼¼õĖĆŃü½ÕōüŃüīĶē»ŃüäŃĆéÕ×óŃü¼ŃüæŃüīŃüŚŃü”ŃĆüŃüÖŃü╣Ńü”Ńü½ńäĪńÉåŃüīŃü¬ŃüäŃĆéÕłāÕæ│ŃüīŃéłŃüäŃĆéĶć¬ńö▒Ńü½ńä╝ […]
ńĀöńŻ©ķüōÕģĘŃéÆTVµÆ«ÕĮ▒ŃüŚŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕłĆÕēŻŃü«ńĀöńŻ©ŃéÆĶĪīŃüåõ╗Ģõ║ŗŃüīŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃéÆńÜåŃüĢŃéōŃü½õ╝ØŃüłŃü”ķĀéŃüæŃéŗŃĆüÕż¦ÕżēŃüéŃéŖŃüīŃü¤Ńüäµ®¤õ╝ÜŃü¦ŃüÖŃĆé õŠŗŃüłŃü░ń¦üŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃĆīÕłĆŃéÆńĀöŃüÉõ╗Ģõ║ŗŃü¬ŃéōŃü”ŃĆüõ╗Ģõ║ŗŃüéŃéōŃü«’╝¤ŃĆŹŃü©ŃüäŃéÅŃéīńČÜŃüæŃü”’╝ō’╝ÆÕ╣┤ŃüīńĄīŃüĪŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŖŃüŗŃüƵ¦śŃü¦ […]
ńČŠÕ░ÅĶĘ»Ńü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü«ńČÜŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéńČŠÕ░ÅĶĘ»Ńü«ķø░Õø▓µ░ŚŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵜©µŚźŃü«Ńā¢ŃāŁŃé░Ńü«ńČÜŃüŹŃü¦ŃüäŃüåŃü©ŃĆüµś»ÕŹ│ŃüĪÕÅżõ║¼ńē®Ńü«ķø░Õø▓µ░ŚŃü¦ŃüÖŃĆé ńäĪķŖśŃĆĆõ║öµØĪ ńäĪķŖśŃĆĆń▓¤ńö░ÕÅŻÕøĮÕ«ē ńäĪķŖśŃü¦ÕÅżõ║¼ńē®Ńü©µźĄŃéüŃéēŃéīŃéŗńē®ŃüīÕģ©Ńü”ŃüōŃü«µ¦śŃü¬Õć║µØźŃü©ŃüäŃüåĶ©│Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéõŠŗŃüłŃü░ […]
õ║¼ńē®Ńü¦Ńééńē╣Ńü½ÕÅżŃüäńē®ŃĆüõĖēµØĪŃā╗õ║öµØĪŃéäÕłØµ£¤ń▓¤ńö░ÕÅŻńē®ńŁēŃéÆÕÅżõ║¼ńē®Ńü©Õæ╝ń¦░ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéńČŠÕ░ÅĶĘ»Õ«ÜÕł®Ńü¬Ńü®Ńééõ╗źÕēŹŃü»ķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻõĖŁµ£¤Ńü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüńĀöń®ČŃüīķĆ▓Ńü┐ķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻÕēŹµ£¤õ╣āĶć│õĖŁµ£¤Ńü©ŃüĢŃéīŃéŗµ¦śŃü½Ńü¬ŃéŖŃĆüńÅŠÕ£©Ńü¦Ńü»ķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻÕēŹµ£¤Ńü«ÕłĆÕĘźŃü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńäĪķŖś […]
ŃüŠŃü¤’╝ÆÕ╣┤Ńé½Ńā╝ŃāēŃéÆķĀ鵳┤ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüõ║¼ÕŹÜŃüĢŃéōŃü½ńö©õ║ŗŃüżŃüäŃü¦Ńü½Õ▒Ģńż║ŃéÆĶ”│Ķ”¦ŃĆé1ķÜÄŃü«õ╗ÅÕāÅŃéÆĶ”ŗŃü¤ŃüÅŃü”ÕģźŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕÉīŃüśŃüÅ’╝æķÜÄŃü«’╝Ģ’╝ī’╝¢Õ▒Ģńż║Õ«żŃü¦ŃĆīÕéÖÕēŹŃā╗ÕéÖõĖŁŃā╗ÕéÖÕŠīŃü«ÕÉŹÕłĆŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕ▒Ģńż║ŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń¤źŃéēŃüÜŃü½ÕģźŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīÕ╣ĖķüŗŃĆé õ╗ŖµŚźŃü« […]
õ┐«ÕŁ”ķÖóķøóÕ««õ╗śĶ┐æŃüīŃüŖµĢŻµŁ®ĶĘØķøóŃü½õĖüÕ║”ŃéłŃüäŃü«Ńü¦ńĄÉµ¦ŗķĀ╗ń╣üŃü½ĶĪīŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéõĖēÕ«ģÕģ½Õ╣ĪŃüŗŃéēõĖēµśÄķÖóŃéÆķĆÜŃéŖŃĆüĶō«ĶŻջ║µ©¬ŃéƵŖ£ŃüæŃĆüķ½śķćÄÕĘØŃéƵĖĪŃéŖĶĄżÕ▒▒ń”ģķÖóÕēŹŃéÆķĆÜŃüŻŃü”õ┐«ÕŁ”ķÖóķøóÕ««ŃĆéķøóÕ««Ńü«ńø┤ŃüÉÕŹŚŃü½ķ¤│ńŠĮÕĘØŃü©ŃüäŃüåÕ░ÅŃüĢŃü¬ÕĘØŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕż¦ķø©Ńü½Ńü¬ŃéŗŃü©ńÖĮÕĘØÕīŚÕż¦ĶĘ»õ╗źÕīŚŃü»Ńüä […]
ń¤ŁÕłĆŃĆĆķŖśŃĆĆµÆŁÕĘ×õĮÅķÜ╝ÕģēõĮ£ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕ╣│µłÉõ║īÕŹüÕøøÕ╣┤ńøøÕżÅŃĆĆ µĪöµóŚķÜ╝ÕģēÕłĆÕīĀŃü«µÖ»ÕģēŃéÆńŗÖŃüŻŃü¤ń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆ鵜ĀŃéŖŃüīĶ”ŗõ║ŗŃü½ÕåŹńÅŠŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüń¼¼7Õø×ŃüŖÕ«łŃéŖÕłĆÕ▒ĢĶ”¦õ╝ÜŃü½µ¢╝ŃüäŃü”ńē╣Ķ│×Ńü«ŃāåŃā¼ŃāōŃüøŃü©ŃüåŃüĪĶ│×ŃéÆÕÅŚĶ│×ŃüĢŃéīŃü¤õĮ£ÕōüŃü¦ŃüÖŃĆé ń¤ŁÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆƵ│ĢÕ╗ŻŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ […]
Õż¬ÕłĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕ«łµ¼Ī’╝łÕÅżķØƵ▒¤’╝ēķØƵ▒¤µ┤ŠŃü«ńź¢Ńü©ŃüäŃéÅŃéīŃéŗÕłĆÕĘźŃüīÕ«ēµ¼ĪŃĆéŃüØŃü«ÕŁÉŃüīÕ«łµ¼ĪŃü¦ŃüÖŃĆéÕ«łµ¼ĪŃü»Ķ▓×µ¼ĪŃéēŃü©ÕÉīµ¦śķØƵ▒¤µ┤ŠŃéÆõ╗ŻĶĪ©ŃüÖŃéŗÕÉŹĶĘĪŃü«õĖĆŃüżŃü¦ŃĆüÕłØõ╗Żõ╗źķÖŹÕÉīÕÉŹŃüīÕŹŚÕīŚµ£Øµ£¤ŃüŠŃü¦ńČÜŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéµŖ╝ÕĮóŃü«Õż¬ÕłĆŃü»ķÄīÕĆēõĖŁµ£¤ķĀāŃü«Õ«łµ¼ĪŃü¦ķŖśŃü»Õ░ŵī»ŃéŖŃü¬Ńé┐ŃéżŃāŚŃĆéÕłāķĢĘõ║īÕ░║ÕģŁÕ»Ė […]
ŃĆīńøĖÕĘ×õĖŖÕĘźŃü»Ķ▓×Õ«ŚŃéÆõ╗źŃü”µ£ĆÕŠīŃü«õ║║Ńü©ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃĆŹŃü©Ńü«õĖƵ¢ćŃüīŃĆÄŃĆīńøĖÕĘ×õĖŖÕĘźŃü©ŃüØŃü«õĮ£ķó©Ńü«Õż¦Ķ”üŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆŹµ£¼ķ¢ōķĀåµ▓╗’╝łµśŁÕÆī’╝ō’╝ōÕ╣┤’╝ēŃĆÅŃü½µøĖŃüŗŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃéīõ╗źõĖŗŃü«ńøĖÕĘ×õ╝ØõĖŖõĮŹÕĘźŃéÆńøĖÕĘ×õĖŖÕĘźŃü©ŃüÖŃéŗõ║ŗŃüīķ¢ōķüĢŃüäŃü©Ńü»µĆØŃüäŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüń¦üŃü»µ£¼ķ¢ōÕģł […]
ÕģłµŚźŃā¢ŃāŁŃé░Ńü¦ŃĆīńøĖÕĘ×õĖŖÕĘźŃĆŹŃü©ŃüäŃüåĶ©ĆĶæēŃéÆõĮ┐ŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüń¦üÕ«¤Ńü»ŃüØŃü«Õ«ÜńŠ®ŃéÆń¤źŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéĶē»ŃüÅŃü¬ŃüäŃü¬ŃüüŃü©µĆØŃüäŃü¬ŃüīŃéēŃééŃüżŃüäŃüżŃüäŃĆéńøĖÕĘ×õĖŖÕĘźŃü©ŃüäŃüåĶ©ĆĶæēŃü»Õē▓Ńü©ķĀ╗ń╣üŃü½ńø«Ńü½ŃüÖŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüńøĖÕĘ×õĖŖÕĘźŃü©Ńü»Ńü®Ńü«ń»äÕø▓ŃéÆŃüäŃüåŃü«ŃüŗŃĆüµśÄńó║Ńü½µøĖŃüŗŃéīŃü¤ńē®Ńü½ […]
ńÅŠÕ£©ŃĆüÕźłĶē»ń£īń½ŗµ®┐ÕĤĶĆāÕÅżÕŁ”ńĀöń®ČµēĆõ╗śÕ▒×ÕŹÜńē®ķż©Ńü½Ńü”ŃĆÄńē╣ÕłźķÖ│ÕłŚŃĆīÕłĆÕīĀŃā╗µ▓│ÕåģÕ£ŗÕ╣│Ńü«õ╗Ģõ║ŗŌĆĢÕÅżõ╗ŻÕłĆÕēŻÕŠ®ÕģāŃüŗŃéēńÅŠõ╗ŻŃü«õĮ£ÕłĆŃüŠŃü¦ŌĆĢŃĆŹŃĆÅŃüīķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü¦ŃüÖŃĆé ŃĆĆ’╝łõ╗źõĖŗÕźłĶē»ń£īń½ŗĶĆāÕÅżÕŁ”ÕŹÜńē®ķż©SNSŃéłŃéŖĶ╗óĶ╝ē’╝ē ķ¢ŗÕé¼õĖŁÕźłĶē»ń£īń½ŗµ®┐ÕĤĶĆāÕÅżÕŁ”ńĀöń®ČµēĆķÖäÕ▒×ÕŹÜńē®ķż©ńē╣Õłź […]
’╝Ƶ£łŃü»µ£¼ķā©ŃüŗŃéēŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéµ£¼ķā©ŃüŗŃéēŃü«ķææÕ«ÜÕłĆŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆīńŁöŃüłŃéÆSNSńŁēŃü¦µśÄŃüŗŃüĢŃü¬ŃüäŃü¦õĖŗŃüĢŃüäŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕåģÕ«╣Ńü«ķĆÜķüöŃüīµö»ķā©Õ«øŃü”Ńü½µØźŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦ŃĆüŃüŚŃü░ŃéēŃüÅÕēŹŃüŗŃéēµ£¼ķā©ŃüŗŃéēŃü«ķææÕ«ÜÕłĆŃü½ķ¢óŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüŃüōŃüōŃü¦ŃééńŁöŃüłŃéƵśÄŃüŗŃüĢŃü¬ŃüäŃéłŃüåŃü½ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃü©ŃüäŃüåõ║ŗ […]
õ╣ØÕĘ×ńē®Ńü«ń¤ŁÕłĆŃü«Õ£░ĶēČŃĆéķēäŃüīµ¤öŃéēŃüŗŃüÖŃüÄŃü”ŃāÆŃé▒Ńü½Ķŗ”ŃüŚŃéĆŃĆéŃüŠŃü¤õ╗ŖõĮ┐ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗµŗŁŃüäŃüīÕ░æŃĆģń▓Śńø«Ńü½õĮ£ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗÕŖĀµĖøŃééŃüéŃéŖŃāÆŃé▒µ░ŚÕæ│Ńü¦ŃĆéµŗŁŃüäŃü¦ŃāÆŃé▒ŃéŗŃü¬ŃéōŃü”ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ń┤Āõ║║ŃüŻŃüĮŃüäĶ®▒Ńü¦ŃüÖŃüīŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆéõ╣ØÕĘ×ńē®ŃéēŃüŚŃüäõ╣ØÕĘ×ńē®Ńü©ŃüäŃüåŃéäŃüżŃü»õ╣ØÕĘ×ńäČŃü©ŃüŚŃü¤ńÖĮŃüæµ¢╣Ńü«Õ£░ķēä […]
õ╗ŖµŚźŃü»Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóÕłČõĮ£Ńü«ÕÅ¢µØÉŃéÆŃüŚŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃü®Ńü«ń©ŗÕ║”õĮ┐ŃüŻŃü”ķĀéŃüæŃéŗŃüŗŃü»õĖŹµśÄŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüµŖ╝ÕĮóÕłČõĮ£ķ¢óķĆŻŃü«ÕÅ¢µØÉŃü«µ®¤õ╝ÜŃü»Õ░æŃü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃüŚŃĆüÕż¦ÕżēŃüéŃéŖŃüīŃü¤Ńüäõ║ŗŃü¦ŃüÖŃĆé
ķīåŃü│ÕłćŃéŖŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ń¤ŁÕłĆŃüīń¦üĶ”ŗŃü¦ńøĖÕĘ×õĖŖÕĘźŃü¬Ńü«Ńü¦ÕÅżµŖ╝ÕĮóŃü½Ńü¬ŃüäŃüŗŃü©µż£ń┤óõĖŁŃĆüÕ¤ŗÕ┐ĀÕłĆĶŁ£Ńü½ÕģłµŚźŃü«ķĪŹķŖśõ║īÕŁŚÕøĮõ┐Ŗ’╝łķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓Ī’╝ēŃéÆŃü┐ŃüżŃüæŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüōŃü«ķĪŹķŖśÕøĮõ┐ŖŃü»ÕłĆńŠÄŃü«ÕÉŹÕłĆķææĶ│×Ńü½ķüÄÕÄ╗’╝ōÕ║”µÄ▓Ķ╝ēŃüĢŃéīŃü¤ÕÉŹÕōüŃü¦ŃĆüÕŠ│ÕĘØÕ░åĶ╗ŹÕ«ČŃĆüõ╝ܵ┤źµØŠÕ╣│Õ«ČŃĆüõĖƵ®ŗÕŠ│ÕĘØÕ«ČŃü¬ […]
ńÖĮķŖĆÕĖ½Ńü«õĖŁńö░Ķé▓ńöĘÕģłńö¤Ńü«ÕĘźµł┐Ńü½Ńü”õĖŁńö░µÖāÕÅĖńÖĮķŖĆÕĖ½ŃĆéõĖŁńö░µÖāÕÅĖÕĖ½Ńü»µÖ«µ«ĄŃü»ńź×µłĖŃü«ÕĘźµł┐Ńü¦ŃüŖõ╗Ģõ║ŗŃéÆŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü«µŚźŃü»ķāĮÕÉłŃü¦ÕŖĀµØ▒ÕĖéŃü«Ķé▓ńöĘÕģłńö¤Ńü«ÕĘźµł┐Ńü½ŃĆé õ╗ŖµŚźŃü»ÕĆēµĢĘÕĖéÕģÉÕ│ČŃü«ń¤│Õ┤ÄõĖēķāÄķלÕĖ½Ńü«ÕĘźµł┐Ńü½Õ«īµłÉŃüŚŃü¤Õż¬ÕłĆŃéÆÕÅŚŃüæÕÅ¢ŃéŖŃü½õ╝║ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ÕłĆ […]
’╝æµ£łŃü»µ¢░Õ╣┤õ╝ÜŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüäŃüżŃééŃü«õĖēµ£©ÕŹŖµŚģķż©Ńü¦ŃĆéõĖēµ£©ÕŹŖŃü»ń¼æń”Åõ║ŁķČ┤ńōČŃüĢŃéōŃéäŃĆüŃüéŃü«ŃüŁŃü«ŃüŁŃüĢŃéōŃüīŃāÉŃéżŃāłŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃü¤µŚģķż©Ńü¦ŃüÖŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕłĆĶéźÕēŹŃĆéķĢĘŃüäŃĆéõ║īÕ░║õ║öÕ»ĖĶČģŃüŗŃĆéÕÅŹŃéŖµĄģŃéüŃü¦Ķ║½Õ╣ģÕ║āŃüäŃĆéķćŹŃüŁŃü»Ķ║½Õ╣ģŃü½µ»öŃüŚŃü”ĶŗźÕ╣▓Ķ¢äŃéüŃĆéĶ®░Ńü┐ķüÄŃüÄŃü¬ŃüäÕ£░ĶéīŃĆéÕż¦õ║ÆŃü«ńø«ŃéÆ […]
õ╗ŖÕø×Ńü»ķüÄÕÄ╗õĖĆńĢ¬Ńü½ÕŖøŃü«µ£ēŃéŗµŗŁŃüäŃüīÕć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕŖĀµĖøŃéÆŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░µ┐āŃüÅÕģźŃéŖķüÄŃüÄŃüŠŃüÖŃĆéķēäĶéī’╝æ’╝É’╝É’╝ģŃĆé’╝Æ’╝Éõ╗ŻŃü«ķĀāŃü½ÕłØŃéüŃü”Õć║õ╝ÜŃüäŃĆüŃüÜŃüŻŃü©ńÉåµā│Ńü©ŃüŚŃü”ŃüŹŃü¤ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕć║µØźŃü¤ńē®Ńü»ķüÄÕÄ╗µ£ĆĶē»Ńü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕĤÕøĀŃüīÕłåŃüŗŃéēŃüÜŃü¦ŃüÖŃĆé
Ķź┐ķÖŻĶł¤µ®ŗŃü«ńø┤ŃüÉÕŹŚŃĆüµÖ┤µśÄńö║Ńü½Ńü»ŃĆīµÖ┤µśÄńź×ńżŠŃĆŹŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕÅżŃüäĶ│ćµ¢ÖŃü½ŃéłŃéŗŃü©ÕēĄÕ╗║ÕĮōµÖéŃü«µÖ┤µśÄńź×ńżŠŃü»ŃĆüµØ▒Ńü»ÕĀĆÕĘØķĆÜŃĆüĶź┐Ńü»ķ╗Æķ¢ĆķĆÜŃĆüÕīŚŃü»ÕģāĶ¬ōķĪśÕ»║ķĆÜŃĆüÕŹŚŃü»õĖŁń½ŗÕŻ▓ķĆÜŃü©ŃüäŃüåÕ║āÕż¦Ńü¬ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃüŻŃü¤ŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéÕ£░Õø│Ńü¦ńó║Ķ¬ŹŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüŃüōŃü«ķØóń®ŹŃü»õ╗ŖŃü«õ║īµØĪÕ¤ÄŃü«ÕŹŖÕłå […]
ŃüøŃüŻŃüŗŃüÅŃü¬Ńü«Ńü¦ĶĪīŃüŻŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéķø¬ŃééŃüĪŃéēŃüżŃüŹŃĆüõ╗ŖÕ╣┤Ńü¦õĖĆńĢ¬Õ»ÆŃüŗŃüŻŃü¤ŃüŗŃééŃü¦ŃüÖŃĆéŃĆé Ķź┐ķÖŻĶł¤µ®ŗŃü«ń¤│µ©ÖŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüōŃü«Õ£░Ńü½Õ¤ŗÕ┐ĀÕ«ČŃüīŃüéŃüŻŃü¤ŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéÕøĀŃü┐Ńü½ŃĆüÕÉīÕ£░Ńü½Ńü»µ£¼ķś┐Õ╝źÕ«ČŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃĆīńē╣ÕłźÕ▒Ģ Õ¤ŗÕ┐Ā µĪāÕ▒▒ÕłĆÕēŻńĢīŃü«ķøäŃĆŹÕø│ķī▓Ńü½ŃéłŃéŖŃüŠ […]
ÕģłµŚźŃĆüµĪāÕĘØķĢĘÕÉēŃü«õ║ŗŃü¦HPŃüŗŃéēŃüŖÕĢÅÕÉłŃüøŃéÆķĀéŃüŹŃĆüÕ░æŃüŚŃéäŃéŖÕÅ¢ŃéŖŃéÆŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńČŠµØēĶéīŃü«ńäĪķŖśŃü½ŌĆصĪāÕĘØŌĆØŃü«µźĄŃéüŃéÆĶ”ŗŃéŗõ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃééŃüØŃééÕ£©ķŖśŃü«µĪāÕĘØŃéÆĶ”ŗŃéŗµ®¤õ╝ÜŃüīµ«åŃü®Ńü¬ŃüÅŃĆéŃĆīõĮĢµĢģŃü½ńČŠµØēŃüīµĪāÕĘØ’╝¤ŃĆŹŃü©µĆØŃüäŃüżŃüżŃééŃüØŃéīõ╗źõĖŖĶĆāŃüłŃü¤õ║ŗŃüīŃüé […]
ŃüäŃüżŃééÕż¦ÕżēŃüŖõĖ¢Ķ®▒Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗµ¢╣ŃüŗŃéēµŁŻÕ«ŚÕŹüÕō▓Õ▒ĢŃü«Õø│ķī▓ŃéÆķĆüŃüŻŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéķüÄÕÄ╗Ńü½ŃüéŃüŻŃü¤Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆüµÄ▓Ķ╝ēÕłĆÕēŻŃü╗Ńü╝Õģ©Ńü”ŃüīŃé½Ńā®Ńā╝Õģ©Ķ║½ÕāÅŃĆüŃüØŃüŚŃü”Õģ©Ńü”Ńü½Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃĆéŃééŃüĪŃéŹŃéōµÄ▓Ķ╝ēŃü«Ķ½¢µ¢ćŃü»ŃüÖŃü░ŃéēŃüŚŃüÅŃĆéµÄ▓Ķ╝ēÕłĆÕēŻÕģ©Ńü”Ńü½Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü»ŃĆüÕłĆÕēŻÕ▒ĢÕø│ķī▓ÕÅ▓õĖŖ […]
Õ╣┤µ£½ŃüŗŃéēµŗŁŃüäŃüīŃü╗Ńü╝ńäĪŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüµōéŃüŻŃü¤ńē®ŃüīŃüéŃüŻŃü¤Ńü»ŃüÜŃü©Ńü«ŃéōŃü│ŃéŖŃüŚŃü”ŃüäŃü”ŃĆéŃüäŃü¢µÄóŃüÖŃü©ńäĪŃüÅŃü”ŃĆüµōéŃéŗŃĆé’╝łŃāĪŃāÄŃé”Ńü«µ¢╣’╝ēĶē»Ńüäõ║ŗŃü»ÕłåŃüŗŃüŻŃü”ŃüäŃéŗķēäĶéīŃü¬Ńü«Ńü¦µ░ŚµīüŃüĪÕżÜŃéüŃü½ŃĆé ŃüŚŃü░ŃéēŃüÅÕēŹŃü½Ķ▓ĘŃüŻŃü¤Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½ńöŻŃü«ńŻüķēäķē▒ńĄÉµÖČŃü»ķ®ÜŃüÅń©ŗŃü½ŃāĆŃāĪ […]
ŃüĪŃéćŃüŻŃü©Ńā”Ńā╝ŃāóŃā®Ńé╣Ńü¬ķŠŹŃü¦ŃüÖŃüīŃĆéÕÅ»µäøŃüÅŃü”ńĄÉµ¦ŗÕźĮŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆé
õ║¼ķāĮÕøĮń½ŗÕŹÜńē®ķż©Ńü½Ńü”ŃĆüĶ¬┐µ¤╗ńĀöń®ČŃü«Ńü¤Ńéüµ¤ÉÕż¬ÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōŃéÆĶĪīŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ║¼ÕŹÜŃüĢŃéōŃü¦Ńü«Õć║Õ╝ĄµÄĪµŗōõĮ£µźŁŃü»õĮĢÕø×ńø«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéŃĆéõĮĢÕ║”ŃüŗŃüŖŃüōŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕēŹÕø×ŃüŗŃéēŃü»ŃééŃüåõĮĢÕ╣┤ŃüŗńĄīķüÄŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«õĮĢÕ╣┤ŃüŗŃü«ķ¢ōŃü½ŃĆüń¦üŃü«ńø«Ńü»ÕģēķćÅŃüīÕ░æŃü¬ŃüäÕĀ┤Ńü¦Ńü« […]
õ╗ŖÕø×Ńü»ÕĮōńĢ¬Ńü¦ŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüÕ╣│Õ«ēµÖéõ╗Ż’Į×µ▒¤µłĖÕŠīµ£¤ŃüŠŃü¦Ńü«ÕłĆŃéÆķøåŃéüŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆńäĪķŖś’╝łõ║öµØĪ’╝ēŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ē’╝ÆÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆķĪŹķŖśŃĆĆÕøĮõ┐Ŗ’╝łõ║īÕŁŚÕøĮõ┐Ŗ’╝ēŃĆĆ’╝łÕøĮµīćÕ«ÜķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓Ī’╝ē’╝ōÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆĶéźÕēŹÕøĮÕ┐ĀÕÉē’╝öÕÅĘŃĆĆń¤ŁÕłĆŃĆĆŃĆĆ […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕéÖÕĘ×ķĢĘĶł╣õĮŵ©¬Õ▒▒ńźÉÕīģ’╝łń¤│ÕłćÕŖöń«Łńź×ńżŠĶöĄ’╝ēŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆƵśÄµ▓╗õĖēÕ╣┤Õģ½µ£łµŚź ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆńæ×µ│ēÕĀĆõ║Ģõ┐Ŗń¦Ć (ĶŖ▒µŖ╝)ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕå©Õ▓ĪµĖģĶĪīµēƵīüŃĆƵśŁÕÆīÕŹüõ║īõĖüõĖæõ║īµ£łÕÉēµŚź Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕŖĀĶ│ĆÕøĮõĮŵŁŻÕ│» µ¢╝Õéśń¼Āõ║ŁõĮ£õ╣ŗ µĆØķŻøķÄīÕĆēµ£¤ µ╝éõĖƵ¢ćÕŁŚõĖŖŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆƵśŁÕÆīõĖÖ […]
ÕłĆŃĆĆńäĪķŖśŃĆĆńø┤µ▒¤Õ┐Śµ┤źÕż¦ÕÆīµēŗµÄ╗Õīģµ░ÅŃüīńŠÄµ┐āÕøĮÕ┐Śµ┤źŃü½ń¦╗õĮÅŃüŚÕģ╝µ░ÅŃü©µö╣ÕÉŹŃĆüķÄīÕĆēµÖéõ╗Żµ£½µ£¤ŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚµ£ØµÖéõ╗ŻŃü½ŃüŗŃüæŃü”µ┤╗Ķ║ŹŃüŚõĖĆķ¢ĆŃüīń╣üµĀäŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«õ║īõ╗Żńø«õ╗źķÖŹÕÅŖŃü│õĖĆķ¢ĆŃü«ńĘÅń¦░Ńüīńø┤µ▒¤Õ┐Śµ┤źŃü¦ŃüÖŃĆé’╝łÕłĆŃü«õĖ¢ńĢīŃü¦Ńü»ŃĆīÕ┐Śµ┤źŃĆŹŃĆīńø┤µ▒¤ŃĆŹŃü©ÕłĆÕĘźÕÉŹŃü«µ¦śŃü½õĮ┐ńö©ŃüŚŃü” […]
µ£▒ķŖśŃĆüÕģ╝Õ¤║ŃĆĆÕģ½ÕŹüõĖĆń┐üµØŠÕ║Ą(ĶŖ▒µŖ╝) ŃüŚŃü░ŃéēŃüÅÕēŹŃü«ÕłĆÕēŻńŠÄĶĪōŃĆīÕÉŹÕłĆķææĶ│×ŃĆŹŃü½µØźÕøĮÕģēŃü«µØŠÕ║Ąµ£▒ķŖśŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüõ╗źõĖŗŃüØŃü«Ķ¦ŻĶ¬¼ŃéÆÕ╝Ģńö©ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé ŃĆÄŃĆīµØŠĶÅ┤ŃĆŹŃü»µśÄµ▓╗µÖéõ╗ŻŃü«µĢģÕ«¤Õ«ČŃü¦ŃĆüµØ▒õ║¼ÕĖØÕ«żÕŹÜńē®ķż©(ńÅŠµØ▒õ║¼ÕøĮń½ŗÕŹÜńē®ķż©)Ńü«ÕŁ”ĶŖĖÕ¦öÕōĪŃéÆÕŗÖŃéü […]
õ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©Õģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝ÜŃüīńÅŠÕ£©Ńü«µ¢ćÕī¢ĶŖĖĶĪōõ╝Üķż©Ńü½ń¦╗ŃéŗÕēŹŃĆüõ║¼ķāĮń¦üÕŁ”õ╝Üķż©Ńü¦ĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃü¤ÕĮōµÖéŃĆüķææÕ«ÜÕłĆŃü½Õģ╝ÕÉēŃüīÕć║Ńü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃü«µÖéµŗØĶ”ŗŃüŚŃü¤Õģ╝ÕÉēŃüīõ║¼ķāĮÕøĮń½ŗÕŹÜńē®ķż©Ńü½ÕģźŃéŗÕēŹŃü«ŃüōŃü«ÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆéŃééŃüå’╝æ’╝Ś’╝ī’╝śÕ╣┤Ńü╗Ńü®ÕēŹŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéŃĆé’╝æŃü«µ£ŁŃü¦ŃĆüńĄČÕ»ŠÕĮōŃü¤ŃéŖ […]
ÕŁ½ÕģŁÕģ╝ÕģāŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüńä╝ŃüŹÕłāŃüīŃüŗŃü¬ŃéŖµĢ┤ŃüåŃé┐ŃéżŃāŚŃü¦ŃüÖŃĆé
ńÅŠµÖéńé╣Ńü¦µēŗÕģāŃü½ŃüéŃéŗÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆÕģ©Ńü”ŃüōŃü«µ¦śŃü¬ńö╗ÕāÅŃü½õĮ£µłÉõĖŁŃü¦ŃüÖŃĆéÕģ©õĮōŃü½Ńü¤ŃéÅŃü┐Ńü¬Ńü®ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüĶć¬ńäČŃü¦Õ½īŃüäŃüśŃéāŃü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé
Õ║”ŃĆģŃā¢ŃāŁŃé░Ńü½µøĖŃüäŃü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüń¦üŃü»Õģźķ╣┐ŃééÕźĮŃüŹŃü¦ŃüÖŃüīÕĮōķ║╗ŃééÕż¦ÕźĮŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃüØŃü«ÕĮōķ║╗Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüńøĖÕĘ×ĶĪīÕģēŃü½ķØ×ÕĖĖŃü½õ╝╝Ńü¤õĮ£ķó©Ńü©ŃüĢŃéīŃĆüķææÕ«ÜŃü¦Ńü»ÕĮōķ║╗Ńü©ŃüÖŃéŗŃüŗĶĪīÕģēŃü©ŃüÖŃéŗŃüŗŃĆüÕłżµ¢ŁŃü«ķøŻŃüŚŃüäńē®ŃééÕżÜŃüäŃü©ŃüäŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕłĆÕ▒ŗŃüĢŃéōŃü«ŃĆīÕĮōķ║╗ŃĆŹŃü«ÕĢåÕōüĶ¦ŻĶ¬¼Ńü¬Ńü®Ńü½ŃĆü […]
Ķ¬┐µ¤╗ńĀöń®Čńö©Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüÕć║Õ╝ĄŃü¦ŃĆīõ║½õ┐ØÕÉŹńē® ń©▓Ķæēµ▒¤ŃĆŹŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃĆīµ▒¤ŃĆŹŃéƵēŗŃü½ÕÅ¢ŃüŻŃü¤Ńü«Ńü»ķüÄÕÄ╗ŃüŖŃüØŃéēŃüÅ’╝æ’╝ÉÕÅŻń©ŗÕ║”Ńü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü«ń©▓Ķæēµ▒¤Ńü«Õć║µØźŃü»µĀ╝ÕłźŃü¦ŃüÖŃĆéÕ£░ÕłāŃü«Õå┤ŃüłŃü»Õ░ŗÕĖĖŃü¬ŃéēŃü¢ŃéŗŃééŃü«ŃĆéÕłĆńŠÄÕÉŹÕłĆķææĶ│×Ńü¦Ńü»ŃĆīÕĮ╝Ńü«õĮ£õĖŁ […]
õĖĪķļµ¦ŹŃü«µŗŁŃüäõĮ£µźŁŃĆéõĖĪķļŃü¬Ńü«Ńü¦’╝öķØóŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃéäŃéŖµ¢╣Ńü»ĶżćµĢ░ŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüķļŃü«ÕĘ”ķØóŃüŗŃéēÕ¦ŗŃéüŃéŗŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüµ¼ĪŃü½ĶŻÅŃü½Ķ┐öŃüŚŃĆüŃüŠŃü¤ÕĘ”ķØóŃĆéµēŗŃéÆÕżēŃüłŃü”ÕÅ│ķØóŃĆüĶŻÅĶ┐öŃüŚŃü”ŃüŠŃü¤ÕÅ│ķØóŃĆéŃüōŃéīŃü¦ÕøøķØóŃĆéµēŗŃéÆÕżēŃüłŃü¬ŃüäŃāæŃé┐Ńā╝Ńā│ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéķļŃü«ÕĘ”ÕÅ│õĖĪķØóÕÉīµÖéŃü½ĶĪīŃüäŃĆüĶŻÅŃü½ […]
µŚźÕłĆõ┐Øõ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©ŃĆüń¦ŗŃü«ńĀöõ┐«µŚģĶĪīŃüīõ╣ģŃĆģŃü½ĶĪīŃéÅŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕÅéÕŖĀĶĆģŃü»’╝Æ’╝ÉÕÉŹÕ╝▒ŃĆéŃüōŃéōŃü¬Ńü½ÕżÜŃüäńĀöõ┐«µŚģĶĪīŃü»ń¦üŃüīÕģźõ╝ÜŃüŚŃü”õ╗źķÖŹŃü¦Ńü»ÕłØŃéüŃü”ŃüĀŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆéĶĪīŃüŹÕģłŃü»ķĢĘĶł╣ÕłĆÕēŻÕŹÜńē®ķż©Ńü©Õż¦Õ▒▒ńźćńź×ńżŠŃĆéķĢĘĶł╣ÕłĆÕēŻÕŹÜŃü¦Ńü»ńÅŠÕ£©ŃĆÄń¦ŗÕŁŻńē╣ÕłźÕ▒ĢŃĆīĶĄżńŠĮÕłĆŃü©Ńü¤Ńü®Ńéŗµł”ÕŠīŃü« […]
µ╗ŗĶ│Ćń£īµØ▒Ķ┐æµ▒¤ÕĖéŃü«Ķ┐æµ▒¤ÕĢåõ║║ÕŹÜńē®ķż©Ńü½Ńü”ŃĆīÕīŚÕĘصŁŻÕ┐ĀŃĆĆÕ╣╗Ńü«ÕłĆÕēŻŃü½µīæŃéĆŃĆĆŃā╝ÕģĄõĖ╗Õż¦ńżŠÕŠĪńź×Õ«ØÕŠ®ÕģāŃüĖŃü«ķüōŃā╝ŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéĶ®│ŃüŚŃüÅŃü»ŃāüŃā®ŃéĘŃéÆŃüöĶ”¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆéÕīŚÕĘصŁŻÕ┐ĀÕłĆÕīĀHP
µś©µŚźńĀöŃüÄÕĀ┤Ńü½Ńü”ŃĆüÕŹŚń┤ĆķćŹÕøĮŃü«ĶäćÕĘ«ŃéƵŗØĶ”ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕłØõ╗ŻŃü»õ╣ģµ¢╣µī»ŃéŖŃüŗŃééŃü¦ŃüÖŃĆéķćŹŃüŁŃüīÕÄÜŃüÅŃĆüķļŃüīŃéäŃéäķ½śŃüÅŃĆüķļգ░Õ╣ģŃüīŃüŗŃü¬ŃéŖÕ║āŃüäķĆĀŃéŖĶŠ╝Ńü┐Ńü¦ŃüÖŃĆéÕ£░ķīĄŃüīŃéłŃüÅõ╗śŃüŹŃĆüÕģ©Ķ║½Ńü½ń┤░ŃüŗŃü¬Õ£░µÖ»ŃüīĶæŚŃüŚŃüÅńÅŠŃéīń½ŗõĮōµä¤ŃüīÕćäŃüäÕ£░ķēäŃĆéńø┤ÕłāĶ¬┐Ńü¦ÕŹŚń┤ĆŃü«Õż¦ÕÆīõ╝ØŃü©ÕłåķĪ×ŃüĢŃéī […]
ŃüōŃéīŃü«ÕåģµøćŃéÆÕ╝ĢŃüÅŃĆéÕģłµŚźŃĆüń┤░ÕÉŹÕĆēŃüŠŃü¦Ńü«ÕĘźń©ŗŃü»Õż¦ÕżēĶē»ŃüäńĀźÕĮōŃü¤ŃéŖŃüĀŃü©µøĖŃüäŃü¤ŃüīŃĆüÕåģµøćŃééÕ╝ĢŃüŹŃéäŃüÖŃüäŃü©Ńü»ķÖÉŃéēŃü¬ŃüäŃĆéŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃü¦ŃĆüŃéäŃü»ŃéŖÕåģµøćÕĘźń©ŗŃü»Õ░æŃĆģĶŗ”ÕŖ┤ŃéÆŃüÖŃéŗõ║ŗŃü½Ńü¬ŃüŻŃü¤ŃĆéĶ┐æÕ╣┤ŃāĪŃéżŃā│Ńü©ŃüŚŃü”õĮ┐ńö©ŃüŚŃü”ŃüŹŃü¤ÕåģµøćńĀźŃü»Ķ╗ÆõĖ”Ńü┐ÕŖ╣ŃüŗŃüÜŃĆüõ╣ģŃĆģŃü½HPŃĆīÕż® […]
õ╣▒ŃéīÕłāŃü«ĶéźÕēŹÕłĆŃĆüńé╣Õ£©ŃüÖŃéŗķīåŃü«ķÖżÕÄ╗ŃüŗŃéēń┤░ÕÉŹÕĆēŃĆéń┤░ÕÉŹÕĆēŃüīŃüōŃéōŃü¬Ńü½ŃééÕŖ╣ŃüäŃü”ŃüÅŃéīŃéŗÕłĆŃü»õ╣ģŃĆģŃüŗŃééŃĆéńĀźÕĮōŃü¤ŃéŖŃü»ŃéĄŃā®ŃāāŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃü”Õ╝ĄŃéŖŃééŃüéŃéŗŃĆéÕēŹÕĘźń©ŗŃü«ńĀźńø«ŃüīµŖ£ŃüæŃéäŃüÖŃüÅŃĆüõ╗Ŗõ╗śŃüÅńĀźńø«Ńü»µĄģŃüÅń┤░ŃüŗŃüäŃĆéńø┤ÕłāŃü«ĶéźÕēŹÕłĆŃéłŃéŖµ¢ŁńäČńĀöŃüÄŃéäŃüÖŃüäŃĆéŃü¤ŃüĀŃĆüÕåģµøćŃéŖ […]
Ķ¼øÕĖ½Ńü»ńåŖĶ░ĘÕÆīÕ╣│Õģłńö¤ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆŃüŖŃüØŃéēŃüÅõ║īÕ░║ÕģŁÕ»Ėń©ŗŃü¦ķĢĘÕ»ĖŃĆüńø«ń½ŗŃüŻŃü”Ķģ░ÕÅŹŃéŖŃĆüÕģāÕ╣ģÕż¦ÕżēÕ║āŃüÅĶĖÅŃéōÕ╝ĄŃéŖŃüīŃüŗŃü¬ŃéŖÕ╝ĘŃüÅÕ«īÕģ©Ńü½Õ┐£µ░ĖÕ¦┐ŃĆéĶģ░Ńü«ķ¢ŗŃüÅõ║ÆŃü«ńø«Ńü¦ŃĆüÕģāŃü«’╝Æ’╝ÉŃÄØń©ŗÕ║”Ńü»ķļŃü½Õ▒ŖŃüŹńÜåńä╝ńŖČŃĆéÕģ©õĮōŃü½ÕłāĶéīŃüīńø«ń½ŗŃüżŃĆéµŻÆµ©ŗŃü©ķĆŻŃéīµ©ŗŃéÆķÄ║õĖŖŃü¦õĖĖńĢÖŃéüŃĆé […]
ÕģłµŚźµØźķĆ▓ŃéüŃü”ŃüäŃéŗÕż¦Õż¬ÕłĆ’╝łÕż¦Ķ¢ÖÕłĆ’╝ēŃü«µŖ╝ÕĮóŃü«ÕēŹŃü½ŃĆüÕÅżÕéÖÕēŹÕ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃĆüĶéźÕēŹÕ┐ĀÕÉēÕłĆŃü©ŃĆüõĖĪÕłāń¤ŁÕłĆŃü«µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆéŃüōŃü«õĖĪÕłāń¤ŁÕłĆŃü»õ╗źÕēŹŃéłŃéŖõ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©ķĢĘŃü«ÕÉēµØæµ╗ŗÕż¬Õģłńö¤ŃüŗŃéēŃüŖĶü×ŃüŹŃüŚŃü”ŃüäŃü¤µ¢ćµśÄÕŹüõĖēÕ╣┤ń┤ĆŃü«õĖĪÕłāń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé’╝łµŚźÕłĆõ┐Øõ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©’╝æ’╝ɵ£łõŠŗõ╝Ü […]
µŖ╝ÕĮóÕ▒Ģńż║Ńü«õ╗ČŃü¦ÕłĆÕēŻÕŹÜŃü½ĶĪīŃüŻŃü¤µÖéŃĆüµ£©ńĪ»’╝łŃééŃüŻŃüæŃéō’╝ēŃü«ÕŁśÕ£©ŃéƵĢÖŃüłŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃāćŃéóŃé┤Ńé╣ŃāåŃéŻŃā╝ŃāŗŃü«ķĆ▒ÕłŖµŚźµ£¼ÕłĆ’╝ś’╝öÕÅĘŃü«ńē╣ķøåĶ©śõ║ŗŃĆīµŖ╝ÕĮóŃü«ńŠÄÕŁ”ŃĆŹŃü½ŃééµøĖŃüäŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüń¦üŃüīµŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōµÖéŃü½µ»ÄÕø×õĖĆńĢ¬Õ╝ĘŃüŵäÅĶŁśŃüŚŃü”ŃüäŃéŗõ║ŗŃü»ŃĆüµŁŻńó║Ńü¬µŖ╝ÕĮóŃéƵÅÅŃüÅõ║ŗ […]
µā│ÕāÅõ╗źõĖŖŃü½ķĢĘÕż¦Ńü¬Õż¬ÕłĆ’╝łĶ¢ÖÕłĆ’╝ēŃĆéÕÅ│Ńü½Ķ▓╝ŃéēŃéīŃü¤µŖ╝ÕĮóŃü¦’╝ÆÕ░║’╝öÕ»Ė’╝ĢÕłåŃü«ÕłĆŃĆé
µĢ░Õ╣┤ÕēŹŃĆüµ¤ÉÕŠĪÕ««µ¦śÕŠĪµēĆĶöĄŃü«Õż¦Õż¬ÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü«ÕłČõĮ£ŃéÆõ║łÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüń¦üŃüīĶé®ŃéÆķ¬©µŖśŃüŚŃü”ŃüŚŃüŠŃüäÕłČõĮ£Õć║µØźŃüÜŃü½ŃüŖŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶé®Ńü«Ķ¬┐ÕŁÉŃééŃüÖŃüŻŃüŗŃéŖĶē»ŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüµŖ╝ÕĮóŃéÆŃĆé’╝łHPŃüĖŃü«µÄ▓Ķ╝ēŃü«ŃüŖĶ©▒ŃüŚŃéÆķĀéŃüäŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖ’╝ē µŖ╝ÕĮóńö©ń┤ÖŃéÆĶŻüµ¢ŁŃĆéÕĮō […]
Õģźķ╣┐ŃĆüÕż®ńŗŚŃĆüÕŹŚń┤ĆńŁēŃéÆĶżćµĢ░µŗØĶ”ŗŃĆéÕłØõ╗ŻŃü«ÕŹŚń┤ĆŃü»Õ║”ŃĆģĶ”ŗŃéŗŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕŠīõ╗ŻŃéÆĶ”ŗŃéŗµ®¤õ╝ÜŃü»ŃüØŃéīń©ŗÕżÜŃüÅŃü¬ŃüÅŃĆéķüÄÕÄ╗Ńü½’╝Æõ╗Ż’╝ōõ╗ŻŃü«ÕŹŚń┤ĆŃü½Õć║õ╝ÜŃüŻŃü¤µÖéŃü»ŃüéŃéīŃüōŃéīĶĆāŃüłŃéŗõ║ŗŃééŃü¬ŃüŵĄüŃüŚŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü»Õ░æŃüŚŃéåŃüŻŃüÅŃéŖµŗØĶ”ŗŃĆéńĄÉµ×£ŃĆüõŠŗŃüłŃü░Õģźµ£ŁķææÕ«ÜŃü½ […]
’╝æÕÅĘŃĆĆÕłĆķĢĘÕ»ĖÕÅŹŃéŖµĄģŃĆéÕ░ÅķīĄŃü«õĖüÕŁÉÕłāŃü¦µł┐ń┤░ŃüŵÅāŃéÅŃüÜŃĆéńä╝ŃüŹÕć║ŃüŚńäĪŃüŚŃĆéĶĪ©Ńü½ķŠŹŃĆüĶŻÅŃü½ķ¢ōŃü«Õ║āŃüäĶŁĘµæ®ń«ĖŃĆéÕż¦ŃüŹŃü¬ÕłĆŃĆéÕłØĶ”ŗŃü»Õģ©ŃüÅÕłåŃüŗŃéēŃüÜŃĆéõĮĢÕ║”ŃüŗĶ”ŗŃéŗŃüåŃüĪŃü½ŃĆīŃüōŃü«Ķŗ”µēŗµäÅĶŁśŃü»ŃüäŃüżŃééŃü«ŃüéŃéīŃüŗ’╝¤ŃĆŹŃü©µĆØŃüłŃü”µØźŃü¤ŃĆéÕĮ½Ńü»Õ░æŃüŚµĄģŃéüŃüĀŃüīķ▒ŚŃéäŃé»Ńā¬Ńé»Ńā¬Ńü«ńø«Ńü»ŃüØ […]
ń¦üŃĆüŃüÜŃüŻŃü©õ╗źÕēŹŃüŗŃéēµĆØŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕłĆŃéÆĶ”ŗŃéŗŃéłŃéŖÕłĆĶüĘŃü«õ╗Ģõ║ŗŃü«µ¢╣ŃüīŃüÜŃüŻŃü©Ķ”ŗŃü”ŃüäŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé õ╗Ŗµ£łŃééµ£¼ĶāĮÕ»║Õż¦Ķ│ōµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü¦Ńü«ÕłĆĶüĘĶĆģÕ«¤µ╝öŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé ’╝╗ķ¢ŗÕé¼µŚź’╝Į’╝Öµ£ł’╝ƵŚź’╝łÕ£¤’╝ēŃĆü’╝ōµŚź’╝łµŚź’╝ēŃĆü9µŚź’╝łÕ£¤’╝ēŃĆü10µŚź’╝łµŚź’╝ēŃĆü16µŚź’╝łÕ£¤’╝ē […]
µ£¼ĶāĮÕ»║Õż¦Ķ│ōµ«┐Õ«Øńē®ķż©ÕłĆĶüĘÕ«¤µ╝öŃü½Ńü”ŃĆüµØŠńö░µ¤äÕĘ╗ÕĖ½ŃüīÕ«¤µ╝öŃü«µ¦śÕŁÉŃéƵƫÕĮ▒ŃüŚŃü”ŃüÅŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĖŖŃüŗŃéēŃĆüÕż¦ŃüŹŃéüŃü«ŃüŚŃéāŃüÅŃéŖńĀöŃüÄ’╝łń¬üŃüŹ’╝ēŃĆüÕĘ”ÕÅ│Ńü«ÕŗĢŃüŹŃü«Õ░ÅŃüĢŃüäŃüŚŃéāŃüÅŃéŖńĀöŃüÄ’╝łń¬üŃüŹ’╝ēŃĆüķØóÕĮó’╝łŃüżŃéēŃü¬ŃéŖ’╝ēÕ╝ĢŃüŹŃĆüµ░┤Õ╣│Õ╝ĢŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéÕÅ│Ńü»Õż¦ķ¢ĆńĀöÕĖ½Ńü¦ŃüÖŃĆé ’╝Öµ£ł’╝æ’╝ɵ£ł […]
µ£¼ĶāĮÕ»║ŃüĢŃéōŃü«Õż¦Ķ│ōµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü½Ńü”µśĀńö╗Ńü«Õģ¼ķ¢ŗŃüīÕ¦ŗŃüŠŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüķĆ▒µ£½Ńü»ÕłĆĶüĘĶĆģŃü½ŃéłŃéŗÕ«¤µ╝öŃééĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõ╗ŖµŚźŃü»ń¦üŃééÕÅéÕŖĀŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃĆüµØŠńö░µ¤äÕĘ╗ÕĖ½ŃĆüÕż¦ķ¢ĆńĀöÕĖ½Ńü©Ńü©ŃééŃü½Õ«¤µ╝öŃéÆŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗ŖķĆ▒ŃééÕłĆĶüĘĶĆģŃü«Õ«¤µ╝öŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéń¦üŃü»’╝Æ’╝¢µŚźŃü½ńĀöńŻ©ŃéÆŃüĢ […]
ń¦üŃü«Õ╣┤õ╗ŻŃü¦µ£©ķĆĀŃü«µĀĪĶłÄŃü½ķĆÜŃüŻŃü¤õ║║Ńü»Õ░æŃü¬ŃüäŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüń¦üŃü»õĖŁÕŁ”Ńü«’╝ōÕ╣┤ķ¢ōŃĆüµ£©ķĆĀŃü«µĀĪĶłÄŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéŃé«ŃéĘŃé«ŃéĘŃü¦ŃüÖŃüīÕ║āŃüÅķćŹÕÄÜŃü¬Õ╗ŖõĖŗŃéäµēŗŃé║Ńā¼Ńü¦ŃāäŃā½ŃāäŃā½Ńü«µēŗµæ║ŃéŖŃü»õĖĆõĮōõĮĢŃü«µ£©ŃüĀŃüŻŃü¤ŃéōŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéÕĮōµÖéŃü»ŃüéŃü«µĀĪĶłÄŃü«Ķē»ŃüĢŃü¬ŃéōŃü”ÕłåŃüŗŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ […]
Ķŗ”ń»ĆÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮó270µ×ÜŃĆüńŁåŃééĶē▓ŃĆģõĮ┐ŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõ╗ŖÕż£ŃéłŃüåŃéäŃüŵÄ┤ŃéōŃüĀŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆéķĢĘŃüŗŃüŻŃü¤ŌĆ”ŃĆéõ╗ŖŃüŠŃü¦ŃüÜŃüŻŃü©ŃĆüÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÅÅŃüÅõ║ŗŃéÆ”ńĘ┤ń┐Æ”Ńü©Ķ©ĆŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüØŃéīŃü»µ£¼ÕĮōŃüĀŃüŻŃü¤ŃéōŃü¦ŃüÖŃĆéń¦üŃü«õĖŁŃü¦Ńü»µ£¼ÕĮōŃü½ŃüÜŃüŻŃü© […]
õ╗ŖÕø×Ńü»µ£¼ķā©ŃüŗŃéēŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆķĢĘÕ»ĖŃĆüÕ░æŃüŚń┤░Ķ║½ŃĆéĶĖÅŃéōÕ╝ĄŃéŖŃüéŃéŖŃĆüÕģłŃü¦ń┤░ŃüÅŃü¬ŃéŗŃĆéÕÅŹŃéŖµĘ▒ŃüÅĶÅ»ĶĪ©µ░ŚÕæ│ŃĆéÕģāµØźŃééŃüåÕ░æŃüŚÕģłÕ╣ģŃüīµ£ēŃéŖµø┤Ńü½ÕŖøÕ╝ĘŃüäÕ¦┐ŃĆéÕ£░ķēäĶ®░Ńü┐ŃĆüńģ¦ŃéŗŃĆéõĖŁńø┤ÕłāŃü¦Õ░æŃüŚµ╣ŠŃéīŃĆéÕłāõĖŁŃü«ÕāŹŃüŹŃü»Õ░æŃü¬ŃüäŃĆéŃüäŃüżŃüŗŃü»Ķ”ÜŃüłŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃüīÕłĆńŠÄŃü«µ£¼ķā©ķææÕ«ÜÕłĆ […]
õĖŖķćÄõ┐«ĶĘ»ŃüĢŃéōŃü½ķĆĀŃüŻŃü”ķĀéŃüäŃü¤ŃĆīĶĘ│ķø©ŃĆŹŃü«Õż¦ÕÆīÕÅżÕŹ░Ńü¦ŃüÖŃĆéõĖüÕ»¦Ńü¬õĮ£ŃéŖŃü«Õ▒ŗõ╣ģµØēŃü«ÕÅ»µäøŃüäÕ░Åń«▒Ńü½ÕģźŃéīŃü”ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ń¼¼’╝ōÕ«ż-Õż¦ÕÆīÕÅżÕŹ░(ķŖģÕŹ░) | õĖŖķćÄŃü«ÕŹÜńē®ķż© (nihonbi.sakura.ne.jp)
ÕģłµŚźµØźŃĆüķÄīÕĆēµ£¤Õ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃĆüÕŹŚÕīŚµ£Øµ£¤Õ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃĆüÕ«żńö║ÕŠīµ£¤Õ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃĆüÕŹŚÕīŚµ£Øµ£½µ£¤õ╣āĶć│Õ«żńö║ÕłØµ£¤Õ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃĆüķÄīÕĆēµ£½µ£¤õ╣āĶć│ÕŹŚÕīŚµ£Øµ£¤Õ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆéŃüŚŃü░ŃéēŃüÅŃü»µ£ĆĶ┐æÕźĮŃüŹŃü¬ńŁåŃü¦µÅÅŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõĖŗµēŗŃüĢŃü½µé▓ŃüŚŃüÅŃü¬ŃéŖõ╣ģŃĆģŃü½õĖŗńŁåµśźĶÜĢķŻ¤ÕÅČÕŻ░Ńü½ […]
õ╗ŖµŚźŃü»ńźćÕ£ÆńźŁÕ▒▒ķēŠÕĘĪĶĪīŃü¦ŃĆüÕ░æŃüŚŃüĀŃüæĶ”ŗŃü½ĶĪīŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń½ŗŃüŻŃü”Õ▒ģŃéŗŃüĀŃüæŃü¦µ▒ŚŃüīŃü½ŃüśŃü┐Õć║ŃéŗµÜæŃü䵌źŃü¦ŃüÖŃĆéķĢĘÕłĆķēŠŃü«ŃüŖń©ÜÕģÉŃüĢŃéōŃü«µ│©ķĆŻńĖäÕłćŃéŖŃééńäĪõ║ŗõĖĆÕż¬ÕłĆŃü¦µłÉÕŖ¤ŃüŚŃü¤ŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéõ╗źÕēŹŃüōŃü«Õż¬ÕłĆŃü»ÕĘ”ĶĪīń¦ĆŃüĀŃü©Ķü×ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤Ńüīõ╗ŖŃééŃüØŃüåŃü¬ŃéōŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé ķĢĘÕłĆŃĆĆ […]
µ¤┤ńö░µ×£Ńü«Ńé│Ńā¼Ńé»ŃéĘŃā¦Ńā│Ńü»ÕŻ«Õż¦Ńü¦ŃüØŃü«µĢ░Ńü»µĢ░ÕŹāŃü©ŃééŃüäŃéÅŃéīŃéŗŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüõĖĆĶł¼µäøÕłĆÕ«ČŃü¦Ńü¬ŃüÅÕłĆŃü«ĶŻĮõĮ£ĶĆģŃü¦ŃüéŃéŗõ║║ńē®Ńü«Ńé│Ńā¼Ńé»ŃéĘŃā¦Ńā│Ńü©Ńü»Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬ńē®ŃüĀŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéÕģłµŚźĶ¬ŁŃéōŃü¦ŃüäŃü¤µ£¼Ńü½µÖ®Õ╣┤Ńü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗĶć¬ńŁåŃü«ĶöĄÕłĆńø«ķī▓ŃüīŃüéŃéŗõ║ŗŃüīĶ©śŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃüØ […]
Ķ¬ŁŃéōŃü¦ŃüäŃü¤µ£¼Ńü½µ¤┤ńö░µ×£Ńü«õ║ŗŃüīµøĖŃüŗŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕłĆķŹøÕåČŃü¦ŃüéŃéŖÕż¦ÕżēŃü¬ÕÅÄķøåÕ«ČŃü¦ŃééŃüéŃüŻŃü¤õ║ŗŃü»ń¤źŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüĶ®│ŃüŚŃüÅń¤źŃéēŃüÜŃü¦ŃĆéķ揵¢ćŃü«Õ░ÅÕż£ÕĘ”µ¢ćÕŁŚŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃü¤µ¢╣Ńü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüŁŃĆéŃāŹŃāāŃāłµż£ń┤óŃüÖŃéŗŃü©ŃüØŃü«õ║ŗŃüīµ▓óÕ▒▒Õć║Ńü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵤┤ńö░µ×£Ńü«ń¤ŁÕłĆŃü»ķüÄÕÄ╗’╝Æ […]
’╝æÕÅĘŃĆĆÕłĆń¤ŁÕ»ĖŃü¦ĶäćÕĘ«ŃéĄŃéżŃé║ŃüŗŃééŃĆéµ£½ÕéÖÕēŹŃĆéÕģ©õĮōŃü½ŃéłŃüÅÕÅŹŃéŗŃĆéµ£½ÕéÖÕēŹŃü«õĖüÕŁÉŃĆéÕģ©Ķ║½Ńü½õ╣▒ŃéīµśĀŃéŖŃüīŃéłŃüÅńÅŠŃéīŃéŗŃĆéĶĪ©ĶŻÅŃü½Õģ½Õ╣ĪÕż¦ĶÅ®Ķ¢®Ńü©µśźµŚźÕż¦µśÄńź×ŃĆéõĖŖŃü½µŻÆµ©ŗŃü©ķĆŻŃéīµ©ŗŃĆéÕŗØÕģēµÖéõ╗ŻŃüŗńźÉիܵÖéõ╗ŻŃüŗŃü«Õłżµ¢ŁŃü»µĪłÕż¢ķøŻŃüŚŃüÅŃĆéŃĆéŃüōŃü«Õ░ŵī»ŃéŖŃü¬ķø░Õø▓µ░ŚŃüīÕŗØÕģēŃéēŃüŚŃüĢµ║ĆĶ╝ē […]
ŃüĪŃéćŃüōŃüŻŃü©ŃüŖĶŖ▒Õ▒ŗŃüĢŃéōŃü½ĶĪīŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃéäŃü»ŃéŖÕ▒▒Ńü¦ŃüŗŃüŻŃüōŃüäŃüäÕĮóŃü«ńä╝ŃüŹńē®Ńü«ńĀ┤ńēćŃéÆĶ”ŗŃüżŃüæŃü¬ŃüäŃü©ŃāĆŃāĪŃü¦ŃüÖŃüŁ’Į×ŃĆé ŃüåŃüĪŃü«ÕŻüŃü½ŃééŃüōŃéōŃü¬ń┤ĀµĢĄŃü¬ń®┤Õć╣Ńüīµ¼▓ŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé
µŁżÕć”Ńü«µēĆŃü╗Ńü╝ķĆŻńČÜŃü¦ÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐õ╗ĢõĖŖŃüÆŃéÆ’╝¢ÕÅŻĶĪīŃüäŃĆüµ¼ĪŃééÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐Ńü¦ŃĆüŃüØŃü«µ¼ĪŃééÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐Ńü«ÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüéŃéŖŃü¦ŃĆéÕ░æŃĆģń¢▓ŃéīŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüŠŃüĀĶĪīŃüæŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃüŖµĢŻµŁ®Ńé│Ńā╝Ńé╣ŃéƵŁ®ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĖŖķ½śķćÄŃü«ÕŠĪĶöŁńź×ńżŠŃüĖŃĆüÕģ½ńĆ¼ŃüŗŃéēŃü¦Ńü¬ŃüÅÕÅĪķø╗õĖēÕ«ģÕģ½Õ╣Īķ¦ģµ¢╣ķØóŃüŗŃéēŃĆéÕŠĪĶöŁńź×ńżŠŃü»õĖŖķ½ś […]
µ£¼µŚźŃéłŃéŖµ£¼ĶāĮÕ»║ŃüĢŃéōŃü½Ńü”ŃĆīµŚźµ£¼ÕłĆŃü«ńŠÄŃĆŹńē╣ÕłźÕ▒ĢŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõ║¼ķāĮŃü½ŃüŖĶČŖŃüŚŃü«ķÜøŃü»µś»ķØ×ŃüŖń½ŗŃüĪÕ»äŃéŖŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆéŃĆƵśĀńö╗ŃĆī µŚźµ£¼ÕłĆŃü«ńŠÄŃĆŹ ÕåģÕ«╣Ńü»’╝öµ£¤Ńü½µĖĪŃéŖŃĆüõ╝ܵ£¤Ńü»’╝Æ’╝É’╝Æ’╝ōÕ╣┤’╝¢µ£ł’╝Æ’╝æµŚź’Į×’╝Æ’╝É’╝Æ’╝öÕ╣┤’╝öµ£ł’╝æ’╝æµŚźŃüŠŃü¦ŃĆé õ╗źõĖŗÕ▒Ģńż║ÕłĆŃü«õĖĆķā© ÕÅżÕéÖ […]
µ»ÄµŚźńĀöńŻ©ŃéÆķĆ▓ŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõ╝æµå®µÖéķ¢ōŃü»µŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōŃéÆŃĆéŃüōŃüōŃüŚŃü░ŃéēŃüÅŃü¦ÕżÜÕłåõĖŖŃüÆŃü”ŃüäŃü¬ŃüäÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕÅŹŃéŖŃü«µĘ▒ŃüäÕłĆŃü«Õż¢ÕĮóŃéÆŃü©ŃéŗµÖéŃĆüķćŹŃéŖŃéÆŃü│ŃüŻŃüŚŃéŖõĖ”Ńü╣Ńü”ŃééŃü®ŃüåŃüŚŃü”Ńééń┤ÖŃü½ŃéĘŃā»ŃüīŃéłŃéŖŃüīŃüĪŃü¦ŃĆüÕż▒µĢŚŃüōŃüØŃüŚŃüŠŃüøŃéōŃüīńĄÉµ¦ŗķØóÕĆÆŃü¬õĮ£µźŁŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗ŖµŚźŃéäŃüŻŃü©õĖŖµēŗŃüäÕÅ¢ŃéŖµ¢╣ŃéÆńÖ║Ķ”ŗŃĆüµ¼ĪŃüŗŃéēŃü»ŃüØŃéīŃü¦ŃüäŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé µ£ĆĶ┐æŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü«õĖĆŃüżŃĆéÕģāŃüŗŃéēÕģłŃüŠ […]
µĀ╣µ┤źÕłĆÕīĀŃü«ÕĆŗÕ▒ĢŃü½ŃüŖŃüśŃéāŃüŠŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ¢░õĮ£ÕłĆŃü»ń¤│Ńü«õĮ┐Ńüäµ¢╣Ńü½ŃéłŃüŻŃü”µ¦śŃĆģŃü¬ÕżēÕī¢ŃéÆĶ”ŗŃüøŃéŗķØóńÖĮŃüäķēäĶ│¬Ńü¦ŃüÖŃĆéÕÉīŃüśÕłĆŃü¦ŃééńĀöÕĖ½Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Õģ©ŃüÅķüĢŃüåńĄÉµ×£Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦ŃĆüõ╗¢Ńü«ńĀöÕĖ½ŃüīńĀöńŻ©ŃüŚŃü¤µ¢░õĮ£ÕłĆŃü╗Ńü®ÕŗēÕ╝ĘŃü½Ńü¬Ńéŗńē®Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéõ╗ŖµŚźŃééĶ▓┤ķćŹŃü¬ńĄīķ©ōŃéÆŃüĢŃüø […]
’╝¢µ£ł’╝ōµŚźŃüŗŃéē’╝Śµ£ł’╝ō’╝ɵŚźŃüŠŃü¦ŃĆüõĖĪÕøĮŃü«ÕłĆÕēŻÕŹÜńē®ķż©Ńü½Ńü”ŃĆīµŚźµ£¼ÕłĆ Ķ©śķī▓Ńü«ń│╗ĶŁ£ -Ķ©śķī▓Ńü«µŁ┤ÕÅ▓Ńü©Ķ©śķī▓ŃüĢŃéīŃü¤ŃāóŃāÄŃü¤ŃüĪ-ŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕłĆÕēŻÕŹÜńē®ķż© (touken.or.jp)ŌåæÕ▒Ģńż║ÕōüŃü½ŃüżŃüŹŃüŠŃüŚŃü”Ńü»ÕłĆÕēŻÕŹÜńē®ķż©HPŃü«Twitterńö╗ķØóŃü½ […]
ŃüäŃüżŃééÕż¦ÕżēŃüŖõĖ¢Ķ®▒Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖµĀ╣µ┤źń¦ĆÕ╣│ÕłĆÕīĀŃüīÕĆŗÕ▒ĢŃéÆķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé µŚźµÖéŃĆĆ2023Õ╣┤5µ£ł21µŚź’╝łµŚź’╝ē’Į×27µŚź’╝łÕ£¤’╝ēŃĆĆ10µÖé’Į×17µÖéõ╝ÜÕĀ┤ŃĆĆõ╗ÅÕāÅÕåÖń£¤Ńé«ŃāŻŃā®Ńā¬Ńā╝ ķŻøķ│źÕ£Æ’╝łŃĆÆ630-8213 ÕźłĶē»ÕĖéńÖ╗Õż¦ĶĘ»59’╝ēÕģźÕĀ┤ńäĪµ¢Ö õ╗ÅÕāÅÕåÖń£¤Ńé« […]
õ╗ŖÕø×Ńü»ń¦üŃüīÕĮōńĢ¬Ńü¦ŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüÕéÖÕēŹńē®Ńā╗ÕéÖÕēŹõ╝ØŃü«õ║ÆŃü«ńø«ŃéÆŃāåŃā╝Ńā×Ńü©ŃüŚŃü”ÕłĆŃéÆķøåŃéüŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆń¤ŁÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆƵ│ĢÕ╗ŻŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕ╣│µłÉõ║īÕŹüõĖĆÕ╣┤ķ«ÄÕŁŻŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕłāķĢĘŃĆĆÕģ½Õ»ĖÕģ½ÕłåŃĆĆÕåģŃü×ŃéŖ’╝ÆÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕć║ńŠĮÕøĮõĮÅõ║║Õż¦ […]
ÕĘ”õ║¼Õī║Ķü¢ĶŁĘķÖóŃü½ńÅŠõ╗ŻÕłĆÕ░éķ¢ĆŃéĘŃā¦ŃāāŃāŚŃĆīńÅŠõ╗ŻńŠÄĶĪōÕłĆÕēŻŃĆŹŃüīĶ¬Ģńö¤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµØ▒Õ▒▒õĖĖÕż¬ńö║ŃéƵØ▒ŃüĖńø┤ŃüÉŃü«ÕĀ┤µēĆŃĆéÕ╣│Õ«ēńź×Õ««Ńü«ÕīŚĶź┐ŃĆ鵣”ÕŠ│µ«┐ŃüŗŃéēՊƵŁ®’╝ōÕłåŃü¦ŃüÖŃĆé ĶÉĮŃüĪńØĆŃüäŃü¤ķø░Õø▓µ░ŚŃü«Õ║ŚÕåģŃü½Ńü»ŃĆü’╝ō’╝ÉÕÅŻŃü╗Ńü®Ńü«µ¢░õĮ£ÕłĆŃüīÕ▒Ģńż║ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ¢░õĮ£ŃéÆńĀöńŻ©ŃüĢŃüøŃü”ķĀé […]
õ╗ŖÕø×Ńü»ńåŖĶ░ĘÕÆīÕ╣│Õģłńö¤ŃéÆĶ¼øÕĖ½Ńü½ŃüŖµŗøŃüŹŃüŚŃü”Ńü«Õģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝ÜŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆÕÅżŃüäÕż¬ÕłĆÕ¦┐ŃĆéńä╝ŃüŹÕć║ŃüŚµśĀŃéŖŃüīĶ”ŗŃüłŃĆüńö¤ŃüČŃü©µĆØŃüåŃĆéĶéīń½ŗŃüĪµ░ŚÕæ│ŃĆ鵜ĀŃéŖŃüīÕżÜŃüäŃüīµÜŚÕĖ»ķā©ŃüīµśÄńףŃü¬Ńé┐ŃéżŃāŚŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃĆéÕéÖÕēŹŃü«ķĀŁµÅāŃüäµ░ŚÕæ│Ńü«õĖüÕŁÉŃĆéńē®µēōŃüŗŃéēõĖŖŃü»ķĢĘÕģēķó©ŃĆéÕłāĶéīŃüīŃüŗŃü¬ […]
ńÅŠõ╗ŻÕłĆÕ░éķ¢ĆŃéĘŃā¦ŃāāŃāŚŃüīõ║¼ķāĮŃü½Ńé¬Ńā╝ŃāŚŃā│ŃüÖŃéŗõ║ŗŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤’╝üŃüōŃü«Õ║ŚĶłŚŃüīÕøĮÕåģÕż¢Ńü½ÕÉæŃüæŃü¤µ¢░õĮ£ÕłĆŃü«Ķ▓®ÕŻ▓µŗĀńé╣Ńü©Ńü¬ŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖ’╝ü’╝üµäøÕłĆÕ«ČŃü«ńÜåŃüĢŃéōŃü½µ¢░õĮ£ÕłĆŃü«ń┤ĀµÖ┤ŃéēŃüŚŃüĢŃéÆń¤źŃüŻŃü”ķĀéŃüÅŃü¤ŃéüŃĆüÕģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝ÜŃü«ķææÕ«ÜÕłĆŃü©ŃüŚŃü”µ¢░õĮ£ÕłĆÕć║ķĪīŃü«µ®¤õ╝ÜŃéÆÕóŚŃéäŃüØŃüåŃü©Õ«¤ĶĪīŃüŚ […]
õĖŖķā©ŃāĪŃāŗŃāźŃā╝Ńü«Õģźµ£ŁķææÕ«ÜĶ©śŃĆü’╝Æ’╝É’╝æ’╝öÕ╣┤ĶŠ║ŃéŖõ╗źÕēŹŃü«Ńā¬Ńā│Ńé»ÕģłŃüīŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ńĄéõ║åŃüŚŃü¤Ńé”Ńé¦Ńā¢Ńā¬Ńā¢ŃāŁŃé░ŃüĀŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ÕłćŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚńÅŠÕ£©Ńü«Ńā¢ŃāŁŃé░Ńü½ń¦╗ĶĪīÕć║µØźŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüżŃü¬ŃüÄŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé’╝Æ’╝É’╝É’╝śÕ╣┤ÕłåŃü»ŃüĢŃéēŃü½ŃüØŃü«ÕēŹŃü½ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ńĄéõ║åŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ŃāżŃā¢ […]
õ╗ŖÕø×Ńü»µ£¼ķā©ŃüŗŃéēŃĆéµ£¼ķā©ÕłĆŃü»ńŁöŃüłŃü»õĖŖŃüÆŃü¬Ńüäµ¢╣ŃüīŃéłŃüäŃüØŃüåŃü¬Ńü«Ńü¦ŃĆüńŁöŃüłŃü»ńäĪŃüŚŃü¦ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆĶäćÕĘ«Õ╣│ķĆĀŃéŖŃĆüń£¤Ńü«µŻ¤ŃĆüĶ║½Õ╣ģÕ║āŃüÅŃĆüķćŹŃüŁµźĄĶ¢äŃüÅŃĆüÕÅŹŃéŖŃüīõ╗śŃüÅŃĆéµØ┐ńø«Ńü¦µŻ¤Õ»äŃéŖŃü»µ¤Šńø«ŃüīŃüåŃüŁŃéŗŃĆéõ║ÆŃü«ńø«Ńü©µ╣ŠŃéīŃéÆÕ¤║Ķ¬┐Ńü½ńÜåńä╝ŃĆéÕĖĮÕŁÉõ╣▒ŃéīĶŠ╝Ńü┐ÕģłÕ░¢ŃéŖŃüöŃüōŃéŹŃĆüĶ┐öŃéŖŃüŗ […]
Õ░æŃĆģÕż¬Ńüäõ║īńŁŗµ©ŗŃüĀŃüŗŃéēŃü¦Ńü»ŃüéŃéŗŃüīŃĆüÕģłµŚźŃü«ķüōÕģĘŃü«ŃüŖŃüŗŃüÆŃü¦Ńé╣ŃāłŃā¼Ńé╣ńäĪŃüŚŃü«õĮ£µźŁŃüīÕć║µØźŃü¤ŃĆéõ║īńŁŗµ©ŗŃüīµ£ēŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕĘ«ŃüŚĶĪ©Ńü©ÕĘ«ŃüŚĶŻÅŃü¦ÕłāńĘÜŃü©Õ║ĄŃéÆÕÉłŃéÅŃüøŃéŗŃü©’╝æ’╝öµ£¼Ńü«ķĢĘŃüäńĘÜŃéÆÕ╝ĢŃüÅõ║ŗŃü½Ńü¬ŃéŗŃĆéõĖĪŃāüŃā¬ŃüĀŃü©’╝æ’╝¢µ£¼ŃĆüń£¤Ńü«µŻ¤Ńü½Ńü¬ŃéīŃü░’╝æ’╝śµ£¼ŃééŃĆé’╝łµ¢ćÕŁŚŃü½ŃüŚŃü”µö╣ […]
õ║īńŁŗµ©ŗŃĆüõĖĪŃāüŃā¬Ńü«µ©ŗŃĆüµĘ╗Ńüłµ©ŗŃéäķĆŻŃéīµ©ŗŃü¬Ńü®ŃĆüÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü¦µēŗķ¢ōŃüīµÄøŃüŗŃéŗõĮ£µźŁŃüīÕ╣ŠŃüżŃüŗŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé ÕģłµŚźŃü«õ║īńŁŗµ©ŗŃéÆõ┐«µŁŻŃüŚŃü”ŃüäŃü”ŃĆüµ░Śõ╗śŃüäŃü¤Ńéē’╝æµÖéķ¢ōõ╗źõĖŖŃüŗŃüŗŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ÕåÖń£¤ŃüśŃéāÕģ©ńäČŃéÅŃüŗŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüÕģ©õĮōŃü¦Ķ”ŗŃéŗŃü©ńĘÜŃü»Ķē»ŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé’╝ł […]
’╝Ƶ£łõŠŗõ╝Ü ’╝æÕÅĘŃĆĆÕłĆĶéźÕēŹŃĆéÕÅŹŃéŖÕ░æŃüŚµĄģŃüäŃĆüÕģāÕ╣ģÕ║āŃüäŃĆüńø┤ŃüÉÕłāŃĆéÕĖĮÕŁÉńČ║ķ║ŚŃĆéÕ░æŃüŚµśĀŃéŖµ░ŚŃĆéŃéłŃüÅĶ”ŗŃéŗõĖŁńø┤ÕłāŃü½µ»öŃü╣ŃĆüńä╝ŃüŹÕ╣ģĶŗźÕ╣▓ńŗŁŃüäŃĆéÕīéŃüäÕÅŻŃüØŃéīń©ŗµĘ▒ŃüÅŃü¬ŃüäŃĆéÕłāķīĄŃüīÕłāÕģłŃü½ÕÉæŃüŗŃüäńø┤ńĘÜńÜäŃü½µŁóŃüŠŃéŗńŗ¼ńē╣Ńü«ķø░Õø▓µ░ŚŃüīķĪĢĶæŚŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃĆéÕ░æŃüŚŃü░ŃüĢŃüæŃü”µÅ║ŃéēŃüÉŃĆéŃéä […]
ÕéÖÕēŹńē®Ńü«µŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōŃéÆÕ░æŃüŚµĖøŃéēŃüØŃüåŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕģłµŚźŃü«ÕÉēÕ▓ĪõĖƵ¢ćÕŁŚŃü½ńČÜŃüŹŃüŠŃü¤õ║īÕÅŻŃĆéÕéÖÕēŹńē®Ńü«Õ£¦ÕĆÆńÜäŃü¬µĢ░Ńü«ÕżÜŃüĢŃüŗŃéēŃü®ŃüåŃüŚŃü”ŃééŃüōŃüåŃü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃééŃüåõ╗Ģµ¢╣Ńü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆéŃü½ŃüŚŃü”Ńééõ║īńŁŗµ©ŗŃü«µÄĪµŗōŃüīķøŻŃüŚŃüä’╝łķØóÕĆÆ’╝ēŃĆéķļńŁŗŃéÆķļńŁŗŃü¦Ńü©Ńéŗµä¤ŃüśŃü« […]
NHKŃü¦2022Õ╣┤1µ£łŃü½µöŠķĆüŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīÕ╣Ģµ£½ÕźćĶŁÜ ń¤źŃéƵŁ”ÕÖ©Ńü½ŃüŗŃüÅķŚśŃüłŃéŖŃĆŹŃü»ŃüöĶ”¦Ńü½Ńü¬ŃéēŃéīŃüŠŃüŚŃü¤Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé µ▒¤µłĖÕŠīµ£¤Ńü«ÕäÆÕŁ”ĶĆģÕ▒▒µ£¼õ║ĪńŠŖŃü«ń¦üÕĪŠŃĆüŌĆØÕ▒▒µ£¼Ķ¬ŁµøĖÕ«żŌĆØŃü«ŃüŖĶ®▒Ńü¦ń¦üŃééÕż¦ÕżēĶłłÕæ│µĘ▒ŃüŵŗØĶ”ŗĶć┤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕ▒▒µ£¼Ķ¬ŁµøĖÕ«żŃü»ÕĮōµÖéŃü«ń¤źŃü«ńĄÉķøåŃü¦ŃĆüĶ│ć […]
õĮÉķćÄńŠÄĶĪōķż©ŃüĢŃéōŃü½µĢ░µŚźŃüŖõĖ¢Ķ®▒Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüķÜåµ│ēĶŗæŃüīµö╣õ┐«ÕĘźõ║ŗõĖŁŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéńō”Ńü«Ķæ║ŃüŹµø┐ŃüłŃü¦ÕÅżŃüäÕ▒ŗµĀ╣ńō”ŃéÆķÖŹŃéŹŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüµĖĪķéēńÉåõ║ŗķĢĘŃü½ŃüŖķĪśŃüäŃüŚńō”ŃéÆõĖƵ×ÜķĀ鵳┤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĖĆĶ╝¬µī┐ŃüŚŃü«ÕÅ░Ńü½ŃüŚŃéłŃüåŃü©µĆØŃüäķĀéŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü«ŃüŠŃüŠŃü¦Ńü»Õż¦ŃüŹķüÄŃüÄ […]
µŖ╝ÕĮóŃéÆÕÅÄń┤ŹŃüŚŃü”ŃüäŃéŗńŁÆŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕż¦ŃüŹŃü¬ŃéĄŃéżŃé║ŃüīŃüéŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦Õ╣ģŃü«Õ║āŃüäń┤ÖŃü»ŃüØŃü«ńŁÆŃü½ÕģźŃéīŃéŗõ║ŗŃü½ŃĆéńö╗ÕāÅõĖŁÕż«Ńü«Ķ¢ÖÕłĆŃĆüµÖ«ķĆÜŃéĄŃéżŃé║Ńü½Ķ”ŗŃüłŃüŠŃüÖŃüīÕłāķĢĘŃü¦õ║īÕ░║õĖēÕ»ĖÕģŁÕłåŃü¦ŃüÖŃĆéÕĘ”Ńü»ÕłāķĢĘõĖēÕ░║õĖēÕ»ĖŃĆüÕÅ│ŃüīÕłāķĢĘõĖēÕ░║ÕøøÕ»ĖÕģŁÕłåŃĆéÕż¦Õż¬ÕłĆ’╝łÕż¦Ķ¢ÖÕłĆ’╝ēŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóµÄĪµŗōŃü»µ£¼ […]
’╝ōµ£ł’╝ś’Į×’╝æ’╝ōµŚźŃĆüķś¬µĆźŃüåŃéüŃüĀµ£¼Õ║ŚŃü½Ńü”ŃĆüŃĆīµŚźµ£¼ÕłĆÕ▒ĢŃĆƵ£łÕ▒▒ GASSANŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéĶ®│ń┤░Ńü»õĖŗĶ©śHPŃü½Ńü”ŃĆé µŚźµ£¼ÕłĆÕ▒Ģ µ£łÕ▒▒ | ķś¬µĆźŃüåŃéüŃüĀµ£¼Õ║Ś | ķś¬µĆźńÖŠĶ▓©Õ║Ś (hankyu-dept.co.jp)
ÕØéÕ¤Äńö║ ķēäŃü«Õ▒Ģńż║ķż©Ńü¦ŃüÖŃĆé
õ║īÕŁŚÕøĮõ┐ŖŃü«ń¤ŁÕłĆŃü»ķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃü«µäøµ¤ōÕøĮõ┐Ŗ’╝łķŖś ÕøĮõ┐Ŗ ÕłāķĢĘ õ╣ØÕ»Ėõ║öÕłå ÕÅŹŃéŖ Õģ½ÕÄś’╝ēŃü«Ńü┐Ńü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕ╣│µłÉ’╝Æ’╝ŚÕ╣┤ŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü½õ║īÕŁŚÕøĮõ┐ŖÕ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃüīķćŹĶ”üÕłĆÕēŻŃü½µīćÕ«ÜŃüĢŃéī’╝łķŖś ÕøĮõ┐Ŗ ÕłāķĢĘ õĖāÕ»ĖõĖēÕÄś ÕÅŹŃéŖ õĖēÕÄś’╝ēŃĆüõ║īÕÅŻńø«Ńü«õ║īÕŁŚÕøĮõ┐Ŗń¤ŁÕłĆŃüīõĖ¢ […]
ÕÉēÕ▓ĪõĖƵ¢ćÕŁŚńö¤ŃüČĶīÄŃü«Õż¬ÕłĆŃĆüÕåģµøćŃéŖŃéÆÕ╝ĢŃüÅŃĆéńĀöńŻ©ÕēŹŃĆüÕģ©Ķ║½ńÖ║ķīåķüÄÕżÜŃü½Ńü”ńĀöńŻ©Õ┐ģĶ”üńŖȵģŗŃĆéÕÉäķīåķā©ÕłåńĀöńŻ©Ńü½Ńü”ķÖżÕÄ╗ŃĆéńÖ║ķīåń«ćµēĆÕżÜµĢ░Ńü½ŃüżŃüŹÕåģµøćõ╗źķÖŹÕģ©Ķ║½ńĀöńŻ©ŃĆé Õø│ĶŁ£Ķ¦ŻĶ¬¼Ńü½Ńü»ŃĆīÕ╣ĮŃüŗŃü½µśĀŃéŖŃü¤ŃüĪŃĆŹŃü©µøĖŃüŗŃéīńÅŠńē®ŃéÆĶ”ŗŃü”Ńééńó║ŃüŗŃü½ŃüØŃü«ńŖȵģŗŃĆéŃü©ŃüäŃüåŃüŗŃü╗Ńü╝µśĀŃéŖŃü» […]
ķēäķÄ║Ńü»ÕÅżŃüäÕż¬ÕłĆŃéäĶ¢ÖÕłĆŃü½ń©ĆŃü½Ķ”ŗŃüŠŃüÖŃüīŃĆüķćæńØĆŃüøÕż¬ÕłĆķÄ║Ńü«µ¦śŃü½Ńé╣ŃāāŃéŁŃā¬Ńé╣Ńé½ŃāāŃü©ŃüŚŃü¤ńē®Ńü»Õ░æŃü¬Ńü䵦śŃü½µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµÖéõ╗ŻŃü«Õ¦┐µĢģŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéŃüØŃéīŃü©Ńééń┤ĀµØÉŃüīÕĤÕøĀŃüŗŃĆ鵦ŗķĆĀĶć¬õĮōŃĆüķēäķÄ║Ńü»Õ¤║µ£¼Ńü®ŃéīŃééńĄÉµ¦ŗĶ¢äŃüäŃéōŃü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚķćŹŃüäÕ¦┐ŃĆéµ»öķćŹŃü«ķ¢óõ┐éõĖŖŃĆüķćæķŖĆķŖģĶŻĮ […]
ķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃü¦µśźµŚźÕż¦ńżŠµēĆĶöĄŃü«µ¤Åµ£©ÕģÄĶģ░ÕłĆŃü«ÕåÖŃüŚŃéÆõ╣ģŃĆģŃü½µŗØĶ”ŗŃĆéŃüŠŃü¤Ńü¢ŃüŻŃüÅŃéŖŃü©Ķ©łµĖ¼ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüåŃüĪŃü«ńö░ĶłÄŃü¦Ńü»ŃāĢŃé»ŃāŁŃé”Ńü«õ║ŗŃéÆŃĆīŃüĄŃéŗŃüżŃüÅŃĆŹŃü©ŃüäŃüäŃüŠŃüÖŃĆéķ½ś’╝ÆŃü«µÖéŃĆüķāĘķćīŃü«µØēÕ▒▒Ńü¦ķćÄńö¤Ńü«ŃāĢŃé»ŃāŁŃé”ŃéÆĶ”ŗŃü¤ŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃāłŃāōŃéłŃéŖõĖĆÕø×ŃéŖÕż¦ŃüŹ […]
ń¤ŁÕłĆµŗĄŃü«Õ¦┐ŃéƵö╣ŃéüŃü”ÕŗēÕ╝ĘŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶź┐ÕååÕĀéŃüŗŃéēÕć║Ńü¤Ńü©Ķ©ĆŃéÅŃéīŃéŗķלŃéÆÕģāŃü½µ¤äŃéÆÕŠ®ÕģāŃüŚŃü¤ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕłĆĶ║½Ńü»Ńü¤ŃüŠŃü¤ŃüŠŃāöŃāāŃé┐Ńā¬ÕÉłŃüŻŃü¤µī»Ķó¢ĶīÄŃü«ń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé Ńü¢ŃüŻŃüÅŃéŖŃü¦ŃüÖŃüīµĢ░ÕĆżŃééµĖ¼ŃéēŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ķלŃéƵÅĪŃüŻŃü¤µÖéÕż¦Õżēķ®ÜŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕŠ®ÕģāŃüĢ […]
ŃüŖµĢŻµŁ®Ńü¦ŃéłŃüÅĶĪīŃüÅķĢĘĶ░ĘÕģ½Õ╣ĪÕ««ŃüĢŃéōŃĆé Õ░ÅŃüĢŃü¬ńżŠÕ»║Ńü»õ║║ÕÅŻµĖøÕ░æŃü½ŃéłŃéŖÕŁśńČÜŃüīķøŻŃüŚŃüÅŃü¬ŃéŖŃĆüµČłµ╗ģŃüÖŃéŗŃü©ŃüōŃéŹŃééÕżÜŃüÅŃüéŃéŗŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚõ║║ÕÅŻŃüīÕóŚŃüłŃü”ŃüäŃéŗÕ£░ŃüĀŃüŗŃéēÕ«ēµ│░Ńü©ŃüäŃüåõ║ŗŃü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéõ╗ŖÕŠīŃü«ÕŁśńČÜŃü»ŃüŠŃüÖŃüŠŃüÖķøŻŃüŚŃüÅŃü¬ŃéŗŃü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé
ÕłĆµÄøŃüæŃü»ĶāīŃü«õĮÄŃüäńē®ŃüīÕźĮŃüŹŃü¦ŃĆüķלÕ║Ģ’╝ÖŃÄØŃü«ŃéóŃé»Ńā¬Ńā½ÕłĆµÄøŃüæŃü½ÕłĆŃéÆńĮ«ŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ŃüäŃüäŃüŁŃüćŃü©µ»ÄµŚźń£║ŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃéēŃĆüÕ░æŃüŚÕ»éŃüŚŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃééµØźŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃĆéŃüøŃüŻŃüŗŃüÅ’╝Ƶ«ĄŃü«ŃéóŃé»Ńā¬Ńā½ÕłĆµÄøŃüæŃééŃüéŃéŗŃéōŃüĀŃüŚŃĆüń¤ŁŃüäńē®Ńüīµ£ēŃéīŃü░Ńü¬ŃüŖÕ¼ēŃüŚŃüÅŃĆéÕ╣ĖŃüäķ”¼µēŗÕĘ«ķŖśŃü«ń¤Ł […]
’╝ōµŚźķĆŻńČÜŃü¦ŃüÖŃüīÕ╣Īµ×ØÕģ½Õ╣ĪÕ««Ńü½ŃĆéŃéäŃü»ŃéŖń¤│µĖģµ░┤ŃüīĶ”ŗŃü¤ŃüÅŃü”ŃĆéŃüØŃü«ÕēŹŃü½ÕøøµØĪńāÅõĖĖŃü½ńö©õ║ŗŃü¦ŃüØŃéīŃüīµĖłŃéōŃüĀÕŠīŃĆüÕīŚÕ▒▒Ńü«õ║¼ķāĮÕ║£ń½ŗõ║¼ķāĮÕŁ”Ńā╗µŁ┤ÕĮ®ķż©Ńü¦ķÖŹŃéŹŃüŚŃü”ŃééŃéēŃüäŃĆüĶ¬┐Ńü╣ńē®ŃéÆŃĆéŃüōŃüōŃüĀŃü©ńź×ńżŠŃü«Ķ│ćµ¢ÖŃüīµ▓óÕ▒▒ŃüéŃéŗŃü»ŃüÜŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃāöŃāāŃé┐Ńā¬Ńü«ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃĆīÕ╣Īµ×ØÕģ½ […]
ÕżĢµ¢╣ŃĆüÕøĮÕ║āŃüīńä╝ŃüŹÕģźŃéīŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤ń¤│µĖģµ░┤ŃéƵÄóŃüŚŃü½ĶĪīŃüŻŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕ▓Ėµ£¼Õģłńö¤ŃüīµøĖŃüŗŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕ╣Īµ×ØÕøĮÕ║āńÖ║Ķ”ŗŃü©Õ£ŗÕ╗ŻÕż¦ķæÆÕłČõĮ£µÖéŃü«Ńé©ŃāöŃéĮŃā╝ŃāēŃüīÕłĆńŠÄŃü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃéīŃü½Ńü»ŃüōŃü«ń¤│µĖģµ░┤Ńü«ÕåÖń£¤ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé µĆźŃüäŃü¦µŁ®ŃüäŃü”ŃééÕ«ČŃüŗŃéē’╝ö’╝ī’╝Ģ’╝ÉÕłåŃüŗŃüŗŃéŗŃü«Ńü¦µŚó […]
ÕĀĆÕĘØÕ£ŗÕ╗ŻŃü«Õż®µŁŻµēōŃéÆńĀöńŻ©ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüŃüŖµĢŻµŁ®Ńü¦õ╣ģŃĆģŃü½Õ╣Īµ×ØÕģ½Õ╣ĪÕ««Ńü½ĶĪīŃüŻŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ķćŹńŠÄŃü«Õ╣Īµ×ØÕ£ŗÕ╗ŻŃü»µŚźÕłĆõ┐Øõ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©Ńü«µö»ķā©ķĢĘŃéÆÕŗÖŃéüŃéēŃéīŃü¤Õ▓Ėµ£¼Ķ▓½õ╣ŗÕŖ®Õģłńö¤ŃüīŃĆüÕż¦µŁŻÕŹüõ║öÕ╣┤Ńü½ŃüōŃü«Õ╣Īµ×ØÕģ½Õ╣ĪÕ««ŃüŗŃéēńÖ║Ķ”ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé’╝łõ║¼ķāĮÕŠĪµēĆŃü«µØ▒Õ▒▒ÕŠĪµ¢ćÕ║½ […]
Ķ¬┐Ńü╣ńē®ŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃü”Õż£õĖŁŃü½Ńü¬ŃéŖŃĆüÕż¢ŃéÆĶ”ŗŃü¤ŃéēŃüōŃéōŃü¬õ║ŗŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé µ»ÄÕ╣┤µüÆõŠŗŃü«ķø¬ÕåÖń£¤Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü»ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ķø¬ÕżÜŃéüŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕŁ”µĀĪŃü¦ńö¤ŃüæĶŖ▒Ńü«µÄłµźŁŃüīŃüéŃüŻŃü¤ŃüØŃüåŃü¦ŃĆüÕ©śŃüīõĮÖŃüŻŃü¤ŃüŖĶŖ▒ŃéƵīüŃüŻŃü”ÕĖ░ŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗źÕēŹŃĆüÕŖĀĶŚżķØÖÕģüÕģłńö¤ŃüŗŃéēÕ░ÅŃüĢŃü¬õĖĆĶ╝¬µī┐ŃüŚŃü©ŃüØŃéīŃüīµÄ▓Ķ╝ēŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗµ£¼ŃéÆķĀ鵳┤ŃüŚŃü”ŃüäŃü”ŃĆüõ╣ģŃĆģŃü½µī┐ŃüŚŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéōŃü¬Õ░ÅŃüĢŃü¬ĶŖ▒ÕÖ©õĖĆŃüżŃüīÕģ©Ńü”Ńü«ń®║µ░Śµä¤ŃéÆÕżēŃüłŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃéō […]
µ¢░Õ╣┤õ╝ÜŃü¦õĖēµ£©ÕŹŖŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕłĆŃĆĆÕÅŹŃéŗŃĆéÕ╣ģÕ║āŃéüŃü¦ĶĖÅŃéōÕ╝ĄŃéŗŃĆéõĖŁķŗÆŃĆéŃéłŃüÅĶ®░Ńü┐ŃĆüń½ŗŃüżÕż¦ÕżēĶē»ŃüäÕ£░ķēäŃĆéÕ╣│Õ£░ķļգ░Ńü©ŃééÕÉīŃüśĶéīŃĆéń┤░ŃéüŃü½ńä╝ŃüŹÕć║ŃüŚŃĆüÕ░æŃüŚĶĪīŃüŻŃü”Ķć¬ńäČŃü½õĖŁńø┤ÕłāŃü½ŃĆéµÖ«µ«ĄŃéłŃéŖÕīéŃüäÕÅŻŃü«Õ╣ģŃüīńŗŁŃüÅŃĆüÕłāõĖŁŃü«ÕāŹŃüŹŃééÕ░æŃü¬ŃüäŃĆéÕĖĖŃü½ŃāÅŃéżŃā¼ŃāÖŃā½ŃüĀŃüīńē╣Ńü½ŃāÅŃéż […]
ŃüŠŃü¤µŗĄŃü«õ║ŗŃü¦ŃüÖŃüīŃĆéÕ░ŵ¤äŃü»ĶĄżķŖģńŗ¼µźĮÕø│Ńü¦ŃüÖŃĆéķŁÜÕŁÉŃü»µēŗµō”ŃéīŃü¦ŃāłŃāŁŃāłŃāŁŃü½ŃĆéÕż®µŁŻµŗĄŃü»õĖēµēĆŃü¬Ńü®Ńü½µÅāŃüłŃüÜŃāÉŃā®ŃāÉŃā®Ńüīµ£¼µØźŃüĀŃü©ŃüäŃüåĶ®▒ŃéäŃĆüŃéäŃü»ŃéŖÕÅżÕŠīĶŚżŃü¦µÅāŃüłŃü”ŃüōŃüØŃüĀŃü©ŃüŗŃĆüÕø│µ¤äŃü¦µÅāŃüłŃéŗŃü╣ŃüŹŃĆüµł¢ŃüäŃü»µŖƵ│ĢŃü¦µÅāŃüłŃéŗŃü╣ŃüŹ’╝łõŠŗŃüłŃü░Õ░ŵ¤äń¼äŃéÆŃüåŃüŻŃü©ŃéŖŃü¦µÅāŃüł […]
µŗĄŃüłŃüīŃü╗Ńü╝Õ«īµłÉŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé’╝łõĖŗŃüÆńĘÆŃüīŃüŠŃüĀŃü¦ŃĆüõ╗ŖŃü»µŻÜŃü½ÕģźŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ķü®ÕĮōŃü¬ńē®ŃéÆÕĘ╗ŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝ēķלķĢĘń┤ä’╝Ś’╝ōŃÄØŃĆüµ¤äķĢĘń┤ä’╝Æ’╝æŃé╗Ńā│ŃāüŃĆéÕż®µŁŻµŗĄŃüīµ¼▓ŃüŚŃüÅŃĆüõĖĆńö¤Ńü½õĖƵ£¼Ńü©µĆØŃüäÕłĆĶŻģÕģʵÄóŃüŚŃéÆÕ¦ŗŃéüŃĆüŃüØŃéīŃüŗŃéēõĮĢÕ╣┤ŃüŗŃüŗŃüŻŃü¤Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéŃĆé’╝śÕ╣┤’╝ŚÕ╣┤Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéõĖĆ […]
youtubeŃāüŃāŻŃā│ŃāŹŃā½ŃĆīµŚźµ£¼ÕłĆŃü«ńŠÄŃĆŹõ╗ŖÕø×Ńü»µ▓│ÕåģõĖĆÕ╣│ÕłĆÕīĀŃü«ŃüŖĶ®▒Ńü¦ŃüÖŃĆé õ╝ØńĄ▒ÕĘźĶŖĖµ£©ńéŁńö¤ńöŻµŖĆĶĪōõ┐ØÕŁśõ╝Ü https://www.mokutanworks.com
õ╣ģŃĆģŃü½ķćæÕ▒×õ╣│ķēóŃéÆĶ│╝ÕģźŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńĄČÕ”ÖŃü½õĖüÕ║”ŃüäŃüäÕż¦ŃüŹŃüĢŃĆéõĮĢŃéłŃéŖŃāĢŃé┐ŃüīÕ¼ēŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃüåŃüäŃüåń▓ÆŃéäń▓ŚŃüäķēäĶéīŃéÆńĀĢŃüŵÖéŃĆüĶóŗŃü½ÕģźŃéīŃü”ķćæÕ║ŖõĖŖŃü¦ÕÅ®ŃüäŃü¤ŃéŖŃĆüõĖƵēŗķ¢ōµÄøŃüŗŃéŖķØóÕĆÆŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüķćæÕ▒×õ╣│ķēóŃü©õ╣│µŻÆŃü¦ŃüŚŃüŗŃééŃāĢŃé┐õ╗śŃüŹŃü¬Ńü«Ńü¦Õ«īńƦŃü¦ŃüÖŃĆéŃāĢŃé┐ŃéÆŃüŚŃü¤ […]
ÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐ńĀöŃüÄŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüŃüäŃüżŃü¦ŃééŃüÜŃüŻŃü©ńČÜŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃĆé ÕēŹÕø×Ķ▓ĘŃüŻŃü¤µŗŁŃüäŃü»ŃüōŃéīŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃü®ŃüåŃééŃéłŃéŹŃüŚŃüÅŃü¬ŃüÅŃĆ鵤ÉÕøĮńöŻŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüĶĄżŃüŻŃü”ŃüéŃéŖÕŠŚŃéŗŃéōŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗ’╝ü’╝¤µŗŁŃüäŃüŻŃü”µō”ŃüŻŃü”Ķ”ŗŃü¬ŃüäŃü©µ£¼ÕĮōŃü«Ķē▓ŃüīÕłåŃüŗŃéēŃéōŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéÕłāŃü½ŃééŃéłŃüÅÕŖ╣ŃüÅŃü©Ńüä […]
ŃüéŃüæŃüŠŃüŚŃü”ŃüŖŃéüŃü¦Ńü©ŃüåŃüöŃüåŃü¢ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµ£¼Õ╣┤ŃééŃü®ŃüåŃü×ŃéłŃéŹŃüŚŃüÅŃüŖķĪśŃüäĶć┤ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé ŃüōŃéōŃü¬ķó©Ńü½Ķ╗óŃü░Ńü¬Ńü䵦śŃü½õ╗ŖÕ╣┤ŃééķĀæÕ╝ĄŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õ╗ŖÕ╣┤Ńé鵦śŃĆģŃü¬ńĄīķ©ōŃéÆŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵌źÕĖĖŃü«ńĀöńŻ©ŃüŗŃéēŃĆüŃüŠŃüĢŃüŗõ║║ńö¤Ńü¦ŃüōŃéōŃü¬ńĄīķ©ōŃéÆŃüÖŃéŗŃü¬ŃéōŃü”Ńü©ŃüäŃüåń¬üķŻøŃü¬ńē®ŃüŠŃü¦µ£¼ÕĮōŃü½Õ╣ģÕ║āŃüÅŃĆéŃüØŃéōŃü¬ńĄīķ©ōŃéƵźĮŃüŚŃéüŃéŗõ║║Ńü¬ŃéēŃüōŃéōŃü¬Ńü½µźĮŃüŚŃüäõ║ŗŃü»ńäĪŃüäŃü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüīŃĆüń¦üŃü»Õģ©ńäȵźĮŃüŚŃéüŃü¬ŃüäŃé┐ŃéżŃāŚŃü¬Ńü«Ńü¦ŃĆüõ║║ńö¤µÉŹŃéÆ […]
’╝ōÕ░║’╝ÆÕ»ĖŃü«Õż¦Õż¬ÕłĆńĀöńŻ©ŃĆéµŻÆµ©ŗŃüīµÄ╗ŃüŗŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕ╣│Õ£░Ńü«µ©ŗĶ¦Æ’╝łķļķÜø’╝ēŃü½ķĢĘŃüÅńä╝ŃüŹŃüīÕģźŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé’╝łµ¢ŁńČÜńÜäŃü¦Ńü»ŃüéŃéŗŃüīÕżÜµĢ░’╝ēŃĆéŃüōŃü«ńŖȵģŗŃéÆĶ”ŗŃéŗŃü©ŃĆüńä╝ŃüŹÕģźŃéīŃü»µ©ŗÕģł’╝łŃü▓ŃüøŃéō’╝ēŃüśŃéāŃü¬ŃüŗŃéŹŃüåŃüŗŃü©µā│ÕāÅŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéńÅŠõ╗ŻŃü«õĮ£ÕłĆŃü¦Ńü»ńä╝ŃüŹÕģźŃéīÕŠīŃü½µ©ŗŃéƵÄ╗ŃüÅ […]
Ńā×Ńā╝ŃāåŃéŻŃā│ÕÉøŃüŗŃéēµŗŁŃüäŃü«ÕĘ«ŃüŚµ¢╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«µīüĶ½¢ŃéÆĶü×ŃüÅŃüōŃü©ŃüīÕ║”ŃĆģŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃéīŃüīńĄÉµ¦ŗń╣Ŗń┤░Ńü©ŃüäŃüåŃüŗń┤░ŃüŗŃüäÕåģÕ«╣Ńü¦ŃĆéŃĆĆńĀöńŻ©Ńü«’╝æ’Į×’╝æ’╝ÉŃüŠŃü¦ŃéÆŃé╣ŃāŁŃāÉŃéŁŃéóŃü¦Ńü╗Ńü╝ńŗ¼ÕŁ”Ńü½Ķ┐æŃüäÕĮóŃü¦õĮĢÕ╣┤ŃééĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃéŗķ¢ōŃü½ŃĆüµ¦śŃĆģŃü¬µīüĶ½¢ŃüīÕø║ŃüŠŃüŻŃü”ŃüäŃüŻŃü¤Ńü«ŃüĀŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖ […]
’╝æ’╝Ƶ£łµö»ķā©õŠŗõ╝ÜŃü»ń¦üŃüīµŗģÕĮōŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆü’╝ĢÕÅŻŃü«ÕŠĪÕłĆŃéÆŃüöńö©µäÅŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ķææÕ«ÜÕłĆ ŃĆĆ’╝æÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕÉøõĖ浣│ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆń£¤ķŹŗń┤öÕ╣│õĮ£ŃĆĆõ╗żÕÆīÕøøÕ╣┤ń¦ŗÕÉēµŚźŃĆĆ’╝ÆÕÅĘŃĆĆń¤ŁÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆńé║µŻ«ń╣üõ╣ģÕĮīń┐üŃĆĆÕ¢äÕŹÜõĮ£ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ […]
µ¢░õĮ£ÕłĆŃü«ńĀöńŻ©ŃüīõĮĢÕÅŻŃééńČÜŃüŹĶ║½õĮōŃüīŃā£ŃāŁŃā£ŃāŁŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃéōŃü¬Ńü½µ▓ĪķĀŁÕć║µØźŃéŗõ╗Ģõ║ŗŃü»Ńü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆéŃü¬ŃéōŃü¦ŃüŚŃéćŃüŗŃüōŃü«µä¤Ķ”ÜŃü»ŃĆéŃüōŃéōŃü¬Ńü½ŃééķøŻŃüŚŃüÅŃĆüŃüōŃéōŃü¬Ńü½ŃééÕż¦ÕżēŃü¬ńĀöńŻ©Ńü¬Ńü«Ńü½ŃĆéŃĆéÕżÜÕłåŃüōŃéīŃüīÕģłµŚźŃĆīÕłĆÕēŻńĢīŃĆŹŃü½µøĖŃüŗŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü¤ķĆÜŃéŖŃü«õ║ŗŃü¬ŃéōŃüĀŃü© […]
õ╗ŖÕø×Ńü»µ£¼ķā©ŃüŗŃéēµŚźķćÄÕĤÕģłńö¤ŃéÆŃüŖµŗøŃüŹŃüŚŃü”Ńü«ķææÕ«Üõ╝ÜŃü¦ŃüÖŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆń¤ŁÕłĆķćŹŃüŁĶ¢äŃéüŃü½µä¤ŃüśŃéŗŃĆéńäĪÕÅŹŃéŖŃĆéń£¤Ńü«µŻ¤õĖŁÕ║āŃĆéÕÅżńĀöŃüÄŃü¦Ķē»ŃüŵēŗÕģźŃéīŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕ£░ķēäŃĆéÕ░æŃüŚµśĀŃéŖµ░ŚŃĆéÕīéŃüäµĘ▒ŃüŵĀ╝Ķ¬┐ķ½śŃüäń▓ÆÕŁÉŃĆéÕłāÕÅ¢ŃéŗŃü©ńø┤ŃüÉĶ¬┐Ńü½Ńü¬ŃéŗÕłāŃü¦ŃĆüÕć║ÕģźŃéŖŃü»Õ░ÅŃüĢŃüÅŃĆüŃüŚŃüŗŃüŚÕŗĢŃüŹ […]
µŖ╝ÕĮóŃü½ŃüŚŃü¤ŃüäÕłĆÕģ©ķā©ŃéÆŃü©ŃéŗµÖéķ¢ōŃééŃü¬ŃüÅŃĆüŃü©ŃéŖŃüéŃüłŃüÜõ╗ŖŃü»ŃüéŃü©ń¤ŁÕłĆŃü©µÅÅŃüŹŃüŗŃüæŃü«Õż¬ÕłĆŃü©µ£½ÕéÖÕēŹŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕģłµŚźµØźķĆ▓ŃéüŃü”ŃüäŃü¤Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃĆéŌåæŃüōŃüōŃüŠŃü¦ķĆ▓ŃéōŃü¦ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīÕģ©ńäČŃāĆŃāĪŃü¬Ńü«Ńü¦ŃéäŃéüŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé Ōåæõ║īµ×Üńø«ŃĆéńĀöŃüÄŃééµŖ╝ÕĮóŃééŃĆüŃéäŃéŖńø┤ŃüÖµÖéŃü»ńäĪŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”õĮ£µźŁŃéÆĶĪīŃüåŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüńäĪŃü½Ńü¬ŃéŖķüÄŃüÄŃü”ĶīÄŃéƵæ║ŃüŻŃü¤µ£ĆÕŠīŃü½ĶīÄŃü«Ķ╝¬ķāŁŃéÆńĪ¼Ķ│¬Ķē▓ķēøńŁåŃü¦µśÄńףŃü½ŃüÖŃéŗõĮ£µźŁŃéÆÕ┐śŃéīŃü” […]
µśöŃü»ÕłāÕłćŃéīŃéƵ░ŚŃü½ŃüŚŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤Ķ¬¼ŃééŃéäŃü»ŃéŖÕĢÅķĪīŃüéŃéŖŃüŗŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕłĆŃéÆõĮ┐ńö©ŃüŚŃü¤ķÜøõĖƵÆāŃü¦µŖśŃéīŃü¤ŃéŖŃĆüµł¢ŃüäŃü»õĮĢÕ║”ŃüŗŃü«õĮ┐ńö©Ńü¦ń¬üńäȵŖśŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ÕłźŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüõĮĢÕ║”ŃééõĮ┐ńö©ŃüŚµ«ĄķÜÄńÜäŃü½ÕéĘŃéōŃü¦ĶĪīŃüŹŃéäŃüīŃü”µŖśŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüŠŃüܵ£ĆÕłØŃü½ĶĄĘŃüōŃéŗńÅŠĶ▒ĪŃüīŃĆüµø▓ŃüīŃéŖŃĆüŃüåŃüżŃéĆ […]
µ▒¤µłĖµÖéõ╗Żõ╗źÕēŹŃü»ńÅŠõ╗ŻŃü«ŃéłŃüåŃü½ŌĆØÕłāÕłćŃéīŌĆØŃéƵ░ŚŃü½ŃüŚŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤Ķ¬¼ŃéÆÕö▒ŃüłŃéŗõ║║Ńü»ńĄÉµ¦ŗÕżÜŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé’╝łµ£¼ÕĮōŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃĆüń¦üŃü½Ńü»ÕłåŃüŗŃéŖŃüŠŃüøŃéō’╝ēÕÉīŃüśµ¦śŃü½ŃĆüÕłĆŃü«ķŹøŃüłÕéĘŃéƵ░ŚŃü½ŃüÖŃéŗŃü«Ńü»ńÅŠõ╗ŻŃüĀŃüæŃüĀŃü©ŃüäŃüåõ║║ŃééÕ▒ģŃéŗŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃéīŃü»Ķ©ĆŃüäķüÄŃüÄŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆé ÕåÖń£¤Ńü»µĢ░µēō […]
ŃüōŃéōŃüŗŃüäŃü»’╝É’╝ÖŃéĘŃāŻŃā╝ŃāÜŃā│Ńü¦õĖŗµøĖŃüŹŃéÆŃĆéŃā¢ŃāŁŃé░Ńü»µ»ÄµŚźµŖ╝ÕĮóŃü«õ║ŗŃü░ŃüŗŃéŖŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüńĀöńŻ©õ╗źÕż¢Ńü«µÖéķ¢ōŃü½ĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃéŗõĮ£µźŁŃü¦ŃüÖŃĆéńĀöńŻ©Ńü«ŃüŖõ╗Ģõ║ŗŃü»ŃüŚŃüŻŃüŗŃéŖŃü©ķĆ▓ŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ń¦üŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Ńā×Ńā│Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüŚõ╝ØńĄ▒ĶüĘõ║║Ńü¬Ńü«Ńü¦Ķć¬ÕłåŃüŗŃéēÕć║ŃéŗĶ©ĆĶæēŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéō […]
µśĀŃéŖŃü»ŃüŗŃü¬ŃéŖµĘĪŃüäŃü«Ńü¦µÅÅŃüŹĶŠ╝ŃüŠŃüÜŃü½Õ«īµłÉŃü©ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµÅÅŃüäŃü¤µ¢╣ŃüīĶ│æŃéäŃüŗŃü½Ńü¬ŃéŖõĖŖµēŗŃüÅŃü¬ŃüŻŃü¤ŃéłŃüåŃü¬µ░ŚÕłåŃü½Ńü¬ŃéīŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«ńé║Ńü½Ńü©ŃüäŃüåŃü«Ńü»ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ķüĢŃüäŃüŠŃüÖŃüŚŃüŁŃĆé ķĆöõĖŁŃüĀŃüŻŃü¤Õż¬ÕłĆŃü½µł╗ŃéŖńČÜŃüŹŃéÆŃĆéÕģłµŚźŃüŠŃü¦Ńü©Ńü»ķ®ÜŃüÅń©ŗŃü½ÕŗصēŗŃüīķüĢŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüéŃéé […]
ÕģłµŚźµØźŃü«ÕÅżŃüäŃü©ŃüōŃéŹŃü«Õż¬ÕłĆŃĆüõĮ®ĶĪ©Ńü«ķĆöõĖŁŃü¦õĮ®ĶŻÅŃü«õĖŗµøĖŃüŹŃü½ń¦╗ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńēćķØóŃüźŃüżÕ«īµłÉŃüĢŃüøŃéŗŃé┐ŃéżŃāŚŃü«µŖ╝ÕĮóµÅÅŃüŹŃééŃüäŃüŠŃüÖŃüŚŃĆüķā©ÕłåŃüöŃü©ŃĆüµĢ░Ńé╗Ńā│ŃāüÕŹśõĮŹŃü¦Ńü╗Ńü╝Õ«īµłÉŃüĢŃüøŃü¬ŃüīŃéēķĆ▓ŃéĆõ║║ŃééŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńÜåŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü«ŃéäŃéŖµ¢╣ŃüīŃĆéŃéĘŃāŻŃā╝ŃāÜŃā│Ńü¦õĖŗµøĖŃüŹŃéÆŃüÖŃéŗõ║ŗŃééŃüéŃéŖ […]
ŃééŃüåÕ░æŃüŚķĆ▓Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵜ĀŃéŖŃü»ŃĆīķļջäŃéŖŃü½µĘĪŃüÅŃĆŹŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéõĖĆķā©Õ£░µ¢æķó©Ńü«õ╣▒ŃéīµśĀŃéŖŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüŗŃü¬ŃéŖµĘĪŃüäŃü«Ńü¦µÖ«ķĆÜŃü»Ķ”ŗŃüłŃü¬ŃüäŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµēƵ£ēĶĆģŃüĢŃéōŃéäńĀöÕĖ½Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Ńü»ŃüōŃü«µśĀŃéŖŃéÆŃééŃüŻŃü©ń½ŗŃü”Ńü¤ŃüäŃü©µĆØŃüåŃüŗŃééń¤źŃéīŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüŃüØŃü«ŃüŠŃüŠŃüīĶē»Ńüäõ║ŗŃééŃüéŃéŗ […]
ÕģłµŚźŃü«µóĄÕŁŚŃü«Õż¬ÕłĆŃü«ķĆöõĖŁŌåæŃüŗŃéēŌåōŃü½ŃāüŃé¦Ńā│ŃéĖŃüÖŃéŗŃĆé ÕÅżŃüäµēĆŃü«Õż¬ÕłĆŃĆéÕāŹŃüŹĶ▒ŖÕ»īŃĆéŃüØŃüåŃüäŃüłŃü░µśĀŃéŖŃü»Ńü®ŃüåŃüĀŃüŻŃü¤ŃüŗŃĆéŃĆéŃüŠŃüĀÕłāµ¢ćŃüŚŃüŗĶ”ŗŃü”ŃüäŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦Õ£░Ńü»µäÅĶŁśŃü½ÕģźŃüŻŃü”ŃüŖŃéēŃüÜŃĆéµŖ╝ÕĮóŃü»ÕłĆŃü«ÕŗēÕ╝ĘŃü½Ńü¬ŃéŗŃü©Ńü»Ķ©ĆŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüĶ”üŃü»µäÅĶŁśµ¼Īń¼¼Ńü¦ŃüÖŃĆéµŖ╝ÕĮóŃü¬Ńéō […]
µ¢░õĮ£ÕłĆÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃĆéÕāŹŃüŹĶ▒ŖÕ»īŃü¦ŃüÖŃĆé ńÅŠõ╗ŻÕłĆŃü»Ńé┐Ńé¼ŃāŹµ×ĢŃüīń½ŗŃüŻŃü”ŃüäŃü”ķŖśŃéƵæ║ŃéŖÕć║ŃüÖŃü«Ńü»Õ«╣µśōŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéń¤│ĶÅ»Õó©ŃéÆń┤░ŃüŗŃüÅŃüŚŃü”ŃééŃé┐Ńé¼ŃāŹŃü«ķÜøŃüŠŃü¦Ķ▓¼ŃéüŃéŗŃü«Ńü»ŃüŗŃü¬ŃéŖķøŻŃüŚŃüÅŃĆéõ╗źÕēŹŃüŗŃéēµĆØŃüŻŃü”ŃüäŃü¤õ║ŗŃéÆÕłØŃéüŃü”Õ«¤ĶĘĄŃüŚŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃéēŃĆüŃüŗŃü¬ŃéŖŃü«ÕŖ╣µ×£Ńü¦ŃüŚŃü¤ […]
µŖ╝ÕĮóŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃéŗµÖéŃü»ÕåÖńĄīŃü«µ¦śŃü¬µ░ŚµīüŃüĪŃü¦Ńā╗Ńā╗Ńā╗Ńü©Ķ®▒ŃüÖõ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü«Õż¬ÕłĆŃü«µóĄÕŁŚŃéÆÕåÖŃüŚŃü”ŃüäŃéŗµÖéŃü»µŁŻŃü½ÕåÖńĄīŃéƵä¤ŃüśŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĖēµĄ”ńĀöÕĖ½Ńü©õĮĢÕ║”ŃüŗĶĪīŃüŻŃü¤ŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüŖÕ»║Ńü¦ÕåÖńĄīŃéÆŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüÅŃü«Ńü»µ£¼ÕĮōŃü½µ░ŚµīüŃüĪŃü«Ķē»ŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃüŁŃĆé
ń¦üŃü«µŖ╝ÕĮóŃüĖŃü«ŃüŖŃééŃüäŃéÆŃĆü1ŃüżŃüĀŃüæńŠÄĶĪōķż©ŃüĢŃéōŃü¬ŃéŖŃü«Ķ¦ŻķćłŃü¦ŃüŠŃü©ŃéüŃü”ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé 22.11.7-12.4 Sword or Soul – 1ŃüżŃüĀŃüæńŠÄĶĪōķż©Õģ¼Õ╝ÅŃéĄŃéżŃāł (jimdofree.com)
1ŃüżŃüĀŃüæńŠÄĶĪōķż©ŃüĢŃéōŃü¦ŃĆüµŖ╝ÕĮóŃü«Ńé¬Ńā¬ŃéĖŃāŖŃā½Ńé░ŃāāŃé║ŃéÆõĮ£ŃüŻŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃé¬Ńā│Ńā®ŃéżŃā│ŃéĘŃā¦ŃāāŃāŚŃü¦Ķ│╝ÕģźÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüÖŃĆéÕÅÄńøŖŃü»’╝æŃüżŃüĀŃüæńŠÄĶĪōķż©ŃüĢŃéōŃü«ķüŗÕ¢ČĶ▓╗Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé Õģźķ╣┐Õ»”ńČ▒Ńü«µ¦ŹŃüīŃé╣Ńā¬ŃāĀŃéĄŃā╝ŃāóŃé╣ŃāåŃā│Ńā¼Ńé╣Ńā£ŃāłŃā½Ńü½Ńā╝Ńā╝’╝üÕ▒▒ķ│źµ»øŃü«µŖ╝ÕĮóŃéÆŃā×Ńé░Ńé½ŃāāŃāŚŃéä […]
ń¦üŃééŃüŖµēŗõ╝ØŃüäŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤µśĀńö╗ŃĆīµŚźµ£¼ÕłĆŃü«ńŠÄŃĆŹŃü«Ńé╣Ńé»Ńā¬Ńā╝ŃāŗŃā│Ńé░&ŃāłŃā╝Ńé»ŃéżŃāÖŃā│ŃāłŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé µŚźµ£¼ÕłĆŃü«ńŠÄ_J_flyer (nagano.art.museum) ÕÅŚõ╗śńĄéõ║åŃüŠŃü¦ÕāģŃüŗŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüöĶłłÕæ│Ńü«ŃüéŃéŗµ¢╣ […]
õ╗ŖŃüŠŃü¦’╝Ģ’╝ÉŃéä’╝æ’╝É’╝ÉŃü¦Ńü»ŃüŹŃüŗŃü¬ŃüäµĢ░Ńü«ńŁåŃéÆõĮ┐ŃüŻŃü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃéäŃüŻŃü©Ķ”ŗŃüżŃüæŃü¤ŃüŗŃééŃü¦ŃüÖŃĆéÕźĮŃüŹŃü¬ńŁåŃéÆŃĆéķĢĘŃüäķüōŃü«ŃéŖŃüĀŃüŻŃü¤ŃĆéŃĆéŃü©Ńü»ŃüäŃüłķüÄÕÄ╗Ńü½ŃééõĮĢÕ║”ŃüŗÕÉīŃüśŃéłŃüåŃü¬õ║ŗŃéÆĶ©ĆŃüŻŃü¤µ░ŚŃééŃüÖŃéŗŃüīŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚÕżÜÕłåõ╗ŖÕø×Ńü»Õż¦õĖłÕż½ŃĆéŃü©ŃéŖŃüéŃüłŃüÜÕźĮŃüŹŃü½Ńü¬ŃüŻŃü¤ńŁåŃüīµ┐ĆÕ«ē […]
ķ”ÖÕĘØń£īķ½śµØŠÕĖéŃü½’╝æ’╝æµ£ł’╝ŚµŚźŃüŗŃéēŃé¬Ńā╝ŃāŚŃā│õ║łÕ«ÜŃü«ŃĆīõĖĆŃüżŃüĀŃüæńŠÄĶĪōķż©ŃĆŹŃüĢŃéōŃü«ń¼¼õĖĆÕø×õ╝üńö╗ŃüīŃĆīµŖ╝ÕĮóŃĆŹŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé 1ŃüżŃüĀŃüæńŠÄĶĪōķż© HOME – 1ŃüżŃüĀŃüæńŠÄĶĪōķż©Õģ¼Õ╝ÅŃéĄŃéżŃāł (jimdofree.com) Õ▒Ģńż║µ£¤ķ¢ōŃü»’╝æ’╝æµ£ł’╝Ś […]
õ╗źÕēŹńĀöńŻ©ŃüŚŃü¤µ£ēÕÉŹŃü¬ńøĖÕĘ×õ╝ØÕż¦ńŻ©õĖŖŃüÆŃüīµģČķĢĘŃü½Ķ”ŗŃüłŃĆüŃüäŃüŠŃüäŃüĪµĢ┤ńÉåŃüīõ╗śŃüŗŃüÜŃĆéŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚÕĖĮÕŁÉŃüīŃüØŃéīõ╗źÕż¢Ńü½Ńü»ńäĪŃüÅŃĆüŃéäŃü»ŃéŖµźĄŃéüķĆÜŃéŖŃü©ĶĆāŃüłŃéŗŃü╣ŃüŹŃü¬Ńü«ŃüŗŃĆéŃüØŃéōŃü¬õĖŁŃĆüńøĖÕĘ×õ╝ØŃü«µ£¼ÕøĮńē®Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäÕłĆŃĆéÕłØĶ”ŗŃü»ŃĆīŃéäŃü»ŃéŖÕżÜŃüäŃéłŃü¬ŃüüĶŗźŃüäńē®ŃüīŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆŹŃüŚŃüŗŃüŚŃüōŃü« […]
ŃāŹŃāāŃāłŃü¦µēŗÕ╝ĢŃüŹŃü«ÕŗĢńö╗ŃéÆĶ”ŗŃüŠŃüŚŃü¤’╝üŃüĪŃéćŃüŻŃü©µä¤µ┐ĆŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃü«Õż¦ŃüŹŃüÅķćŹŃüäńĀźń¤│Õłćµ¢Łńö©ķŗĖŃü«õĖĪń½»ŃéÆõ║īõ║║Ńü¦µīüŃüĪŃĆüõ║żõ║ÆŃü½Õ╝ĢŃüäŃü”ÕłćŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé’╝æ’╝ɵ£ł’╝æ’╝öµŚźŃü»ŌĆØńĀźń¤│Ńü«µŚźŌĆØŃü¬ŃéōŃü¦ŃüÖ’╝łĶ¬×ÕæéÕÉłŃéÅŃüø’╝ēŃĆéõ║¼ķāĮŃü«ŃĆīŃü┐ŃéäŃüōŃéüŃüŻŃüøŃĆŹŃü¦µ»ÄÕ╣┤ŃéżŃāÖŃā│ŃāłŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃüŠ […]
õĖƵś©µŚźŃü»õ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©Ńü«Õģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝ÜŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéõĖĆŃāĄµ£łķüÄŃüÄŃéŗŃü«ŃüīµŚ®ķüÄŃüÄŃü”Ńā¢ŃāŁŃé░ŃüīÕģźµ£ŁķææÕ«ÜŃü«õ║ŗŃü░ŃüŗŃéŖŃü¦ŃüÖŃüīŃĆéŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃüĀŃü©µĆØŃüåŃĆéĶ╝¬ÕÅŹŃéŖŃü¦Õ░æŃüŚÕÅŹŃéŖÕ╝ĘŃéüŃĆéĶĖÅŃéōÕ╝ĄŃéŖŃüīŃüéŃéŖŃĆüķÄ║õ╗śĶ┐æŃü½ńä╝ŃüŹÕć║ŃüŚµśĀŃéŖŃüīĶ”ŗŃüłŃĆüńö¤ŃüČŃüĀŃü©µĆØŃüåŃĆéµØ┐ńø«ŃüīµĄüŃéīµĮżŃüåĶē»ŃüäĶéī […]
Õ╣│Õ«ēÕŠīµ£¤ŃĆüÕÅżõ║¼ńē®ŃĆéńä╝ŃüŹķĀŁŃü½µ▓┐Ńüåµ╣»ĶĄ░ŃéŖŃüīõ║īķćŹÕłāŃā╗õĖēķćŹÕłāķó©Ńü½ÕāŹŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéõĖēµŚźµ£łÕ«ŚĶ┐æŃü»õĖēķćŹÕłāŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃü”’╝łÕøøķćŹŃü½ŃééŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüŻŃüæ’╝¤Ķ©śµåČķüĢŃüäŃüŗŃā╗Ńā╗Ńā╗’╝ēŃĆüŃüØŃéīŃüīńĀöŃüĵĖøŃéŖŃü½ŃéłŃéŖķĆöÕłćŃéīķĆöÕłćŃéīŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõĖ╣µ│óŃü«ń░ŠÕłāŃü«ńÖ║µā│ […]
HPõĖŖķā©Ńü«ŃāĪŃāŗŃāźŃā╝Ńü½ŃüéŃéŗŃĆīÕģźµ£ŁķææÕ«ÜĶ©śŃĆŹŃü«µø┤µ¢░ŃéÆķĢĘŃéēŃüÅÕ┐śŃéīŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦µø┤µ¢░ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗ŖŃü«ŃüōŃü«HPŃü½ŃüéŃéŗÕģźµ£ŁķææÕ«ÜĶ©śŃü»’╝Æ’╝É’╝É’╝śÕ╣┤ŃüŗŃéēŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«ķææÕ«ÜÕłĆŃü«ÕÉłĶ©łŃü»’╝Ģ’╝Ś’╝ŚÕÅŻŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéõĮĢÕ║”ŃüŗÕÉīŃüśÕłĆŃüīÕć║Ńü¤ŃéŖŃééŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃāØŃā│Ńé│ŃāäĶ©śµåČ […]
õ╗ŖÕø×Ńü»Õ▓®µēŗń£īńøøÕ▓ĪÕĖéŃéłŃéŖŃĆüńåŖĶ░ĘÕÆīÕ╣│Õģłńö¤ŃéÆĶ¼øÕĖ½Ńü©ŃüŚŃü”ŃüŖĶ┐ÄŃüłŃüŚŃü”Ńü«Õģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝ÜŃü¦ŃüÖŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃü½Ķ”ŗŃüłŃéŗŃĆé ńĘŵ¤ŠÕż¬ÕłĆŃĆéµēŗµīüŃüĪĶ╗ĮŃüäŃĆéÕģ©õĮōŃü½Õ░æŃüŚń┤░Ķ║½Ńü¦ŃĆüÕģāÕ╣ģŃü©ÕģłÕ╣ģŃü½ÕĘ«ŃüīŃüéŃéŖŃĆüĶģ░ÕÅŹŃéŖµ░ŚÕæ│Ńü¦ŃĆüŃüŚŃüŗŃüŚÕģłŃüŠŃü¦ÕÅŹŃéŖŃéÆńČŁµīüŃüÖŃéŗķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻŃü«Õż¬ÕłĆÕ¦┐ŃĆé […]
ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ŃüŠŃü¤ÕłźŃü«ńŁåŃéÆĶ▓ĘŃüŻŃü”Ńü┐Ńü¤ŃéŖÕłźŃü«µÅÅŃüŹµ¢╣Ńü½ŃüŚŃü”Ńü┐Ńü¤ŃéŖŃü¦ŃĆüÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü¦ķĢĘŃüäńē®ŃéÆ’╝¢ÕÅŻµÄĪµŗōŃĆéķÄīÕĆēńö¤ŃüČÕ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃĆüÕŹŚÕīŚÕż¦ńŻ©õĖŖŃüÆŃĆüÕŹŚÕīŚÕż¦ńŻ©õĖŖŃüÆŃĆüÕ«żńö║µ£½µ£¤ńö¤ŃüČÕ£©ķŖśÕłĆŃĆüÕ£¤õĮɵ¢░ÕłĆŃĆüµ▒¤µłĖµ¢░ŃĆģÕłĆŃĆéµ▒¤µłĖµ¢░ŃĆģÕłĆŃü»õ║īÕ░║Õģ½Õ»ĖÕ╝▒Ńü¦ķĢĘŃüäŃĆéµÅÅŃüäŃü¤Õłāµ¢ćŃü»Õģ©ķā© […]
ķ¢óĶź┐Õż¦ÕŁ”ÕŹÜńē®ķż©Ńü½Ńü”ķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃü¤ŃĆüńź×ńö░õ╝»Õ▒▒ŃüĢŃéōŃü«Ķ¼øĶ½ćŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃü»õ╝»Õ▒▒ŃüĢŃéōŃü©µ▓│ÕåģÕ£ŗÕ╣│ÕłĆÕīĀŃü«Õ»ŠĶ½ćŃü©ŃüäŃüåÕż¦ÕżēµźĮŃüŚŃüäŃéżŃāÖŃā│ŃāłŃü½ĶĪīŃüŗŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ÕÅżĶćŁŃüäŃü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüīń¦üŃĆüŃüöŃüŵ£ĆĶ┐æŃü«Ńā×ŃéżŃā¢Ńā╝ŃāĀŃüīµĄ¬µø▓Ńü¦ŃĆéŃĆéµŖ╝ÕĮóŃéƵÅÅŃüŹŃü¬ŃüīŃéēYouT […]
ÕłĆÕīĀõ╝ÜŃü«õĖēõĖŖÕłĆÕīĀŃüŗŃéēŃĆüµźĮŃüŚŃü┐Ńü¬ńŠÄĶĪōķż©ŃéÆŃüŖµĢÖŃüłķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃĆÉńŠÄĶĪōķż©ķüŗÕ¢ČŃü«ńø«ńÜäŃĆæ – 1ŃüżŃüĀŃüæńŠÄĶĪōķż©Õģ¼Õ╝ÅŃéĄŃéżŃāł (jimdofree.com)ŃĆīõĖĆŃüżŃüĀŃüæńŠÄĶĪōķż©ŃĆŹŃü»ŃüŠŃüĀķ¢ŗķż©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüŃüōŃéōŃü¬ń┤ĀµĢĄŃü¬ń®║ķ¢ōŃüīń¦üŃü«Ķ║½Ķ┐æ […]
ńēćŃāüŃā¬Ńü½µ»öŃü╣ŃéŗŃü©õĖĪŃāüŃā¬Ńü«ÕłĆŃü»Õ£¦ÕĆÆńÜäŃü½Õ░æŃü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéķā©ÕłåµŖ╝ÕĮóń©ŗÕ║”Ńü¬ŃéēŃéłŃüäŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕģ©Ķ║½Ńü©Ńü¬ŃéŗŃü©Õ«¤Ńü»õĖĪŃāüŃā¬Ńü«ÕłĆŃü»ķØ×ÕĖĖŃü½ķøŻŃüŚŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéķļŃü«ńĘÜŃüīŃü¢ŃüŻŃüÅŃéŖŃü©Õć║Ńéŗµ¦śŃü¬µÄĪŃéŖµ¢╣Ńü¬ŃéēŃü░ń░ĪÕŹśŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüµśÄńףŃü¦Õ╝ĘŃüäńĘÜŃéÆŃüĀŃüØŃüåŃü©ŃüÖŃéŗŃü©ŃüŗŃü¬ŃéŖŃü«µēŗ […]
µ¤ÉµŚźńźćÕ£ÆŃĆéõ║¼ķāĮŃééõ║║ŃüīÕóŚŃüłŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīÕģāŃü½µł╗ŃéŗŃü«Ńü»ŃüŠŃüĀÕģłŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆé µ¤ÉµŚźŃĆüÕīŚÕż¦ĶĘ»µ®ŗŃüŗŃéēÕŹŚŃéƵ£øŃéĆŃĆé µ¤ÉµŚźÕøøµØĪÕż¦µ®ŗŃüŗŃéēÕĘØÕ║ŖŃĆé ÕŁÉõŠøŃéēŃéÆķĆŻŃéīŃü”Õ░æŃüŚÕĘØķüŖŃü│Ńü½ŃĆéõĖŁÕŁ”Ńü©ķ½śµĀĪńö¤Ńü¦ŃüÖŃüīÕ¢£ŃéōŃü¦µØźŃü”ŃüÅŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńłČŃüĪŃéāŃéōŃüīõĖĆńĢ¬Õ¢£ŃéōŃü¦ŃüŠŃüÖŃĆé õĖŖĶ│ĆĶīéńź×ńżŠ […]
Õż®ńäČńĀźń¤│µ»öĶ╝āNo.132ŃéÆÕłāÕ╝ĢŃüŹŃü½õĮ┐ńö©ŃüÖŃéŗŃĆé ŃüōŃü«ń¤│Ńü»ķĀéŃüŹńē®Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüéŃüŵ░┤’╝łµ┤ŚŃéĮŃā╝ŃāƵ░┤’╝ēŃü¦µŁ╗ŃéōŃü¦ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦õĮ┐ńö©Ńü»Õø░ķøŻŃü©µĆØŃüäõĮ┐ŃéÅŃüÜŃü½ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕ£░ńĀźŃü¬Ńü®Ńü«ńĪ¼ŃüäńĀźń¤│Ńü»µ«åŃü®µ░┤ŃéÆÕÉĖŃéÅŃü¬ŃüäŃü«Ńü¦Õż¦õĖłÕż½Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕłāÕ╝ĢŃüŹńŁēµ¤öŃéēŃüŗŃéüŃü«ńĀźń¤│Ńü»µ┤ŚŃéĮ […]
ÕģłµŚźŃüĪŃéćŃüŻŃü©Ńé¼ŃāüŃāŻŃé¼ŃāüŃāŻŃüŚŃü¤ÕĀ┤µēĆŃü¦Ķ¢äķīåĶ║½Ńü«ńäĪķŖśń¤ŁÕłĆŃéƵŗØĶ”ŗŃĆéÕ╣ģÕ║āÕåģÕÅŹŃéŖµī»Ķó¢ĶīÄŃĆé õ╗źÕēŹµŗØĶ”ŗŃüŚŃü¤ń¤ŁÕłĆŃĆüÕģźķ╣┐Õ»”ÕÅ»ŃĆéĶīĵŻ¤Ńā®ŃéżŃā│Ńéäµī»ŃéŖµ¢╣ŃéäõĖŖĶ║½ÕĮóńŖČŃüīńŗ¼ńē╣Ńü¦Õ┐śŃéīŃéŗõ║ŗŃü«ńäĪŃüäÕ¦┐Ńü¦ŃĆéŃüØŃéīŃü©ÕÉīŃüśŃĆéÕģłµŚźŃü«ń¤ŁÕłĆŃééÕ»”ÕÅ»ŃüśŃéāŃü¬ŃüŗŃéŹŃüåŃüŗŃĆéÕģźķ╣┐Õ»”ÕÅ»µŗØĶ”ŗŃĆé […]
Ńé│ŃāŁŃāŖŃü«ÕĮ▒ķ¤┐Ńü¦õĖŁµŁóŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Õ▒▒ķēŠÕĘĪĶĪīŃüī’╝ōÕ╣┤µī»ŃéŖŃü½ķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé’╝łÕåÖń£¤Ńü»Õ«ĄŃĆģÕ▒▒Ńü«ķĢĘÕłĆķēŠ’╝ēĶ”│Ńü½ĶĪīŃüŹŃü¤Ńüäµ░ŚµīüŃüĪŃéƵŖæŃüłŃĆüõ╗ŖµŚźŃü»Õģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝ÜŃüĖŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕłĆÕÅŹŃéŖ’╝ŚÕłåÕ╝▒ŃüŗŃĆéńĘŵ¤ŠŃĆéńĀöŃüÄŃü«ÕģĘÕÉłŃü¦ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ÕłåŃüŗŃéŖķøŻŃüäŃüīÕżÜÕłåķļգ░Ńé鵤Šńø«ŃĆ鵤ŠŃüīÕ░æ […]
ķ¢óĶź┐Õż¦ÕŁ”ÕŹÜńē®ķż©Ńü½Ńü”µ▓│ÕåģÕ£ŗÕ╣│Õģłńö¤Ńü«õ╝üńö╗Õ▒ĢŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõ╗źõĖŗŃĆüķ¢óĶź┐Õż¦ÕŁ”ÕŹÜńē®ķż©HPŃéłŃéŖ 2022Õ╣┤Õ║”ķ¢óĶź┐Õż¦ÕŁ”ÕŹÜńē®ķż©ÕżÅÕŁŻõ╝üńö╗Õ▒ĢŃĆĆŃĆīķ¢óÕż¦Ńü©ÕłĆÕīĀÕ£ŗÕ╣│ŃĆŹŃü«ķ¢ŗÕé¼Ńü½ŃüżŃüäŃü” 2022Õ╣┤Õ║”ķ¢óĶź┐Õż¦ÕŁ”ÕŹÜńē®ķż©ÕżÅÕŁŻõ╝üńö╗Õ▒ĢŃĆĆŃĆīķ¢óÕż¦Ńü©ÕłĆÕīĀÕ£ŗÕ╣│ŃĆŹ ÕłĆÕīĀ┬Ę […]
Õ░æŃüŚÕēŹŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüńł║ŃüĢŃéōŃü½õ╝ÜŃüäŃü½ĶĪīŃüōŃüåŃü©µĆØŃüäń½ŗŃüĪŃĆüÕłØŃéüŃü”ķØ¢ÕøĮŃü½ĶĪīŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé’╝łńź¢ńłČŃü»µśŁÕÆī’╝Æ’╝ÉÕ╣┤’╝Śµ£łŃĆüńłČŃüī’╝ƵŁ│Ńü«ķĀāÕż¦ķś¬µ╣ŠŃü½Ńü”µł”µŁ╗’╝ēń¦üŃüī’╝ō’╝Éõ╗ŻŃü«ķĀāõ║ĪŃüÅŃü¬ŃüŻŃü¤ńź¢µ»ŹŃü»ŃĆüńź¢ńłČŃü«ÕóōÕÅéŃéŖŃéƵ»ÄµŚźµ¼ĀŃüŗŃüÖõ║ŗŃü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéń¦üŃüīń¤źŃéŗķÖÉŃéŖµ»ÄµŚźŃü¦ŃüÖ […]
Õ░æŃüŚÕēŹŃü½õ╣ģŃĆģŃü½ÕłāĶēČŃéÆĶ▓╝ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüäŃüżõ╗źµØźŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéŃüĪŃéćŃüŻŃü©õĖŹµśÄŃü¦ŃĆéÕēŹÕø×Ńé½ŃāāŃāłŃüŚŃü”ŃüäŃü¤õĖŁŃüŗŃéēÕ┐ģĶ”üŃü¬ńĀźĶ│¬’╝ōń©«ŃéÆ’╝Ģ’╝ɵ×Üń©ŗŃĆéÕēŹÕø×Ńü«Ńé½ŃāāŃāłŃü¦Ńü»Ńü®ŃüåŃéäŃéē’╝¢ń©«ń©ŗÕ║”ŃéÆŃé½ŃāāŃāłŃüŚŃü”ŃüäŃü¤µ©Īµ¦śŃĆéŃüØŃéīŃü½ŃüŚŃü”ŃééŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü«Ķ▓╝ŃéŖÕģĘÕÉłŃüīķüÄÕÄ╗’╝ō’╝ÉÕ╣┤ķ¢ōõĖŁµ£ĆŃéé […]
ÕÅżÕ«ćÕżÜŃü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗńø┤ÕłāŃü«ÕłĆŃéÆńĀöńŻ©ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńäĪķŖśŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦Ķ”ŗµ¢╣Ńü»Ķē▓ŃĆģŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕÅżÕ«ćÕżÜŃü«Ķ”ŗµ¢╣ŃüīõĖĆńĢ¬Õ”źÕĮōŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆ鵜öŃüŗŃéēÕ║”ŃĆģŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüńäĪķŖśŃü¦Õć║µØźŃüīĶē»ŃüäÕłĆŃüĀŃü¬ŃüüŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃü”ŃĆüŃüØŃü«ÕŠīÕ»®µ¤╗Ńü½Õć║ŃüĢŃéīŃĆüõ╗śŃüäŃü¤µźĄŃéüŃüīŃĆīÕÅżÕ«ćÕżÜŃĆŹŃĆéńĄÉµ¦ŗŃüéŃéŖ […]
õ╗ŖÕø×Ńü»µ£¼ķā©ŃéłŃéŖµŁ”ńö░Õģłńö¤ŃéÆŃüŖµŗøŃüŹŃüŚŃü”Ńü«Õģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝ÜŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆķĢĘÕ»ĖŃü¦ķćŹķćÅŃü¤ŃüŻŃüĘŃéŖŃĆéÕłćŃüŻÕģłŃü»Õ░ÅŃüĢŃüÅŃĆüÕģāÕ╣ģŃüīŃüéŃüŻŃü”ĶĖÅŃéōÕ╝ĄŃéŖŃüīÕ╝ĘŃüäŃĆéÕģłõ╝ÅŃüĢŃüÜÕģłŃüŠŃü¦ÕÅŹŃéŖŃéÆńČŁµīüŃĆéµØ┐ńø«µØóńø«ŃüīĶéīń½ŗŃüżŃĆéÕ£░µ¢æµśĀŃéŖŃüīķ««µśÄŃü¦ŃĆüµ©ŗŃüīńäĪŃüæŃéīŃü░ķļգ░ŃüŠŃü¦µśÄńףŃü½µśĀ […]
Õ╣│Ķ║½Ńü¦ĶČŖÕēŹõĖŗÕØ鵤ÉŃü«ķŖśŃü«ŃüéŃéŗÕåģµøćŃéŖŃéÆÕ╝ĢŃüÅŃĆéµö╣µŁŻ’Į×ń┤░ÕÉŹÕĆēŃü¦ŃééńĀźÕĮōŃü¤ŃéŖŃü«Ķē»ŃüĢŃéƵä¤ŃüśŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕåģµøćŃéŖŃü¦ńó║õ┐ĪŃü¦ŃüÖŃĆéÕåģµøćŃéŖŃü«Õ╝ĢŃüŹÕæ│Ńü»ķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻŃü©ÕÉīńŁēŃĆéÕŹśŃü½µ¤öŃéēŃüŗŃüäŃüĀŃüæŃü«ńē®Ńü¬ŃéēÕ«żńö║ŃüŗŃéēńÅŠõ╗ŻŃüŠŃü¦µ▓óÕ▒▒ÕŁśÕ£©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕåģµøćŃéŖŃü«ÕŖ╣ŃüŹŃüīµŚ®ŃüÅ […]
Õ«ČŃü«ĶŻÅŃü½ŃüéŃüŻŃü¤ńø┤ÕŠä’╝Æ’╝ÉŃÄØÕ╝▒Ńü«µ×»ŃéīŃü¤ŃéŁŃā│ŃāóŃé»Ńé╗ŃéżŃü«µ£©ŃéÆÕłćŃéŖÕĆÆŃüŚŃĆüŃüöŃü┐ÕÅÄķøåĶ╗ŖŃüīµīüŃüŻŃü”ĶĪīŃüŻŃü”ŃüÅŃéīŃéŗŃéłŃüåŃĆü’╝Ģ’╝ÉŃé╗Ńā│Ńāüń©ŗÕ║”Ńü½ÕłćŃéŖÕł╗Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµĀ╣ŃééÕć║µØźŃéŗŃüĀŃüæµÄśŃéŖŃĆüµÄśŃéŖÕłćŃéīŃü¬Ńüäķā©ÕłåŃü»Õłćµ¢ŁŃüŚÕłćŃéŖµĀ¬ŃééµÆżÕÄ╗ŃĆéķüōÕģĘń«▒Ńü½ŃüéŃüŻŃü¤ŃāÄŃé│Ńé«Ńā¬Ńü»ÕåģµøćŃéŖŃéÆ […]
ķćÄõĖŁķēäÕĘź’╝łÕ««ńöÜ’╝ēŃüĢŃéōŃüŗŃéēķŗÅńĀöńŻ©Ńü«ŃüöõŠØķĀ╝ŃéÆķĀéŃüŹńĀöŃüīŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéķŗÅŃü»Õ«¤ńö©Ńü«Õłāńē®Ńü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ķĆÜÕĖĖŃü»ŃüØŃéīŃü½ķü®ŃüŚŃü¤ķŗ╝µØÉŃéÆõĮ┐ńö©ŃüŚĶŻĮõĮ£ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü»ńŠÄŃüŚŃüäÕłāµ¢ćŃü©Õ£░ķēäŃéƵ▒éŃéüŃĆüÕłØŃéüŃü”ńÄēķŗ╝’╝łµŚźÕłĆõ┐ØŃü¤Ńü¤Ńéē’╝ēŃéÆõĮ┐ńö©ŃüŚĶŻĮõĮ£ŃüĢŃéīŃü¤ŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆé […]
ń¼¼106Õø×õ╝üńö╗Õ▒ĢŃĆīµł”ÕøĮõĖŖÕĘ×Ńü«ÕłĆÕēŻŃü©ńö▓ÕåæŃĆŹ | ńŠżķ”¼ń£īń½ŗµŁ┤ÕÅ▓ÕŹÜńē®ķż© (pref.gunma.jp) ŃĆīµł”ÕøĮõĖŖÕĘ×Ńü«ÕłĆÕēŻŃü©ńö▓ÕåæŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕ▒ĢĶ”¦õ╝ÜŃüīŃĆīńŠżķ”¼ń£īń½ŗµŁ┤ÕÅ▓ÕŹÜńē®ķż©ŃĆŹŃü¦ĶĪīŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕ▒Ģńż║ÕōüŃü«Ķ®│ń┤░Ńü»ÕłåŃüŗŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīHPŃéÆĶ”ŗŃéŗŃü©µ£©õĖŗµŁŻÕ«Ś […]
õ╝ܵ£¤’╝Ü2022Õ╣┤6µ£ł1µŚź(µ░┤) ’Į× 2022Õ╣┤6µ£ł6µŚź(µ£ł)õ╝ÜÕĀ┤’╝ܵŚźµ£¼µ®ŗõĖēĶČŖµ£¼Õ║Śµ£¼ķż©6ķÜÄńŠÄĶĪōńē╣ķüĖńö╗Õ╗ŖõĮŵēĆ’╝ÜŃĆÆ103-8001 µØ▒õ║¼ķāĮõĖŁÕż«Õī║µŚźµ£¼µ®ŗÕ«żńö║1-4-1 ŌåōŃāćŃéĖŃé┐Ńā½Ńé½Ńé┐ŃāŁŃé░ŃéÆŃüöĶ”¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäõ╗żÕÆīŃü«ÕłĆµśÄµ▓╗Ńü«µŗĄÕ▒Ģ | eb […]
ķææÕ«ÜŃü«ÕĮōńĢ¬Ńü¦ŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦õ╗ŖÕø×Ńü»ń¤ŁÕłĆ’╝łÕɽջĖÕ╗Č’╝ēŃü░ŃüŗŃéŖ’╝æ’╝ÉÕÅŻŃü¦Ńü«Õģźµ£ŁķææÕ«ÜŃü©ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ķææÕ«ÜÕłĆ’╝łĶŻĮõĮ£Õ╣┤õ╗ŻŃü«µ¢░ŃüŚŃüäńē®ŃüŗŃéēÕÅżŃüäńē®ŃüĖķĀåńĢ¬Ńü½õĖ”Ńü╣ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤’╝ē ŃĆĆ’╝æÕÅĘŃĆĆĶäćÕĘ«ŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆĶĪ©ŃĆĆÕÉēķćÄÕ▒▒õ║║Õ£ŗÕ╣│õ╣ŗŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆĶŻÅŃĆĆ […]
ÕģłµŚźŃüŖŃüśŃéāŃüŠŃüäŃü¤ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗źÕēŹŃüŗŃéēµĆØŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃéäŃü»ŃéŖÕłĆŃü«Õ▒Ģńż║Ńü»µĢ░ŃüśŃéāŃü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆé’╝ō’╝ÉŃéé’╝ö’╝ÉŃééŃĆüµł¢ŃüäŃü»ŃééŃüŻŃü©µ▓óÕ▒▒ŃüéŃüŻŃü¤Ńü©ŃüŚŃü”ŃééĶ”ŗŃüłŃü¬ŃüäÕ▒Ģńż║ŃüśŃéāµäÅÕæ│ŃüīńäĪŃüäŃĆéŃüŚŃüŻŃüŗŃéŖĶ”ŗŃüłŃéŗÕ▒Ģńż║Ńü¬ŃéēŃü░Õż¦Ķ”ŵ©ĪÕ▒ĢĶ”¦õ╝ÜŃü¦Ńü¬ŃüÅŃü©ŃééÕŹüÕłåÕĀ¬ĶāĮŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖ […]
õ╣ģŃĆģŃü½Õģźµ£ŁķææÕ«ÜŃüīÕć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆéŃĆĆÕ░ÅķŗÆŃĆéŃéłŃüÅÕÅŹŃéŗ’╝łĶģ░ÕÅŹŃéŖµ░ŚÕæ│’╝ēŃĆéÕ░æŃüŚÕģłõ╝ÅŃüÖŃĆéķĢĘŃüäŃĆéń┤░Ķ║½ŃĆéĶĖÅŃéōÕ╝ĄŃéŖÕ╝ĘŃüäŃĆéńĀöńŻ©Ńü½ŃéłŃéŗŃü©ŃüōŃéŹŃüīÕż¦ŃüŹŃüäŃüīŃĆüÕģ©õĮōŃü½ķ╗ÆÕæ│ŃüīÕ╝ĘŃüäŃĆéÕż¦µØ┐ńø«Ńü½µØóńø«ŃĆéńÅŠńŖČŃüŗŃü¬ŃéŖÕż¦ĶéīŃüīń½ŗŃüżŃĆéńø┤ŃüÉĶ¬┐Ńü«ÕłāŃü¦ĶżćķøæŃü½ÕāŹŃüÅ’╝łµŖ╝ […]
µ£ĆĶ┐æŃüōŃü«ńĀźń¤│Ńü½µĄĖŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃĆĆÕż®ńäČńĀźń¤│µ»öĶ╝āŃĆĆ103ŃĆ£104 | ńÄēńĮ«ńŠÄĶĪōÕłĆÕēŻńĀöńŻ©Õć”’Į£õ║¼ķāĮŃā╗ÕĘ”õ║¼Õī║ (kyoto-katana.com)ŃüōŃü«µÖéŃü«Ńé│ŃāĪŃā│ŃāłŃü»ŃĆīNo.103Ńü»ķØ×ÕĖĖŃü½Ķē»ŃüäÕłāÕ╝ĢŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃĆŹŃü¤ŃüĀŃüōŃéīŃüĀŃüæŃĆéķØ×ÕĖĖŃü½Ķē»ŃüäńĀźń¤│ […]
ŃĆÉĶÖÄÕ▒ŗ õ║¼ķāĮŃé«ŃāŻŃā®Ńā¬Ńā╝ŃĆæŃĆīõĮ£ÕłĆ50Õ╣┤ ÕłĆÕīĀ µ▓│ÕåģÕ£ŗÕ╣│Õ▒ĢŃĆŹ ķ¢ŗÕé¼Ńü«ŃüŖń¤źŃéēŃüø ĶÖÄÕ▒ŗ õ║¼ķāĮŃé«ŃāŻŃā®Ńā¬Ńā╝Ńü½Ńü”ŃĆüńÅŠõ╗ŻŃéÆõ╗ŻĶĪ©ŃüÖŃéŗÕłĆÕīĀŃā╗µ▓│ÕåģÕ£ŗÕ╣│(ŃüŗŃéÅŃüĪ ŃüÅŃü½Ńü▓Ńéē)ÕłĆÕīĀŃü«ŃĆüõĮ£ÕłĆ50Õ╣┤ŃéÆĶ©śÕ┐ĄŃüŚŃü¤Õ▒ĢĶ”¦õ╝ÜŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé ĶÖÄÕ▒ŗõ║¼ķāĮŃé«ŃāŻŃā®Ńā¬Ńā╝Ńü¦ […]
ŌĆØķלµ¢ćŌĆØŃü«ķĆÜń¦░Ńü¦ń¤źŃéēŃéīŃü¤ķלÕĖ½µ¢ÄĶŚżµ¢ćÕÉē’╝łµØ▒õ║¼’╝ēŃüīĶŻĮõĮ£ŃüŚŃü¤ŃüŗŃééń¤źŃéīŃü¬ŃüäńÖĮķלŃüīŃüéŃéŖĶ¬┐Ńü╣Ńü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ¢ÄĶŚżķלÕĖ½Ńü»ŃüŗŃü¬ŃéŖŃü«ÕÉŹõ║║Ńü¦ŃĆüÕ╣│õ║ĢÕŹāĶæēŃéēÕÉŹõ║║ńĀöÕĖ½Ńü©Õģ▒Ńü½µĢ░ŃĆģŃü«ÕÉŹÕōüŃü«ķלŃéƵēŗµÄøŃüæŃü¤ŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéµēŗÕģāŃü½ŃüéŃéŗŃüōŃü«ķלŃĆüÕē▓ŃéīŃü░õĖŁŃü½ķלÕĖ½Ńü«ķŖśŃüīµ£ēŃéŗŃüŗ […]
ÕÅżŃüäńÖĮķלŃü½ÕĮōŃü¤ŃéŖŃüīŃüéŃéŖŃĆüÕē▓ķלŃéÆŃüŚŃü”ŃééŃéēŃüåŃü¤ŃéüķĢĘĶł╣Ńü½ŃĆéÕłĆĶ║½ŃéƵŖ£ŃüŹķ»ēÕÅŻŃü«Ķ▒ĪńēÖŃéÆÕż¢ŃüŚŃü”ķĀéŃüäŃü”ŃüäŃéŗµÖéŃĆüõĖŹµäÅŃü½ÕģźÕŁÉŃüīķĀŁŃéÆÕć║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕģźÕŁÉķלŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüķÄ║ĶóŗŃéÆĶ”ŚŃüÅŃü©ÕģźÕŁÉŃéÆÕ╝ĢŃüŻÕ╝ĄŃéŖÕć║ŃüÖŃü¤ŃéüŃü«Ķ¦ÆĶŻĮŃü«ÕÖ©ÕģĘŃüīÕåģĶćōŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¤ŃéŖŃĆüÕ╝ĢŃüŻµÄøŃüæŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ń®┤ […]
ķć£õĮ£Ķ▓×Õ«ŚŃüīµ░ŚŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”õ╣ģŃĆģŃü½’╝ł’╝Æ’╝ÉÕ╣┤Ńü╗Ńü®ŃüČŃéŖ’╝¤’╝ēµÄóŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃéēŃĆüŃüłŃéēŃüÅÕÅżŃüäÕłĆńŠÄŃü½Ķ╝ēŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé’╝¢ÕåŖŃü½µĖĪŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüäŃüżŃééŃüŖõĖ¢Ķ®▒Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗµ¢╣ŃüŗŃéēÕøĮń½ŗÕŹÜńē®ķż©Ńü«ŃéĘŃā│ŃāØŃéĖŃé”ŃāĀŃü«Ńā¼ŃéĖŃāźŃāĪŃéÆĶ”ŗŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń¦üŃü«Õæ©ŃéŖŃü½Ńü»ŃĆüÕÅżÕłĆŃü«ÕĤµ¢ÖŃü»õĖĆĶł¼Ńü½õ┐ĪŃüśŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗµ¦śŃü¬ńē®Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü©Ńü«ĶĆāŃüłŃéÆŃüŖµīüŃüĪŃü«µ¢╣ŃüīÕżÜŃüäŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕø×Ķ”ŗŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü¤ÕåģÕ«╣Ńü»ŃüØŃéīŃéÆŃüŚŃüŻŃüŗŃéŖĶŻÅõ╗ś […]
Õ░ŖµĢ¼ŃüÖŃéŗõ║║Ńü»’╝¤Ńü©Ķü×ŃüŗŃéīŃéŗŃü©ŃĆīõĖŖÕ╣│õĖ╗ń©ÄŃĆŹŃü©ńŁöŃüłŃüŠŃüÖŃĆé’╝łµĆصā│ńÜäŃü½Ńü©ŃüäŃüåŃéÅŃüæŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüĶē▓ŃĆģµ£¼ÕĮōŃü½ń½ŗµ┤ŠŃü¬µ¢╣Ńü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃĆéÕŹüµ┤źÕĘØĶŹēĶÄĮĶ©ś | ÕÉēĶ”ŗ Ķē»õĖē |µ£¼ | ķĆÜĶ▓® | Amazon’╝ēõĖŖÕ╣│õĖ╗ń©ÄŃü»ń¦üŃü«ńö░ĶłÄŃü«õĖŁŃü«ŃĆīķćÄÕ░╗ŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕ£░ […]
ĶČŖÕēŹµ¢░ÕłĆŃĆéĶīÄŃü½ķīåŃüīķģĘŃüäŃü«ŃüŗńÖĮķלŃü«µ¤äŃüīµŖ£ŃüæŃüÜŃĆéµ£©µ¦īŃü¦ÕÅ®ŃüäŃü”µŖ£ŃüÅŃü©ŃĆüĶīÄŃü½ķģĘŃüÅńøøŃéŖõ╗śŃüÅĶĄżķīåŃü¦ķŖśŃüīÕłżĶ¬ŁŃüŚĶŠøŃüäńŖȵģŗŃĆéõĖĆĶł¼ńÜäŃü¬ĶČŖÕēŹµ¢░ÕłĆŃü¦ŃüÖŃüīńĀöńŻ©ńĄīķ©ōŃü»Ńü¬ŃüÅŃĆüõĖĆÕ┐£ÕŗēÕ╝ĘŃü«Ńü¤ŃéüŃü½Õ║ĘńČÖÕż¦ķææŃéÆķ¢ŗŃüÅŃü©µēĆĶ╝ēÕōüŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆ鵜ŁÕÆī’╝ō’╝ĢÕ╣┤ÕĮōµÖéŃü«ĶīÄŃü»ŃĆüµé¬ķīåõĖĆÕłć […]
õ╗źÕēŹńĀöńŻ©ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü¤Õ£©ķŖśŃü«µŁŻÕ«ŚŃü½Ńü»ŃüōŃü«µ¦śŃü¬ńø«ķī▓Ńüīõ╗śŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶ╝¬ķāŁŃü«Ńü┐Ńü¦ŃüÖŃüīµŖ╝ÕĮóõ╗śŃüŹŃü¦’╝łµ¢ćµö┐ÕøøÕ╣┤’╝ēŃĆéńÅŠõ╗ŻŃü½ÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗÕłĆŃü»ń£¤Ķ┤ŗŃü½ŃüżŃüäŃü”ķØ×ÕĖĖŃü½ÕÄ│ŃüŚŃüäµĖ”õĖŁŃü½ŃüéŃéŗŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃéōŃü¬Ńü½Õż¦ÕłćŃü½ŃüŚŃü”ŃééŃéēŃüłŃéŗµÖéõ╗ŻŃüīŃüéŃüŻŃü¤ŃéōŃü¦ŃüÖŃéłŃüŁŃĆéŃĆéń¦ü […]
HPŃü«ŃāŚŃāŁŃāĢŃéŻŃā╝Ńā½ŃāÜŃā╝ŃéĖŃü©ńĀöńŻ©Ķ©śķī▓ŃāÜŃā╝ŃéĖŃéƵø┤µ¢░ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
õ╣ģŃĆģŃü½ńĀöńŻ©Ķ©śķī▓ŃāÜŃā╝ŃéĖŃéƵø┤µ¢░ŃüŚŃéłŃüåŃü©µĆØŃüŻŃü¤ŃéēŃĆüµōŹõĮ£µ¢╣µ│ĢŃéÆŃé╣ŃāāŃéŁŃā¬ŃüĢŃüŻŃü▒ŃéŖÕ┐śŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤Ńā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃüōŃéōŃü¬Ńü½ŃééĶ”ŗõ║ŗŃü½Õ┐śŃéīŃéŗŃééŃéōŃü¬ŃéōŃü¦ŃüÖŃüŁŃüćŃĆéŃĆéŃü¤ŃüĀŃüéŃéīŃüōŃéīĶ¦”ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃüåŃüĪŃü½ŃĆüµĆØŃüäÕć║ŃüŚŃü»ŃüŚŃüŠŃüøŃéōŃüīµ¢░Ńü¤Ńü¬ńŗ¼Ķ欵¢╣µ│ĢŃü¦µø┤µ¢░Õć║µØźŃéŗµä¤Ńüś […]
µ£½ńøĖÕĘ×ŃüŗÕ│Čńö░ŃüŗŃĆéńäĪķŖśŃü¦ŃüÖŃĆéÕŹāÕŁÉŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéµØ▒µĄĘķüōńŁŗŃĆüńÜåŃéłŃüÅõ╝╝Ńü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃü«Ńü»ķØóńÖĮŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéĶĪŚķüōŃü½ŃéłŃéŖõ╝╝Ńü¤ńē®Ńü½Ńü¬ŃéŗŃü«Ńü»ÕŠĪµē┐ń¤źŃü«ķĆÜŃéŖŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüµØ▒µĄĘķüōŃü»ńē╣Ńü½õ╝╝Ńü”ŃüäŃü”ŃĆüŃéłŃéŖŃüĪŃéāŃéōŃü©ÕŗēÕ╝ĘŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░ÕłżÕłźŃü»ķøŻŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆéŃüŠŃü¤ĶīÄŃéÆÕŠīŃüŗŃéēÕŖĀ […]
µŖ╝ÕĮóÕłČõĮ£ŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃü¬Ńüäµ£¤ķ¢ōŃüīÕ░æŃüŚŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµ£ĆĶ┐æŃü»ŃüŠŃü¤Õ¦ŗŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé’╝ō’╝É’╝ÉõĖćÕÅŻŃĆüÕģ©Ńü”ŃéƵÄĪµŗōÕć║µØźŃü¤Ńéēń┤ĀµÖ┤ŃéēŃüŚŃüäŃĆéŃāćŃā╝Ńé┐Õī¢µĢ┤ńÉåŃüŚķ¢▓Ķ”¦ÕÅ»ĶāĮŃü½ŃüÖŃéŗŃĆéŃüØŃéōŃü¬Ńü«ŃüīĶ”ŗŃéēŃéīŃü¤ŃéēµźĮŃüŚŃüÅŃü”µŁ╗Ńü½ŃüŠŃüÖŃüŁŃĆé ÕĀĆÕĘØÕ£░ķēäŃĆéŃü¢ŃéōŃüÉŃéŖĶéīŃü«ńĀöńŻ©Ńü»õĖĆńĢ¬µźĮŃüŚ […]
ÕÅżķØƵ▒¤ńé║µ¼ĪµŖśŃéŖĶ┐öŃüŚķŖśŃĆé’╝Æ’╝É’╝æ’╝śÕ╣┤Ńü«µö»ķā©ķææÕ«ÜÕłĆŃü©ŃüŚŃü”õĮ┐ŃéÅŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü¤ÕŠĪÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆéŃĆī’╝Ƶ£łµŚźÕłĆõ┐Øõ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©õŠŗõ╝ÜŃĆŹŃüéŃéīŃüīŃééŃüå’╝öÕ╣┤ŃééÕēŹŃü¦ŃüÖŃüŗŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃüŖŃüØŃéŹŃüŚŃéäŃĆéŃéäŃüŻŃü©Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆÕłČõĮ£Õć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńé║µ¼ĪŃü«õ╗ŻĶĪ©õĮ£Ńü»ÕøĮÕ«ØŃü«ŃĆīńŗÉŃāČÕ┤Äńé║µ¼ĪŃĆŹŃĆéŃüØŃü«õ╗¢ńé║ […]
Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆķĆ▓ŃéüŃéŗŃĆéÕģ©õĮōŃü½µś©µŚźŃü©Ńü»Õ░æŃüŚķüĢŃüåķø░Õø▓µ░ŚŃü½ŃĆéµŖ╝ÕĮóŃü»õ║īÕŹüµĢ░Õ╣┤ŃéäŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃü©µĆØŃüåŃüīŃĆüń¦üŃü«Õłāµ¢ćµÅÅÕåÖŃü»õ╗ŖÕø×Ńü«ŃüōŃü«ķø░Õø▓µ░ŚŃüīÕ«īµłÉÕĮóŃüŗŃééń¤źŃéīŃü¬ŃüäŃĆéµ┐āŃüÅŃü”ŃüŗŃüŻŃüōŃüäŃüäÕłāµ¢ćŃü»µÅÅŃüæŃüÜŃĆéńĄČÕ”ÖŃü¬Ķ¢äŃüĢŃü¦ŃāÅŃéżŃé╣ŃāöŃā╝ŃāēŃĆüÕż¦ĶāåŃüŗŃüżń╣Ŗń┤░Ńü¬ŃüéŃü«µŖĆĶĪōŃééńäĪńÉå […]
ÕÅżķØƵ▒¤ŃéƵŗØĶ”ŗŃüŚŃü¤ŃéŖńĀöńŻ©ŃéÆŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüÅõ║ŗŃü»Õ║”ŃĆģŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüķŁģÕŖøńÜäŃü¬ÕłĆŃüīÕżÜŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé’╝łµŖ╝ÕĮóŃü»ŃüŠŃüĀķĆöõĖŁŃü¬Ńü«Ńü¦µŻ¤Õī║Ńüīń╣ŗŃüīŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéō’╝ēÕÅżÕéÖÕēŹŃü½ŃéłŃüÅõ╝╝Ńü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦ķææÕ«ÜŃü½Õć║Ńü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü¬Ńü®Ńü»Ķ┐ĘŃüåńē®Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕĆŗõ║║ńÜäµä¤µā│Ńü¦ŃüäŃüłŃü░ŃĆüÕÅżÕéÖÕēŹŃéłŃéŖķćÄĶČŻŃéƵä¤ŃüśŃéŗńē® […]
ķüÄÕÄ╗Ńā¢ŃāŁŃé░Ńü«Ķ¬┐Ńü╣ńē®ŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃéēŃĆīńÅŠõ╗ŻÕłĆńø«Õł®ŃüŹĶ¬ŹÕ«ÜÕż¦õ╝ÜŃĆŹŃü«Ńā¢ŃāŁŃé░Ķ©śõ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃĆüĶ”ŗŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüäŃéäŃüüŃĆüµźĮŃüŚŃüĢŃüīĶśćŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃĆĆŃĆĆńÅŠõ╗ŻÕłĆŃü«Õģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝Ü | ńÄēńĮ«ńŠÄĶĪōÕłĆÕēŻńĀöńŻ©Õć”’Į£õ║¼ķāĮŃā╗ÕĘ”õ║¼Õī║ (kyoto-katana.com)ŃĆīõ╗Ŗ […]
õ╗ŖÕø×ŃééÕĮōńĢ¬Ńü¦ŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ÕłĆŃéÆķøåŃéüŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕĮōńĢ¬Ńü«µÖéŃü»Õģźµ£ŁÕć║µØźŃü¬ŃüäŃü«Ńü¦µ«ŗÕ┐ĄŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕģźµ£ŁĶĆģŃü«µĆØĶĆāÕø×ĶĘ»ŃéÆĶ”ŗŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüÅŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃüŗŃéēÕż¦ÕżēÕŗēÕ╝ĘŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé ķææÕ«ÜÕłĆŃĆĆ1ÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆƵŁŻµüÆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ(ÕÅżÕéÖÕēŹŃā╗ńē╣ÕłźķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ […]
ŃüĪŃéćŃüŻŃü©õ╣ģŃĆģŃü½ķÉöŃéÆÕć║ŃüŚŃü”ń£║ŃéüŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕøøµ«Ąń«▒Ńü¦õ║īµ×ÜŃüźŃüżŃĆüĶ©łÕģ½µ×ÜŃĆéŃüŖµ░ŚŃü½ÕģźŃéŖŃééÕżēÕī¢ŃüŚŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦µ£ĆÕłØŃü«µÅāŃüäŃü©Ńü»ÕåģÕ«╣ŃééÕżēŃéÅŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõ╣ģŃĆģŃü½Ķ”ŗŃéŗŃü©ŃéäŃü»ŃéŖĶē»ŃüäŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆéµö╣ŃéüŃü”µ░ŚŃü½ÕģźŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕż®µŁŻķó©µŗĄŃüłŃü«µ¢╣Ńü»ŃĆüµ¤äńø┤ŃüŚŃü½Õć║ŃüŚŃü”ÕÉłĶ©ł […]
ÕģłµŚźŃĆüĶöĄŃüŗŃéēÕć║Ńü”µØźŃü¤Ńü©ŃüäŃüåńĀźń¤│ŃéÆĶ”ŗŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤’╝łķ│┤µ╗Øõ╗śĶ┐æŃüŗŃéēńöŻÕć║Ńü«ńĀźń¤│Ńü¬Ńü«ŃüĀŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖ’╝ēŃĆéõ╗źÕēŹŃééÕ║”ŃĆģµøĖŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüńĀźń¤│Ńü«Õü┤ķØóŃü½µēŗÕ╝ĢŃüŹŃü«ĶĘĪŃüīńó║Ķ¬ŹŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéńÅŠÕ£©Ńü»õĖĖķŗĖŃü¦Õłćµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦ŃĆüÕü┤ķØóŃü½Ńü»õĖĖķŗĖŃü«ĶĘĪŃüīµ¢£ŃéüŃü½µ«ŗŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü« […]
ńĀöŃüÄķüōÕģĘŃü»Õ╣┤ŃĆģÕóŚŃüłŃéŗõĖƵ¢╣Ńü¦ŃüÖŃĆ鵌źÕĖĖŃü«ńö¤µ┤╗ńö©ÕōüŃü¬Ńü®Ńü»µēĆĶ¼éŃĆīµ¢ŁµŹ©ķøóŃĆŹŃü¦Ķē»ŃüäŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõ╗Ģõ║ŗķüōÕģĘŃü½ŃüØŃüåŃü»µĆØŃéÅŃü¬ŃüäŃé┐ŃéżŃāŚŃü¦ŃüÖŃĆéĶĪŻķĪ×Ńü¬Ńü®Ńü»ŌŚŗŌŚŗÕ╣┤ńØĆŃü”ŃüäŃü¬Ńüäńē®Ńü»µŹ©Ńü”ŃüŠŃüŚŃéćŃüåńÜäŃü¬õ║ŗŃéÆķĀæÕ╝ĄŃüŻŃü”ĶĪīŃüäŃüŠŃüÖŃüī’╝łķĀæÕ╝ĄŃüŻŃü”Ńü¦ŃüÖ(^-^;’╝ēŃĆüńĀöŃüÄ […]
µś©Õ╣┤ŃééńäĪÕåĀŃü«ķīåĶ║½ŃüŗŃéēÕøĮÕ«ØŃüŠŃü¦ŃĆüÕżÜµĢ░Ńü«ÕÉŹÕłĆŃéÆńĀöńŻ©ŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»µēŗŃü½ÕÅ¢ŃéŖµŗØĶ”ŗŃüÖŃéŗõ║ŗŃüīÕć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ£¼ÕĮōŃü½µ▓óÕ▒▒µŗØĶ”ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüńē╣Ńü½Õ┐āŃü½µ«ŗŃéŗÕłĆŃü»Ńā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆéÕ»ĖÕ╗ČķĢĘķŖśńøĖÕĘ×Õ╗ŻÕģē’╝łµŁŻÕ╣│Õ╣┤ń┤Ć’╝ēŃĆüÕ£©ķŖśÕģēÕ┐ĀÕż¬ÕłĆ├Ś’╝ÆŃĆüÕ£©ķŖśĶ▓×Õ«Śń¤ŁÕłĆ’╝łÕüĮķŖśŃü«Ńü»ŃüÜ’╝ēŃĆüńäĪķŖśÕĘ”µ¢ć […]
µśÄŃüæŃüŠŃüŚŃü”ŃüŖŃéüŃü¦Ńü©ŃüåŃüöŃü¢ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµ£¼Õ╣┤ŃééŃü®ŃüåŃü×ŃéłŃéŹŃüŚŃüÅŃüŖķĪśŃüäŃüäŃü¤ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕåĘŃüłŃüŠŃüÖŃüŁŃüćŃĆéµ»öÕÅĪÕ▒▒Ńééķø¬Ńü¦ŃüÖŃĆéõ╗ŖÕ╣┤ŃééķĀæÕ╝ĄŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õ╗ŖµŚźŃééńäĪõ║ŗŃü½ńĀöńŻ©Ńü«õ╗Ģõ║ŗŃéÆńĄéŃüłŃéŗõ║ŗŃüīÕć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃü«ÕŠīµŖ╝ÕĮóõĮ£µźŁŃééÕ░æŃüŚķĆ▓ŃéüŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüØŃéīŃééńäĪõ║ŗńĄéõ║åŃĆéŃĆīÕłĆÕēŻńĀöńŻ©Ńü«ŃüŖõ╗Ģõ║ŗŃü¦õĖĆńĢ¬Õ┐āµÄøŃüæŃü”ŃüäŃéŗõ║ŗŃü»õĮĢŃü¦ŃüÖŃüŗ’╝¤ŃĆŹŃü©Ńü«Ķ│¬ÕĢÅŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗõ║ŗŃü»Õ║”ŃĆģŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõ╝ØńĄ▒µ¢ćÕī¢Ńā╗õ╝ØńĄ▒µŖĆĶĪōŃü«ńČÖµē┐ŃĆüµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃéÆÕ«łŃéŗ […]
µ¢░õĮ£ÕłĆŃü«ńĀöŃüÄńø┤ŃüŚŃéÆŃĆéõ╗źÕēŹÕłØŃéüŃü”µŗØĶ”ŗŃüŚŃü¤µÖéŃĆüÕĘ”µ¢ćÕŁŚŃü½ŃüŚŃü”Ńü»ÕÅŹŃéŖŃüīńäĪŃüäŃüŚŃā╗Ńā╗Ńā╗Ńü¬ŃéōŃüĀŃéŹŃüŗŃĆéŃĆéŃü©ŃüäŃüåÕģĘÕÉłŃü½ŃüŗŃü¬ŃéŖĶ┐ĘŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃĆīŃü¬Ńü½ŃüŗÕłåŃüŗŃéēŃü¬ŃüäŃüīķćŹÕłĆŃüĀŃü©µĆØŃüåŃĆŹŃü©ŃüäŃüåĶČŻµŚ©Ńü«ŃüŖńŁöŃüłŃéÆŃüŚŃü¤Ķ©śµåČŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«ŃüŗŃü¬ŃéŖÕŠīŃĆüÕłĆķŹøÕåČŃüĢŃéō’╝łõĮ£ […]
’╝æ’╝æµ£łµö»ķā©ķææÕ«Üõ╝ÜŃĆüķææĶ│×ÕłĆŃü©ŃüŚŃü”ķ¢óŃü«Õģ╝Õ«ŻŃü«ÕłĆŃüīõĖ”Ńü│ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüĪŃéćŃüŻŃü©µÄóŃüŚõ║ŗŃü¦ķüÄÕÄ╗Ńā¢ŃāŁŃé░ŃéÆĶ”ŗŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃéēŃüōŃéōŃü¬ÕåģÕ«╣ŃüīŌåōŃĆéÕÅżŃüäÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐ńĀöŃüÄŃéƵŗØĶ”ŗ | ńÄēńĮ«ńŠÄĶĪōÕłĆÕēŻńĀöńŻ©Õć”’Į£õ║¼ķāĮŃā╗ÕĘ”õ║¼Õī║ (kyoto-katana.com) ŌåæŃüōŃéī […]
õĮĢŃüīÕż¦ÕżēŃüŻŃü”ŃĆüĶ”ŗŃüłŃü½ŃüÅŃüäÕłāµ¢ćŃüīõĖĆńĢ¬Õż¦ÕżēŃü¦ŃüÖŃĆéÕģēŃü«Ķ¦ÆÕ║”ŃéÆŃüéŃéīŃüōŃéīÕżēŃüłŃü¬ŃüīŃéēµÄóŃüŚŃü”ŃééŃĆüń£ĀŃüÅŃü”Ķ”ŗŃüłŃü¬ŃüäÕłĆŃü»ńĄÉµ¦ŗŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃü¬Ńü«Ńü¦µŖ╝ÕĮóŃéƵÅÅŃüÅķÜøŃü»ŃĆüńĀöŃüÄŃü¦ĶĄżŃüÅÕ½īŃéēŃüŚŃüÅń½ŗŃü”ŃéēŃéīŃü¤ÕłāŃĆüŃééŃüŚŃüÅŃü»ÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐ńĀöŃüÄŃü«ÕłĆŃü«µ¢╣ŃüīµźĮŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆéÕĘ«ŃüŚĶŠ╝Ńü┐Ńü¦ń£¤ […]
ŃéäŃü»ŃéŖµ░ŚµīüŃüĪµé¬ŃüäŃü«Ńü¦ÕåŹÕ║”ÕłåķĪ×ŃüŚŃĆüńŁÆŃü½ńĢ¬ÕÅĘŃéÆõ╗śŃüæÕģźŃéīµø┐ŃüłŃéÆŃĆéõ╗ŖŃüŠŃü¦ńŁÆŃü«µĢ░ŃüīńäĪķ¦äŃü½ÕżÜŃüŗŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüŗŃü¬ŃéŖµĖøŃéēŃüÖõ║ŗŃüīÕć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ÕéÖÕēŹŃĆĆ’╝ö’╝öÕ▒▒Õ¤ÄŃĆĆ’╝Æ’╝¢ńÅŠõ╗ŻŃĆĆ’╝æ’╝¢ńŠÄµ┐āŃĆĆ’╝æ’╝ĢÕż¦ÕÆīŃĆĆ’╝æ’╝ōń┤Ćõ╝ŖŃĆĆŃĆĆ’╝ÖĶéźÕēŹŃĆĆŃĆĆ’╝ÖńøĖµ©ĪŃĆĆŃĆĆ’╝śÕż¦ÕØéŃĆĆŃĆĆ’╝śµŁ”ĶöĄ […]
Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü»ŃĆüÕ¤║µ£¼ńÜäŃü½µÄĪŃéŖŃü¤ŃüäŃü©µĆØŃüŻŃü¤ńē®ŃéƵÄĪŃéŗŃé╣Ńé┐Ńā│Ńé╣Ńü¦µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗ŖµēŗÕģāŃü½Ńü®ŃéōŃü¬ńē®ŃüīŃüéŃéŗŃü«ŃüŗŃĆüŃüØŃüåŃüäŃüłŃü░ŃüØŃü«õ║ŗŃü»Õģ©ŃüÅĶĆāŃüłŃü”µØźŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµÄĪµŗōķĀåŃü½ŃüŠŃü©ŃéüŃü”ńŁÆŃü½µöŠŃéŖĶŠ╝ŃéōŃü¦ŃüäŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü»õĮĢŃüŗŃü«µÖéŃü½µÄóŃüÖŃü«ŃüīÕż¦ÕżēŃü¦ŃüÖŃĆéÕĘ«ŃüŚõĖŖŃüÆŃéŗõ║ŗ […]
Õ░æŃüŚÕēŹŃü½µÅÅŃüŗŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü¤ķÄīÕĆēÕłØµ£¤ŃüŗŃü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗÕż¬ÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆÕ╝ĢŃüŻÕ╝ĄŃéŖÕć║ŃüŚŃĆüĶē▓ŃĆģńó║Ķ¬ŹŃĆéÕłØŃéüŃü”µŗØĶ”ŗŃüŚŃü¤µÖéŃüŗŃéēÕżēŃéÅŃéēŃüÜŃéäŃü»ŃéŖÕćäŃüäÕż¬ÕłĆŃü¦ŃĆüŃüōŃéīń│╗Ńü«µ£Ćķ½śÕ│░Ńü«õĖĆŃüżŃüĀŃü©µĆØŃüåŃĆéÕī║Ńü«ĶĖÅŃéōÕ╝ĄŃéŖŃü«ńŠÄŃüŚŃüĢŃüīÕ░ŗÕĖĖŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃĆéńĀöŃüÉń½ŗÕĀ┤Ńü¦ĶĆāŃüłŃéŗŃü©ŃĆüńä╝ŃüŹĶÉĮ […]
ÕłżĶĆģŃü«µÖéŃüīÕ║”ŃĆģŃü¦ŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüÕģźµ£ŁÕć║µØźŃéŗŃü«Ńü»’╝Æ’╝É’╝Æ’╝ÉÕ╣┤Ńü«’╝Ƶ£łõ╗źµØźŃü¦ŃüÖŃĆéŃüäŃéäŃééŃüåµ£¼ÕĮōŃü½µźĮŃüŚŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃüŁŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃüÉŃüŻŃü¤ŃéŖń¢▓ŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝öÕÅĘŃĆĆÕłĆŃĆĆÕÅŹŃéŖŃüīÕ╝ĘŃüäŃĆéĶŻÅŃüīµ©ŗõĖŁŃü½µóĄÕŁŚŃü«µĄ«ÕĮ½Ńü¬Ńü®ŃĆéõ┐ĪÕøĮŃüŗŃĆé’╝æÕÅĘŃĆĆń¤ŁÕłĆŃĆĆÕåģÕÅŹŃéŖŃüĀŃüīÕłāŃü«ŃāÉŃā®Ńā│Ńé╣ŃüŗŃéē […]
ŃĆīµØ▒µśĀõ║¼ķāĮµÆ«ÕĮ▒µēĆŃĆŹķ¢æµĢŻŃü«õ╗Ŗ – Yahoo!ŃāŗŃāźŃā╝Ńé╣ŃüĪŃéćŃüŻŃü©Õ»éŃüŚŃüäŃāŗŃāźŃā╝Ńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆéķüÄÕÄ╗Ńü½µÖéõ╗ŻÕŖ浜Āńö╗ńŁēŃü«ŃüŖµēŗõ╝ØŃüäŃéÆŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃĆüµØŠń½╣ŃéäµØ▒µśĀŃü«µÆ«ÕĮ▒µēĆŃü½Ńü»õĮĢÕ║”ŃééĶĪīŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵜ĀÕāÅõĮ£ÕōüŃü»Ńü╗ŃéōŃü«Õ░æŃüŚŃü«ŃéĘŃā╝Ńā│Ńü¦ŃééõĖĆÕ║”ķ¢óŃéÅŃéŗŃü©’╝ö […]
ÕģłµŚźŃĆü’╝æ’╝ɵ£łŃü«µö»ķā©õŠŗõ╝ÜŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵜©Õ╣┤’╝æ’╝ɵ£łõ╗źµØźŃĆüŃüĪŃéćŃüåŃü®’╝æÕ╣┤µī»ŃéŖŃü«ķ¢ŗÕé¼Ńü¦ŃüÖŃĆé ķææÕ«ÜÕłĆ ’╝æÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕŖ®ķĢĘ’╝łķĢĘĶł╣’╝ēŃĆĆŃĆĆķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ÆÕÅĘŃĆĆĶäćÕĘ«ŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆƵŁ”ÕĘ×õĖŗÕĤõĮÅńģ¦ķ插╝ōÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆńäĪķŖś’╝łń£¤Õ«ł’╝ēŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝öÕÅĘŃĆĆĶäćÕĘ« […]
ÕģłµŚźŃü«µŖ╝ÕĮóŃüīõĮĢŃüŗŃéƵĆØŃüäÕć║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕ░æŃüŚŃüĀŃüæķĀŁŃü«ķÜģŃü½ŃüéŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüŠŃüĢŃüŗŃüéŃü«ÕÄ│ŃüŚŃü䵌źń©ŗŃü«õĖŁŃĆüµÅÅŃüäŃü”ŃüäŃéŗĶ©│ŃüīŃü¬ŃüäŃüŚŃā╗Ńā╗Ńā╗Ńü©ŃĆüµĆØŃüäŃü«õĖŁŃüŗŃéēķÖżÕż¢ŃüŚŃü”ŃüäŃü”ŃĆéŃüéŃüŠŃéŖŃü½µÖéķ¢ōŃüīńäĪŃüäõĖŁŃü¦Õż£õĖŁŃü½ńäĪŃü«ńŖȵģŗŃü¦µÅÅŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ńē®ŃüĀŃüæŃüīµ«ŗŃéŖĶ©śµåČŃü½Ńü»Ńü¬Ńüŗ […]
ń¦üŃü»ŌĆØķææÕ«ÜĶć│õĖŖõĖ╗ńŠ®ĶĆģŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŌĆØŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃéÆõĖĆÕ┐£ÕģłŃü½µøĖŃüäŃü”ŃüŖŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«õĖŖŃü¦ŃĆüÕģźµ£ŁķææÕ«ÜŃü»µźĮŃüŚŃüÅŃü”Õż¦ÕźĮŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃüŠŃüÜŃüŠŃüÜÕĮōŃü¤Ńéŗõ║ŗŃééÕżÜŃüäµ¢╣ŃüĀŃü©Ńü»µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃüīÕż¦Õż¢ŃüŚŃééķĀ╗ń╣üŃü¦ŃĆüńĄÉÕ▒ĆÕĮōŃü¤ŃéŗŃüŗŃéēµźĮŃüŚŃüäĶ©│Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüØŃéŖŃéāŃüŠŃüüÕĮōŃü¤ŃéŗŃü©Õ¼ēŃüŚ […]
µö»ķā©õŠŗõ╝ÜŃü«µ║¢ÕéÖŃü¦ŃĆüÕģēÕ┐ĀķĢĘÕģēµÖ»ÕģēŃü¬Ńü®Ńü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü¦ńó║Ķ¬ŹŃüŚŃü¤Ńüäõ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃĆüµŖ╝ÕĮóŃéÆÕģźŃéīŃü”ŃüäŃéŗńŁÆŃüŗŃéēĶē▓ŃĆģŃü©Õ╝ĢŃüŻÕ╝ĄŃéŖÕć║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü”Ńā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆé ķææĶ│×õ╝ÜŃü¦Ķ”ŗŃü¤ÕłĆŃü»µÖéķ¢ōŃüīńĄīŃüżŃü©Õ┐śŃéīŃü”ŃüŚŃüŠŃüåõ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖ’╝łÕ«īÕģ©Ńü½Õ┐śŃéīŃéŗŃéÅŃüæŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüŃü®ŃüåŃüŚŃü”Ńéé […]
ÕłČõĮ£ķĆöõĖŁŃüĀŃüŻŃü¤ķÄīÕĆēµ£½µ£¤Õ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆõ╗ŖÕż£Õ«īµłÉŃüĢŃüøŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃéäŃü»ŃéŖńø┤ÕłāŃü»µŚ®Ńüä’╝łµÖéķ¢ōń¤ŁńĖ«Ńü«Ńü¤ŃéüÕó©Ńü»õĖĆÕłćõĮ┐ńö©ŃüøŃüÜ’╝ēŃĆ鵜ĀŃéŖŃüīÕģāŃüŗŃéēÕģłŃüŠŃü¦ķĆöÕłćŃéīŃéŗõ║ŗńäĪŃüÅńČÜŃüŹŃĆüµśĀŃéŖµÅÅÕåÖŃü«µ¢╣ŃüīµÖéķ¢ōŃüīµÄøŃüŗŃüŻŃü¤Ńüŗ’╝łŃüōŃéīŃüĀŃüæķĆöÕłćŃéīŃüÜŃü╗Ńü╝ÕØćõĖĆŃü½ńČÜŃüŵśĀŃéŖŃü» […]
ńĀöńŻ©Ńü½Õć║Õ╝ĄŃü½Ńü©ķØ×ÕĖĖŃü½Õ┐ÖŃüŚŃüÅŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüńĀöńŻ©Ńü¦õĮōŃüīÕŗĢŃüŗŃü¬ŃüÅŃü¬ŃüŻŃü¤ÕŠīŃü»ŃĆüÕć║µØźŃéŗķÖÉŃéŖµŖ╝ÕĮóõĮ£µźŁŃééńČÜŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµ£ĆĶ┐æŃü¦Ńü»ķÄīÕĆēÕēŹµ£¤ńäĪķŖśÕż¬ÕłĆÕģ©Ķ║½ŃĆüÕ╣│Õ«ēµ£½’Į×ķÄīÕĆēÕēŹµ£¤ńäĪķŖśÕż¬ÕłĆÕģ©Ķ║½ŃĆüķÄīÕĆēµ£½µ£¤ńäĪķŖśÕż¬ÕłĆÕģ©Ķ║½ŃĆüńÅŠõ╗ŻÕż¬ÕłĆÕģ©Ķ║½ŃĆüÕ┐£µ░ĖÕ£©ķŖśÕ»Ė […]
µś©µŚźŃüŗŃéēÕģ¼ķ¢ŗŃü«µśĀńö╗ŃĆīńćāŃüłŃéłÕēŻŃĆŹŃĆéÕŖćõĖŁŃĆüÕē»ķĢĘÕ£¤µ¢╣ŃüīµīüŃüżÕłĆŃü»ŃüōŃü«ÕÆīµ│ēÕ«łÕģ╝Õ«ÜŃü¦ŃüÖŃĆé13ac85424406b61f9a9cd1e26f9b918b.jpg (5727├Ś986) (kyoto-katana.com)õ╝ܵ┤ź11õ╗ŻŃü¦ […]
µĢ░µŚźķĢĘĶł╣ŃĆéŃüäŃüżŃééÕż¦ÕżēŃüŖõĖ¢Ķ®▒Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗĶüʵ¢╣ŃüĢŃéōķüöŃéäÕŁ”ĶŖĖÕōĪŃüĢŃéōķüöŃü½ŃüŖõ╝ÜŃüäÕć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŌĆØÕéÖÕēŹŃüŖŃüĢŃüĄŃüŁÕłĆÕēŻŃü«ķćīŌĆØŃü»Õż¦ÕźĮŃüŹŃü¬ÕĀ┤µēĆŃü¦ŃüÖŃĆé ńē╣ķ揵īćÕ«ÜÕ▒ĢŃĆéŃü¤ŃüŠŃü¤ŃüŠõĖĆõ║║Ńü¦ŃéåŃüŻŃüÅŃéŖķææĶ│×Õć║µØźŃéŗĶ▓┤ķćŹŃü¬µÖéķ¢ōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé ńĀöŃüÄÕĀ┤Ńü½Ńü”õ║½õ┐ØÕÉŹńē®ÕɽŃéĆĶ▓┤ķćŹŃü¬ […]
õ╗ŖµŚźŃééõĮōŃüīÕŗĢŃüŗŃü¬ŃüÅŃü¬ŃéŗŃüŠŃü¦ńĀöŃüÄŃéÆķĀæÕ╝ĄŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃā¼ŃāÖŃāāŃé½’╝ł’╝æ’╝Ö’╝ś’╝¢Õ╣┤µŚ®ń©▓ńö░GIG’╝ēŃü┐Ńü”Õ»ØŃüŠŃüÖŃĆéŃĆé youtubeŃüōŃü«ŃéóŃā│Ńé│Ńā╝Ńā½µø▓ŃüŚŃüŗĶ▓╝ŃéīŃüÜŃĆéŃĆéµ£¼ÕĮōŃü»Õģ©’╝¢µø▓Ķü×ŃüÅ’╝łŃü┐Ńéŗ’╝ēŃü©ŃéłŃéŖÕģāµ░ŚŃü½Ńü¬ŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ńä╝ŃüäŃü¤ķēäĶéīŃéÆÕģ©ķā©µōéŃéŗŃü«Ńü»µÖéķ¢ōŃüīµÄøŃüŗŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõĮĢµŚźŃééŃüŗŃüæŃü”Õģ©ķā©µōéŃüŻŃü¤ŃüīÕģ©ńäČŃāĆŃāĪµŗŁŃüäŃüĀŃüŻŃü¤Ńā╗Ńā╗Ńā╗Ńü¬ŃéōŃü”õ║ŗŃééµÖ«ķĆÜŃü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦ŃĆüŃüŠŃüÜŃü»Õ░æķćÅŃéÆŃĆéµ£ĆÕłØŃü»Õż¦ŃüŹńø«Ńü«õ╣│ķēóŃü¦ŃĆéµōéŃéŖµŻÆŃééÕż¦ŃüŹŃüÅķćŹŃüäŃĆéõĖƵŚźõĖŁµ¢░õĮ£ÕłĆŃü«õĖŗÕ£░ŃéÆŃéäŃüŻŃü¤ÕŠīŃü«ĶģĢŃü½Ńü»Ńé╣Ńā×ŃāøŃü« […]
ńä╝ŃüŹńĄéŃéÅŃéŖŃĆéŃé╣Ńā¬Ńü½ÕģźŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ńŖȵģŗŃü«Ķ”ŗŃü¤ńø«Ńü»ńä╝ŃüŹÕēŹŃü©ÕżēŃéÅŃéēŃü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃĆĆÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆķÄ«ÕøĮńź×ÕÖ©õ╝»ĶĆåÕøĮÕż¦µ¤┐Õ««µ£¼ĶāĮńÖ╗Õ«łĶÅģÕĤµ£ØĶćŻÕīģÕēćŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆƵśÄµ▓╗ÕģāÕ╣┤ÕŹüµ£łÕģ½µŚźÕźēń©▓ĶŹĘńżŠń┤Źń©▓ĶŹĘńź×Õ▒▒ÕēŻń¤│ńÖŠµŚźÕÅéń▒ĀŃéĘŃāåĶ¼╣ķŹøõ╣ŗŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ’╝łõ╝ÅĶ”ŗń©▓ĶŹĘÕż¦ńżŠµēĆĶöĄ’╝ē ŃüōŃü«ÕłĆŃü«ķŖśŃü½ŃüéŃéŗÕ««µ£¼ÕīģÕēćŃü«ń©▓ĶŹĘ […]
ŃüŠŃü¤µ»ÄµÖ®õĮ£ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüäŃüŻŃü▒ŃüäõĮ£ŃéēŃéōŃü©ÕłåŃüŗŃéēŃéōŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéķĢĘÕ╣┤õĮ┐ŃüŻŃü¤ÕēŹŃü«ŃāŚŃāüŃüīõĖĆńĢ¬ŃüĀŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõ╗ŖÕ║”Ńü«ŃāŚŃāüŃééńĄÉµ¦ŗµ░ŚŃü½ÕģźŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃéōŃü¬ŃééŃéōŃü¦ŃüÖŃĆé
Õż®ńäČńĀźŃü»õĖƵ£¤õĖĆõ╝ÜŃü¦ŃĆüÕć║õ╝ÜŃüŻŃü¤ŃüØŃü«µÖéÕģźµēŗŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░µ¼ĪŃü»ńäĪŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚÕ«¤Ńü»õ║║ķĆĀńĀźŃü¦ŃééŃüØŃü«ÕéŠÕÉæŃü»Õ╝ĘŃüŗŃüŻŃü¤ŃéŖŃééŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéµĢ░ŃāĄµ£łÕŹśõĮŹŃü¬Ńü®ń¤ŁŃüäŃé╣ŃāæŃā│Ńü«Ķ®▒Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīõ║║ķĆĀńĀźŃééķĢĘÕ╣┤õĮ┐ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃĆüÕĤµ¢ÖŃüīÕżēŃéÅŃüŻŃü¤ŃéŖŃĆüĶŻĮķĆĀõĖŁµŁóŃü½Ńü¬ŃüŻŃü¤ […]
õ╝ÜŃĆƵ£¤:õ╗żÕÆī3Õ╣┤9µ£ł18µŚź’╝łÕ£¤’╝ē’Į×õ╗żÕÆī3Õ╣┤11µ£ł7µŚź’╝łµŚź’╝ēõ╝ÜŃĆĆÕĀ┤’╝ܵ׌ÕĤńŠÄĶĪōķż©ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆÆ700-0823 Õ▓ĪÕ▒▒ÕĖéÕīŚÕī║õĖĖŃü«Õåģ2-7-15ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆTEL086-223-1733ŃĆĆFAX086-226-3089ķ¢ŗķż©µÖéķ¢ō’╝ÜÕŹłÕēŹ1 […]
ŃéäŃüŻŃü©Ķ▓ĘŃüłŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕÅ¢ŃüŻµēŗŃüīńäĪŃüÅŃü”ŃüĪŃéćŃüŻŃü©õĖŹõŠ┐ŃĆéÕåŹķ¢ŗŃĆé
Ķ╗ŹÕłĆŃéÆĶ▓ĘŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗źÕēŹŃüŗŃéēńÖĮķלŃü½ÕģźŃéīŃüܵŗĄŃü½ÕģźŃüŻŃü¤ńŖȵģŗŃü«ÕłĆŃüīÕźĮŃüŹŃüĀŃü©Ķ©ĆŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕÅżŃüäµŗĄŃü¦Ńééµ¢░ŃüŚŃüäµŗĄŃü¦ŃééŃĆüńÅŠõ╗ŻõĮ£Ńü«µŗĄŃü¦ŃééŃüØŃéīŃü»ÕżēŃéÅŃéēŃüÜŃü¦ŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃüōŃü«ŃéĄŃā╝ŃāÖŃā½Ńü¦ŃééŃüØŃüåŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéŃü¤ŃüĀŃĆüÕłĆĶ║½ŃüīķīåŃü│Ńü”ŃüŠŃüÖ(’Į░’Į░;)ŃĆĆŃüōŃü«ÕģłµÖéķ¢ō […]
ńÅŠÕ£©ķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü«ŃĆīńÖŠķī¼ń▓ŠķÉĄ ÕłĆÕīĀ µ£łÕ▒▒Ķ▓×Õł®Õ▒ĢŃĆŹŃü½ŃüŖõ╝║ŃüäĶć┤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ń¦üŃü»ńĀöÕĖ½Ńü½Ńü»ÕÅżÕÉŹÕłĆŃü«Õ▒ĢĶ”¦õ╝ÜŃéłŃéŖŃééŃĆüńÅŠõ╗ŻÕłĆÕīĀŃüĢŃéōŃü«ÕĆŗÕ▒ĢŃü«µ¢╣ŃüīµĢ░µ«ĄÕŗēÕ╝ĘŃü½Ńü¬ŃéŗŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕłĆŃü«õĖ¢ńĢīŃü½ķÖÉŃéēŃüÜŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕĆŗÕ▒ĢŃü»Ķ¬░Ńü¦ŃééÕć║µØźŃéŗŃééŃü«Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéÕ«ēÕ«ÜŃüŚ […]
ŃĆīµ£ĆÕŠīŃü«ŌŚŗŌŚŗ ’Į×µŚźµ£¼Ńü«Ńā¼ŃāāŃāēŃāćŃā╝Ńé┐’Į×ŃĆŹõ╗ŖÕø×Ńü»Õż®ńäČńĀźń¤│ŃüīÕÅ¢ŃéŖõĖŖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé ĶŹēÕĮģÕēøÕÅĖõ╝ÜŃĆĆNHK BSŃāŚŃā¼Ńā¤ŃéóŃāĀŃĆīµ£ĆÕŠīŃü«ŌŚŗŌŚŗŃĆŹń¼¼õ║īÕ╝ŠµöŠķĆüµ▒║Õ«Ü’╝ü | µ¢░ŃüŚŃüäÕ£░Õø│ (atarashiichizu.com)ĶŹēÕĮģ ÕēøŃüīĶ”ŗŃüżŃéüŃéŗŃĆüŃĆīµŚź […]
HPõĖŖķā©Ńü«ŃāĪŃāŗŃāźŃā╝Ńü½ŃĆīÕż®ńäČńĀźń¤│µ»öĶ╝āŃĆŹŃéÆĶ┐ĮÕŖĀŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃā¢ŃāŁŃé░Ńü¦ĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Õż®ńäČńĀźń¤│Ńü«õĮ┐ńö©µ»öĶ╝āŃüĖŃü«Ńā¬Ńā│Ńé»ŃéÆĶ▓╝ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŖõ╗Ģõ║ŗŃü«Õ«ēÕģ©ńźłķĪśŃĆéĶ▒¬ķø©Ńü«ń▓¤ńö░ńź×ńżŠ’Į×ķØÆĶō«ķÖóŃĆé µśöŃĆüń▓¤ńö░ńź×ńżŠŃü«ŃāōŃéóŃé¼Ńā╝ŃāćŃā│Ńü¦Õ£¤ńĀéķÖŹŃéŖŃü©Ķ┐ģķøĘŃü«õĖŁŃĆüÕż¦µ©╣Ńü«ÕģāŃü¦ķø©Õ«┐ŃéŖŃéÆŃüŚŃü¤õ║ŗŃéƵĆØŃüäÕć║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéķĢĘńöĘŃü»ŃüŠŃüĀŃāÖŃāōŃā╝Ńé½Ńā╝Ńü½õ╣ŚŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüŗŃĆéŃĆéµ»öÕÅĪÕ▒▒ŃĆüÕÉēńö░Õ▒▒ŃĆüķŖĆķ¢ŻÕ»║ŃĆüķćæµłÆÕģēµśÄÕ»║ŃĆüÕŹŚń”ģÕ»║µ¢╣ […]
ķāĮÕÉłŃü¦ńĀöŃüÄÕÅ░ŃéÆõ╣ģŃĆģŃü«ķģŹńĮ«Ńü½ŃĆéŃüōŃéīĶÉĮŃüĪńØĆŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü¦ĶĪīŃüōŃüåŃüŗŃĆé
ķø╗µ░ŚńéēŃüīÕŻŖŃéīŃü¤ŃĆé’╝æ’╝É’╝É’╝ɵÖéķ¢ōõ╗źõĖŖń©ŗÕ║”Ńü»õĮ┐ŃüŻŃü”ŃüŹŃü¤Ńü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃéīŃüÅŃéēŃüäŃü¦ÕŻŖŃéīŃéŗŃéōŃü¦ŃüÖŃüŗŃüŁŃüćŃĆéŃĆéŃāÆŃāźŃā╝Ńé║Ńü»ÕłćŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃüŚŃĆéÕłåĶ¦ŻŃüŚŃü”Ńü┐ŃéłŃüåŃüŗŃü©µĆØŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüń┤Āõ║║ŃüīÕżēŃü½ŃüĢŃéÅŃüŻŃü”õ╗«Ńü½ńø┤ŃüŻŃü¤Ńü©ŃüŚŃü”ŃééŃĆüÕ«ēÕģ©ķØóŃü¦Õ┐āķģŹŃü¦ŃüÖŃüŚµ¢░ŃüŚŃüäńē® […]
õ╝ÜÕĀ┤’╝Üõ║¼ķāĮķ½ÖÕ│ČÕ▒ŗ6ķÜÄńŠÄĶĪōńö╗Õ╗ŖŌĆ╗µ£ĆńĄéµŚźŃü»ÕŹłÕŠī4µÖéķ¢ēÕĀ┤ŌĆ╗õ║¼ķāĮķ½ÖÕ│ČÕ▒ŗŃü«Õ¢ČµźŁµÖéķ¢ōŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»HPŃéÆŃüöńó║Ķ¬ŹõĖŗŃüĢŃüäŃĆé µ£łÕ▒▒ķŹøÕåČŃü»ķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻÕłØµ£¤Ńü«ķ¼╝ńÄŗõĖĖŃéÆńź¢Ńü©ŃüŚŃĆüÕźźÕĘ×µ£łÕ▒▒Ńü«ķ║ōŃü¦ķÄīÕĆēŃĆüÕ«żńö║µ£¤Ńü½µĀäŃüłŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ£łÕ▒▒ķŹøÕåČŃü«µ£ĆÕż¦Ńü«ńē╣ÕŠ┤Ńü»ŃĆüÕłĆĶ║½Õģ©õĮōŃü½µ│ó […]
Õ▓Éķś£ń£īÕŹÜńē®ķż©Ńü½Ńü”ķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü¦ŃüÖ’╝üÕ▓Éķś£ń£īÕŹÜńē®ķż©HP 2021/07/23(ķćæ)’Į× 2021/09/26(µŚź) ŃĆƵ▒¤µłĖõĖŁµ£¤ŃĆüĶ¢®µæ®ĶŚ®Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Õ«¤µ¢ĮŃüĢŃéīŃü¤µ£©µøĮõĖēÕĘØŃü«Õ«ØµÜ”µ▓╗µ░┤ÕĘźõ║ŗŃüīÕźæµ®¤Ńü©Ńü¬ŃéŖŃĆüµśŁÕÆī46Õ╣┤Ńü½ķ╣┐ÕģÉÕ│Čń£īŃü©Õ▓Éķś£ń£īŃü©Ńü« […]
ÕģłµŚźŃü«ŃüōŃéīŃü»ńäĪõ║ŗĶē»ŃüäµŗŁŃüäŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃéäŃü»ŃéŖńä╝ŃüŹµ¢╣ŃüīĶéØĶ”üŃü©µö╣ŃéüŃü”ńó║Ķ¬ŹŃĆé ŃüŚŃüŗŃüŚÕĤµ¢ÖŃü½ŃéłŃéŗķüĢŃüäŃééńó║Ķ¬ŹŃüŚŃü”ŃüŖŃüŹŃü¤ŃüÅŃĆüõĖĆńĢ¬ÕźĮŃüŹŃü¬µŗŁŃüäÕĤµ¢ÖŃü«ķēäĶéīŃéÆõ╗ŖõĖĆÕ║”ķĀ鵳┤ŃüÖŃéŗõ║ŗŃüīÕć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃü©ŃéŖŃüéŃüłŃüÜńä╝ŃüŹÕēŹŃééµŗŁŃüäŃü½ŃüŚŃü”Ķ®”ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéķ╗ÆŃüäµŗŁŃüäŃĆé […]
õ╣ģŃĆģŃü½Ķ”ŗŃü¤ŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüŚŃü”ŃĆé’╝Æ’╝É’╝ŚÕłåŃĆüńĄéŃéÅŃéŗŃü«ŃüīÕ»éŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüĢŃü”ŃüĢŃü”ŃĆüŃā¢ŃāŁŃé░Ńü«ÕåģÕ«╣Ńüīµ░ŚŃü½Ńü¬ŃéŖŃüĪŃéćŃüŻŃü©ńó║Ķ¬ŹŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕ│Čńö░ÕŗśÕģĄĶĪøŃü«ń¤ŁÕłĆŃĆéWikipediaŃü¦Ńü»Õ╣│ķĆĀŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃéäŃü»ŃéŖÕåĀĶÉĮķĆĀŃü¦ŃüÖŃüŁŃĆéŃü¦ŃĆüŃü®ŃüåŃüŚŃü”ŃééÕÅżÕłĆŃü½Ķ”ŗŃüłŃü¬ŃüÅ […]
ÕģłµŚźŃü«µŗŁŃüäŃü«Ńā¢ŃāŁŃé░Ńü«Ńü©ŃüŹķüÄÕÄ╗Ńü«Ńā¬Ńā│Ńé»ŃéÆĶ▓╝ŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ŃéēŃĆīõĖāõ║║Ńü«õŠŹŃĆŹŃü«Õ”äµā│ŃüīÕć║Ńü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶ¬ŁŃéōŃü¦Ńü┐ŃéŗŃü©µźĮŃüŚŃüŗŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ÕåŹÕ║”ŃĆéõĖāõ║║Ńü«õŠŹ | ńÄēńĮ«ńŠÄĶĪōÕłĆÕēŻńĀöńŻ©Õć”’Į£õ║¼ķāĮŃā╗ÕĘ”õ║¼Õī║ (kyoto-katana.com)ÕŗصēŗŃü¬Õ”äµā│Ńü¦ŃüÖŃĆéŃāĢŃéĪ […]
No.130ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ8/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ3/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.131ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ4/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.132ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ3/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ4/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ× […]
ńĀźń¤│Ńü«Ķ®▒ŃĆüŃééŃüåŃüäŃüäÕŖĀµĖøķŻĮŃüŹŃü¤ŃéÅ’╝üŃü©ŃüäŃéÅŃéīŃüŠŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüŃüĪŃéćŃüŻŃü©ÕłźŃü«Ķ®▒ķĪīŃü¦ŃééŃĆéŃü©ŃüäŃüŻŃü”ŃééŃüōŃéōŃü¬ŃüŖĶ®▒Ńü½Ńü¬ŃüŻŃüĪŃéāŃüåŃéōŃü¦ŃüÖŃüīŃā╗Ńā╗Ńā╗(^-^; õĮ┐ńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ŃüŖµ░ŚŃü½ÕģźŃéŖŃü«µŗŁŃüäŃéÆõĮ┐ŃüäÕłćŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃĆüŃüōŃü«õĖĆŃāĄµ£łŃü╗Ńü®ŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü¬µŗŁŃüäŃéÆõĮ£ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚ […]
’╝Æ’╝Éõ╗ŻŃü«ķĀāŃĆüõ║īÕŹüµĢ░µ£¼ÕÉīµÖéŃü½Ķ│╝ÕģźŃüŚŃü¤ńē®Ńü¦ŃĆüńøĖÕ▓®Ķ░ĘŃüĀŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆé’╝łĶÅ¢ĶÆ▓ŃééµĘĘŃü¢ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃü«ŃüŗŃééń¤źŃéīŃüŠŃüøŃéō’╝ēµ╗ŗĶ│Ćń£īķ½śÕ│ČÕĖéŃü¦Ńü»ŃĆüńøĖÕ▓®Ķ░ĘŃü©Õ”ÖĶ”ÜĶ░ĘŃü¦ńĀźń¤│ŃéÆńöŻÕć║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤’╝łõĖĪÕ▒▒Ńü©Ńé鵌óŃü½ķ¢ēÕ▒▒’╝ēŃĆéĶ│╝ÕģźÕĮōµÖéŃĆüńøĖÕ▓®Ķ░ĘŃü«µÄĪµÄśŃéÆŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¤µ£©µØæµĮöŃüĢŃéō […]
No.114ÕÄÜŃüĢ34’ĮŹ’ĮŹńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝¢/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝Ģ/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ķØóŃüīÕ╝ĘŃüÅõ╗śŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü¤ŃéüÕ░æŃĆģńĪ¼Ńüŵä¤ŃüśŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕ«īÕģ©ŃāĢŃā®ŃāāŃāłŃü¬ŃéēŃü░ŃééŃüåÕ░æŃüŚµ¤öŃéēŃüŗŃüäõĮ┐ŃüäÕ┐āÕ£░Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé’╝łńĀöŃüĵ▒üŃüīÕłåķøóŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü« […]
No.112ÕÄÜŃüĢ’╝Ģ’Įā’ĮŹŃĆéĶĪ©ĶŻÅŃü©ŃééķØóŃüīõ╗śŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕü┤ķØóŃéÆĶ”ŗŃéŗŃü©ĶĪ©ĶŻÅŃü¦ÕżÜÕ░æĶ│¬ŃüīķüĢŃü嵦śŃü¦ŃüÖŃĆé ĶĪ©ķØóńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ4/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 µÄøŃüŗŃéŖŃüīõ╗ŖõĖĆŃü¬Ńü«Ńü¦ĶŻÅŃéÆŃĆéŃĆé ĶŻÅķØóńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝¢/10ńĀöńŻ©ÕŖø […]
No.110ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ5/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.111ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ5/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.110ŃĆĆÕÄÜŃüĢ’╝ĢŃÄØõ╗źõĖŖŃĆéõĖĆń×¼Õż¦Õ╣│ŃüśŃéāŃü¬ŃüÅĶ”ŗŃüłŃüŠŃüÖŃüīÕż¦Õ╣│Ńü¦ […]
No.108ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ5/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ1/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.109ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ5/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ7/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.108Ńü»ńĄÉµ¦ŗõ╗źÕēŹŃüŗŃéēµīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõĮ┐ŃüŻŃü¤Ķ©śµåČŃüīŃüéŃéŖŃüŠ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝ō/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝¢/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 µĢ░ÕŹüÕ╣┤ÕēŹŃü½ńöŻÕć║ŃüĢŃéīŃü¤ĶÅ¢ĶÆ▓ŃĆéÕż¦Õ×ŗŃü«ńĀźń¤│Ńü¦ÕÄÜŃü┐ŃééĶ│╝ÕģźµÖéŃü»’╝Ģ’╝ō’ĮŹ’ĮŹŃüéŃéŖŃĆüÕĀéŃĆģŃü«õĮćŃüŠŃüäŃĆéŃüŖŃüØŃéēŃüÅ’╝ĢŃĆü6Õ╣┤ÕēŹŃü½Ķ│╝ÕģźŃüŚŃĆüŃüŚŃüŻŃüŗŃéŖŃüŚŃü¤ńä╝ŃüŹŃü«ÕłĆŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗŃāĪŃéżŃā│Ńü«ńĀźń¤│Ńü©ŃüŚ […]
No.105ŃüōŃü«µēŗŃü«Ńé½Ńā®Ńé╣Ńü«ńĀźń¤│Ńü»ŃĆüŃüéŃéŗŃü©Õ”ÖŃü½Õ¼ēŃüŚŃüÅŃü¬Ńéŗń¤│Ńü¦ŃüÖŃĆéÕ░æŃüŚńŗŁŃüäÕ╣ģŃü¦ŃüÖŃüīńĀöŃüÄŃéäŃüÖŃüÅŃĆüµÖ«µ«ĄõĮ┐ŃüäŃü«Õ░ÅÕłĆŃéÆńĀöŃüÉŃü«Ńü½õĮ┐ńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃü®Ńü«Õ▒▒ńöŻŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŌĆ”ŃĆéŃüŖŃüØŃéēŃüŵóģŃé▒ńĢæÕæ©ĶŠ║Ńü«Õ▒▒Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéŃüōŃüåŃüäŃüåńĀźń¤│Ńü½ÕłĆŃéÆÕĮōŃü”Ńü¤ńĀöµ▒üŃéÆĶ”ŗŃéŗ […]
No.103ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝ö/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ5/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.104ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝ö/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝ö/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.103Ńü»ķØ×ÕĖĖŃü½Ķē»ŃüäÕłāÕ╝ĢŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéNo.104Ńü»ÕłāÕ╝ĢŃüŹŃü©ŃüŚ […]
No.101ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝ö/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.102ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ3/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 Ńü®ŃüĪŃéēŃééĶ”ŗŃü¤ńø«Ńü»ńĪ¼ŃüØŃüåŃü½Ķ”ŗŃüłŃĆüńē╣Ńü½No.101Ńü»ńĪ¼ŃüÅĶ”ŗŃüłŃéŗŃĆé […]
ŃüōŃü«õĮĢÕ╣┤ŃüŗŃĆüµ¢░Õ╣╣ńĘÜŃü½õ╣ŚŃéŗŃü¤Ńü│Ńü½õĖŖÕ╣│õĖ╗ń©ÄŃü«õ║ŗŃéƵøĖŃüäŃü¤µ£¼ŃéÆĶ¬ŁŃéōŃü¦ŃüäŃü”ŃĆüŃĆīµ¢░Õ│ČŃü½ĶĪīŃüŻŃü”Ńü┐Ńü¤ŃüäŃü¬ŃüüŃā╗Ńā╗ŃĆŹŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüĢŃéēŃü½ŃüÜŃüŻŃü©ÕŹŚŃü«Õģ½õĖłÕ│ČŃüŗŃéēńĀźń¤│ŃüīµÄĪŃéīŃéŗŃüØŃüåŃü¬ŃéōŃü¦ŃüÖŃĆéŃüäŃüżŃééŃüŖõĖ¢Ķ®▒Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗµ¢╣ŃüŗŃéēYahoo!ŃāŗŃāźŃā╝Ńé╣ […]
ķØÆńĀźÕÉäń©«ŃĆéķØÆńĀźŃü»ÕīģõĖüńŁēŃü«Õłāńē®ńĀöńŻ©Ńü¦Ńü»ŃéłŃüÅõĮ┐ńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕłĆŃéÆńĀöŃüÉńĀöÕĖ½Ńü»Õ░æŃüäŃü©µĆØŃéÅŃéīŃĆüń¦üŃééÕłĆŃéÆńĀöŃüÉÕĘźń©ŗŃü¦Ńü»õĮ┐ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃü¦ŃĆüÕłĆŃéÆÕĮōŃü”Ńü¤µÖéŃü«ńē╣µĆ¦ŃéƵŖŖµÅĪŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüõ╗ŖŃü»ŃüōŃü«ĶŠ║Ńü«ńĢ¬µēŗŃü»õ║║ķĆĀńĀźŃüīŃüéŃéŗŃüŗŃéēõĮ┐ŃéÅŃü¬ŃüäŃĆüŃü¤ŃüĀ […]
õ╗ŖÕø×Ńü»ÕĤń¤│ŃéäÕż¦ÕłżŃéÆŃĆéÕĆēÕ║½Ńü½ŃüéŃéŗńĀźń¤│Ńü½µēŗŃéÆÕć║ŃüÖŃü©ŃüĪŃéćŃüŻŃü©Õż¦ÕżēŃü¬Ńü«Ńü¦ŃĆüńÄäķ¢óÕģłŃü©ńĀöŃüÄÕĀ┤ÕåģŃü½ńĮ«ŃüäŃü”ŃüéŃéŗń¤│Ńü¦ŃĆé No.89ÕĤń¤│Ńü«õĖŖŃü½ńĮ«ŃüäŃü¤ńĀźń¤│ŃüīķĆÜÕĖĖŃü«Õż¦ŃüŹŃüĢŃü¦ŃüÖŃĆéń½»Ńü«ķØóŃéÆÕć║ŃüŚŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃü®ŃüōńöŻŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆüńöŻÕ£░õĖŹµśÄŃü¦ŃüÖŃĆéń▓ÆÕ║”Ńü»ĶŹÆ […]
õ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©Ńü¦Ńü»µśŁÕÆī’╝ō’╝æÕ╣┤õ╗źµØźõ╝ÜÕĀ▒ŃéÆńÖ║ĶĪīŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝łÕłØµ£¤Ńü»ŃĆīµ£āÕĀ▒ŃĆŹŃĆüŃüØŃü«ÕŠīÕÉŹŃéƵö╣ŃéüŃĆīµ┤źŃü®ŃüäŃĆŹŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤’╝ēŃĆéńÅŠÕ£©’╝Ö’╝ŚÕÅĘŃüŠŃü¦µØźŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©Ńü¦Ńü»ŃüōŃü«Õ║”ŃĆü’╝Ö’╝śÕÅĘŃéÆŃāćŃéĖŃé┐Ńā½ńēłŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüÕēĄÕłŖÕÅĘ’Į×’╝Ö’╝ŚÕÅĘŃüŠŃü¦Ńü«ÕÉłµ£¼ŃéÆÕłČõĮ£ŃüŚŃüŠŃüŚ […]
ńĀźń¤│Õ▒ŗŃüĢŃéōŃü½ķĆÜŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃĆüŃéĄŃā│ŃāŚŃā½ŃéäŃüŖÕ£¤ńöŻÕōüńÜäŃü½ńĀźń¤│ŃéÆķĀéŃüÅõ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃéīŃü»µ£¬ńĄīķ©ōŃü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüæŃéŗĶ▓┤ķćŹŃü¬µ®¤õ╝ÜŃĆéŃü¤ŃüŗŃüīŃéĄŃā│ŃāŚŃā½Ńü©õŠ«ŃéŗŃü¬ŃüŗŃéīŃĆéµĆØŃéÅŃü¼ÕÉŹńĀźŃü½Õć║õ╝ÜŃüåõ║ŗŃééŃüŚŃü░ŃüŚŃü░Ńü¦ŃĆéŃĆīÕż®ńäČńĀźń¤│µ»öĶ╝āŃĆĆ34ŃĆ£47ŃĆŹŃü«No.46 […]
No.78ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ5/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝ö/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.79ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ3/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.80ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ6/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ […]
Ķ®│ń┤░Ńü»ŃĆīÕ¦½ĶĘ»ÕĖéń½ŗńŠÄĶĪōķż©HPŃĆŹŃéÆŃüöĶ”¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüä ĶČŻµŚ© µ£¼Õ▒ĢŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńŠÄµäÅĶŁśŃéÆĶ▒ĪÕŠ┤ŃüÖŃéŗÕłĆÕēŻŃü«Õłāµ¢ćŃü«ńŠÄŃéƵēŗµÄøŃüŗŃéŖŃü½ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ķó©Õ£¤ŃüīÕ¤╣ŃüŻŃü”ŃüŹŃü¤µĘ▒µĘĄŃü½ŃüŚŃü”Ķ▒Ŗń®ŻŃü¬Õ┐āĶ▒Īķó©µÖ»Ńü½Ķ¦”ŃéīŃĆüŃüØŃü«õĖ¢ńĢīĶ”│Ńü«ńŗ¼Ķ欵ƦŃĆüŃüŠŃü¤µÖ«ķüŹµĆ¦ŃéÆÕżÜÕĮ®Ńü¬Ķ”¢ńé╣Ńü¦µÄóµ▒éŃüŚŃéłŃüåŃü©ŃüÖ […]
õĖŁÕ▒▒ńöŻŃĆéÕłĆÕēŻŃü«ńĀöńŻ©Ńü¦Ńü»Ķ¦ÆńĀźŃü©ŃüŚŃü”õĮ┐ŃüåńĀöÕĖ½Ńü»Õ░æŃü¬ŃüäŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆéķĆÜÕĖĖŃü»ŌåōŃü«µ¦śŃü¬Ńé│ŃāāŃāæŃüŗŃéēÕ£░ĶēČŃéÆõĮ£ŃéŖõĮ┐ńö©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé õ╣ģŃĆģŃü½õĖŁÕ▒▒Ńü«ķ╗äµØ┐ŃéÆŃāŹŃāāŃāłŃü¦µÄóŃüŚŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµ«åŃü®Ķ”ŗŃüżŃüŗŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéµĢ░Õ╣┤ÕēŹŃüŠŃü¦Ńü»ŃüŠŃüĀÕģźµēŗÕć║µØźŃü¤ŃéōŃü¦ŃüÖŃüīŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆé […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝¢/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝ö/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüŗŃü¬ŃéŖµśöŃĆüĶČŻÕæ│ńĀöńŻ©Ńü«µ¢╣ŃüŗŃéēķĀéŃüäŃü¤ń¤│Ńü¦ŃüÖŃĆé […]
ń¦üŃĆüõ║║Ńü«ÕÉŹÕēŹŃéÆĶ”ÜŃüłŃéŗõ║ŗŃüīĶŗ”µēŗŃüĀŃüŻŃü¤ŃéŖŃĆüŃüŖķĪöŃü©ŃüŖÕÉŹÕēŹŃüīõĖĆĶć┤ŃüŚŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗŃé┐ŃéżŃāŚŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕłĆŃü«ķŖśŃéäÕłāµ¢ćŃĆüńē╣Ńü½Õ£░ķēäŃü¬Ńü®Ńü»ńĄÉµ¦ŗķĀŁŃü½µ«ŗŃéŗõ║║Ńü¦ŃüÖ’╝łŃü¤ŃüĀń¦üŃü¬ŃéōŃüŗŃéłŃéŖµ¢Łńäȵ«ŗŃéŗµ¢╣ŃéÆĶżćµĢ░ń¤źŃüŻŃü”ŃüäŃü”ŃĆüµ»ÄÕø×ÕćäŃüäŃü¬ŃüüŃü©µä¤Õ┐āŃüÖŃéŗµ¼Īń¼¼Ńü¦ŃüÖ’╝ēŃĆéŃüŚŃüŗ […]
No.71ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ5/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 No.72ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝Ģ/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝Ģ/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē® […]
Õż®ńäČńĀźń¤│ŃéÆĶ▓ĘŃüäŃü½ĶĪīŃüŹŃĆüµł¢ŃüäŃü»Õż®ńäČńĀźń¤│ŃéÆõĮ┐Ńüåõ║║Ńü©õ╝ÜŃü䵌źµ£¼ÕłĆŃü«ńĀöÕĖ½Ńü©ÕÉŹŃü«ŃüŻŃü¤µÖéŃĆüµŁōĶ┐ÄŃüĢŃéīŃü¤Ķ©śµåČŃéłŃéŖŃééŃéĆŃüŚŃ鏵Ģ¼ķüĀŃüĢŃéīŃéŗŃüŗķģĘŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü»ķ”¼ķ╣┐Ńü½ŃüĢŃéīŃü¤ŃĆüŃüØŃéōŃü¬Ķ©śµåČŃü«µ¢╣ŃüīÕ╝ĘŃüŵ«ŗŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃĆƵĢ¼ķüĀŃüĢŃéīŃü¤µÖéŃĆüńÉåńö▒ŃéÆĶü×ŃüäŃü¤õ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕłĆŃü« […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ7/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ8/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé Õģ½µ£©ŃāÄÕČŗŃü¦ŃüÖŃĆé(µ¢ŁÕ«ÜŃüŚŃü¤Ķ©ĆŃüäµ¢╣Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüń¦ü […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ3/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ńĀöńŻ©ÕŖøĶŗźÕ╣▓Õ╝▒ŃéüŃü«ÕłāÕ╝ĢŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéõ╗ŖµĆØŃüłŃü░ŃĆüŃéÅ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝Ś’Į×’╝Ö/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝ś/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé Ķ”ŗµģŻŃéīŃü¬ŃüäŃü©ÕÉŹÕĆēŃü½Ķ”ŗŃüłŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃüŗŃééń¤ź […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝ö/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝ö/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé µŁŻńĄ▒ńÜäÕłāÕ╝ĢŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«ń¤│Ńü½Ńü»ÕŹśŃü½ķ╗ÆŃüäńĀöµ▒ü […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ7’Į×’╝ś/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝Ś’Į×’╝Ö/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ŃĆīÕż®ńäČńĀźń¤│µ»öĶ╝ā’╝ĢŃĆŹŃĆīÕż®ńäČńĀźń¤│µ»öĶ╝ā […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ7/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝Ś/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ÕåÖń£¤Ńü¦Ķ”ŗŃéŗŃü©ÕēŹÕø×Ńü«Õż®ńĀźń¤│µ»öĶ╝āŃĆī34ŃĆ£47 […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4~7/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ5~7/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé µ£ĆĶ┐æŃüŠŃü©ŃéüŃü”UPŃüīÕóŚŃüłŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüī […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝ś/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝Ś/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüäŃüÜŃéīŃü«ń¤│ŃééŃĆüŃĆīÕ£░Õ╝ĢŃüŹŃĆŹµł¢ŃüäŃü»ŃĆīÕ£░ńĀźŃĆŹŃü© […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ’╝Æ/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝Æ/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ŃĆīÕż®ńäČńĀźń¤│µ»öĶ╝ā’╝æŃĆŹŃü©ÕÉīń©«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«ń¤│ŃüīµÄĪ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ7/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé Õż®ńäČńĀźń¤│µ»öĶ╝ā20Ńü©ÕÉīń©«Ńü«ńĀźń¤│ŃĆéńĄÉÕ▒ĆŃüōŃü«µÖé […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ’╝ö/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé Õż®ńäČńĀźń¤│µ»öĶ╝āŃü«ŃĆī’╝ŚŃĆŹŃéäŃĆī’╝æ’╝öŃĆŹŃü½Ķ┐æŃüäńĀźĶ│¬ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ7/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ĶŻÅŃéäÕü┤ķØóŃü½ŃĆīńÄēŃĆŹŃü©µøĖŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ¦śŃü½ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ5/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ĶĪ©ķØóÕåÖń£¤õĖŖÕŹŖŃü«ŃāżŃé▒Ńü»ńĪ¼ŃüäŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüõĖŗÕŹŖŃü» […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ7/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ6/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé 10Õ╣┤Ńü╗Ńü®ÕēŹõĖĆÕ║”ŃüĀŃüæĶ®”ŃüŚŃü¤ŃüŹŃéŖŃü¦ŃĆüõ╗ŖÕø×õ╣ģ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ6/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃü«ńĀźń¤│ŃĆüĶŻÅĶĪ©ŃüīÕÅŹÕ»ŠŃüĀŃü©µĆØŃéÅŃéīŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüØ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ6/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃü«ń¤│Ńü»µ¤öŃéēŃüŗŃüĢŃü©ńĀöńŻ©ÕŖøŃüīńĄČÕ”ÖŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüī […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ2/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé Ķ”ŗŃü¤ńø«Ńü»ńČ║ķ║ŚŃü¬Ńü«Ńü¦Õż¦Õżēķ½śõŠĪŃü¬ńĀźń¤│Ńü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ5/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ4/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé ńĄÉÕ▒ĆŃü®Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆõĮ┐ŃüåŃüŗŃü»õ╗¢Ńü©Ńü«µ»öĶ╝āŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ7/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ9/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆé Õ║”ŃĆģµøĖŃüŹŃüŠŃüÖŃüīŃĆüĶ”ŗŃü¤ńø«Ńü½ńČ║ķ║ŚŃü¬ńĀźń¤│Ńüīµ¼▓ŃüŚŃüä […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ7/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ7/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé ńĪ¼ŃüäńĀźń¤│Ńü»ŃéłŃüÅńĘĀŃüŠ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ5/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ6/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé Õ░ÅŃüĢŃü¬Ńé│ŃāāŃāæŃü¦ŃüÖŃüī […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ3/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ1/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé ŃüōŃüōŃüŠŃü¦µ│źµ░ŚŃüīÕ╝ĘŃüä […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ3/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ3/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé ŃüōŃü«ń¤│Ńü»õĖƵÖéµ£¤ŃéłŃüÅ […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ3/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ4/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé ńČ║ķ║ŚŃü¬ńĀźń¤│Ńüīµ¼▓ŃüŚŃüä […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ5/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ1/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé ŃüéŃéŗń©ŗÕ║”Ńü«ńĪ¼ŃüĢŃüīµ£ē […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ4/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé ĶŻÅŃü½ńÜ«ŃüīńäĪŃüÅĶĪ©ĶŻÅŃü® […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ7/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé ŃüōŃü«Õ▒▒Ńü«ń¤│Ńü»ńŗ¼ńē╣Ńü« […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ5/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé ŃüōŃéīŃéé10Õ╣┤ń©ŗÕēŹŃü» […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ4/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ5/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé 10µĢ░Õ╣┤ÕēŹŃüöŃéŹõĖ╗ÕŖø […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ6/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ7/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 ńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüäŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅķāĮÕ║”Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦Ńü«µĢ░ÕĆżŃü¦ŃüÖŃĆéŃü¦ŃüÖŃü«Ńü¦ÕŠīŃĆģÕżēŃéÅŃéŗŃüŗŃééŃĆé 30ŃĆ£25Õ╣┤ń©ŗÕēŹŃĆü […]
ńĀźń¤│ńĪ¼Õ║”ŃĆĆŃĆĆ2/10ńĀöńŻ©ÕŖøŃĆĆ2/10ÕłĆĶ║½Ńü»µ£½ńøĖÕĘ×ŃĆéÕłĆĶ║½ńĪ¼Õ║”6/10 õĖƵÖéµ£¤ŃéłŃüÅĶ”ŗŃüŗŃüæŃü¤Ńé┐ŃéżŃāŚŃü«ńĀźń¤│ŃĆéŃé½Ńā®Ńé╣Ńüīńē╣ÕŠ┤ńÜäŃĆé ĶīČĶē▓Ńü«ńŁŗŃü»ÕĮōŃü¤ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéķ╗ÆŃü»Õż¦õĖłÕż½ŃĆéńĀöńŻ©ÕŖøµĢ░ÕĆżŃü»ŃüōŃü«ÕłĆĶ║½Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģ©Ńü”Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ®”ŃüŚń║ÅŃéüŃü¤ńē®ŃéƵøĖŃüä […]
µś©µŚźŃü«Ńā¢ŃāŁŃé░Ńü¦ŃĆīÕŖ╣ŃüÅÕŖ╣ŃüŗŃü¬ŃüäŃéłŃéŖŃééŃĆüÕ£░ŃéÆÕ╝ĢŃüÅŃüŗÕ╝ĢŃüŗŃü¬ŃüäŃüŗŃĆüŃüØŃüåŃüäŃüåÕłżµ¢ŁŃü¦Ķē»ŃüäµÖéõ╗ŻŃüĀŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃüŗŃĆŹŃü©µøĖŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµøĖŃüŹŃü¬ŃüīŃéēŃĆüŃüĪŃéćŃüŻŃü©ķ¢ōķüĢŃüŻŃü¤õ║ŗŃéƵøĖŃüäŃü”ŃéŗŃü¬ŃüüŃü©µĆØŃüäŃü¬ŃüīŃéēŃééŃĆüŃüØŃü«ŃüŠŃüŠŃü½ŃüŚŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĖĆÕ┐£Ķ©éµŁŻŃü©ŃüäŃüäŃüŠŃüÖ […]
ŃüŚŃü░ŃéēŃüÅÕēŹŃü½Ķ¦ÆńĀźŃü¦Ńü»ÕłØŃéüŃü”Ķ▓ĘŃüåÕ▒▒Ńü«ÕåģµøćĶ│¬Ńü«ńĀźń¤│ŃéÆĶ│╝ÕģźŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüńĄÉµ¦ŗŃü¬ńĀöńŻ©ÕŖøŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéµÖ«ķĆÜŃü¬ŃéēŃé░Ńā¼Ńā╝Ńü«ķā©ÕłåŃüīÕżÜŃüÅŃü¬ŃéŗŃü╣ŃüÅĶ”ŗŃü¤ńø«Ńü½ńČ║ķ║ŚŃü¬ńĀźń¤│ŃéƵ▒éŃéüŃéŗŃü©ŃüōŃéŹŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü«Õ▒▒Ńü«ŃüōŃü«Õ▒żŃü«Ķ│¬Ńü»ķüĢŃü嵦śŃü¦ŃüÖŃĆé’╝łĶō«ĶÅ»Ńü¬Ńü®Ńü»ÕĮōńäČŃüŠŃüśŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆé […]
Õż®ńäČńĀźń¤│ŃéÆķĀ鵳┤Ķć┤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ÕåÖń£¤õ╗źÕż¢Ńü½ŃééÕżÜµĢ░Ńü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕåģµøćŃéŖŃüī3’╝ÉõĖüõ╗źõĖŖŃĆéÕÉŹÕĆēŃā╗ń┤░ÕÉŹÕĆēŃüī’╝æ’╝Éń©ŗÕ║”ŃĆéŃüäŃüżŃééÕźĮŃéōŃü¦õĮ┐ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗÕż¦Õ╣│Ńü«ÕÉłńĀźŃéé’╝æ’╝Éõ╗źõĖŖŃĆéŃüéŃü©Ńü»ÕłĆńĀöÕĖ½Ńü½Ńü»ŃééŃüŻŃü¤ŃüäŃü¬ŃüäõĖŁÕ▒▒ŃéäńöŻÕ£░õĖŹµśÄŃü«Õż¦ÕłżńĀźń¤│ŃüīÕżÜµĢ░ŃĆé ÕåģµøćŃéŖńö©Ńü«µŻÜ […]
Ńü«õ║ŗŃü»µ£ĆĶ┐æµøĖŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüŻŃüæ’╝¤ŃĆƵøĖŃüäŃü¤µ░ŚŃééŃüŚŃüŠŃüÖŃüīŃü®ŃüåŃüĀŃüŻŃü¤ŃüŗŃĆéŃĆéŃüŠŃüäŃüäŃüŗŃĆé Ńü©Ńü½ŃüŗŃüÅńĀźń¤│Ńü»µĖøŃéēŃü¬ŃüäŃü½ĶČŖŃüŚŃü¤õ║ŗŃü»Ńü¬ŃüäŃĆéńĀöńŻ©Ńü«ńĄīķ©ōŃüīÕóŚŃüłŃéīŃü░ÕóŚŃüłŃéŗŃü╗Ńü®ŃĆüńĀźń¤│Ńü»µĖøŃéēŃü¬ŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ĶŹÆńĀźŃĆüõĖŁńĀźŃĆüÕåģµøćńĀźŃĆüŃü®ŃéīŃééÕÉīŃüśŃü¦ŃüÖŃĆéńĄīķ©ōŃüīµĄģ […]
ŃüōŃüōŃü«Ńü©ŃüōŃéŹÕżÜÕłå’╝ö’╝ɵŚźõĖŁ’╝Æ’╝ɵŚźõ╗źõĖŖŃüīÕłāÕÅ¢ŃéŖõĮ£µźŁŃü¦ŃüŚŃü¤’╝łõĖĆÕÅŻŃü«ÕłĆŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéō’╝ēŃĆé ÕÉīŃüśÕłĆŃü¦õĮĢµŚźŃééÕłāÕÅ¢ŃéŖõĮ£µźŁŃéÆńČÜŃüæŃéŗŃü©ŃĆüµīćŃüīµō”ŃéīŃéŗķā©ÕłåŃü«Õ£░ķēäŃü«Ķē▓ŃüīÕżēŃéÅŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŌĆØŃü╝ŃüåŃüÜŌĆØŃü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃéŗńÅŠĶ▒ĪŃüīĶĄĘŃüōŃéŗŃü«ŃüĀŃü©Õ║”ŃĆģĶü×ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéń¦üŃü»µīćŃü½ŌĆØ […]
µĢ░ŃāĄµ£łÕēŹŃĆüŃāŹŃāāŃāłŃāŗŃāźŃā╝Ńé╣Ńü½Õż®ńäČńĀźń¤│Ńü«õ║ŗŃüīÕć║Ńü”ŃüäŃéŗŃéłŃü©ŃĆüŃüäŃüżŃééŃüŖõĖ¢Ķ®▒Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗµ¢╣ŃüŗŃéēŃüöķĆŻńĄĪŃéÆķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń¦üŃü»ÕłØŃéüŃü”Ķü×ŃüÅńĀźń¤│Ńü¦ŃĆéńĀźń¤│Ńü½ķÖÉŃéēŃüÜŃü®ŃéōŃü¬ķüōÕģĘŃü¦ŃééŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕłĆÕēŻńĀöńŻ©Ńü¦Ńü«õĮ┐ńö©Ńü«ÕÅ»ÕÉ”Ńü»Õ«¤ķÜøõĮ┐ŃéÅŃü¬ŃüÅŃü©ŃééńĀöÕĖ½Ńü¬ŃéēÕż¦õĮōÕłżµ¢Ł […]
õ╗ŖµŚźŃééõĖƵŚźõ╗Ģõ║ŗŃéÆķĀæÕ╝ĄŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüŗŃüŻŃüōŃüäŃüäŃāÖŃā╝Ńé╣ŃĆé Ńü¤ŃéÆŃéäŃéüŃü«Õ▓ĪµØæŃüĢŃéōŃü«µ¦śŃü½µśÄµŚźŃüŗŃéēŃééÕ¤ĘÕ┐ĄŃü«ńĀöŃüÄŃü¦ķĀæÕ╝ĄŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ķ¢ōŃüīń®║ŃüäŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃĆ鵜©Õ╣┤Õ║”Ńü»ķ¬©µŖśŃéäŃü¬ŃéōŃéäŃüŗŃéōŃéäŃü¦õĖēŃāȵ£łķ¢ōŃü╗Ńü®õ╗Ģõ║ŗŃüīÕć║µØźŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõ╗ŖŃü»Õ«īÕģ©Õø×ÕŠ®Ńü¦µŚźŃĆģńĀöńŻ©ŃéÆķĀæÕ╝ĄŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµ£ĆĶ┐æŃééÕ░ÅŃüĢŃü¬ķüŗŃü«µé¬ŃüĢŃü»Õ║”ŃĆģŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃā╗Ńā╗ŃĆé Ńé▒Ńā╝ŃéŁŃü½ŃüōŃéōŃü¬ŃéōŃüīÕģźŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ŃéŖŃĆé […]
ÕģāŃĆģÕĘ╗ńē®(µÄøĶ╗ĖńŁē)ŃéÆÕĘ╗ŃüŹÕÅ¢ŃéŗŃü«ŃüīĶŗ”µēŗŃü¦µ»ÄÕø×µ▒ÜŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé(ńēćÕü┤Ńü½ńĢ░µ¦śŃü½Ńé║Ńā¼Ńü¤ŃéŖŃĆüŃüØŃéīŃéÆõ┐«µŁŻŃüŚŃüżŃüżÕĘ╗ŃüŹÕÅ¢ŃüŻŃü¤ńĄÉµ×£ŃĆüŃé¼ŃāāŃéĄŃā╝ŃüŻŃü©ķøæŃü½ŃüŠŃü©ŃéüŃü¤ŃāłŃā®Ńā│ŃāŚŃü«µ¦śŃü½õĖĪŃéĄŃéżŃāēŃüīŃé¼Ńé┐Ńé¼Ńé┐Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü¤ŃéŖŃü©)ŃĆé ŃüŚŃüŗŃüŚÕ»ÆÕ▒▒µŖ╝ÕĮóŃĆ£ŃĆüńČ║ķ║ŚŃü½ÕĘ╗Ńüæ […]
’╝Æ’╝ĢÕ╣┤Ńü╗Ńü®ÕēŹŃü½Ķ│╝ÕģźŃüŚŃü¤µ©ŗńö©Ńü«ńŻ©ŃüŹµŻÆŃü¦ŃüÖŃüīÕĮóńŖČŃüīÕźĮŃü┐Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅõ╗ŖŃüŠŃü¦Ńü½’╝æ’╝ÉÕø×ń©ŗÕ║”ŃüŚŃüŗõĮ┐ńö©ŃüŚŃü¤õ║ŗŃüīŃü¬ŃüÅŃĆéŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚń£ĀŃéēŃüøŃü”ŃüŖŃüÅŃü«ŃééŃü¬ŃéōŃü¦ŃüÖŃüŚŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆé ÕźĮŃü┐Ńü«ÕĮóńŖČŃü½ÕŖĀÕĘźŃĆéŃé┐Ńā│Ńé¼ŃāŁŃéżŃü»ńĪ¼ŃüäŃĆéŃüĪŃéćŃüŻŃü©Ķ¢äŃüÖŃüÄŃü¤ŃüŗŃééŃĆéńŻ©ŃüŹńŁŗŃüīµ«ŗŃéŗŃéłŃüåŃü¬Ńéē […]
ń¦üŃü«ŌĆØõĖĆńö¤µīüŃü”Ńü¬ŃüäŃü¦ŃüéŃéŹŃüåµ£¼Ńā¬Ńé╣ŃāłŌĆØŃü½µ£©Õ▒ŗµŖ╝ÕĮóŃü©Õ»ÆÕ▒▒µŖ╝ÕĮóŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµ£¼µŚźÕ»ÆÕ▒▒µŖ╝ÕĮóŃéÆķĀ鵳┤ŃüäŃü¤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé’╝łµ£©Õ▒ŗµŖ╝ÕĮóŃü»ŃüŚŃü░ŃéēŃüÅÕēŹŃü½Ķ│╝Õģź’╝ēÕ»ÆÕ▒▒µŖ╝ÕĮóŃü½Ńü®Ńü«µ¦śŃü¬ÕōüŃüīµÄ▓Ķ╝ēŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü«ŃüŗŃéÆń¤źŃéēŃüÜŃü½Õ▒ģŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüéŃüŠŃéŖŃü½ŃééÕćäŃüÅŃü”ŃĆéŃĆé […]
µ»ÄµŚźńĀöńŻ©ŃĆéŃü¤ŃüŠŃü½µŖ╝ÕĮóŃĆé ńČ║ķ║ŚŃü¬Õ£░ķēäŃĆéńÖĮŃĆüķ╗ÆŃĆüŃé░Ńā¼Ńā╝Ńü½Ķē▓ÕłåŃüæŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüķ╗ÆŃü»Õģ©ķā©Õ£░µÖ»Ńü©ŃüäŃüŻŃü”ŃééķüÄĶ©ĆŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃĆé Õć║Õ╝ĄŃü¦Ńü«µŖ╝ÕĮóõĮ£µźŁŃĆüÕż¬ÕłĆŃü©ÕłĆŃéÆ’╝ƵŚźŃü¦’╝ÆÕÅŻŃĆéŃé╣ŃāöŃā╝ŃāēUPŃü«Õ┐ģĶ”üµĆ¦ŃéÆńŚøµä¤Ńü¦ŃüÖŃĆéńŁöŃüłŃü»ÕłåŃüŗŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüĶä▒ŃüÖŃéŗõ║ŗŃüīÕć║µØźŃü¬ […]
ÕÆīµŁīÕ▒▒ń£īń½ŗÕŹÜńē®ķż©Ńü½Ńü”ŃĆīńē╣ÕłźÕ▒ĢŃĆĆŃüŹŃü«ŃüÅŃü½ÕłĆÕēŻŃā»Ńā╝Ńā½ŃāēŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõ╝ܵ£¤ŃĆĆõ╗żÕÆī’╝ōÕ╣┤’╝öµ£ł’╝Æ’╝öµŚź’Į×’╝¢µ£ł’╝¢µŚźĶ®│ń┤░Ńü»ŃāüŃā®ŃéĘŃéÆŃüöĶ”¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüä ŃüŠŃüĀńÖ║ĶĪ©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃüīÕ▒Ģńż║Ńā¬Ńé╣ŃāłŃü½ŃéłŃéŗŃü©µĢ¼µäøŃüÖŃéŗŌĆØÕģźķ╣┐ŌĆØŃééÕć║ķÖ│õ║łÕ«ÜŃü¦ŃüÖŃĆé’╝łµĢ¼µäøŃü«õĮ┐ […]
µŚźÕłĆõ┐Øõ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©õ╝ÜÕĀ▒Ńü»µśŁÕÆī’╝ō’╝æÕ╣┤ÕēĄÕłŖŃü¦ŃüÖŃĆéÕĮōÕłØŃü«ĶĪ©ķĪīŃü»ŃĆīõ╝ÜÕĀ▒ŃĆŹŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµśŁÕÆī’╝ö’╝ÖÕ╣┤Ńü«ń¼¼’╝ö’╝æÕÅĘŃéłŃéŖŃĆīµ┤źŃü®ŃüäŃĆŹŃü©µö╣ŃéüńÅŠÕ£©’╝Ö’╝ŚÕÅĘŃüŠŃü¦ńÖ║ĶĪīŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõ╗źÕēŹŃĆüµö»ķā©HPÕłČõĮ£Ńü«Ńü¤ŃéüÕģ©ÕåŖŃéÆŃüŖķĀÉŃüŗŃéŖŃüŚŃü”õ╗źµØźń¦üŃüīõ┐Øń«ĪŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü«Õ║”µ¢░ […]
ń¢▓ŃéīŃü¤µÖéŃü»Ńé½ŃāāŃé│ŃüäŃüäŃā¢Ńā½Ńā╝Ńé╣Ńā¢Ńā®ŃéČŃā╝Ńé║Ńü¦ JB ńĀöŃüÄŃü«õ╗ĢõĖŖŃüÆŃéäµŖ╝ÕĮóŃü¦õĖŖµēŗŃüÅŃüäŃüŻŃü¤µÖéŃü»ŃüōŃü«ŃéĘŃā╝Ńā│Ńü«µ░ŚÕłå’╝öÕłå’╝æ’╝śń¦Æ’Į×
µś©Õż£ŃüŗŃéēŃü«ńČÜŃüŹŃĆéµ│óÕ╣│Ńü«õĮ®ĶĪ©Ķ╝¬ķāŁŃü©ĶīÄŃĆüŃüØŃüŚŃü”Õłāµ¢ćŃéƵÅÅŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕ£©ķŖśŃü¦ŃüÖŃüīń┤░ķÅ©Ńü¬Ńü«Ńü¦Ķ”ŗŃüłķøŻŃüäķŖśŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃéīŃü»ń¦üŃü»ÕĀ┤ÕÉłŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüµŖ╝ÕĮóŃü»ńĀöńŻ©Ńü«õ╗Ģõ║ŗŃü«ÕÉłķ¢ōŃü«õĮ£µźŁŃü¦ŃüéŃéŖõ╗Ģõ║ŗŃü©ŃüŚŃü”ĶĪīŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗĶ©│Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéÕÉŹÕōüŃéÆŃüśŃüŻŃüÅŃéŖŃü©µÖéķ¢ōŃéÆŃüŗŃüæ […]
Õż¦ÕÆīńē®ŃĆüķÄīÕĆēµ£½µ£¤Ńü«Õ£©ķŖśÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃĆéķÄīÕĆēµ£¤Ńü«Õż¦ÕÆīµ£¼ÕøĮńē®Ńü»Õ£©ķŖśÕōüŃüīÕ░æŃü¬ŃüÅĶ▓┤ķćŹŃĆé ŃüØŃü«ÕŠīŃĆüÕż¦ÕÆīń│╗Õ£©ķŖśÕż¬ÕłĆÕģ©Ķ║½Ńü½ŃĆéµÖéõ╗ŻŃü»Õ«żńö║õĖŁµ£¤Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéÕÅżŃüÅŃü┐ŃüīŃüĪŃü¬Õć║µØźŃü¦ŃĆüŃüōŃüåŃüäŃüåÕż¬ÕłĆŃü»Õģźµ£ŁķææÕ«ÜŃü½õĮ┐ŃüåŃü©ķØóńÖĮŃüäŃĆéÕć║ŃüĢŃéīŃéŗÕü┤ŃüĀŃü©Ķŗ”ÕŖ┤Õ┐ģĶć│Ńü¦ŃüÖ […]
õĖēµ£¼µØēŃü«µŖ╝ÕĮóŃüīÕć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃééŃüåÕ░æŃüŚµÖéõ╗ŻŃü«õĖŗŃüīŃéŗõĖēµ£¼µØēŃü»õ║ÆŃü«ńø«Ńü«ķĀŁŃüīÕ░¢ŃéŗŃĆīÕ░¢õ║ÆŃü«ńø«ŃĆŹŃü«ķĆŻńČÜŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü«Õłāµ¢ćŃü»Õ░Åõ║ÆŃü«ńø«Ńü«ķĆŻńČÜŃü¦ŃüÖŃĆéõĖēµ£¼µØēń│╗Ńü»ķüÄÕÄ╗Ńü½ķēøńŁåŃéäŃéĘŃāŻŃā╝ŃāÜŃā│Ńü¦Ńü«ńĄīķ©ōŃü»µ£ēŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüŖŃüØŃéēŃüÅÕó©ńŁåŃü¦Ńü»ÕłØŃéüŃü”ŃĆéõĖĆÕ┐£ŃĆīÕó©ńŁå […]
ńö╗Ķ│¬ŃüīķģĘŃüäŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüµśöŃü«ÕŗĢńö╗ŃüīÕć║Ńü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃééŃüå’╝ŚÕ╣┤ń©ŗÕēŹŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéÕŗĢńö╗ÕåģŃü¦ŌĆØŃü®ŃüōŃü½ŃééUPŃüŚŃü¬ŃüäŌĆØŃü©Ķ©ĆŃüŻŃü”ŃüŠŃüÖŃüīŃā╗Ńā╗Ńā╗Ńü¬ŃéōŃüĀŃüŗń¦üŃé鵟ĮŃüŚŃüØŃüåŃü½ńĀöŃüäŃü¦ŃüäŃüŠŃüÖŃüŁŃüćŃĆéõĖŖŃüÆŃüĪŃéāŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖēõ║║Ńü©ŃééŃü½ÕåģµøćõĮ£µźŁŃĆéÕĘ”ŃüŗŃéēõĖēµĄ”ńĀöÕĖ½ŃĆüńÄēńĮ«ŃĆüÕ░ÅķćÄńö░ […]
µ£▒ķŖśŃĆüÕģ╝Õ¤║ŃĆĆÕģ½ÕŹüõĖĆń┐üµØŠÕ║Ą(ĶŖ▒µŖ╝)µ£ØŃüŗŃéēńÅŠõ╗ŻÕłĆŃü«Õłāõ╗śŃüæŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤ÕŠīŃü¦ĶģĢŃüīŃāŚŃā½ŃāŚŃā½Ńü¦ŃĆéŃĆéÕłāµ¢ćµÅÅÕåÖŃü½ÕģźŃéŹŃüåŃü©µĆØŃüŻŃü¤Ńüīµ¢ŁÕ┐ĄŃĆé ŃüŚŃü░ŃéēŃüÅÕēŹŃü«ÕłĆÕēŻńŠÄĶĪōŃĆīÕÉŹÕłĆķææĶ│×ŃĆŹŃü½µØźÕøĮÕģēŃü«µØŠÕ║Ąµ£▒ķŖśŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüõ╗źõĖŗŃüØŃü«Ķ¦ŻĶ¬¼ŃéÆÕ╝Ģńö©ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé […]
µ£▒ķŖśŃü«ÕłĆŃĆüÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆŃü©ŃéŗŃĆéµ£▒ķŖśŃü»ĶīÄŃü«ńÖĮŃüŵ«ŗŃüŚŃü¤ń«ćµēĆŃü½µ£▒Õó©ŃéÆńŻ©ŃüŻŃü”µøĖŃüŹÕģźŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«õĮ£µźŁŃüīńĄÉµ¦ŗÕźĮŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéµŖ╝ÕĮóŃü½µ£▒ĶéēŃü¦ĶÉĮµ¼ŠŃéƵŖ╝ŃüÖŃü©ķĆöń½»Ńü½Õģ©õĮōŃüīńĘĀŃüŠŃüŻŃü”Ķē»ŃüÅĶ”ŗŃüłŃéŗŃü«Ńü©ÕÉīŃüśŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéķÉöŃü«ĶĄżķŖģĶ”åĶ╝¬ŃéäµŗĄŃü«ķćæńØĆÕłćńŠĮŃü©ÕÉīŃüśŃü¦ŃüÖŃüŗŃüŁŃĆé […]
Ńü®ŃüåŃüŚŃü”ŃééõĮōÕŖøŃü«ķÖÉńĢīŃüŠŃü¦ńĀöńŻ©ŃéÆŃüŚŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕ╣┤ŃĆģõĮōŃééŃüŹŃüżŃüÅŃü¬ŃéŖŃĆéŃĆéõ╝æµå®õĖŁŃü½µŖ╝ÕĮóŃéÆÕłČõĮ£ŃĆéŃü©Ńü»ŃüäŃüłŃĆüĶ╝¬ķāŁŃéÆÕÅ¢ŃüŻŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗŃü«Ńü»µäÅÕż¢Ńü©ŃüŚŃéōŃü®ŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃĆüńĀöŃüÄŃü«ÕŠīŃüĀŃü©ńĄÉµ¦ŗĶŠøŃüäŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆé µ¤ÉķāĘÕ£¤ÕłĆŃĆéÕłØŃéüŃü”Ķü×ŃüÅõ║║Ńü¦ŃüÖŃĆéµÖéķ¢ōŃüīµ£¼ÕĮōŃü½ńäĪ […]
Õ¤ŗÕ┐ĀÕ▒ĢŃü«Ńé»Ńā®ŃāĢŃéĪŃā│ŃĆüŃĆīÕ¤ŗÕ┐ĀÕłĆĶŁ£ŃĆŹŃüīÕ▒ŖŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗źÕēŹŃüŗŃéēÕ¤ŗÕ┐ĀķŖśķææŃü»µīüŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüĶ©śÕ┐ĄŃü«ŃüżŃééŃéŖŃü¦ŃāØŃāüŃéŖŃü©ŃĆéŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚõ╗ŖÕŠīÕ¤ŗÕ┐ĀķŖśķææŃü«µ¢╣ŃéÆķ¢ŗŃüÅõ║ŗŃü»ńäĪŃüĢŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéĶ▓ĘŃüŻŃü”ŃéłŃüŗŃüŻŃü¤ŃĆéÕ¤ŗÕ┐ĀÕłĆĶŁ£Ńü¦Ńü»µ£¼µØźŃü«ķģŹÕłŚķĆÜŃéŖŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃü©Ńü»ń¤źŃüŻŃü” […]
Õ░Åń«▒Ńü«õĖŁŃü½ŃüōŃéōŃü¬µä¤ŃüśŃü¦ŃĆéÕó©ŃüīŃüäŃüäÕīéŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé õĖēµØĪŃĆéńĪ»Ńü©Õó©Ńü»µŚźŃĆģõĮ┐Ńüåńē®Ńü¬Ńü«Ńü¦ŃĆüŃüōŃüåŃüäŃüåŃü«Ńü»Õ¼ēŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéńŁåŃü»Ńé½ŃéĄŃé½ŃéĄńö╗µ│ĢŃü½õĮ┐ńö©ŃüÖŃéŗŃü©ńø┤ŃüÉŃāĆŃāĪŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃü«Ńü¦ķćæńŁŗńö©Ńü½ŃüŚŃéłŃüåŃĆé
µśŁÕÆī’╝ö’╝śÕ╣┤ŃĆüµŚźÕłĆõ┐ØÕģ©ÕøĮÕż¦õ╝ÜŃüīõ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©õĖ╗Õé¼Ńü¦ķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃĆüŃüØŃü«Ķ©śÕ┐ĄŃü©ŃüŚŃü”ŃĆīĶŹēĶ¢ÖÕ╗╝ĶłÄµŖ╝ÕĮó’╝łŃüÅŃüĢŃü¬ŃüÄŃü«ŃéäŃüŖŃüŚŃüīŃü¤’╝ēŃĆŹŃüīÕć║ńēłŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«µ£¼Ńü»õ║¼ķāĮÕ║£µö»ķā©ń¼¼õ║īõ╗Żµö»ķā©ķĢĘŃü¦õ║¼ķāĮŃü«ĶĆüĶłŚÕłĆÕēŻÕ║ŚŃĆīĶŹēĶ¢ÖÕ╗╝ĶłÄ’╝łŃüÅŃüĢŃü¬ŃüÄŃü«Ńéä’╝ēŃĆŹŃü«õĖēõ╗Żńø«Ńü¦ŃüéŃüŻŃü¤Õ▓Ė […]
ŃüĪŃéćŃüŻŃü©õ╣ģŃĆģŃü½Õż¦Õ×ŗµøĖń▒ŹŃéÆĶ│╝ÕģźŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ£©Õ▒ŗµŖ╝ÕĮóŃĆ鵜öŃüŗŃéēµ¼▓ŃüŚŃüŗŃüŻŃü¤µ£¼Ńü¦ŃüÖŃĆéÕ▒ŖŃüŹŃüŠŃüŚŃü”µŚ®ķƤĶŹĘĶ¦ŻŃüŹŃéÆŌĆ”ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚõĖĆÕåŖŃüŚŃüŗÕģźŃüŻŃü”ŃüŖŃéēŃüÜŃĆéŃĆéµ£©Õ▒ŗµŖ╝ÕĮóŃü»ķŠŹõ╣Ģõ║īÕĘ╗Ńü«Ńü»ŃüÜŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆéŃĆéŃü¦ŃĆüķ¢ŗŃüäŃü”Ńü┐Ńü”ÕłØŃéüŃü”ń¤źŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüōŃü«µ¦śŃü½ķĢĘŃüäõĖƵ×ÜńŖČŃü« […]
ķ¦┐µ▓│ÕŠ│µ¼ĪķāÄŃüĢŃéōŃü«µŖ╝ÕĮóŃĆéµ¢░ÕłĆŃĆüµ¢░ŃĆģÕłĆńĘ©ŃéÆĶ¬┐Ńü╣Ńü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ńÜåńä╝Ńü«ĶéźÕŠīĶ╝ØŃĆéŃüōŃéīŃü»Ķ”ŗŃü”Ńü┐Ńü¤ŃüäŃü¦ŃüÖŃüŁŃüćŌĆ”ŃĆ鵳”ńüĮŃü½ŃüéŃéÅŃüÜŃü½µ«ŗŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃéÆķĪśŃüäŃüŠŃüÖŃĆé õ╗ÖÕÅ░ÕłØõ╗ŻŃĆüńÅŠÕ£©ķćŹÕłĆµīćÕ«ÜŃĆé Õ║ĘńČÖõĖ¢Õ¢£Õ«┐ķŖśŃĆéĶ▓┤ķćŹŃü¬ÕōüŃü¦ŃüÖŃĆé Õø║Õ▒▒ŃĆéńÅŠÕ£©ķćŹÕłĆŃĆé ÕŠ│ķä░ŃĆé […]
ķ¦┐µ▓│µŖ╝ÕĮóŃéÆÕ░æŃüŚĶ¬┐Ńü╣Ńü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ÕģāÕŠ│ÕģāÕ╣┤Ńü«ńø┤µ¼ĪŃĆüńÅŠÕ£©ńē╣ķ揵īćÕ«ÜŃĆé µØæµŁŻŃü©µŁŻķćŹŃĆüńÅŠÕ£©ķćŹÕłĆµīćÕ«ÜŃĆé µØźÕøĮĶĪīŃĆüµØźÕøĮķĢĘŃĆüńÅŠÕ£©ķćŹÕłĆµīćÕ«ÜŃĆéõ╗¢Ńü½ŃééĶē▓ŃĆģŃüéŃéŖŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆé ķ¦┐µ▓│ŃüĢŃéōŃüīŃĆīŌŚŗŌŚŗµ░ÅŃĆŹŃĆīŌŚŗŌŚŗÕÉøŃĆŹŃü¬Ńü®ÕĮōµÖéŃü«µēƵīüĶĆģŃéÆĶ©śŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕłĆÕēŻńĢīŃü« […]
ĶäćÕĘ«ŃĆüķŖśŃĆĆÕ╣│Õ«ēÕ¤ÄÕ«ēÕ╗Żµ¢╝ń┤ĆÕĘ×ÕÉŹĶŹēķāĪÕÆīµŁīÕ▒▒õĮ£õ╣ŗ ’╝Ģ’╝ōÕø×ńø«Ńééń┤ĆÕĘ×ÕłĆŃĆüń┤ĆÕĘ×ń¤│ÕĀéŃü«Õ«ēÕ╗ŻŃü¦ŃüÖŃĆéń¤│ÕĀéµ┤ŠŃü»Ķ┐æµ▒¤ÕøĮŃü«ńÖ║ńźźŃü¦ŃĆüµ▒¤µłĖŃĆüń┤ĆÕĘ×ŃĆüń”ÅÕ▓Ī’╝łńŁæÕēŹ’╝ēŃü¬Ńü®Ńü½ń¦╗õĮÅŃüŚń╣üµĀäŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕ«ēÕ╗ŻŃééĶ┐æµ▒¤ÕøĮŃéłŃéŖń¦╗õĮÅŃüŚŃü¤õĖĆõ║║Ńü¦ŃüÖŃĆéÕ«ēÕ╗ŻŃü»ń┤ĆÕĘ×Ńü«ĶŚ®ÕĘźŃü©ŃüŚŃü”µ┤╗Ķ║ŹŃüŚŃü” […]
Ķ¢ÖÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕż®ńŗŚ ŃüŚŃü░ŃéēŃüÅń®║ŃüäŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõĮĢÕ║”ńø«Ńü¦ŃüÖŃüŗŃĆü’╝Ģ’╝ÆÕø×ńø«Ńü¦ŃüÖŃüŗŃĆéµŖ╝ÕĮóń┤╣õ╗ŗŃü¦ŃüÖŃĆéÕģłµŚźŃĆüÕż®ńŗŚŃü«Ķ¢ÖÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆŃü©ŃéēŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕż®ńŗŚŃü©Ńü»ń┤ĆÕĘ×ķŹøÕåČŃü¦ŃĆüÕ▒▒Õ¤ÄŃü«ķ׏ķ”¼ķ¢óŃü«µ£½Ķ¬¼Ńü¬Ńü®ŃĆüŃüØŃü«ńÖ║ńö¤Ńü½Ńü»Ķ½ĖĶ¬¼ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕłĆ’╝łĶäćÕĘ«ŃĆüń¤Ł […]
µŚ¦Õ╣┤õĖŁŃü»Õż¦ÕżēŃüŖõĖ¢Ķ®▒Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü”Ķ¬ĀŃü½µ£ēķøŻŃüåŃüöŃü¢ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ£¼Õ╣┤ŃééŃü®ŃüåŃü×ŃéłŃéŹŃüŚŃüÅŃüŖķĪśŃüäńö│ŃüŚõĖŖŃüÆŃüŠŃüÖŃĆé õ╗ŖÕ╣┤Ńü»ŃüŖµ░ŚŃü½ÕģźŃéŖŃü«ńø«Ķ▓½ŃéÆõĮ┐ŃüäŃĆüµ¤äŃéÆÕĘ╗ŃüŹńø┤ŃüŚŃü”ŃééŃéēŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃüÜŃü»ÕłćńŠĮŃéÆĶ¢äŃüÅŃüŚŃü¤ŃüäŃü«Ńü¦ńÅŠÕ£©ÕłćńŠĮµ¢░Ķ¬┐õĖŁŃĆéÕ«īµłÉŃüīµźĮŃüŚŃü┐Ńü¦ŃüÖŃĆé
Õ░æŃüŚŃü«µÖéķ¢ōŃü¦ŃüÖŃüīķÖŹŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé õ╗ŖÕ╣┤ŃééõĖĆÕ╣┤ŃĆüÕż¦ÕżēŃüŖõĖ¢Ķ®▒Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü”Ķ¬ĀŃü½ŃüéŃéŖŃüīŃü©ŃüåŃüöŃü¢ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé µØźÕ╣┤ŃééķĀæÕ╝ĄŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃü®ŃüåŃü×ŃéłŃéŹŃüŚŃüÅŃüŖķĪśŃüäńö│ŃüŚõĖŖŃüÆŃüŠŃüÖŃĆé
µś©µŚźŃü«ķ¦┐µ▓│µŖ╝ÕĮóŃĆüń│ŖŃü¦Ķ▓╝ŃüŻŃü”ŃüäŃü¬ŃüäõĖƵ×ÜŃéÆĶć¬ÕłåŃü«µŖ╝ÕĮóĶ©śķī▓ŃāĢŃéĪŃéżŃā½Ńü½ń¦╗ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤õ║ŗŃéƵĆØŃüäÕć║ŃüŚŃĆüõ╗Ŗµ£ØÕłØŃéüŃü”ķ¢ŗŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕģłµŚźŃü«Õ¤ŗÕ┐ĀÕ▒ĢŃü¦ŃééÕ▒Ģńż║ŃüĢŃéīŃü¤ķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃü«Õ▒▒õ╝ÅÕøĮÕ║āŃü¦ŃüÖŃĆéµ£ØõĖĆõ║║Ńü¦ŃĆīŃüłŃā╝’╝üŃĆŹŃüŻŃü”Ķ©ĆŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ÕżÜÕłåŃééŃüå’╝Æ’╝ÉÕ╣┤Ķ┐æŃüÅÕēŹŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüķ¬©ĶæŻÕ▒ŗŃüĢŃéōŃüŗŃéēµŖ╝ÕĮóķøåŃéÆķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕć║ńēłŃüĢŃéīŃü¤ŃééŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕĆŗõ║║ŃüīµÄĪµŗōŃüŚŃü¤µŖ╝ÕĮóÕĤµ£¼Ńü¦ŃüÖŃĆé µÄĪµŗōĶĆģŃü»ķ¦┐µ▓│µ░ÅĶŚÅŃüĢŃéō(Ķć¬ÕłåŃü«õ║ŗŃü»µ░ÅŃü©Ķ©ĆŃéÅŃü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃüŚŃĆüŃüŖÕÉŹÕēŹŃü¬Ńü«ŃüĀŃü©µĆØŃüåŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüĪŃéćŃüŻŃü©ŃéÅŃüŗŃéŖŃüŠŃüøŃéō)ŃĆé […]
ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ńÅŹŃüŚŃüäķ”¼µēŗÕĘ«(ŃéüŃü”Ńü¢ŃüŚ)Ńü«µŗĄŃéƵŗØĶ”ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤’╝łµÖéõ╗ŻŃü»Õ╣Ģµ£½ń©ŗÕ║”Ńü©µ¢░ŃüŚŃüäńē®Ńü¦ŃüÖ’╝ēŃĆéķĆÜÕĖĖŃĆüÕłĆŃü»ÕĘ”Ķģ░Ńü½ÕĘ«ŃüÖŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüķ”¼µēŗÕĘ«ŃüżŃüŠŃéŖÕÅ│µēŗÕĘ«ŃüŚŃü»ÕÅ│Ķģ░Ńü½ÕĘ«ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé(µĀŚÕ×ŗŃü«õĮŹńĮ«ŃéÆĶ”ŗŃü”ķĀéŃüÅŃü©ÕłåŃüŗŃéŖŃéäŃüÖŃüäŃüŗŃééń¤źŃéīŃüŠŃüøŃéōŃĆéĶŻÅŃü½õ╗śŃüäŃü”ŃüäŃüŠ […]
Õć║ÕģłŃü½Ńü”µ£½ÕéÖÕēŹŃéÆõ║īÕÅŻµŗØĶ”ŗŃĆéÕģ©ŃüÅŃü©Ķ©ĆŃüŻŃü”ŃüäŃüäŃü╗Ńü®ńĀöŃüĵĖøŃéŖŃüīŃü¬ŃüÅŃĆüķØ×ÕĖĖŃü½ÕüźÕģ©ŃĆéµ¢░ŃĆģÕłĆŃü«µ¦śŃü¬ńŖȵģŗŃü¦ŃĆéķŖśÕŁŚŃééń½»µŁŻŃĆéõĖĆŃüżŃü»µ£½ńē®ńäČŃü©ŃüŚŃü¤Õ£░ķēäŃĆüŃééŃüåõĖĆŃüżŃü»Õ░æŃĆģÕÅżĶ¬┐Ńü¬Õ£░ķēäŃü¦ŃĆéµ£½ÕéÖÕēŹŃü½Ńü»ÕĆŗõ║║ńÜäÕźĮŃü┐ŃüīÕģ©ŃüÅńäĪŃüäŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃüåŃüäŃüåŃü«ŃéÆĶ”ŗŃü”ŃüŚŃüŠŃüå […]
µ£½ÕĘ”ŃĆüķĢĘńŠ®ŃĆüķ½śµ£©Ķ▓×Õ«ŚŃĆüÕēćķćŹŃĆüĶ▓×Õ«ŚŃĆüĶĪīÕģēŃĆüŃüØŃüŚŃü”ŃüŠŃü¤ķĢĘńŠ®Ńü©Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪµŗōŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃüōŃüŠŃü¦ńøĖõ╝Øń│╗ŃüīńČÜŃüäŃü¤Ńü«Ńü»ÕłØŃéüŃü”Ńü¦ŃĆüÕüČńäČŃü©Ńü»ŃüäŃüłõĮĢŃüĀŃüŗÕćäŃüäŃĆé
ŃüŗŃü¬ŃéŖõ╣ģŃĆģŃü½µŖ╝ÕĮóńö©Ńü«ķćŹŃéŖŃéÆõĮ£ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé ń¦üŃü«ŃéäŃéŖµ¢╣Ńü¦Ńü»ŃĆüõ╗ŖŃüŠŃü¦12ÕĆŗŃü¦ŃéäŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµ£¼ÕĮōŃü»14ÕĆŗŃüīŃāÖŃé╣ŃāłŃü¬Ńü«Ńü¦ŃĆé
ķŖĆÕ║¦ńøøÕģēÕĀéŃüĢŃéōŃü«youtubeŃāüŃāŻŃā│ŃāŹŃā½ŃĆīµŚźµ£¼ÕłĆŃü«ńŠÄŃĆŹŃü½ķĢĘķćÄń»ćŃüīUPŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ░ĖÕÆīÕĀéµ£ØÕĆēŃüĢŃéōŃü«ŃüöµĪłÕåģŃü¦ń£¤ńö░Õ«Øńē®ķż©Ńü¬Ńü®Ńüīń┤╣õ╗ŗŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµØŠõ╗ŻĶŚ®ĶŹÆĶ®”ŃüŚŃü½õĮ┐ńö©ŃüĢŃéīŃü¤Õż¦µģČńø┤ĶāżŃü«ÕłĆŃüīÕć║Ńü”µØźŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüŖŃü│Ńü¤ŃüĀŃüŚŃüäÕłāµ»ĆŃéīŃü¦ŃĆüĶŹÆĶ®”ŃüŚŃü« […]
Õ▒▒ķ│źµ»øÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃĆéÕłĆńĄĄÕø│Ńü»ÕŹ░ÕłĘŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüĶÉĮµ¼ŠŃü»ÕŹ░ÕłĘŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅÕ«¤ķÜøŃü½ÕŹ░ŃéƵŖ╝ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤Õø│ńēłŃü«Ķ®▒Ńü¦ŃüÖŃüīŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆéŃĆīń¦ŗµ░┤Ńü«ńŠÄŃĆŹŃü«ÕēŹÕŹŖŃü»Õ£░ķēäŃü«Ķ”ŗŃüłŃéŗŃé½Ńā®Ńā╝ÕåÖń£¤Ńü½µ£Ćķ½śŃü«µŖ╝ÕĮóõ╗śŃüŹŃĆéŃüŚŃüŗŃééÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóÕżÜµĢ░Ńü©ŃüäŃüåĶ▒¬ĶÅ»µī»ŃéŖŃĆéÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü«ÕżÜŃüĢŃü¦Ńü»ŃĆīÕéÖÕēŹÕłĆÕēŻńÄŗÕøĮŃĆŹŃééŃĆéŃĆīµŁŻÕ«ŚŃĆŹŃü»ńøĖÕĘ×õ╝ØÕÉŹõĮ£ķøåŃüŗŃéēŃü«Ķ╗óĶ╝ēŃü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗµŖ╝ÕĮóŃüīÕłĆĶ║½Ńé½Ńā®Ńā╝ÕåÖń£¤ […]
µēŗµīüŃüĪŃü«Õ▒ĢĶ”¦õ╝ÜÕø│ķī▓ŃéäĶöĄÕōüķøåŃü«ŃüåŃüĪõĖēÕŹüµĢ░ÕåŖń©ŗÕ║”ŃéÆŃü¢ŃüŻŃü©ńó║Ķ¬ŹŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕłĆĶ║½ÕåÖń£¤Ńü©ÕÉłŃéÅŃüøŃü”µŖ╝ÕĮóŃééÕżÜµĢ░µÄ▓Ķ╝ēŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃééŃü«Ńü»’╝Ś’╝ī’╝śÕåŖń©ŗÕ║”Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéµĆØŃüŻŃü¤ŃéłŃéŖÕżÜŃüÅŃü”ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ķ®ÜŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃĆīÕģ©Ķ║½ÕåÖń£¤Ńü©ķā©ÕłåÕåÖń£¤ŃĆéĶīÄŃü«ķā©ÕłåÕåÖń£¤Ńü»Õ«¤ńē®Ńü½Ķ┐æŃüäĶē▓ÕÉł […]
Õ░æŃüŚÕēŹŃĆüÕ¤ŗÕ┐ĀÕ▒ĢŃü½ŃĆ鵟ĮŃüŚŃü┐Ńü½ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤Õø│ķī▓ŃĆéµ£ĆĶ┐æŃü«Õø│ķī▓Ńü»ń┤ĀµÖ┤ŃéēŃüŚŃüäĶ½¢µ¢ćŃüīµÄ▓Ķ╝ēŃüĢŃéīŃéŗõ║ŗŃééÕżÜŃüÅŃĆüŃüØŃéīõĖĆÕåŖŃü¦ŃééŃüåÕģ©ķā©OKŃü¬µä¤ŃüśŃü¦ķØ×ÕĖĖŃü½ŃüéŃéŖŃüīŃü¤ŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéÕż¦ķææõĖ”Ńü©ŃüäŃüłŃü░ŃĆüŃüØŃéōŃü¬ŃééŃéōŃüśŃéāŃü¬ŃüäŃü©ÕÅ▒ŃéēŃéīŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃéīń©ŗŃü«õŠĪÕĆżŃüīŃüéŃéŗŃü©µĆØŃüäŃüŠ […]
ŃĆĆÕ¤ŗÕ┐ĀÕłĆĶŁ£ĶżćĶŻĮŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»Ńāł ŃĆīÕ¤ŗÕ┐ĀÕ▒ĢŃĆŹķ¢ŗÕé¼Ķ©śÕ┐ĄŃĆĆÕÉŹÕłĆŃü«Ķ©śķī▓ŃüīŃéłŃü┐ŃüīŃüłŃéŗ’╝üµŖ╝ÕĮóķøåŃĆÄÕ¤ŗÕ┐ĀÕłĆĶŁ£ŃĆÅĶżćĶŻĮŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»Ńāł Õ¤ŗÕ┐ĀÕ▒Ģķ¢ŗÕé¼ŃéÆĶ©śÕ┐ĄŃüŚŃü”ŃĆīÕ¤ŗÕ┐ĀÕłĆĶŁ£ŃĆŹŃüīŃéłŃü┐ŃüīŃüłŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕĮōńäČÕ¤ŗÕ┐ĀķŖśķææŃü»µīüŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃéäŃü»ŃéŖŃüōŃüĪŃéēŃééµ¼▓ŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃéł […]
Ńé│ŃāŁŃāŖŃü«ÕĮ▒ķ¤┐Ńü¦’╝Ƶ£łõ╗źķÖŹŃü«ķææÕ«Üõ╝ÜŃüīõ╝æµŁóŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤Ńüīµ╝ĖŃüÅŃü«ķ¢ŗÕé¼Ńü¦ŃüÖŃĆéõ╗ŖÕø×Ńü»ń¦üŃüīÕĮōńĢ¬Ńü¦ŃĆüõ╣ģŃĆģŃü«ķææÕ«ÜŃéÆŃéłŃéŖµźĮŃüŚŃéōŃü¦ķĀéŃüæŃéŗŃéłŃüåŃü½ŃĆü’╝śÕÅŻŃü«ķææÕ«ÜÕłĆŃü©ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝æÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆĶČŖÕēŹÕ«łÕŖ®Õ║āŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆŖµ¤ÅÕĤńŠÄĶĪōķż©µēĆĶöĄÕōü’╝łµŚ¦Õ▓®ÕøĮ […]
Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆŌ¢ĪÕ┐Ā’╝łÕøĮµīćÕ«ÜķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃĆƵŚ¦ÕĄ»Õ│©ÕŠĪµēĆ Õż¦µ£¼Õ▒▒ Õż¦Ķ”ÜÕ»║ĶöĄ/õ║¼ķāĮÕøĮń½ŗÕŹÜńē®ķż©Õ»äĶ©ŚÕÅÄĶöĄÕōü’╝ēŃĆĆŃĆĆÕłāķĢĘŃĆĆõ║īÕ░║Õģ½Õ»Ėõ╣ØÕłåŃĆĆÕÅŹŃéŖŃĆĆõĖĆÕ»Ėõ║īÕłåõĖēÕÄś µ║ɵ░ÅŃü«ķćŹÕ«ØŃü©õ╝ØŃüłŃéēŃéīÕż¦Ķ”ÜÕ»║Ńü½ĶöĄŃüÖŃéŗÕż¬ÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé’╝łĶ¢äńĘæńĄÉńĖüŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»Ńāł’╝ēķŖśŃü«õĖĆÕŁŚńø«Ńüīµ£ĮŃüĪĶŠ╝ […]
ŃĆīµŚ¦ÕĄ»Õ│©ÕŠĪµēĆÕż¦µ£¼Õ▒▒Õż¦Ķ”ÜÕ»║ŃĆŹŃü½µ¢╝ŃüŹŃüŠŃüŚŃü”Ķ¢äńĘæńĄÉńĖüµ│Ģõ╝Ü’╝łŃüåŃüÖŃü┐Ńü®ŃéŖŃüæŃüĪŃüłŃéōŃü╗ŃüåŃüł’╝ēŃüīÕ¤ĘŃéŖĶĪīŃéÅŃéīŃĆüÕć║ÕĖŁŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃĆīÕż¦Ķ”ÜÕ»║µēĆĶöĄµ¢ćÕī¢Ķ▓Īõ┐ØÕŁśõ┐«ÕŠ®õ║ŗµźŁŃĆŹŃü«õĖĆńÆ░Ńü¦ŃĆÄÕż¬ÕłĆŃĆīĶ¢äńĘæ’╝łĶåØõĖĖ’╝ēŃĆŹńĄÉńĖüŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃĆÅŃü©ŃüŚŃü”Õŗ¦ķĆ▓Ńü½ŃéłŃüŻŃü”µĄäĶ▓ĪŃéÆÕŗ¤ […]
õ╗Ŗµ£ł10µ£ł31µŚź’╝łÕ£¤’╝ēŃüŗŃéē12µ£ł14µŚź’╝łµ£ł’╝ēŃüŠŃü¦ŃĆüÕż¦ķś¬µŁ┤ÕÅ▓ÕŹÜńē®ķż©Ńü½µ¢╝ŃüŹŃüŠŃüŚŃü”ŃĆüŃĆÄńē╣ÕłźÕ▒ĢŃĆīÕ¤ŗÕ┐ĀŃĆłUMETADAŃĆēµĪāÕ▒▒ÕłĆÕēŻńĢīŃü«ķøäŃĆŹŃĆÅŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéń¦üŃĆüÕżÜÕłåŃüōŃü«’╝æ’╝ÉÕ╣┤Ńü¦õĖĆńĢ¬µźĮŃüŚŃü┐Ńü½ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕ▒ĢĶ”¦õ╝ÜŃü¦ŃüÖŃĆé ÕēŹµ£¤ÕŠīµ£¤Ńü¦ÕģźŃéīµø┐ŃüłŃüéŃéŖ […]
ń”Åõ║ĢÕĖéń½ŗķāĘÕ£¤µŁ┤ÕÅ▓ÕŹÜńē®ķż©Ńü½Ńü”ń¦ŗÕŁŻńē╣ÕłźÕ▒ĢŃĆīÕīŚķÖĖŃü«ÕÅżÕłĆŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕ▒Ģńż║õĮ£ÕōüŃā¬Ńé╣Ńāł ŃĆĆõ╗ŖŃüŗŃéēÕŹāÕ╣┤õĮÖŃéŖµśöŃĆüÕ╣│Õ«ēµÖéõ╗ŻÕŠīµ£¤Ńü½ńö¤ŃüŠŃéīŃü¤µŚźµ£¼ÕłĆŃü»ŃĆüŃü»ŃüśŃéüÕż¦ÕÆīŃā╗Õ▒▒դĒ╝łńÅŠÕ£©Ńü«ÕźłĶē»ń£īŃā╗õ║¼ķāĮÕ║£’╝ēŃü©ŃüäŃüŻŃü¤µö┐µ▓╗Ńü«õĖŁÕ┐āÕ£░ŃéäÕéÖÕēŹ’╝łńÅŠÕ£©Ńü«Õ▓ĪÕ▒▒ń£ī’╝ēŃā╗Õźź […]
õ╝ܵ£¤’╝Üõ╗żÕÆī’╝ÆÕ╣┤10/28(µ░┤)’Į×11/3(ńü½ńźØ)õ╝ÜÕĀ┤’╝ܵŚźµ£¼µ®ŗķ½ÖÕ│ČÕ▒ŗ’╝│.C.ŃĆƵ£¼ķż©’╝¢ķÜÄńŠÄĶĪōńö╗Õ╗ŖŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆÆ103-8265 µØ▒õ║¼ķāĮõĖŁÕż«Õī║µŚźµ£¼µ®ŗ2õĖüńø«4ńĢ¬1ÕÅĘŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆTEL:(03) 3211ŌĆÉ4111ŌĆ╗µ£ĆńĄéµŚźŃü»ÕŹłÕŠī’╝öµÖéķ¢ēÕĀ┤ ’╝ł […]
ÕłĆŃĆüńäĪķŖśŃĆĆÕēćķćŹ Ńā¢ŃāŁŃé░Ńü¦Ńü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóń┤╣õ╗ŗŃĆüńĀöńŻ©Ķ©śķī▓ŃāÜŃā╝ŃéĖŃü¦Ńü»µ£¬Õģ¼ķ¢ŗŃü«ńē®Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü¦’╝Ģ’╝ÉÕø×ńø«Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüäŃüżŃééõĖĖńŁÆŃü½ÕģźŃéīŃü”õ┐Øń«ĪŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦õĮĢµ×ÜŃüéŃéŗŃüŗµĢ░ŃüłŃüÜŃé╣Ńé┐Ńā╝ŃāłŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüōŃéōŃü¬Ńü½µÄĪµŗōŃüŚŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüŁŃĆéŃĆéõ╗ŖÕø×Ńü»ķÄīÕĆēµ£½ […]
ŃĆīõ╗żÕÆī’╝ÆÕ╣┤Õ║” ń¼¼’╝Ģ’╝¢Õø× õ║¼ķāĮķØ×Õģ¼ķ¢ŗµ¢ćÕī¢Ķ▓Īńē╣ÕłźÕģ¼ķ¢ŗŃĆŹŃüīķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü¦ŃüÖŃĆéõ╗źÕēŹńĀöńŻ©ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤Ķ│ĆĶīéÕłźķøĘńź×ńżŠµ¦ś’╝łõĖŖĶ│ĆĶīéńź×ńżŠ’╝ēÕŠĪµēĆĶöĄŃü«ÕłĆÕēŻķĪ×ŃééńÅŠÕ£©Õģ¼ķ¢ŗõĖŁŃü¦ŃüÖŃĆéÕģ¼ķ¢ŗµ£¤ķ¢ōńŁēŃü»ÕÉäÕģ¼ķ¢ŗÕĀ┤µēĆŃü½ŃéłŃéŖńĢ░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆüĶ®│ŃüŚŃüÅŃü»õĖŗĶ©śHPŃéÆŃüöĶ”¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé […]
ŃĆĆÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆĶéźÕēŹÕøĮÕ┐ĀÕÉēĶäćÕĘ«ŃĆüķŖśŃĆĆĶéźÕēŹÕøĮÕ┐ĀÕÉē ’╝ö’╝ÖÕø×ńø«Ńü»Õģ½õ╗ŻÕ┐ĀÕÉēŃü«Õż¦Õ░ÅŃü¦ŃüÖŃĆéĶéźÕēŹõĖŖõĖēõ╗ŻŃĆüŃüżŃüŠŃéŖÕłØõ╗ŻÕ┐ĀÕÉē’╝łµŁ”ĶöĄÕż¦µÄŠÕ┐ĀÕ╗Ż’╝ēŃĆüõ║īõ╗ŻĶ┐æµ▒¤Õż¦µÄŠÕ┐ĀÕ╗ŻŃĆüõĖēõ╗ŻķÖĖÕźźÕ«łÕ┐ĀÕÉēŃĆüŃüōŃü«õĖēÕĘźŃü«µŖĆķćÅŃü«ķ½śŃüĢŃü»µŚóŃü½Ńā¢ŃāŁŃé░Ńü¦ŃééŃüöń┤╣õ╗ŗŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüĶéźÕēŹÕłĆŃü« […]
Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕŖ®Õīģ’╝łÕøĮµīćÕ«ÜķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓Ī’╝ē ’╝ö’╝śÕø×ńø«Ńü¦ŃüÖŃĆéÕŖ®ÕīģŃü»ŃĆüÕÅżÕéÖÕēŹŃü©õĖƵ¢ćÕŁŚŃü½ÕÉīÕÉŹŃü¦µĢ░ÕĘźÕŁśÕ£©ŃüŚŃĆüķŖśŃü«µøĖõĮōŃü»µĢ░ń©«ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ķŖśŃü«Õż¦ŃüŹŃüĢŃééÕż¦õĖŁÕ░ÅŃüīŃüéŃüŻŃü”ŃüØŃü«ŃüäŃüÜŃéīŃééŃüīÕłźõ║║Ńü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖĆĶ¬¼Ńü½Ńü»Õ░ŵī»ŃéŖķŖśŃéÆÕÅżÕéÖÕēŹŃĆüÕż¦µī»ŃéŖķŖśŃéÆ […]
õ╗źÕēŹµēĆÕ£©õĖŹµśÄŃü«ÕøĮÕ«ØŃā╗ķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńā¢ŃāŁŃé░Ńü½µøĖŃüäŃü¤õ║ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃĆƵēĆÕ£©õĖŹµśÄŃü«ÕøĮÕ«ØŃā╗ķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓Ī’╝ł’╝Æ’╝É’╝æ’╝Ģ’╝ē µ¢ćÕī¢Õ║üŃüīŃüōŃü«Ńā¬Ńé╣ŃāłŃéÆńÖ║ĶĪ©ŃüŚŃü”õ╗źµØźŃĆüÕÉäµ¢╣ķØóŃü«µäÅĶŁśŃü«ķ½śŃüŠŃéŖŃééŃüéŃüŻŃü”ńÖ║Ķ”ŗŃüīńøĖµ¼ĪŃüÄŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╣ģŃĆģŃü½µ¢ćÕī¢Õ║üHPŃü«Ńā¬Ńé╣ŃāłŃéÆŃü┐ […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆõ┐ĪÕĘ×õĮÅĶĪīÕ«Ś’╝łĶŖ▒µŖ╝’╝ēŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕśēµ░ĖÕģŁÕ╣┤õ║īµ£łµŚźŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ’╝łÕłāķĢĘ õ╣ØÕ»Ėõ║öÕłå’╝ē ’╝ö’╝ŚÕø×ńø«Ńü»Õ▒▒µĄ”Õģ╝ĶÖÄÕłØµ£¤ķŖśŃĆüĶĪīÕ«ŚŃü«ń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆéÕģ╝ĶÖÄŃü»Ńā¢ŃāŁŃé░ÕēŹµÄ▓ń£¤ķøäŃü«ÕŁÉŃü¦ńłČń£¤ķøäÕÅŖŃü│ÕÅöńłČµĖģķ║┐Ńü½õĮ£ÕłĆŃéÆÕŁ”ŃéōŃü¦ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé Õģ╝ĶÖÄŃü«õĮ£ÕōüŃü»Õ░æŃü¬ŃüÅķ¢óĶź┐Ńü¬Ńü®Ńü¦ […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆõ┐Īµ┐āÕøĮń£¤ķøä ’╝ö’╝¢Õø×ńø«Ńü»µØŠõ╗ŻĶŚ®ÕĘźÕ▒▒µĄ”ń£¤ķøäŃü¦ŃüÖŃĆéµØŠõ╗ŻĶŚ®ŃĆüń£¤ķøäŃü©µØźŃéīŃü░ŌĆص؊õ╗ŻĶŚ®ĶŹÆĶ®”ŃüŚŌĆØŃü©Ńü¬ŃéŗŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü»Õ«ēµśōŃü½ŃüØŃü«ÕĖĖķüōŃéÆŃü©Ńéŗõ║ŗŃü½µåÜŃéēŃéīŃéŗµ░ŚµīüŃüĪŃüīŃüéŃéŖŃĆüµÄ¦ŃüłŃéŗõ║ŗŃü½ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé Õ▒▒µĄ”ķŹøÕåČŃü©ŃüäŃüłŃü░ń¦üŃü»ŃüŠŃüÜÕłĆÕēŻńŠÄĶĪōĶ¬īŃü½µÄ▓Ķ╝ēŃüĢ […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆƵŁŻÕ«Ś’╝łµØæµŁŻķŖśŃü«µö╣ń½ä’╝ē ’╝ö’╝ĢÕø×ńø«ŃĆéµØæµŁŻõĖēÕÅŻńø«Ńü¦ŃüÖŃĆéõ╗ŖÕø×Ńü»ķŖśŃéƵö╣ń½äŃüĢŃéīŃü¤ń¤ŁÕłĆŃĆéµØæµŁŻŃü«ŃĆīµØæŃĆŹŃü«ÕŁŚŃéÆµČłŃüŚŃĆüõĖŗŃü½ŃĆīÕ«ŚŃĆŹŃéÆĶČ│ŃüŚŃü”ŃĆīµŁŻÕ«ŚŃĆŹŃü©µö╣ń½äŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµØæµŁŻŃü»ÕŠ│ÕĘØÕ«ČŃüŗŃéēÕ┐īķü┐ŃüĢŃéīŃü¤µŁ┤ÕÅ▓ŃüīŃüéŃéŖŃĆüķŖśŃü«õĖĆķā©µł¢ŃüäŃü»Õģ©Ńü”ŃüīµČłŃüĢŃéīŃü¤ […]
õ╝ÜŃĆƵ£¤:’╝Öµ£ł’╝æ’╝ƵŚź’╝łÕ£¤’╝ē’Į×’╝æ’╝æµ£ł’╝Æ’╝ōµŚź’╝łµ£ł’╝ēõ╝ÜŃĆĆÕĀ┤’╝ÜÕØéÕ¤Äńö║ķēäŃü«Õ▒Ģńż║ķż©ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆÆ389-0601ŃĆĆķĢĘķćÄń£īÕ¤┤ń¦æķāĪÕØéÕ¤Äńö║ÕØéÕ¤Ä6313-2ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ Tel. 0268-82-1128ķ¢ŗķż©µÖéķ¢ō:ÕŹłÕēŹ’╝ÖµÖé’Į×ÕŹłÕŠī’╝ĢµÖé’╝łÕģźķż©Ńü»ÕŹłÕŠī’╝öµÖé’╝ō […]
ÕēŹÕø×ŃüŗŃéēŃüéŃüŠŃéŖķ¢ōŃüīń®║ŃüŗŃüÜŃü¦ŃüŠŃü¤ńö¤ÕōüŃü«Õ▒▒ŃéƵŗØĶ”ŗŃĆéõĮĢÕŹüŃüéŃéŗŃüŗµĢ░ŃüłŃüÜŃüĀŃüīÕēŹÕø×Ńü«ÕĆŹõ╗źõĖŖŃüŗŃĆéÕ▒▒ńøøŃéŖŃü«ķלŃü«ķø░Õø▓µ░ŚŃü¦Õż¦õĮōŃü«ńŁŗŃü»ÕłåŃüŗŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃĆéŃüōŃü«Õ▒▒Ńü»Õż¦ÕÉŹŃé»Ńā®Ńé╣ŃüŗŃü©ŃĆéÕż¦ÕÉŹńē®Ńü«Õ▒▒ŃéÆĶ”ŗŃü”ŃééÕ┐ģŃüÜŃü©Ķ©ĆŃüŻŃü”ŃüäŃüäŃü╗Ńü®ŃĆüĶ▒ŖÕŠīĶĪīÕ╣│ŃĆüÕā¦Õ«Üń¦ĆŃĆüĶ▓×µ¼ĪŃĆüÕēćķćŹŃĆü […]
µĢ░ŃāĄµ£łŃüČŃéŖŃü½ńö¤ÕōüŃéÆõ║īÕŹüÕÅŻŃü╗Ńü®µŗØĶ”ŗŃĆéńÄēń¤│µĘʵĘåŃĆé Õż¦ńŻ©õĖŖŃüÆŃü¦õĖĆÕ░║Õģ½Õ»ĖŃü╗Ńü®Ńü«ķīåĶ║½ŃĆéķÄīÕĆēõĖŁµ£¤’Į×µ£½µ£¤Ńü«ÕŖøÕ╝ĘŃüäķĆĀŃéŖĶŠ╝Ńü┐ŃĆéÕÉäµēĆŃü½Ķ”ŗŃüłŃéŗÕ£░ÕłāŃüīķØ×ÕĖĖŃü½Ķē»ŃüäŃĆéŃüØŃü«õ╗¢ŃéÆŃü¢ŃüŻŃü©Ķ”ŗŃü”µ£ĆÕŠīŃü«õĖĆÕÅŻŃĆéÕÅŹŃéŖµĄģŃéüŃü«ÕłĆŃĆéÕ«ÜÕ»ĖŃü╗Ńü®ŃĆéķćŹŃüŁÕÄÜŃüÅĶ║½Õ╣ģÕ░ŗÕĖĖŃĆéõĖŁķŗÆÕ╗ČŃü│Ńüö […]
Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆƵֻÕŖ®’╝łÕÅżÕéÖÕēŹ’╝ē ’╝ö’╝öÕø×ńø«Ńü¦ŃüÖŃĆéńŻ©õĖŖŃüÆŃü¬ŃüīŃéēŃééĶģ░ÕÅŹŃéŖķ½śŃüÅŃĆüÕćøŃü©ŃüŚŃü¤Õż¬ÕłĆÕ¦┐ŃĆéĶīÄŃü«õĖŗÕŹŖÕ╣│Õ£░Ńü½ń┤░ķÅ©Ńü¦µÜóķüöŃü¬µøĖķó©Ńü¦µÖ»ÕŖ®Ńü«ķŖśŃĆéµÖ»ÕŖ®Ńü»ÕÅżÕéÖÕēŹµ┤ŠŃü«ÕłĆÕĘźŃü¦ŃĆüķŖśķææŃü½Ńü»Õ╗║õ┐ØķĀā’╝ł’╝æ’╝Æ’╝æ’╝ōÕ╣┤ ķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻÕłØµ£¤’╝ēŃü©ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéµØ┐ńø«Ńü½µØóõ║żŃüśŃéŖŃĆüÕ£░ […]
ŃéłŃéŖÕ«ēÕģ©Ńü¬HPŃü½ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕåģÕ«╣Ńü»Ńü╗Ńü╝ŃüØŃü«ŃüŠŃüŠŃü¦ŃüÖŃĆéõ╗ŖÕŠīŃü©ŃééŃü®ŃüåŃü×ŃéłŃéŹŃüŚŃüÅŃüŖķĪśŃüäńö│ŃüŚõĖŖŃüÆŃüŠŃüÖŃĆé
ŃĆīµśÄµ▓╗Ńü«µŗĄŃĆüõ╗żÕÆīŃü«ÕłĆŃĆŹŃüīķŖĆÕ║¦õĖēĶČŖŃü½Ńü”ķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé µ£¼Õ▒ĢŃü¦Ńü»ŃĆüµśÄµ▓╗µ£¤Ńü½ĶČŻÕÉæŃü©µŖĆĶĪōŃéÆÕćØŃéēŃüĢŃéīŃü”ĶŻĮõĮ£ŃüĢŃéīŃü¤µŗĄŃéäÕłĆĶŻģÕģĘŃü«µĢ░ŃĆģŃü©ŃĆüõ╗żÕÆīŃü©ÕģāÕÅĘŃéÆÕżēŃüłŃü”ŃééŃü¬ŃüŖĶäłŃĆģŃü©µü»ŃüźŃüÅŃĆüńÅŠõ╗ŻÕłĆÕīĀŃü½ŃéłŃéŗµŚźµ£¼ÕłĆŃéÆõĖŁÕ┐āŃü½ŃĆüÕłĆŃü½ŃüŠŃüżŃéÅŃéŗõĮ£ÕōüŃü«µĢ░ŃĆģŃéÆŃĆüµÖéŃéÆ […]
Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕīģµ░Ė ÕģĄķā©Õż¦Ķ╝öĶŚżÕŁØńŻ©õĖŖõ╣ŗńĢ░ÕÉŹÕÅĘÕģɵēŗµ¤ÅŃĆĆÕż®µŁŻõ║īÕ╣┤õĖēµ£łÕŹüõĖēµŚź (µŻ¤ķŖś)Õż¦ÕÆīÕøĮõĮŵ£łÕ▒▒Ķ▓×Õł®Ķ¼╣õĮ£(ĶŖ▒µŖ╝)Õ╣│µłÉõ║īÕ»┐õ╣ģÕ╣┤õ║öµ£łÕÉēµŚź ’╝łÕģ¼ńøŖĶ▓ĪÕøŻµ│Ģõ║║ ÕŠ│ÕĘØŃā¤ŃāźŃā╝ŃéĖŃéóŃāĀĶöĄ’╝ē ’╝ö’╝ōÕø×ńø«Ńü»µ£łÕ▒▒Ķ▓×Õł®Õģłńö¤Ńü«Õģɵēŗµ¤ÅÕīģµ░ĖÕåÖŃüŚŃü¦ŃüÖŃĆé õ║½õ┐ØÕÉŹńē®ŃĆī […]
ŃüäŃüżŃééÕż¦ÕżēŃüŖõĖ¢Ķ®▒Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖķŖĆÕ║¦ńøøÕģēÕĀéŃü«ķĮŗĶŚżŃüĢŃéōŃüīµŚźµ£¼ÕłĆµ¢ćÕī¢µÖ«ÕÅŖŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüŃĆīµŚźµ£¼ÕłĆŃü«ńŠÄŃĆŹŃü©ŃüäŃüåYouTubeŃāüŃāŻŃā│ŃāŹŃā½ŃéÆķ¢ŗĶ©ŁŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé µś©µŚźŃü»ńĀöŃüÄŃü«ÕÅ¢µØÉŃéÆŃüŚŃü”ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé Ńü®Ńü«ÕŗĢńö╗ŃééÕż¦õ║║Ńü«ĶÉĮŃüĪńØĆŃüäŃü¤ķø░Õø▓µ░ŚŃü«ÕåģÕ«╣ […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆõ║ĢõĖŖń£¤µö╣ ’╝łĶÅŖń┤ŗ’╝ēÕ╗ČÕ«ØÕøøÕ╣┤õ║īµ£łµŚź ’╝ö’╝ÆÕø×ńø«ŃééÕż¦ķś¬µ¢░ÕłĆõ║ĢõĖŖń£¤µö╣ŃĆüķćŹĶ”üńŠÄĶĪōÕōüµīćÕ«ÜŃü«ÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé ÕēŹµÄ▓Ńü«ń£¤µö╣Ńü½µ»öŃüŚŃü”õĖĆĶ”ŗÕż¦õ║║ŃüŚŃüÅĶ”ŗŃüłŃüŠŃüÖŃüīŃĆüńŠÄŃüŚŃüÅŃééÕ╝ĘŃüĢŃü«µ£ēŃéŗÕ£░ķēäŃü½ÕīéŃüäµĘ▒ŃüÅķīĄÕÄÜŃüÅõ╗śŃüÅÕłāµ¢ćŃéÆńä╝ŃüŹŃĆüÕ«¤ńē®ŃéƵēŗŃü½ŃüÖŃéīŃü░Õģ©ŃüÅŃüØŃü«µ¦śŃü¬ […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆõ║ĢõĖŖń£¤µö╣ ’╝łĶÅŖń┤ŗ’╝ēÕ╗ČÕ«ØÕøøÕ╣┤Õģ½µ£łµŚź ’╝ö’╝æÕø×ńø«ŃĆéÕż¦ķś¬µ¢░ÕłĆŃĆüõ║ĢõĖŖń£¤µö╣Ńü¦ŃüÖŃĆé Ķ®░Ńü┐Ńü¬ŃüīŃéēŃééÕ╝ĘŃüäÕ£░ķēäŃĆüÕłāµ¢ćŃü»ÕīéŃüäµĘ▒ŃüÅķīĄÕÄÜŃüÅõ╗śŃüŹŃĆüķćæńŁŗŃĆüńĀ鵥üŃüŚńŁēŃüŚŃüŹŃéŖŃü½ÕāŹŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé ń£¤µö╣Ńü»õĮ£Õ¤¤Ńü½ŃüéŃéŗń©ŗÕ║”Ńü«Õ╣ģŃüīŃüéŃéŖŃüōŃü«ÕłĆŃü»ńø┤ÕłāĶ¬┐Ńü¬ŃüīŃéēµ┐ĆŃüŚŃüäķā©ķĪ× […]
ĶäćÕĘ«ŃĆüķŖśŃĆĆÕÉēķćÄÕ▒▒õ║║Õ£ŗÕ╣│õ╣ŗŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕ╣│µłÉĶü¢õ╗ŻńĄÉŃüĄ ’╝ö’╝ÉÕø×ńø«ŃĆéµ▓│ÕåģÕ£ŗÕ╣│Õģłńö¤Ńü«õĮ£ÕōüŃü¦ŃüÖŃĆé’╝Æ’╝É’╝æ’╝śÕ╣┤ŃĆüµ£¼ĶāĮÕ»║Õż¦Ķ│ōµ«┐Õ«Øńē®ķż©Ńü¦ķ¢ŗÕé¼Ńü«Õ▒ĢĶ”¦õ╝ÜŃĆéõĖĆńĢ¬ÕźźŃü«Õ▒Ģńż║Ńé▒Ńā╝Ńé╣ÕÅ│ń½»Ńü¦ŃĆüŃü▓Ńü©ŃüŹŃéÅńø«ŃéÆÕ╝ĢŃüÅÕ»ĖÕ╗ČŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕ▒ĢĶ”¦õ╝ÜÕŠīŃééŃüÜŃüŻŃü©µ░ŚŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠ […]
µś©µŚźŃü«Ńā¢ŃāŁŃé░ŃĆüµś©Õ╣┤µŗØĶ”ŗŃü«Õż¬ÕłĆŃü©õĖƵś©µŚźµŗØĶ”ŗŃü«Õż¬ÕłĆŃĆé ķÄ║õĖŗÕ╣│Õ£░Ńü«ńĀöÕĖ½Ńü«ŃéĄŃéżŃā│Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕĢÅŃüäÕÉłŃéÅŃüøŃü”ŃüŖµĢÖŃüłķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃéēŃĆüŃéäŃü»ŃéŖÕÉīŃüśõ║║Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆ鵜ĵ▓╗Ńü«ÕÉŹõ║║ńĀöÕĖ½Ńü«Õ╝¤ÕŁÉŃĆé µś©µŚźŃü»ŃĆīķ¢óÕ┐āŃüīĶ¢äŃüäŃü«ŃüŗŃĆŹŃü¬Ńü®Ńü©ŃĆüŃüŠŃéŗŃü¦õ╗¢õ║║õ║ŗŃü«µ¦śŃü½µøĖŃüäŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠ […]
ÕģłµŚźµ¤ÉµēĆŃü½Ńü”ÕøĮÕ«ØŃĆüķ揵¢ćŃĆüķćŹńŠÄńŁēŃéÆ30ÕÅŻŃü╗Ńü®µŗØĶ”ŗŃĆéķ揵¢ćÕż¬ÕłĆŃü«Õ╣│Õ£░ķÄ║õĖŗŃü½ńĀöÕĖ½Ńü«µśÄµ▓╗Õ╣┤ń┤ĆŃü«ŃéĄŃéżŃā│ŃéÆńÖ║Ķ”ŗŃĆéŃü¤ŃüĀµ«ŗÕ┐ĄŃü¬ŃüīŃéēķÄ║Ńü«Ńé╣Ńā¼Ńü¦ĶéØÕ┐āŃü«ÕÉŹÕēŹŃüīĶ¬ŁŃéüŃüÜŃĆéńĀöÕĖ½Ńü«ÕÉŹÕēŹŃéäÕ▒ŗÕÅĘŃéÆÕģźŃéīŃü¤ńē®Ńü»Õ║”ŃĆģĶ”ŗŃüŗŃüæŃéŗŃüīŃĆüķĆÜÕĖĖŃü»ķļգ░Ńü«Õī¢ń▓¦ńŻ©ŃüŹŃü«ķā©ÕłåŃü½ÕģźŃéīŃü” […]
ÕÆīµŁīÕ▒▒ń£īŃü«õ╣ØÕ║”Õ▒▒Ńā╗ń£¤ńö░Ńā¤ŃāźŃā╝ŃéĖŃéóŃāĀŃü½Ńü”õĖŗĶ©śŃü«õ║īŃüżŃü«Õ▒ĢĶ”¦õ╝ÜŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé Õģ©µŚźµ£¼ÕłĆÕīĀõ╝ÜĶ┐æńĢ┐Õ£░µ¢╣µö»ķā©Õ▒ĢŃĆĆŃĆīµéĀõ╣ģŃü«ńŠÄŃā╗µŚźµ£¼ÕłĆÕ▒ĢŃā╝Ķ┐æńĢ┐Ńü¦µ┤╗Ķ║ŹŃüÖŃéŗÕłĆÕīĀŃü¤ŃüĪŃā╝ŃĆŹ µŚźµ£¼ńŠÄĶĪōÕłĆÕēŻõ┐ØÕŁśÕŹöõ╝ÜÕÆīµŁīÕ▒▒ń£īµö»ķā©Õ▒ĢŃĆĆŃĆīńŠÄĶĪōµŚźµ£¼ÕłĆÕ▒Ģ Ńā╝ń┤ĆÕĘ×ÕłĆÕĘźŃéÆõĖŁÕ┐ā […]
ĶäćÕĘ«ŃĆüķŖśŃĆĆµÆŁńŻ©Õ£ŗõĮÅķ½śĶ”ŗÕ£ŗõĖĆõĮ£õ╣ŗ Õ«łĶŁĘķĀåń£¤ ńÜćń┤Ćõ║īÕŹāÕģŁńÖŠõĖāÕŹüõĖāÕ╣┤ ķČ»ķ│┤ ÕĮ½ńē®ŃĆĆÕż½Õ®”ķŠŹ µóĄÕŁŚ’╝łÕģ½Õż¦ķŠŹńÄŗń£¤Ķ©Ć’╝ē ’╝ō’╝ÖÕø×ńø«Ńü»µ¢░õĮ£ÕłĆŃĆüÕģĄÕ║½ń£īŃü«ķ½śĶ”ŗÕ£ŗõĖĆÕłĆÕīĀŃü«õĮ£ÕōüŃü¦ŃüÖŃĆé’╝łńĀöńŻ©Ńü»ń¦üŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüõ╗źÕēŹµŖ╝ÕĮóŃéƵÄĪŃéēŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤’╝ē Ķ║½Õ╣ģ […]
ŃüōŃü«Õż¬ÕłĆŃü»õ║½õ┐ØÕÉŹńē®Ńü«ķ│źķŻ╝µØźÕøĮµ¼ĪŃü©Ńü©ŃééŃü½ķ╗ÆÕĘØÕÅżµ¢ćÕī¢ńĀöń®ČµēĆŃü½Õ»äĶ┤łŃüĢŃéīŃü¤ÕłĆÕēŻķĪ×Ńü«õĖĆŃüżŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Õż¬ÕłĆŃü»õ║½õ┐ØÕÉŹńē®Ńü«ķ│źķŻ╝µØźÕøĮµ¼ĪŃü©Ńü©ŃééŃü½ķ╗ÆÕĘØÕÅżµ¢ćÕī¢ńĀöń®ČµēĆŃü½Õ»äĶ┤łŃüĢŃéīŃü¤ÕłĆÕēŻķĪ×Ńü«õĖĆŃüżŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Õż¬ÕłĆŃü»ŃĆüõ║½õ┐ØÕÉŹńē®Ńü«ķ│źķŻ╝µØźÕøĮµ¼ĪŃü©Ńü©ŃééŃü½ķ╗ÆÕĘØÕÅżµ¢ćÕī¢ńĀöń®ČµēĆŃü½Õ»äĶ┤łŃüĢŃéīŃü¤ÕłĆÕēŻķĪ×Ńü«õĖĆŃüżŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüéŃüäŃü½ŃüÅŃü«ŃüŖÕż®µ░ŚŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüŠŃü¤Õģźķ╣┐Ńü½ŃüÅŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕć║µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕ£ŗõ┐Ŗ’╝łõ║īÕŁŚÕøĮõ┐Ŗ’╝ē ’╝ō’╝ĢÕø×ńø«Ńü¦ŃüÖŃĆé õ║īÕŁŚÕøĮõ┐ŖŃü«ń¤ŁÕłĆŃü»ŃĆüķĢĘŃéēŃüÅķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃü«µäøµ¤ōÕøĮõ┐Ŗ’╝ł’╝Æ’╝ś’╝Ä’╝Ś’╝ÖŃÄØ’╝ēŃü«Ńü┐Ńü©ŃüĢŃéīŃü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüĶ┐æÕ╣┤Õć║ńÅŠŃüŚŃü¤µ£¼ÕłĆ’╝ł’╝Æ’╝æ’╝Ä’╝ōŃÄØ’╝ēŃüīµ¢░Ńü¤Ńü¬õĖĆÕÅŻŃü©ŃüŚŃü”ÕŖĀŃéÅŃéŗõ║ŗŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüŃüØŃüŚŃü”ŃüØŃü«ń¤ŁÕłĆŃüīõ║¼ķāĮŃü½ŃüéŃéŗŃü© […]
ĶäćÕĘ«ŃĆüķŖśŃĆĆÕźēÕæĮ ńø┤µ▒¤ÕŖ®õ┐Ŗ ÕÉī ÕŖ®õ┐ĪĶ¼╣ķĆĀ’╝łń¤│ÕłćÕŖöń«Łńź×ńżŠĶöĄ’╝ē µģČÕ┐£ÕģāÕ╣┤Õģ½µ£łµŚź ’╝ō’╝öÕø×ńø«ŃĆéÕēŹÕø×Ńü½ńČÜŃüŹŃĆüń¤│ÕłćÕŖöń«Łńź×ńżŠµ¦śŃü«ÕŠĪÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé µ░┤µłĖĶŚ®õ╣Øõ╗ŻĶŚ®õĖ╗ÕŠ│ÕĘص¢ēµśŁŃü»ÕłĆŃéÆķŹøŃüłŃü¤õ║ŗŃü¦Ńééń¤źŃéēŃéīŃĆüŃüØŃü«õĮ£ÕōüŃü«ĶīÄŃü½Ńü»ĶæĄń┤ŗÕ┤®Ńü«ń┤ŗń½ĀŃéÆÕł╗Ńü┐ŃüŠŃüÖŃĆé ĶŚ®õĖ╗µ¢ē […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕéÖÕĘ×ķĢĘĶł╣õĮŵ©¬Õ▒▒ńźÉÕīģ’╝łń¤│ÕłćÕŖöń«Łńź×ńżŠĶöĄ’╝ē µśÄµ▓╗õĖēÕ╣┤Õģ½µ£łµŚź ’╝ō’╝ōÕø×ńø«Ńü»µ¢░ŃĆģÕłĆÕéÖÕēŹŃĆüµ©¬Õ▒▒ńźÉÕīģŃĆé ńźÉÕīģŃü»ńźÉµ░ĖŃü©õĖ”Ńü│ŃĆüµ¢░ŃĆģÕłĆµ£¤Ńü«ÕéÖÕēŹŃéÆõ╗ŻĶĪ©ŃüÖŃéŗÕłĆÕĘźŃü¦ŃüÖŃĆé õĖƵÖéŃü»ĶĪ░ķĆĆŃüŚŃü¤ÕéÖÕēŹķŹøÕåČŃééÕ╣Ģµ£½µ£¤Ńü½Ńü»ÕåŹŃü│ķÜåńøøŃüŚŃĆüõĖƵ┤Šńŗ¼ńē╣Ńü«õĖüÕŁÉŃéÆńä╝ŃüÅńźÉÕīģ […]
ÕłĆŃĆüńäĪķŖś’╝łµźĄķŖśµ£ē’╝ē ’╝ō’╝ÆÕø×ŃĆé ĶīÄŃü½Ńü»ÕÅżŃüäµÖéõ╗ŻŃü«µźĄŃéüķŖśŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüńÅŠõ╗ŻŃü«ķææÕ«ÜŃü¦Ńü»ķüĢŃüåĶ”ŗµ¢╣Ńüīķü®ÕĮōŃüŗŃü©µĆØŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦ĶīÄŃü»õ╝ÅŃüøŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé Õż¦ńŻ©õĖŖŃüÆŃü¦Ķ║½Õ╣ģŃéäŃéäÕ║āŃüÅŃĆüķļķ½śŃüÅŃĆüÕłćŃüŻÕģłŃüīÕ░æŃüŚĶ®░ŃüŠŃéŗķĆĀŃéŖĶŠ╝Ńü┐ŃĆé µŖ╝ÕĮóŃüĀŃüæŃü¦Ńü»õ╝ØŃéÅŃéŖķøŻ […]
Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆƵŁŻµüÆ’╝łÕÅżÕéÖÕēŹ’╝ē ’╝ō’╝æÕø×ńø«Ńü»ÕÅżÕéÖÕēŹµŁŻµüÆŃĆüńö¤ĶīÄÕ£©ķŖśŃü«Õż¬ÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé µŁŻµüÆŃü»ÕÅŗµłÉŃü©õĖ”Ńü│ÕÅżÕéÖÕēŹµ┤ŠŃéÆõ╗ŻĶĪ©ŃüÖŃéŗÕłĆÕĘźŃü¦ŃĆüÕÅżÕéÖÕēŹµ┤ŠŃü«õĖŁŃü¦Ńééńē╣Ńü½ķŹøŃüłŃüīÕä¬ŃéīŃéŗÕłĆÕĘźŃü«õĖĆõ║║Ńü¦ŃüÖŃĆé µŖ╝ÕĮóŃü«µŁŻµüÆŃééŃĆüµØ┐ńø«Ńü½µØóŃüīõ║żŃüśŃéŖŃéłŃüÅĶ®░ŃéĆÕ«ÜĶ®ĢķĆÜŃéŖŃü«Õ£░ķēäŃü¦ŃĆüµśĀ […]
Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕéÖÕēŹÕ£ŗÕ«ŚÕ«ēõĮ£ŃĆĆ(Õż¦ķś¬µŁ┤ÕÅ▓ÕŹÜńē®ķż©ĶöĄ) ’╝ō’╝ÉÕø×ŃĆéÕÅżÕéÖÕēŹµ┤ŠŃĆüÕ«ŚÕ«ēŃĆé ŃüōŃü«Õż¬ÕłĆŃü»ŃĆüÕż¦ķś¬µŁ┤ÕÅ▓ÕŹÜńē®ķż©ķż©ĶöĄÕōüõ┐«ÕŠ®õ║ŗµźŁŃü½µ¢╝ŃüäŃü”ńĀöńŻ©ŃéÆŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé ÕÉīµ┤ŠŃéÆõ╗ŻĶĪ©ŃüÖŃéŗÕłĆÕĘźŃü½ÕÅŗµłÉŃü©µŁŻµüÆŃüīŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕ«ŚÕ«ēŃü»ÕÅŗµłÉŃü«Õ╝¤µł¢ŃüäŃü»ÕŁÉŃü©Ńééõ╝Ø […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüńäĪķŖśŃĆĆń▓¤ńö░ÕÅŻÕēćÕøĮ’╝łķÖäµ£¼ķś┐Õ╝źÕģēÕ┐ĀµŖśń┤Ö’╝ē ’╝Æ’╝ÖÕø×ńø«Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕ▒▒Õ¤Äńē®ŃĆüń▓¤ńö░ÕÅŻŃü¦ŃüÖŃĆé ÕēćÕøĮŃü»ń▓¤ńö░ÕÅŻÕģŁÕģäÕ╝¤Ńü«ķĢĘÕģäŃü¦ŃüéŃéŗÕøĮÕÅŗŃü«ÕŁÉŃü¦ÕøĮÕÉēŃü«ńłČŃü©ŃüäŃéÅŃéīŃĆüµÖéõ╗ŻŃü»ķÄīÕĆēÕēŹµ£¤Ńü¦ŃüÖŃĆé ńÅŠÕ£©ŃĆīń¤ŁÕłĆŃĆŹŃü©ń¦░ŃüĢŃéīŃéŗÕĮóńŖČŃü«ÕłĆŃü»Õ╣│Õ«ēµÖéõ╗Żµ£½µ£¤ķĀāŃü½Ńü»µŚó […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆń▓¤ńö░ÕÅŻĶ┐æµ▒¤Õ«łÕ┐ĀńČ▒ŃĆĆÕĮ½ÕÉīõĮ£ ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕ»│µ░Ėõ║öÕ╣┤Õģ½µ£łµŚź ’╝Æ’╝śÕø×ńø«Ńü»Õż¦ÕØéµ¢░ÕłĆŃĆé ń▓¤ńö░ÕÅŻĶ┐æµ▒¤Õ«łÕ┐ĀńČ▒õ║īõ╗Żńø«ŃĆüõĖĆń½┐ÕŁÉÕ┐ĀńČ▒Ńü¦ŃüÖŃĆé õĖĆń½┐ÕŁÉŃü«õ╣▒ŃéīÕłāŃü»õĖüÕŁÉŃéäµČøõ╣▒ķó©Ńü¬Ńü®ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüµŖ╝ÕĮóŃü«Õłāµ¢ćŃü»õ║ÆŃü«ńø«Ńü½µ╣ŠŃéīŃü©ÕŠīĶĆģŃü«ÕģĖÕ×ŗŃü¦ŃĆüÕĮ½ŃéŖńē®Ńü«ķģŹńĮ«ŃéÆ […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆĶéźÕēŹÕøĮõĮÅķÖĖÕźźÕ«łÕ┐ĀÕÉē ’╝Æ’╝ŚÕø×ńø«ŃĆéÕöÉń¬üŃü½ĶéźÕēŹŃü½µł╗ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé’╝śÕø×ńø«Ńü©ÕÉīŃüśŃüÅÕ┐ĀÕÉēÕ«ČõĖēõ╗Żńø«ŃĆüķÖĖÕźźÕ«łÕ┐ĀÕÉēŃĆé Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü«ŃéłŃüäŃü©ŃüōŃéŹŃéÆŃüéŃüÆŃéŗŃü©ŃüŚŃü¤ŃéēŃĆüŃüŠŃüÜÕ¦┐ŃéƵŖŖµÅĪŃüŚŃéäŃüÖŃüäńé╣ŃüīŃüéŃüÆŃéēŃéīŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé ń¦üŃĆüĶ┐æÕ╣┤Ńü»ÕłćŃüŻÕģłŃü©ĶīÄÕ░╗ŃéÆÕÉīŃüśÕ╣ģŃü¦µŖ╝ […]
ĶäćÕĘ«ŃĆüķŖśŃĆĆķÖĖÕźźÕż¦µÄŠõĖēÕ¢äķĢĘķüō ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕ╗ČÕ«Øõ║öÕ╣┤õ║īµ£łµŚź’╝łµĢĘÕ£░ńź×ńżŠĶöĄ’╝ē ’╝Æ’╝¢Õø×ńø«ŃĆéÕēŹÕø×Ńü½ńČÜŃüŹµĢĘÕ£░ńź×ńżŠ’╝łŃéÅŃéēÕż®ńź×’╝ēµ¦śŃü«ĶöĄÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé ķĢĘķüōŃü«ńź¢ńłČķĢĘÕøĮŃü»Õģāõ╝Ŗõ║łµØŠÕ▒▒ĶŚ®Ńü«ÕłĆÕĘźŃü¦ŃĆüĶŚ®õĖ╗ÕŖĀĶŚżÕśēµśÄŃüīõ╝ܵ┤źŃü½ń¦╗Õ░üŃü©Ńü¬ŃéŖŃüØŃéīŃü½õ╝┤ÕŠōŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗źÕŠīõĖēÕ¢ä […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕéÖÕĘ×ķĢĘĶł╣ńźÉÕģē’╝łµĢĘÕ£░ńź×ńżŠĶöĄ’╝ē ’╝Æ’╝ĢÕø×ńø«Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµĢĘÕ£░ńź×ńżŠµ¦śŃü«ń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé Õ«żńö║µÖéõ╗ŻŃü«ÕéÖÕēŹńē®Ńü»ÕłØµ£¤Õ┐£µ░ĖķĀāŃü«ńē®ŃéÆÕ┐£µ░ĖÕéÖÕēŹŃĆüµ░Ėõ║½ķĀāŃéƵ░Ėõ║½ÕéÖÕēŹŃĆüÕ«żńö║µÖéõ╗ŻŃééÕŠīµ£¤Ńü½ÕģźŃéŗÕ░æŃüŚÕēŹŃĆüÕ┐£õ╗üķĀāõ╗źķÖŹŃü«ńē®ŃéƵ£½ÕéÖÕēŹŃü©Õæ╝ŃéōŃü¦ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ķŖśķææŃü¦ […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕģ╝µśÄ ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆķ½śÕż®ńź×’╝łķ½śÕÅ░Õ»║ĶöĄ’╝ē ’╝Æ’╝öÕø×ńø«ŃĆé ķ½śÕż®ńź×Õģ╝µśÄŃü»ńŠÄµ┐āŃéłŃéŖķüĀÕĘ×Ńü½ń¦╗õĮÅŃüŚŃü¤ÕłĆÕĘźŃü¦ŃĆüÕ«żńö║µÖéõ╗ŻõĖŁµ£¤ŃüŗŃéēµ£½µ£¤Ńü½ŃüŗŃüæÕÉīÕ£░Ńü½Ńü”ĶżćµĢ░Ńü«ÕÉīķŖśÕĘźŃüīõĮ£ÕłĆŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ķ¦┐ķüĀĶ▒åõĖēÕĘ×ÕłĆÕĘźŃü«ńĀöń®Č’╝łµŚźµ£¼ńŠÄĶĪōÕłĆÕēŻõ┐ØÕŁśÕŹöõ╝ÜķØÖÕ▓Īń£īµö»ķā©ńÖ║ […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆń¦Ćµ£½õĮ£ ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆĶ▓×ÕÆīõ║öÕĘ│õĖæ (ÕŹŚÕīŚµ£ØµÖéõ╗Ż) ’╝Æ’╝ōÕø×ńø«ŃĆé ń¦Ćµ£½Ńü»ķŖśķææŃü½Ķ©śĶ╝ēŃüīŃü¬ŃüÅŃĆüµēĆĶ¼éķŖśķææµ╝ÅŃéīŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕÅżµ│óÕ╣│Ńü«ÕłĆÕĘźŃü©Ķü×ŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ķŖśķææŃü½ńäĪŃüäÕłĆÕĘźŃü«õĮ£Ńü½ŃééÕÉŹÕōüŃü»ŃüéŃéŖŃĆüŃüōŃü«ń¤ŁÕłĆŃü¬Ńü®Ńü»µŁŻŃü½ŃüØŃéīŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé 201 […]
Ķ¢ÖÕłĆŃĆĆńäĪķŖśŃĆĆõ╝ØÕÅżµ│óÕ╣│’╝łµ£©õĖŗÕŗØõ┐ŖµēĆńö© / ķ½śÕÅ░Õ»║ĶöĄ’╝ē ’╝Æ’╝ÆÕø×ńø«ŃĆé Õż¦ÕÆīķŹøÕåČŃü»ķÄīÕĆēµ£½µ£¤ŃüŗŃéēÕ«żńö║µÖéõ╗ŻŃü½ŃüŗŃüæŃü”ÕÉäÕ£░Ńü½ń¦╗õĮÅŃüŚŃĆüÕ┐Śµ┤źŃĆüÕ«ćÕżÜŃĆüµĄģÕÅżÕĮōķ║╗ŃĆüńŠÄµ┐āÕŹāµēŗķÖóŃĆüÕģźķ╣┐Ńü¬Ńü®Ńü«õĖƵ┤ŠŃéƵłÉŃüŚń╣üµĀäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüŚŃüŗŃüŚÕ╣│Õ«ēµÖéõ╗ŻŃü«µ£½µ£¤ŃĆüµŚóŃü½ÕŹāµēŗķÖóķŹøÕåČ […]
Õż¦Õż¬ÕłĆŃĆüńäĪķŖśŃĆĆõ╝Øķćæµł┐’╝łµ£¼ĶāĮÕ»║ĶöĄ’╝ē ’╝Æ’╝æÕø×ńø«ŃĆé Õ«żńö║µÖéõ╗ŻŃü«Õż¦ÕÆīńē®Ńü½ķćæµł┐õĖƵ┤ŠŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé ŃüōŃü«µ┤ŠŃü«Ķ®│ń┤░Ńü»õĖŹµśÄŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüµēŗµÄ╗ń│╗Ńü©ŃüäŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé õĮ£ķó©Ńü½Õż¦ÕÆīĶē▓Ńü»Ķ¢äŃüÅŃĆüµ£½ÕéÖÕēŹŃéäµ£½ķ¢óŃĆüÕ╣│ķ½śńö░Ńü¬Ńü®Ńü½õ╝╝ŃéŗõĮ£ŃéÆÕżÜŃüÅĶ”ŗŃüŠŃüÖŃĆé ŃüōŃü«Õż¬ÕłĆŃü»ÕłāķĢĘ […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕż¦ÕÆīÕ£ŗõĮÅÕīģĶĪī ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕ»øµŁŻ’Šå’ŠåÕ╣┤ÕŹüõĖƵ£łµŚź 20Õø×ńø«Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüŠŃü¤Õż¦ÕÆīµ£¼ÕøĮŃü½µł╗ŃéŖŃĆüµ£½µēŗµÄ╗Ńü«ÕīģĶĪīŃü¦ŃüÖŃĆé Õ«żńö║µÖéõ╗ŻŃü½ÕģźŃéŖÕż¦ÕÆīÕÉäµ┤ŠŃü»ĶĪ░ķĆĆŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕ░╗µćĖŃü»ÕēćķĢĘŃü©ķŖśŃü«ŃüéŃéŗÕ«żńö║µ£¤Ńü«ń¤ŁÕłĆŃéƵÖéµŖśńø«Ńü½ŃüŚŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕżÜŃüÅŃü»µĢ░µēōŃüĪŃü© […]
ÕłĆŃĆüńäĪķŖśŃĆĆńø┤µ▒¤Õ┐Śµ┤ź ’╝æ’╝ÖÕø×ńø«Ńü¦ŃüÖŃĆé ÕēŹÕø×Ńü»µēŗµÄ╗Ńü¦ŃüŚŃü¤Ńüīõ╗ŖÕø×Ńü»ńø┤µ▒¤Õ┐Śµ┤źŃĆé Õż¦ÕÆīµēŗµÄ╗Õīģµ░ÅŃüīńŠÄµ┐āÕøĮÕ┐Śµ┤źŃü½ń¦╗õĮÅŃüŚÕģ╝µ░ÅŃü©µö╣ÕÉŹŃĆüķÄīÕĆēµÖéõ╗Żµ£½µ£¤ŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚµ£ØµÖéõ╗ŻŃü½ŃüŗŃüæŃü”µ┤╗Ķ║ŹŃüŚõĖĆķ¢ĆŃüīń╣üµĀäŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«õ║īõ╗Żńø«õ╗źķÖŹÕÅŖŃü│õĖĆķ¢ĆŃü«ńĘÅń¦░Ńüīńø┤µ▒¤Õ┐Śµ┤źŃü¦ŃüÖ […]
ÕłĆŃĆü’╝łķćæĶ▒ĪÕĄīķŖś’╝ēÕīģń£¤ ’╝æ’╝śÕø×ńø«Ńü»Õż¦ÕÆīµēŗµÄ╗Ńü¦ŃüÖŃĆéķćæĶ▒ĪÕĄīķŖśŃü¦Õīģń£¤ŃĆé Õ«żńö║µÖéõ╗ŻŃü«µēŗµÄ╗µ┤ŠŃü«õĮ£ÕōüŃü»µ£½µēŗµÄ╗Ńü©ŃéłŃü░ŃéīŃĆüÕīģń£¤ŃééķĆÜÕĖĖµ£½µēŗµÄ╗Ńü½ÕłåķĪ×ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕīģń£¤ÕłØõ╗ŻŃü»Õīģµ░Ėķ¢ĆŃü¦µÖéõ╗ŻŃéÆÕ║ĘÕ«ē’╝łÕŹŚÕīŚµ£Øµ£¤’╝ēŃü©ŃüäŃüäŃüŠŃüÖŃĆé Õż¦ÕÆīõ║öµ┤ŠŃü»Õ«żńö║µÖéõ╗ŻŃü½Ķ┐æŃüźŃüÅŃü© […]
Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆķĢĘÕÉē’╝łõ╝ØķŠŹķ¢Ć’╝ē ’╝æ’╝ŚÕø×ńø«Ńü»ŃüŠŃü¤Õż¦ÕÆīŃü½µł╗ŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé õ╗ŖÕø×Ńü»õ╝ØķŠŹķ¢ĆŃü©µźĄŃéüŃéēŃéīŃü¤ķĢĘÕÉēõ║īÕŁŚķŖśŃĆüńö¤ĶīÄŃü«Õż¬ÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé ķŠŹķ¢ĆķŹøÕåČŃü»ķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻŃĆüÕż¦ÕÆīÕøĮķŠŹķ¢ĆĶŹśŃü¦ÕŗóÕŖøŃéÆĶ¬ćŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Õż¦Õ»║ķÖóŃĆüķŠŹķ¢ĆÕ»║Ńü½ķ¢óõ┐éŃüÖŃéŗķŹøÕåČŃü©ŃüäŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé’╝łÕźłĶē» […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆõ┐ĪķĢĘ’╝łµĄģÕÅżÕĮōķ║╗’╝ē ┬Ā ’╝æ’╝¢Õø×ńø«ŃĆéõ┐ĪķĢĘŃü©õ║īÕŁŚķŖśŃü¦ŃĆīµĄģÕÅżÕĮōķ║╗ŃĆŹŃü©ķææÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé µĄģÕÅżÕĮōķ║╗Ńü»ŃĆüÕż¦ÕÆīÕøĮµĄģÕÅż’╝łńÅŠÕźłĶē»ń£īµĪ£õ║ĢÕĖ鵥ģÕÅż’╝ēŃü½õĮÅŃüŚŃü¤ÕĮōķ║╗õ┐ĪķĢĘŃüīÕ«żńö║µÖéõ╗ŻÕłØµ£¤ŃĆüĶČŖÕēŹŃü½ń¦╗õĮÅŃüŚõ╗ŻŃéÆķćŹŃüŁŃü¤Ńü©ŃüäŃéÅŃéīŃéŗÕłĆÕĘźŃü¦ŃüÖŃĆé ķŖśķææ […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüńäĪķŖśŃĆĆÕĮōķ║╗(ķÖäµ£¼ķś┐Õ╝źÕģēÕ┐ĀµŖśń┤Ö) 15Õø×ńø«ŃééÕż¦ÕÆīńē®ŃĆéÕĮōķ║╗Ńü¦ŃüÖŃĆé ÕĮōķ║╗µ┤ŠŃü«Õ£©ķŖśõĮ£Ńü»ÕāģÕ░æŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕøĮĶĪīŃĆüµ£ēõ┐Ŗ(ÕɽķĢʵ£ēõ┐Ŗ)ŃĆüÕÅŗĶĪīŃĆüÕÅŗķĢĘŃü¬Ńü®Ńü½ķü║ŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüŠŃü¤ŃĆīÕĮōķ║╗ŃĆŹŃü©Ńü«Ńü┐ķŖśŃéÆÕłćŃéŗõĮ£ÕōüŃééµĢ░ńé╣ńó║Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ŃüØŃéīŃéē […]
ÕłĆŃĆüńäĪķŖśŃĆĆÕ░╗µćĖ ’╝æ’╝öÕø×ńø«Ńü»Õż¦ÕÆīńē®ŃĆüÕż¦ńŻ©õĖŖŃüÆńäĪķŖśŃü«Õ░╗µćĖŃü¦ŃüÖŃĆé ķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻŃüŗŃéēÕŹŚÕīŚµ£ØµÖéõ╗ŻŃü½ŃüŗŃüæŃü”Ńü«Õż¦ÕÆīŃü½Ńü»ŃĆüÕŹāµēŗķÖóŃĆüõ┐صśīŃĆüµēŗµÄ╗ŃĆüÕĮōķ║╗ŃĆüÕ░╗µćĖŃü©õ║öÕż¦µĄüµ┤ŠŃüīŃüéŃéŖŃĆüÕż¦ÕÆīõ║öµ┤ŠŃü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé Õż¦ÕÆīńē®Ńü½Õ£©ķŖśŃü«ÕōüŃü»Õ░æŃü¬ŃüÅŃüØŃü«ÕżÜŃüÅŃüīńäĪķŖśŃü¦ŃüÖ […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕéÖÕĘ×ķĢĘĶł╣µĖģÕģē ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕż®µŁŻõ║īÕ╣┤Õģ½µ£łµŚź 13Õø×ŃĆéõ╗ŖÕø×Ńééµ£½ÕéÖÕēŹŃü«µĖģÕģēŃü¦ŃüÖŃĆé ÕēŹÕø×Ńü«µĖģÕģēŃü»ķļńŁŗŃĆüµŻ¤Ķ¦ÆÕģ▒Ńü½ķćŹŃüŁŃüīķØ×ÕĖĖŃü½ÕÄÜŃüÅŃĆüķćŹķćŵä¤Ńü¤ŃüŻŃüĘŃéŖŃü«ķĆĀŃéŖĶŠ╝Ńü┐Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗ŖÕø×Ńü»ķļķćŹŃüŁŃü»ÕŹüÕłåµ£ēŃéŖŃüŠŃüÖŃüīµŻ¤Ńü½ÕÉæŃüŗŃüäÕ░æŃüŚķćŹŃüŁŃéƵĖøŃüśŃéŗķĆĀŃéŖĶŠ╝Ńü┐Ńüī […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕéÖÕēŹÕ£ŗõĮÅķĢĘĶł╣µĖģÕģē ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆƵ░Ėń”äõ╣ØÕ╣┤õ║īµ£łµŚź ’╝æ’╝ÆÕø×ńø«Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ£½ÕéÖÕēŹŃĆüķĢĘĶł╣µĖģÕģēŃü«ÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé µĖģÕģēŃü»Õ┐ĀÕģēŃü©Ńü¬ŃéēŃü│ńø┤ÕłāŃü«ÕÉŹµēŗŃü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõ╣▒ŃéīÕłāŃü«õĮ£ÕōüŃééÕżÜŃüŵ«ŗŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé µ£½ÕéÖÕēŹŃü½Ńü»ÕÉīÕÉŹÕłĆÕĘźŃüīÕżÜµĢ░ŃüäŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦õ┐ŚÕÉŹŃü½Ńéł […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆƵØæµŁŻ 11Õø×ńø«ŃééÕēŹÕø×Ńü½ńČÜŃüŹµØæµŁŻŃü«ń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃéīŃü»ŃüéŃüŠŃéŖĶü×ŃüŗŃü¬ŃüäŃü©Ķ©ĆŃüäŃüŠŃüÖŃüŗĶü×ŃüäŃü¤õ║ŗŃüīńäĪŃüäŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüń¦üŃü»µØæµŁŻŃü«ńĀöńŻ©Ńü»Õż¦ÕżēķøŻŃüŚŃüäŃééŃü«ŃüĀŃü©µĆØŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéķüÄÕÄ╗Õ║”ŃĆģµØæµŁŻńĀöńŻ©Ńü«µ®¤õ╝ÜŃéÆķĀéŃüäŃü”µØźŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüäŃüÜŃéīŃü«õĮ£ÕōüŃééÕż®ńäČńĀź […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆƵØæµŁŻ ’╝æ’╝ÉÕø×ńø«ŃĆüµØæµŁŻŃü¦ŃüÖŃĆé µØæµŁŻŃü»Õ«żńö║µÖéõ╗Żµ£½µ£¤Ńü«õ╝ŖÕŗóŃü«ÕłĆÕĘźŃü¦µ¢ćõ║ĆŃéÆõĖŖķÖÉŃü½ÕÉīÕÉŹŃü«ńČÖµē┐ŃüīµĢ░õ╗ŻŃüéŃéŗŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüńÅŠÕŁśŃüÖŃéŗµŁŻń£¤Ńü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗķŖśŃü½Ńé鵦śŃĆģŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃü«õ╗ŻÕłźŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ńó║Õø║Ńü¤ŃéŗŃééŃü«Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé ’╝łµ¢ćõ║ĆŃéÆÕłØõ╗ŻŃĆüÕż®µ¢ćŃéÆ […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆĶéźÕēŹÕ£ŗõĮÅõ║║Õ┐ĀÕÉēõĮ£ 9Õø×ńø«ŃĆéµģČķĢʵ¢░ÕłĆŃĆüÕłØõ╗ŻÕ┐ĀÕÉēŃü«ń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé õ║īõ╗ŻĶ┐æµ▒¤Õż¦µÄŠÕ┐ĀÕ╗ŻŃü«ń¤ŁÕłĆŃü»ń©Ćµ£ēŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃéīŃü½µ»öŃüÖŃéŗŃü©ÕłØõ╗ŻŃü«ń¤ŁÕłĆŃü»ÕżÜŃüäŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõ╗¢Ńü«µģČķĢʵ¢░ÕłĆŃĆüõŠŗŃüłŃü░ÕĀĆÕĘØÕøĮÕ║āŃü¬Ńü®Ńü©µ»öŃü╣ŃéŗŃü©µ▒║ŃüŚŃü”ÕżÜŃüÅŃü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéō […]
ĶäćÕĘ«ŃĆüķŖśŃĆĆĶéźÕēŹÕ£ŗķÖĖÕźźÕ«łÕ┐ĀÕÉē 8Õø×ńø«Ńü¦ŃüÖŃĆéÕēŹÕø×Ńü«Ķ┐æµ▒¤Õż¦µÄŠÕ┐ĀÕ╗ŻŃü«Õ½ĪÕŁÉŃĆüÕ┐ĀÕÉēÕ«ČõĖēõ╗ŻŃü«ķÖĖÕźźÕ«łÕ┐ĀÕÉēŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃü«õĖēõ╗ŻÕ┐ĀÕÉēŃü«õĮ£ÕōüŃü»ÕłØõ╗ŻŃĆüõ║īõ╗ŻŃü½µ»öŃü╣ŃéŗŃü©ńÅŠÕŁśµĢ░ŃüīµĀ╝µ«ĄŃü½Õ░æŃü¬ŃüäŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃéīŃü»ķĢĘÕ»┐Ńü¦ŃüéŃüŻŃü¤ńłČŃĆüĶ┐æµ▒¤Õż¦µÄŠÕ┐ĀÕ╗ŻŃü«õ╗ŻõĮ£Ńü½ķĢĘÕ╣┤ÕŠōõ║ŗŃüŚ […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆĶéźÕēŹÕ£ŗõĮÅĶ┐æµ▒¤Õż¦µÄŠĶŚżÕĤÕ┐ĀÕ╗Ż ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕ»øµ¢ćõ║īÕ╣┤ÕŹüõ║īµ£łÕ╗┐õ║īµŚź ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆĶ▓«ŃāāĶā┤µł¬µ¢Ł Õ▒▒ķćÄÕŖĀÕÅ│ĶĪøķ¢Ćµ░Ėõ╣ģ(ĶŖ▒µŖ╝) 7Õø×ńø« ÕłØõ╗ŻÕ┐ĀÕÉēŃü«Õ½ĪÕŁÉŃĆüÕ┐ĀÕÉēÕ«Čõ║īõ╗Żńø«ŃéÆńČÖŃüÉĶ┐æµ▒¤Õż¦µÄŠÕ┐ĀÕ╗ŻŃü«ÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆéÕ┐ĀÕ╗ŻŃü»õĮ£ÕłĆµ£¤ķ¢ōŃüīÕģŁÕŹüÕ╣┤õ╗źõĖŖŃü©ķĢĘŃüÅŃĆüÕżÜŃüÅŃü«õĮ£ÕōüŃéÆ […]
ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆ(ĶÅŖń┤ŗ)õĖ╣µ│óÕ«łÕÉēķüō (õ║¼ķāĮÕĖØķćłÕż®ĶöĄŃĆüÕŹŚõĖ╣ÕĖéń½ŗµ¢ćÕī¢ÕŹÜńē®ķż©Õ»äĶ©ŚÕōü) 6Õø×ńø«Ńü»õĖ╣µ│óÕ«łÕÉēķüōŃĆé ŃüŖŃüØŃéēŃüÅõ║īõ╗ŻŃĆüµł¢ŃüäŃü»õĖēõ╗ŻŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé ńø┤ŃüÉŃü½ķĢĘŃüÅńä╝ŃüŹÕć║ŃüŚŃĆüõ║ÆŃü«ńø«õĖ╗õĮōŃü½µ¦śŃĆģŃü¬ÕłāŃéÆõ║żŃüłŃĆüÕīéŃüäµĘ▒ŃüÅķīĄŃéłŃüÅŃüżŃüŹŃĆüńĀ鵥üŃüŚÕģźŃéŖŃĆüŃüØŃüŚŃü”µ╣» […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖś Õźēń┤ŹĶ│ĆĶīéÕŠĪńżŠŃĆĆÕģāń”äÕŹüõ║īÕ╣┤õĖāµ£łÕŹüõĖēµŚź ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ ķĪśõĖ╗ ķ½śµ®ŗÕ░▒⬜’ĖÄ Õż¦ÕÆīõĮÅĶČŖõĖŁÕ«łÕīģÕ£ŗõĮ£(Ķ│ĆĶīéÕłźķøĘńź×ńżŠĶöĄ) 5Õø×ńø«ŃééŃĆüÕēŹÕø×ŃĆüÕēŹŃĆģÕø×Ńü½ńČÜŃüŹŃĆüĶ│ĆĶīéÕłźķøĘńź×ńżŠ(õĖŖĶ│ĆĶīéńź×ńżŠ)Ńü½õ╝ØŃéÅŃéŗÕźēń┤ŹÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃü«ń¤ŁÕłĆŃü»ķŖśµ¢ćŃü½ […]
Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕģ╝µ░Å’╝łĶ│ĆĶīéÕłźķøĘńź×ńżŠĶöĄ’╝ē ’╝öÕø×ńø«ŃĆé ŃüōŃü«Õż¬ÕłĆŃééÕēŹµÄ▓Ńü½ńČÜŃüŹŃĆüĶ│ĆĶīéÕłźķøĘńź×ńżŠŃüĖŃü«Õźēń┤ŹÕłĆŃü¦ÕøĮµīćÕ«ÜķćŹĶ”üµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃü«ńżŠÕŗÖµŚźĶ¬īŃü½ÕÉīńżŠŃüĖŃü«Õźēń┤ŹĶ©śķī▓Ńüīµ«ŗŃéŗÕōüŃü¦ŃüÖŃĆé Õż¬ÕłĆķŖśŃü¦Õģ╝µ░ÅŃü©ķŖśŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕłĆĶ║½Ńü»Õ«żńö║µÖéõ╗ŻŃü«õĮ£Ńü©µĆØŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆé ŃüŚŃüŗŃüŚ […]
ń¤ŁÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕÉēÕēć’╝łĶ│ĆĶīéÕłźķøĘńź×ńżŠĶöĄ’╝ē ’╝ōÕø×ńø«ŃĆüÕ▒▒Õ¤ÄÕøĮõĖēµØĪÕÉēÕēćõ║īÕŁŚķŖśŃü«ń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé õĖēµØĪÕÉēÕēćŃü»ĶżćµĢ░õ╗ŻŃüéŃéŖŃĆüµŚźķĀāńø«Ńü½ŃüÖŃéŗÕÉēÕēćŃü«µ«åŃü®ŃüīÕ«żńö║µÖéõ╗ŻõĖŁµ£¤õ╗źķÖŹŃü«õĮ£Ńü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃü«ÕŠīõ╗ŻÕÉēÕēćŃü»ÕÉäÕ£░Ńü½ķ¦Éµ¦īŃüŚŃĆüÕÆīµ│ēŃĆüõĖēµ▓│ŃĆüĶČŖÕēŹŃü¬Ńü®Ńü«Õć║ÕģłµēōŃüĪŃéƵ«ŗŃüŚŃü”ŃüäŃüŠ […]
Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕ«łµ¼Ī’╝łÕÅżķØƵ▒¤’╝ē ’╝ÆÕø×ńø«Ńü»ÕÅżķØƵ▒¤Õ«łµ¼ĪŃü«Õż¬ÕłĆŃĆé ķĢĘÕ»ĖŃü¦ÕÅŹŃéŖµĘ▒ŃüÅŃĆüńö¤ĶīÄÕ£©ķŖśŃĆüÕĀéŃĆģŃü©ŃüŚŃü¤Õż¬ÕłĆÕ¦┐Ńü¦ŃüÖŃĆé ńÅŠÕ£©Ńü¦ŃééÕŹüÕłåµēŗµīüŃüĪŃü«ķćŹŃüäÕż¬ÕłĆŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüĶīÄŃü«Õ╣ģŃéäķćŹŃüŁŃüŗŃéēŃĆüÕģāµØźŃü»ŃüŗŃü¬ŃéŖŃü«Ķ▒¬ÕłĆŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤õ║ŗŃüīµā│ÕāÅŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
Õż¬ÕłĆŃĆüķŖśŃĆĆÕēćńĖä’╝łń”ÅÕ▓ĪõĖƵ¢ćÕŁŚ’╝ē ķĢĘŃéēŃüÅńĀöńŻ©Ķ©śķī▓ŃāÜŃā╝ŃéĖŃüĖŃü«µŖ╝ÕĮó’╝Ą’╝░ŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµ║¢ÕéÖŃüīÕć║µØźŃü¤ŃééŃü«ŃüŗŃéēķĀåµ¼Ī’╝Ą’╝░ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé ŃüŠŃüÜŃü»Ńā¢ŃāŁŃé░ŃāÜŃā╝ŃéĖŃü½ŃĆé ’╝æÕø×ńø«Ńü»ń”ÅÕ▓ĪõĖƵ¢ćÕŁŚÕēćńĖäŃü«Õż¬ÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé ńö¤Ńü¦ķøēĶģ┐ĶīÄŃĆé Ķģ░ÕÅŹŃéŖŃü«Õż¬ÕłĆ […]
µ░ŚŃüīõ╗śŃüäŃü¤ŃéēõĖĆŃāĄµ£łõ╗źõĖŖµø┤µ¢░ŃüŚŃü”ŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé µŚźŃĆģńĀöńŻ©Ńü½ÕŗżŃüŚŃéōŃü¦ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé ÕģłµŚźŃĆüÕż®ńäČŃü«ÕÉŹÕĆēŃü©ń┤░ÕÉŹÕĆēŃü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗńĀźń¤│ŃéÆķĀ鵳┤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé Õż¦ÕżēĶ▓┤ķćŹŃü¬ń¤│Ńü¦µ£ēķøŻŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé õĖŁŃĆüń┤░ÕÉŹÕĆēŃü»Õģ½Õ╣┤ķ¢ōŃü╗Ńü®Õż®ńäČŃéÆõĮ┐ŃüŻŃü”ŃüäŃü¤µÖéµ£¤ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü« […]
Õ┐£µ░Ėń¦╗õĮÅń│╗õ┐ĪÕøĮŃéÆķŗĖŃü¦ÕłćŃüŻŃü”ŃüäŃü”ŃĆüÕēŹŃüŗŃéēńó║Ķ¬ŹŃüŚŃü”Ńü┐Ńü¤ŃüŗŃüŻŃü¤õ║ŗŃéÆÕ░æŃüŚŃĆé ńö╗ÕāÅ’╝æ Õ░æŃĆģńĀöŃüÄŃü«Õć”ńÉåŃüīõĖŹÕŹüÕłåŃüĀŃüīŃĆüµ£¼Ńü¬Ńü®Ńü¦Õ║”ŃĆģĶ”ŗŃéŗÕłĆĶ║½µ¢ŁķØóŃĆé ŃüōŃü«µēŗŃü«ńö╗ÕāÅŃü»ÕłĆĶ║½µ¦ŗķĆĀŃü«Ķ¦ŻĶ¬¼Ńü¬Ńü®Ńü¦ŃéłŃüÅĶ”ŗŃüŗŃüæŃéŗŃüīŃĆüńĖ”µ¢╣ÕÉæŃü«µ¢ŁķØóŃéÆĶ”ŗŃü¤Ńüŵ¼ĪŃü«ÕŖĀÕĘźŃéÆŃĆé ńö╗ÕāÅ […]
ńĀöŃüÄõĖŖŃüÆŃü¤Õ£©ķŖśŃü«ÕÅżõĖƵ¢ćÕŁŚŃĆéĶģ░Ńü«Õ┤®Ńéīµ¢╣ŃüīĶĪ©ĶŻÅÕģ▒Õ▒▒ķ│źµ»øŃü½Õ░æŃüŚõ╝╝ŃéŗŃĆé õ╗źÕēŹµÆ«ŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ń▓ŚŃüäµÉ║ÕĖ»ńö╗ÕāÅŃü¦ŃüÖŃüīŃĆé ŃüōŃü«Õ┤®Ńéīµ¢╣ŃĆüõ╝╝Ńü¤ńŚćńŖČŃü¦ķØóńÖĮŃüäŃĆéŃüīŃĆüÕÉīŃüśõĮ£ĶĆģŃüĀŃü©Ķ©ĆŃüäŃü¤ŃüäŃéÅŃüæŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé
ń¤ŁÕłĆŃĆüõ╣ØÕ»Ėõ║öÕłåŃĆé ķŖśŃĆƵ¢╝µØ▒õ║¼ķ½śĶ╝¬õ╗źńŹ©ķĆĖķŗ╝ķēä ĶāżÕŗØ ŃĆĆŃĆƵśÄµ▓╗õĖēÕŹüÕģŁÕ╣┤õ║öµ£ł ŌĆØŃāēŃéżŃāäķŗ╝ķēäŌĆØŃĆéÕćäŃüäķ¤┐ŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆé õ╗ŖŃüŠŃü¦ńĀöńŻ©ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüäŃü¤õĖŁŃü«ńĪ¼ŃüĢµ£ĆÕ╝ĘÕłĆŃü»ŃĆüõ║¼ķāĮÕøĮń½ŗÕŹÜńē®ķż©ĶöĄŃü«ń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüŚŃü¤’╝łķŖśŃĆĆÕż¦ķś¬õĮÅķ½śµ®ŗµÖ┤ķø▓ÕŁÉõ┐Īń¦ĆõĖāÕŹüõ║öµŁ│õĮ£ŃĆƵ¢╝õ║¼ķāĮÕĖØÕøĮ […]
õĖĆÕÅĘŃĆĆÕłĆ ÕÅŹŃéŖÕ░æŃüŚµĘ▒ŃüäŃĆéÕģ©õĮōŃü½ÕÅŹŃéŗŃĆéĶ║½Õ╣ģÕ║āŃüÅķćŹŃüŁÕÄÜŃéüŃĆéµŻÆµ©ŗķÄ║õĖŖõĖĖńĢÖŃéüŃĆéÕłćŃüŻÕģłŃāĢŃé»Ńā®Õ╝ĘŃéüŃü½Õ╝ĄŃéŗŃĆé Õ£░ķēäĶ®░Ńü┐µ░ŚÕæ│Ńü¦ĶŗźÕ╣▓Ķéīń½ŗŃüżŃĆé Õ║āŃéüŃü«õĖŁńø┤ÕłāŃĆéÕłāõĖŁŃĆüõĖüÕŁÉĶČ│ŃĆüĶæēŃüīÕżÜŃüÅÕģźŃéŗŃééÕ░æŃüŚÕ»éŃüŚŃüŵä¤ŃüśŃéŗŃĆéõĖŗÕŹŖÕīéŃüäÕŗØŃüĪŃĆéõĖŖÕ░ÅķīĄŃĆéÕĖĮÕŁÉµĘ▒ŃéüŃĆéńĄÉµ¦ŗ […]
Õģāń”äÕ╣┤ń┤ĆŃü«ĶäćÕĘ«ŃĆé ĶīÄŃü½Ńü»ŃééŃüĪŃéŹŃéōŃü«ŃüōŃü©ŃĆüÕ╣│Õ£░ŃĆüµŻ¤ŃĆüÕłāÕģłŃü½ŃééÕłĆķŹøÕåČŃü«µÄøŃüæŃü¤ķæóŃüīŃüØŃü«ŃüŠŃüŠŃü«ńŖȵģŗŃü¦µ«ŗŃéŗŃĆüµēĆĶ¼éŌĆØĶŹÆĶ║½ŌĆØŃĆüµēōŃüĪŃüŖŃéŹŃüŚŃü«Õ╣│ĶäćÕĘ«Ńü¦ŃüÖŃĆé ķĆÜÕĖĖŃü»ŃüōŃü«ńŖȵģŗŃüŗŃéēńĀöÕĖ½Ńü½ŃüŠŃéÅŃüĢŃéīńĀöńŻ©ŃéÆĶĪīŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü«ĶäćÕĘ«Ńü»Õģāń”äÕ╣┤ķ¢ōŃü½ÕłĆķŹøÕåČŃüīńä╝ŃüŹ […]
https://youtu.be/a4n_14nhGrI µśĀńö╗ŃĆīńćāŃüłŃéłÕēŻŃĆŹŃü«Ķ®”ÕåÖõ╝ÜŃü½ŃéłŃéōŃü¦ķĀéŃüŹĶĪīŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé Õģ¼ķ¢ŗŃü»ŃüŠŃüĀŃüŚŃü░ŃéēŃüÅÕģłŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕćäŃü䵜Āńö╗Ńü¦ŃüÖŃĆé ┬ĀµśĀńö╗ŃĆīńćāŃüłŃéłÕēŻŃĆŹÕģ¼Õ╝ÅŃéĄŃéżŃāł
õĖĆÕÅĘŃĆĆÕłĆ ÕÅŹŃéŖµĄģŃüÅķćŹŃüŁÕÄÜŃĆüÕ║ĄµŻ¤ŃüŗŃü¬ŃéŖķ½śŃüäŃĆéĶ®░ŃéōŃü¦ńŠÄŃüŚŃüäÕ£░ķēäŃĆéÕģ©õĮōŃü½µ╣ŠŃéīŃéŗÕłāÕÅ¢ŃéŖŃü¦ķĆÅŃüŗŃüÖŃü©õ║ÆŃü«ńø«Ńü©õĖüÕŁÉŃü«ķĆŻńČÜŃĆéńä╝ŃüŹķĀŁŃüīÕ£░Ńü½ŃüōŃü╝ŃéīŃéŗń«ćµēĆÕżÜµĢ░ŃĆé Õ£░ÕłāŃüīÕģĖÕ×ŗńÜäÕŖ®ńø┤ŃüĀŃü©µĆØŃüåŃüīµŻ¤Ńü«ķ½śŃüĢŃüīŃü®ŃüåŃüŚŃü”Ńééµ░ŚŃü½Ńü¬ŃéŗŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆéÕŖ®ńø┤ŃĆüµĢ░ŃééÕɽŃéüµÖ«µ«Ą […]
ÕźłĶē»ŃĆüµśźµŚźÕż¦ńżŠŃüĢŃéōŃü«ÕøĮիص«┐Ńü½µ¢╝ŃüŹŃüŠŃüŚŃü”ŃĆüŃĆĵ£ĆÕÅżŃü«µŚźµ£¼ÕłĆŃü«õĖ¢ńĢī Õ«ēńČ▒Ńā╗ÕÅżõ╝»ĶĆåÕ▒ĢŃĆÅŃüīķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü¦ŃüÖŃĆé ń¦üŃééÕÅżõ╝»ĶĆåŃü½Ńü»Õż¦ÕżēĶłłÕæ│ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½Õ▒Ģńż║õĖŁŃü«µ£ēńČ▒’╝łń▓¤µ┤źÕ«Čõ╝ØµØź’╝ēŃü«Õż¬ÕłĆŃüīÕż¦ÕźĮŃüŹŃü¦ŃĆé Õ▒Ģńż║Ńü»ÕēŹÕŠīµ£¤ÕģźŃéīµø┐ŃüłŃüéŃéŖŃü¦ŃüÖŃĆé ŃĆĆÕ▒Ģńż║Ńā¬Ńé╣ […]
ķÄīÕĆēµ£½µ£¤ Õ╝ĘŃüÅŃĆüÕż¦ÕżēĶē»ŃüäÕ£░ķēäŃĆéÕłāŃü«ķīĄŃééńŠÄŃüŚŃüÅŃĆüķćæńŁŗÕżÜµĢ░ŃĆé ÕēŹµÄ▓ń¤ŁÕłĆŃü½ńČÜŃüŹÕÉŹń¤ŁÕłĆŃü¦ŃüÖŃĆé
ķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻÕēŹµ£¤ŃĆé Ńé╣Ńā×ŃāøŃü¦ĶŗźÕ╣▓ÕłćŃüŻÕģłµ¢╣ÕÉæŃüŗŃéēµÆ«ŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ÕłćŃüŻÕģłÕü┤ŃüīÕż¦ŃüŹŃüÅķ¢ŗŃüäŃü”Ķ”ŗŃüłŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕ«¤ķÜøŃü»ŃééŃüåÕ░æŃüŚŃüĀŃüæķ¢ēŃüśŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé Ńü½ŃüŚŃü”Ńééµ£ĆĶ┐æŃü»ńäĪÕÅŹŃéŖń¤ŁÕłĆŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕ░æŃüŚÕģłķ¢ŗŃüŹŃü½Ķ”ŗŃüłŃéŗķģŹńĮ«Ńü¦Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃü«µÄĪµŗōŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé Õģ© […]
Õ╣┤µ£½ŃüŗŃéēķÄīÕĆēµ£½µ£¤Õż¦ńŻ©õĖŖńäĪķŖśÕłĆŃĆüķÄīÕĆēÕłØµ£¤ńö¤ĶīÄÕ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃĆüķÄīÕĆēÕēŹµ£¤õ╣āĶć│õĖŁµ£¤ńö¤ĶīÄÕ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃĆüÕ«żńö║µ£½µ£¤Õ£©ķŖśÕ»ĖÕ╗ČŃĆüÕ«żńö║µ£½µ£¤Õ£©ķŖśń¤ŁÕłĆŃü«µŖ╝ÕĮóŃéƵÅÅŃüÅŃĆé Ķē▓ŃĆģĶĆāŃüłŃü¬ŃüīŃéēµÅÅŃüäŃü”ŃüäŃü¤ŃüīŃĆüÕż¦õĮōŃü«õ║ŗŃü»Õ┐śŃéīŃü¤ŃĆé
µ£¼µŚźŃü»ŃüŖÕ«óµ¦śŃüīŃüŖĶČŖŃüŚõĖŗŃüĢŃéŖŃĆüń¤ŁÕłĆŃéäÕēŻŃéÆÕżÜµĢ░ķææĶ│×ŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé õ║ŗÕēŹŃü½ŃĆüŃüĪŃéćŃüŻŃü©ńÅŹŃüŚŃüäķćŹÕłĆŃü«ń¤ŁÕłĆŃéƵŗØĶ”ŗŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüæŃéŗŃü©Ńü«ŃüŖĶ®▒ŃéÆŃüŖĶü×ŃüŹŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüĶē▓ŃĆģŃü©µā│ÕāÅŃéÆŃā╗Ńā╗Ńā╗ŃĆé Ńü®Ńü«µ¢╣ÕÉæŃüŗŃü©Ńü«µāģÕĀ▒ŃüīõĖĆÕłćŃü¬ŃüÅŃĆüŃüĪŃéćŃüŻŃü©ńÅŹŃüŚŃüäŃü©Ńü¬ […]
õ╗żÕÆī’╝ÆÕ╣┤Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé µ£¼Õ╣┤ŃééŃü®ŃüåŃü×ŃéłŃéŹŃüŚŃüÅŃüŖķĪśŃüäńö│ŃüŚõĖŖŃüÆŃüŠŃüÖŃĆé ŃüŖµŁŻµ£łŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃü¦ŃĆüńø«ń½ŗŃüżÕĀ┤µēĆŃü½µäøÕłĆŃéÆķŻŠŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé õĖŁĶ║½Ńü»ÕłĆÕ▒ŗŃüĢŃéōŃü¦’╝śõĖćÕååŃü¦Ķ▓ĘŃüŻŃü¤ÕłĆŃĆé ķØ×ÕĖĖŃü½µäøńØĆŃüīŃüéŃéŖŃĆüµŗĄŃüłŃéƵÄøŃüæŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé µŗĄŃüłŃü«Ķ”ŗµēĆŃü»µ▓óÕ▒▒ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõĖĆńĢ¬ […]
µēŗµīüŃüĪŃü«ń¤ŁÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéÆÕźłĶē»Ńü«ķ¢óÕ▒▒ńĀöÕĖ½Ńü½µÅÅŃüäŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃééŃüå’╝æ’╝ÉÕ╣┤Ķ┐æŃüÅÕēŹŃüŗŃéēŃĆüķ¢óÕ▒▒ńĀöÕĖ½Ńü«µÅÅŃüÅÕłāµ¢ćŃüīõĖĆńĢ¬ÕźĮŃüŹŃü¬ŃéōŃü¦ŃüÖŃĆé ķø░Õø▓µ░ŚŃéÆń£¤õ╝╝ŃéłŃüåŃü©ŃüÖŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīÕÉīŃüśŃü½Ńü»Ńü¬ŃéēŃüÜŃĆüÕ┐ģŃüÜĶć¬ÕłåŃü«ķø░Õø▓µ░ŚŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃĆé ń£¤õ╝╝ŃéŗŃü¬ŃéēŃéä […]
ńäĪķŖśÕÅżõĖƵ¢ćÕŁŚŃĆüÕ£©ķŖśÕÅżõĖƵ¢ćÕŁŚŃĆüńäĪķŖśń”ÅÕ▓ĪõĖƵ¢ćÕŁŚŃü¬Ńü®ŃéƵŗØĶ”ŗŃĆé ÕÅżõĖƵ¢ćÕŁŚŃü«ÕźźŃéåŃüŗŃüŚŃüĢŃüīÕźĮŃüŹŃü¦ŃĆüµŗØĶ”ŗŃüÖŃéŗÕ║”Ńü½ÕéÖÕēŹÕłĆŃü«ÕćäŃüĢŃéƵä¤ŃüśŃéŗŃĆé ŃüōŃü«ń”ÅÕ▓ĪõĖƵ¢ćÕŁŚŃü»õ║īÕø×ńø«ŃĆéõĖĆÕ║”ńø«ŃéłŃéŖŃééķüźŃüŗŃü½ŃéłŃüäÕż¬ÕłĆŃüĀŃü©µä¤ŃüśŃü¤ŃĆéÕÅżÕéÖÕēŹŃéäÕÅżõĖƵ¢ćÕŁŚŃü«µ¢╣Ńüīń¦üŃü»ÕźĮŃü┐Ńü¬Ńü«Ńü¦ […]
ŃüĪŃéćŃüŻŃü©õ╣ģŃĆģŃü½µŖ╝ÕĮóŃéƵÅÅŃüÅŃĆé ÕÅżķØƵ▒¤ńö¤ĶīÄÕ£©ķŖśÕż¬ÕłĆŃĆé ÕÅŹŃéŖŃüīµĘ▒ŃüäŃĆ鵜ĀŃéŖŃüīÕćäŃüäŃĆéķćŹŃüŁŃüīķØ×ÕĖĖŃü½ÕÄÜŃüäŃĆé
Õ»ÆŃüÅŃü¬ŃéŗÕēŹŃü½ÕłāĶēČŃéÆŃĆé ÕēŹÕø×Ńü»ŃüäŃüżķĀāõĮ£ŃüŻŃü¤ŃüŗŃü©µĆØŃüäŃĆüŃā¢ŃāŁŃé░Ńü¦ńó║Ķ¬ŹŃüÖŃéŗŃü©ń┤ä’╝æÕ╣┤ÕēŹŃĆé ÕēŹÕø×ŃééÕÉīń©ŗÕ║”Ńü«ķćÅŃéÆõĮ£ŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦Õż¦õĮōõĖĆÕ╣┤Ńü¦ŃüōŃéīŃüÅŃéēŃüäŃü«µČłĶ▓╗Ńü¦ŃĆüÕłāĶēČŃü«µČłĶ▓╗ķćÅŃü»ÕżÜŃüäŃé┐ŃéżŃāŚŃü«ńĀöÕĖ½ŃüĀŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüÖŃĆé Ķ”ŗŃü¤ńø«Ńü»µé¬ŃüäŃüīŃüōŃü«ń¤│Ńü»ńó║Õ«¤Ńü½Ķē»ŃüäŃü©ńó║ […]
ŃüØŃüåŃüäŃüłŃü░ŃĆüÕģłµŚźŃü«ķææÕ«ÜÕłĆ’╝ĢÕÅĘŃĆüÕ«īÕģ©Ńü¬µ¤Šńø«Ńü½µ┤ŠµēŗŃü¬õĖüÕŁÉÕłāŃĆé µÖ«ķĆÜŃü¬Ńéēµ¤ŠĶéīŃü½Õłāµ¢ćŃüīÕ╝ĢŃüŻÕ╝ĄŃéēŃéīŃĆüÕīéŃüäÕÅŻŃüīµ¤Šńø«Ńü¦ÕłćŃéēŃéīķŻ¤ŃüäķüĢŃüäŃü«ÕāŹŃüŹŃüīńÅŠŃéīŃü¤ŃéŖŃĆüńĀ鵥üŃüŚńŖČŃü½Ńü¬ŃéŗŃü¬Ńü®Ńü«ńÅŠĶ▒ĪŃüīĶĄĘŃüōŃéŗŃü©ŃüōŃéŹŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«µ¦śŃü¬ń«ćµēĆŃü»õĖĆÕłćŃü¬ŃüÅŃĆüÕłāõĖŁŃü½µ¤ŠńŖČŃü«Õīé […]
õ╗ŖÕø×Ńü»µ£¼ķā©ŃéłŃéŖµŚźķćÄÕÄ¤Õż¦Õģłńö¤ŃéÆĶ¼øÕĖ½Ńü½ŃüŖĶ┐ÄŃüłŃüŚÕģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝ÜŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé õĖĆÕÅĘŃĆĆÕłĆ ķćŹŃüŁÕÄÜŃéüŃĆüĶŗźÕ╣▓ń┤░Ķ║½Ńü¦ķļŃüīķ½śŃüäŃĆéÕÅŹŃéŖŃüīµĄģŃüäŃüīķÄīÕĆēµÖéõ╗ŻŃü«ÕłĆŃĆé ńø┤ÕłāĶ¬┐ÕŁÉŃĆéŃéłŃüÅÕāŹŃüÅŃĆ鵜ÄŃéŗŃüäŃĆéńē®µēōŃüŗŃéēµ©¬µēŗõĖŗŃü«Õå┤ŃüłŃüīÕźĮŃüŹŃĆéńēćĶÉĮŃüĪķó©Ńü½Ńü¬Ńéŗķā©ÕłåŃü«Ķ░ĘŃü¬ […]
ń¼¼õĖĆÕø×ńÅŠõ╗ŻÕłĆńø«Õł®ŃüŹĶ¬ŹÕ«ÜÕż¦õ╝ÜŃü½ÕÅéÕŖĀŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ķææÕ«ÜÕłĆŃü»’╝ō’╝ɵī»ŃéŖŃĆé ÕłČķÖɵÖéķ¢ō2µÖéķ¢ōŃü«õĖƵ£¼Õģźµ£ŁŃĆé ÕĮōńäČŃü¦ŃüÖŃüīÕć║ķĪīÕłĆÕĘźŃü«õ║ŗÕēŹńÖ║ĶĪ©Ńü»ńäĪŃüŚŃü¦ŃüÖŃĆé 1’Į×24ÕÅĘŃüīÕż¬ÕłĆŃā╗ÕłĆŃĆü25’Į×30ÕÅĘŃüīń¤ŁÕłĆŃü©ÕēŻŃĆé õĖŁŃü½õĖƵī»ŃéŖŃĆüõ║║ķ¢ōÕøĮÕ«ØŃü«µĢģÕ««ÕģźĶĪī […]
ńÅŠõ╗ŻÕłĆńø«Õł®ŃüŹĶ¬ŹÕ«ÜÕż¦õ╝ÜŃü«µŚźŃüīĶ┐æŃüźŃüäŃü”ŃüŠŃüäŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤’╝ü ŃĆīµŚźµ£¼ÕłĆŃü«µŚźŃĆŹÕłČÕ«ÜĶ©śÕ┐ĄŃĆÄń¼¼1Õø×ŃĆīńÅŠõ╗ŻÕłĆńø«Õł®ŃüŹĶ¬ŹÕ«ÜÕż¦õ╝ÜŃĆŹinÕ▓ĪÕ▒▒ŃĆÅ10/5(Õ£¤) Õć║ķĪīÕłĆŃü»Ńü¬ŃéōŃü©’╝ō’╝ɵī»ŃéŖŃĆé ’╝ō’╝ɵī»ŃéŖŃü«ńÅŠõ╗ŻÕłĆŃéƵēŗŃü½µīüŃüŻŃü”ķææĶ│×Ńü¦ŃüŹŃéŗŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüØŃüŚŃü”ŃüØŃü«ÕłĆŃü¦ […]
õĖĆÕÅĘŃĆĆÕłĆŃĆüŃüĀŃü©µĆØŃüåŃĆé Õ░æŃüŚÕÅŹŃéŖµ░ŚÕæ│ŃĆéńø┤Ķ¬┐ÕŁÉŃü¦Ńü¬ŃüĀŃéēŃüŗŃü½µ╣ŠŃéīŃĆéÕģ©õĮōŃü½Õ░ÅĶČ│ŃüīÕģźŃéŖķĀŁŃü«ńĘĀŃüŠŃéŗÕ░Åõ║ÆŃü«ńø«Ķ¬┐Ńü«ÕłāŃĆéõĖŁķŗÆŃĆ鵜ĀŃéŖŃĆé Ńü▒ŃüŻŃü©Ķ”ŗŃü»µ£½ÕÅżÕłĆŃü½Ķ”ŗŃüłŃéŗŃĆéÕģāµØźŃü»Ķ®░Ńü┐µ░ŚÕæ│Ńü«Õ£░ķēäŃĆéÕÉäµēĆŃü½µŠäĶéīķó©Ńü½ķ╗ÆŃüäķēäŃüīõĖƵ«ĄńøøŃéŖõĖŖŃüīŃüŻŃü”ÕŁśÕ£©ŃĆé Ķ┐ĘŃüåŃü«Ńü¦õĖĆ […]
ICOMõ║¼ķāĮÕż¦õ╝ÜŃü«õĖĆńÆ░Ńü¦ŃĆüµ£¼ĶāĮÕ»║ŃüĢŃéōŃü«Õż¦Õ«Øµ«┐Ńü½Ńü”Õ╝¤ÕŁÉŃü«Ńā×Ńā╝ŃāåŃéŻŃā│ÕÉøŃü©ÕłĆÕēŻńĀöńŻ©Õ«¤µ╝öŃéÆŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ’╝łÕ«¤µ╝öńö©Ńü½µ£¼ĶāĮÕ»║ĶöĄÕōüŃü«Ķ¢ÖÕłĆŃéÆń¬ōķ¢ŗŃüæńĀöńŻ©õĖŁ’╝ē µŚźµ£¼Ńü«ÕłĆÕēŻµäøÕźĮÕ«ČŃüĢŃéōŃéäÕżÜŃüÅŃü«µĄĘÕż¢Ńü«ÕŁ”ĶŖĖÕōĪŃüĢŃéōķüöŃüīŃüöµØźÕĀ┤ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé Ńā× […]
ŃĆīICOMõ║¼ķāĮÕż¦õ╝Üķ¢ŗÕé¼Ķ©śÕ┐Ą┬Ā µØ▒õ║¼Õ»īÕŻ½ńŠÄĶĪōķż©µēĆĶöĄ ┬Ā“ńÖŠĶŖ▒ń╣Üõ╣▒ ŃāŗŃāāŃāØŃā│├ŚŃāōŃéĖŃāźŃāäÕ▒Ģ”ŃĆŹ ķ¢ŗÕé¼ŃéÆŃüŖµĢÖŃüłķĀéŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüõ║¼ķāĮµ¢ćÕī¢ÕŹÜńē®ķż©Ńü¦9µ£ł29µŚźŃüŠŃü¦ĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆīńÖŠĶŖ▒ń╣Üõ╣▒ŃĆĆŃāŗŃāāŃāØŃā│├ŚŃāōŃéĖŃāźŃāäÕ▒ĢŃĆŹŃéÆĶ”ŗŃü½ […]
ŃüŖńøåŃééŃüÜŃüŻŃü©ŃüŖõ╗Ģõ║ŗŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ķ¢ōŃüīń®║ŃüäŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīÕģłµŚźŃü«Ķ¢ÖÕłĆÕģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃüīÕ«īµłÉŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüØŃü«ÕŠīŃĆüµ¢░ÕłĆõĖēÕōüŃü«Õģ©Ķ║½µŖ╝ÕĮóŃéƵÅÅŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüōŃü«ÕģäÕ╝¤ķüöŃü«õĮ£ÕōüŃü»µ▓óÕ▒▒µ«ŗŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüńÜåµ£¼ÕĮōŃü½õĖŖµēŗŃüäŃĆé µ▓óÕ▒▒µ«ŗŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦ķĀ╗ń╣üŃü½Ķ”ŗŃéŗŃéÅŃüæ […]
Õż¦Ķ¢ÖÕłĆŃü«Õģ©Ķ║½ŃéƵÅÅŃüäŃü¤ŃĆé ÕĘ”Ńü»õ║īÕ░║ÕøøÕ»ĖĶČģŃü«ÕłĆŃĆé ŃüØŃüŚŃü”µ¼ĪŃééĶ¢ÖÕłĆŃĆé ŃüōŃü«µ¼ĪŃééÕģ©ķĢĘõ║öÕ░║ŃéÆĶČģŃüłŃéŗĶ¢ÖÕłĆŃüĀŃü©µĆØŃüåŃĆé
õ║¼ķāĮÕŠĪµēĆĶ┐æŃüÅŃü«ŃüĪŃéćŃüŻŃü©ńŠÄÕæ│ŃüŚŃüäĶĢÄķ║”Õ▒ŗŃü½ÕģźŃüŻŃü¤ŃéēńĀźń¤│ŃüīķŻŠŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé Ķ¦”ŃüŻŃü”Ńü┐ŃüĪŃéāŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕżÜÕłåõĖŁÕ▒▒ŃüŗŃü¬ŃüüŃĆéŃéłŃüÅõ╝╝Ńü¤ń¤│Ńü»Ķē▓ŃéōŃü¬Õ▒▒ŃüŗŃéēÕć║ŃéŗŃü«Ńü¦µ¢ŁÕ«ÜŃü»Õć║µØźŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆé µ¤öŃéēŃüŗŃü䵳ĖÕēŹŃü¦ŃüÖŃĆé Õ║ŚÕōĪŃüĢŃéōŃü½Ķü×ŃüÅŃü©ŃĆüŃüŖÕ«óŃüĢŃéōŃüŗŃéēķĀéŃüä […]
ńÅŠÕ£©Õ▓Éķś£ń£īÕŹÜńē®ķż©Ńü½µ¢╝ŃüŹŃüŠŃüŚŃü”ŃĆÄńē╣ÕłźÕ▒ĢŃĆīÕēŻń▓Šķ£ŖĶ▓½ńÖĮĶÖ╣ŃĆĆŌĆĢÕ╣Ģµ£½ńŠÄµ┐āŃü«ÕēŻĶ▒¬Ńü©ÕÉŹÕłĆŌĆĢŃĆŹŃĆÅŃüīķ¢ŗÕé¼õĖŁŃü¦ŃüÖ’╝ü Õ▒ĢĶ”¦õ╝ÜÕÉŹ ńē╣ÕłźÕ▒ĢŃĆīÕēŻń▓Šķ£ŖĶ▓½ńÖĮĶÖ╣’╝łŃüæŃéōŃü«ŃüøŃüäŃéīŃüäŃü»ŃüŻŃüōŃüåŃéÆŃüżŃéēŃü¼ŃüÅ’╝ēŌĆĢÕ╣Ģµ£½ńŠÄµ┐āŃü«ÕēŻĶ▒¬Ńü©ÕÉŹÕłĆŌĆĢŃĆŹ ķ¢ŗÕé¼µ£¤ķ¢ō ’╝Æ’╝É’╝æ’╝ÖÕ╣┤’╝Śµ£ł’╝æ’╝ƵŚź […]
õ╗Ŗµ£łŃü«µö»ķā©õŠŗõ╝Ü’╝łÕģźµ£ŁķææÕ«Üõ╝Ü’╝ēŃü»ń¦üŃüīµŗģÕĮōŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃü¦ŃĆüķææÕ«ÜÕłĆŃéÆ5µī»ŃéŖµ║¢ÕéÖŃüĢŃüøŃü”ķĀéŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé õĖĆÕÅĘŃĆĆÕż¬ÕłĆŃĆĆŃĆĆķŖśŃĆĆÕøĮńČ▒’╝łń▓¤ńö░ÕÅŻŃĆĆńē╣ÕłźķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ē õ║īÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆńäĪķŖśŃĆĆÕÅżõĖƵ¢ćÕŁŚ’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ē õĖēÕÅĘŃĆĆŃĆĆÕłĆŃĆĆńäĪķŖśŃĆĆÕĘ”Õ╝śĶĪīŃĆĆ’╝łķćŹĶ”üÕłĆÕēŻ’╝ē ÕøøÕÅĘ […]
ķīåŃü│Ńü¤ÕłĆŃüīŃüŖµēŗÕģāŃü½ŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃĆīĶē»ŃüÅÕłćŃéīŃéŗµ¦śŃü½ŃĆŹŃĆīķīåŃéÆĶÉĮŃü©ŃüŚŃü¤ŃüäŃĆŹŃü©ŃĆüŃééŃüŚŃééŃüöĶć¬ÕłåŃü¦ńĀöńŻ©ŃéÆŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü¬õ║ŗŃüīŃüéŃéīŃü░ŃĆüŃüØŃü«õŠĪÕĆżŃéÆÕż¦ŃüŹŃüÅĶÉĮŃü©ŃüŚŃĆüÕŠīõĖ¢Ńü½õ╝ØŃüłŃéŗŃü╣ŃüŹÕłĆŃü«Õ»┐ÕæĮŃéÆńĖ«ŃéüŃü”ŃüŚŃüŠŃüåõ║ŗŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŗŃüŁŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ÕłĆÕēŻŃü«ńĀöńŻ©Ńü»ŃĆüµŻ¤Ńā╗ķļգ░Ńā╗Õ╣│Õ£░Ńā╗µ©¬µēŗŃā╗ķŗÆńŁēÕÉäµēĆŃü«ĶéēńĮ«ŃüŹŃéƵĢ┤ŃüłŃüżŃüżķīåŃéÆķÖżÕÄ╗ŃüŚÕłĆµ£¼µØźŃü«ŃüéŃéŗŃü╣ŃüŹÕ¦┐Ńü½ńĀöŃüÄõĖŖŃüÆŃĆüŃüĢŃéēŃü½Õ£░ÕłāŃü«ÕāŹŃüŹŃéÆÕ╝ĢÕć║ŃüŚµł¢ŃüäŃü»µŖæŃüłŃĆüķææĶ│×Ńü½ńøĖÕ┐£ŃüŚŃüäńŖȵģŗŃü½õ╗ĢõĖŖŃüÆŃü”ĶĪīŃüÅŃĆüńĘÅÕĘźń©ŗÕŹüµŚź’Į×õ║īÕŹüµŚźõ╗źõĖŖŃü½ÕÅŖŃüČõĮ£µźŁŃü¦ŃüÖŃĆéŃĆīÕłĆÕēŻńĀöńŻ©ŃĆŹŃü©Ńü»ŃĆüõ╗¢Ńü«Õłāńē®ķĪ×Ńü«ńĀöńŻ©Ńü©Ńü»Õģ©ŃüÅķüĢŃüåõĖ¢ńĢīŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃĆé