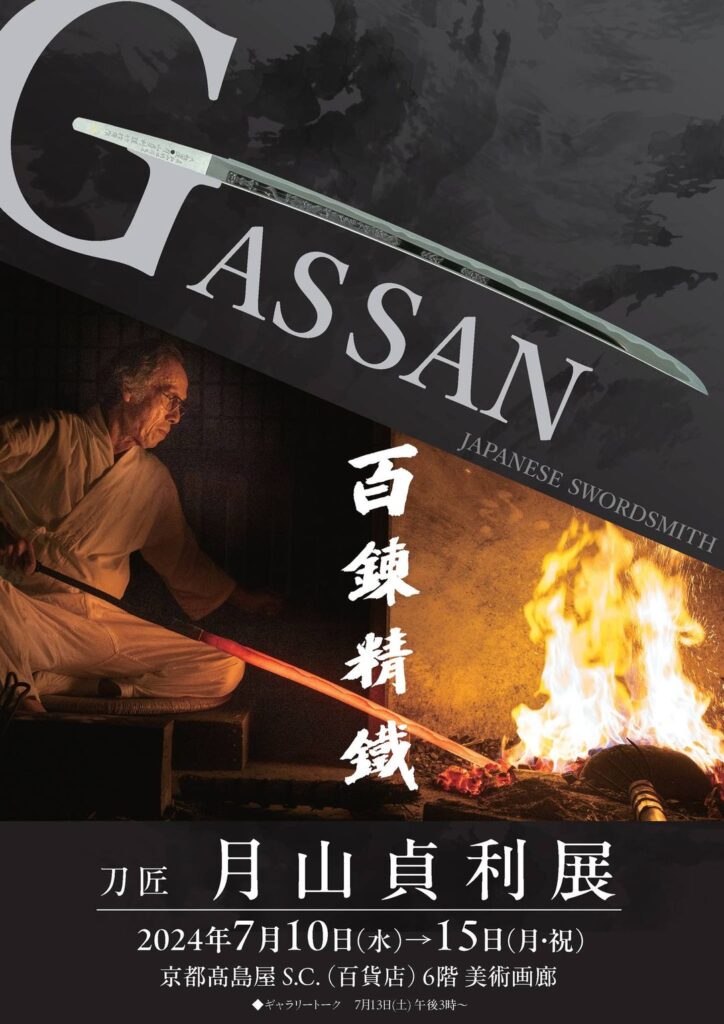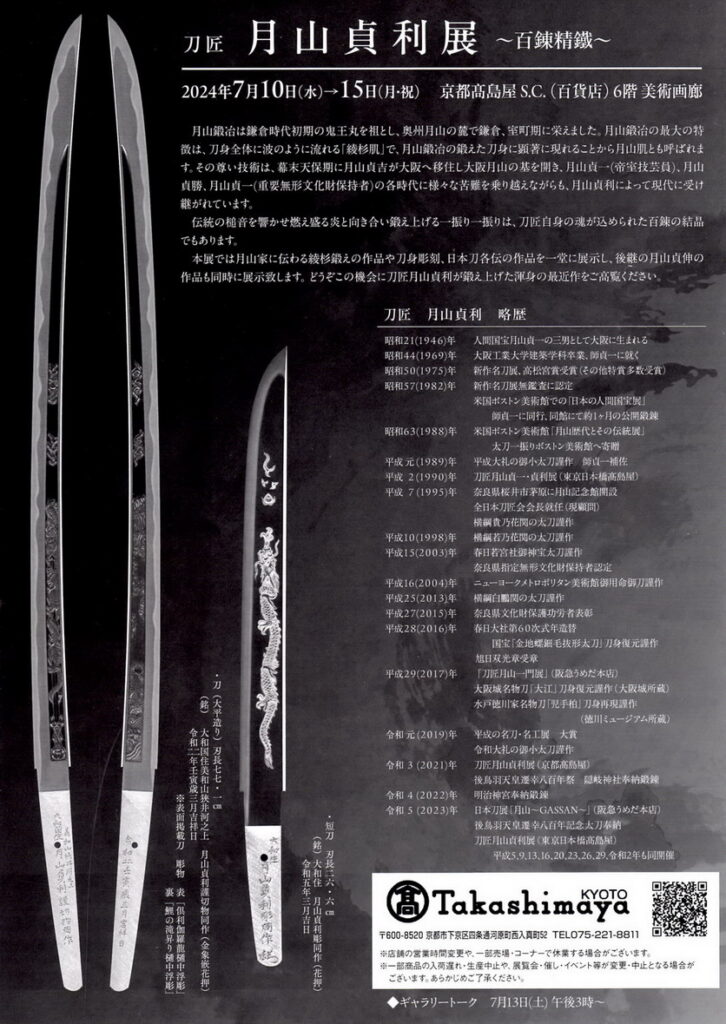肥前吉房研磨
新刀期、肥前刀の数は圧倒的ですが、その殆どは忠吉忠広、正広行広です。それに次ぐのが忠国や宗次などでしょうか。
過去に吉房を研磨した事はなく、手に取るのも初めてだと思います。
元は錆身。肥前の丁子で現在内曇り。
もう古刀ですね。軟らかいのに明るい、南北朝期以前の古刀の内曇りを引いている感覚です。
忠吉忠広は沢山研磨して来ましたが、こんな感覚を味わった事はありません。
吉房は忠吉忠広の作刀を支え生涯を終えたため自身作が少ない訳ですが、相当な腕利きです。肥前刀工の層の厚さを実感しました。