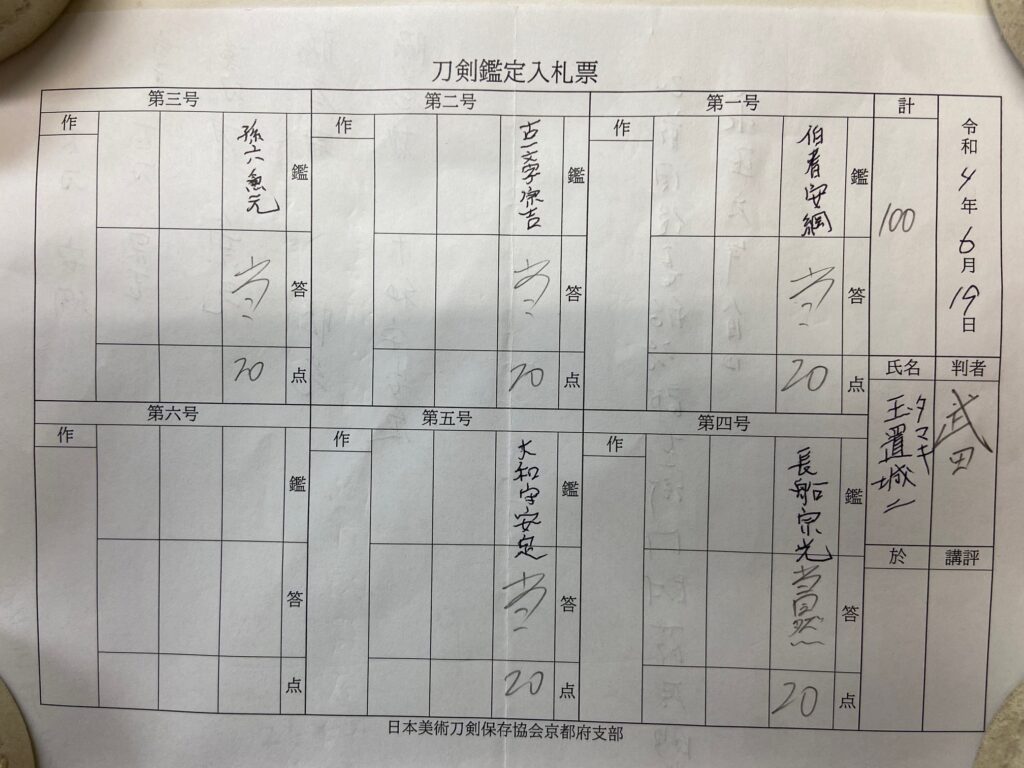刃艶を貼る
少し前に久々に刃艶を貼りました。いつ以来でしょうか。ちょっと不明で。
前回カットしていた中から必要な砥質3種を50枚程。前回のカットではどうやら6種程度をカットしていた模様。
それにしても、今回の貼り具合が過去30年間中最も悪い仕上がりに。
そういえばこの数年どんどん悪くなっていて、今回がその終着地かという悪さに。
私は屋外で貼る事が多く、悪さの原因は風や気温やと色々考えられます。ただ刃艶は砥質が最も重要であり、研磨初心者ならいざ知らず、それなりに経験があればその後の対応いかんで貼り具合は研ぎの仕上がりに影響を及ぼす事は無いのです。
”何を馬鹿な事を”とお思いの方、その通り。刃艶の貼り具合は使い易さに大きく影響しそして研磨の仕上がりにもある程度影響があるのです。
吉野紙の質や国産漆にとまでこだわった刃艶を頂戴し使わせて頂いた事が何度かあります。
その刃艶、漆の濃度(粘度)や厚さが絶妙で、しっかり貼れているのに吉野紙の繊維が程よく出て、刃取時の指との摩擦が強く、手の力を刀身へと全て伝えてくれます。結果その砥石の質をフルに発揮し、刃取り時間の短縮はもちろん、仕上がりの最終到達点にも影響がある勢いで。
この様な”こだわり”は職人には大切ですね。
”こだわり”は経験でカバー出来る事も多く自分の中でどうしても粛清対象になりがちなのですが、こだわりを持ち続ける事の大切さを最低な刃艶を使いながら再認識した次第です。