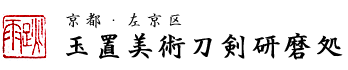研磨工程を ④
某日、細名倉(天然)を突く。
この”突く”と言う研ぎ方は、刀身に残る砥石痕でも分かる通り、棟の線と平行に成る様に体の左側に向い押して研ぐ方法です。
この時、左へ押す運動プラス上下の運動、所謂「しゃくり」も加えます。(改正砥の時書きませんでしたが、改正で筋交に突く時は、「左右+上下+前後」で、刀身の砥石痕は縄を並べた様な状態となります。)(改正は縄を並べた様な状態。中、細名倉は髪の束を並べた様な状態です)
しゃくる研ぎ方がいつ頃から行なわれていたのか私は知りませんが、ただ単に左に向かって水平に押すだけの研磨とは全く違う結果が現れます。
上手に書くのは私には無理ですし、簡単に書ききれる内容では有りませんのでそつなくまとめようとせずとりあえず書いてみます。
まず、しゃくるためには砥石が左右に丸くないとしゃくれません。 左右に平面ですとしゃくる度に左右の角が強く当り、砥石が欠け、刀身に強い止まり目が出来、刃先は刃こぼれする可能性大です。
と言う事で砥石は左右に丸みを付けます。
天然砥石は人造砥と比べると研磨力はかなり落ちます。 しかし昔はこの天然砥しかありませんでした。
伊予、備水、改正、中名倉、細名倉など、この研磨力の天然砥石を使い、最終的には内曇を引ききった状態(肉眼で見る限りでは砥石目が無い状態)に持って行こうとするのですから色々な当て方を考えたと思います。
その中で、”しゃくり”が生まれたのだと思います。
普通に押し引きするよりも、しゃくりを入れた方が砥石は断然効きます。
そして引き、押しでは砥目は手の動いた距離分しっかりと付きますが、しゃくると砥石と刀身が点で当り、砥目が格段に短くなります。 さらに左右の距離と上下の動きの高さで砥目の長さを調整できます。
この砥目の長さが短くなれば、次ぎの砥石に移行した時の研磨作業時間が短縮出来るのです。
ですので、しゃくり方を変えるだけで、同じ砥石でもかなりのバリエーションの砥石目を付ける事が出来るわけです。
改正の砥目を中名倉で取り、同じ中名倉で細名倉と同等の砥石目に持って行く様な事などです。
しかし、しゃくりにも大きな欠点が有ります。
例えば、出入りの激しい乱れ刃の場合、しゃくりを入れ過ぎると焼き刃の谷を凹ませてしまいます。
切れの良い人造砥石ですとこの凹みはなだらかですが、谷が狭く深い刃を天然砥石で数段階にわたり強くしゃくると大きく凹ませてしまう事になります。
私は京都で仕事をしていますから特にそう感じるだけかも知れませんが、寛文~元禄前後の大坂新刀や山城新刀の大互の目や涛乱で、天然砥を強くしゃくったせいで谷を大きく凹ませてしまった刀にかなり多く出会っています。その辺の刀は地刃の硬度差が特に大きいのか、ちょうど凹みやすい地刃の形なのか、刃が硬いのでとにかく強くしゃくった物が多いのか、色々理由はあるのでしょう。(もちろん時代を問わずその他全国のどの種類の刀でも研ぎのせいでかなり凹凸になってしまった刀は多数あります)
だらだら書いてますが大事な事を書き忘れていますので付け加えますが、刀の研磨では”研ぎ減らさない”と言う事も大変重要な事です。
ムラ無く研ぎ上げる事も大切ですが、あえてムラを残し極力研ぎ減りを避けつつ下地を進め、仕上げに持って行く事も有ります。
この時、天然・人造を問わず、砥石の前後左右の丸みが重要になります。
「しゃくりは凹ませる」的に書きましたが、凹んだ部分に大きな修正を避けつつ上手く当てるにはしゃくる必要が有りますので、研ぎ減らさない事としゃくる事の関係は深い訳です。(しかしこれは悪循環にもなりますので注意が必要ですね)
刀剣趣味の方はご存知だと思いますが、細名倉の次ぎは内曇砥に移ります。この内曇砥は、今までの”押し・突き”に変わって”引き”の研ぎになります。
因みに、中名倉や細名倉で”引き”をすると、その刀に有る一番大雑把な肌目だけが目立ってきます。
今回の平脇指、焼きは総体に低めで刃は湾れ主調の互の目。 谷はなだらかですし、互の目の谷は強く沸え付き焼き頭も締まっていません。
そして地刃の硬度差も低く、この刀ですと天然砥で強めにしゃくっても凹む心配はそれほどありません。