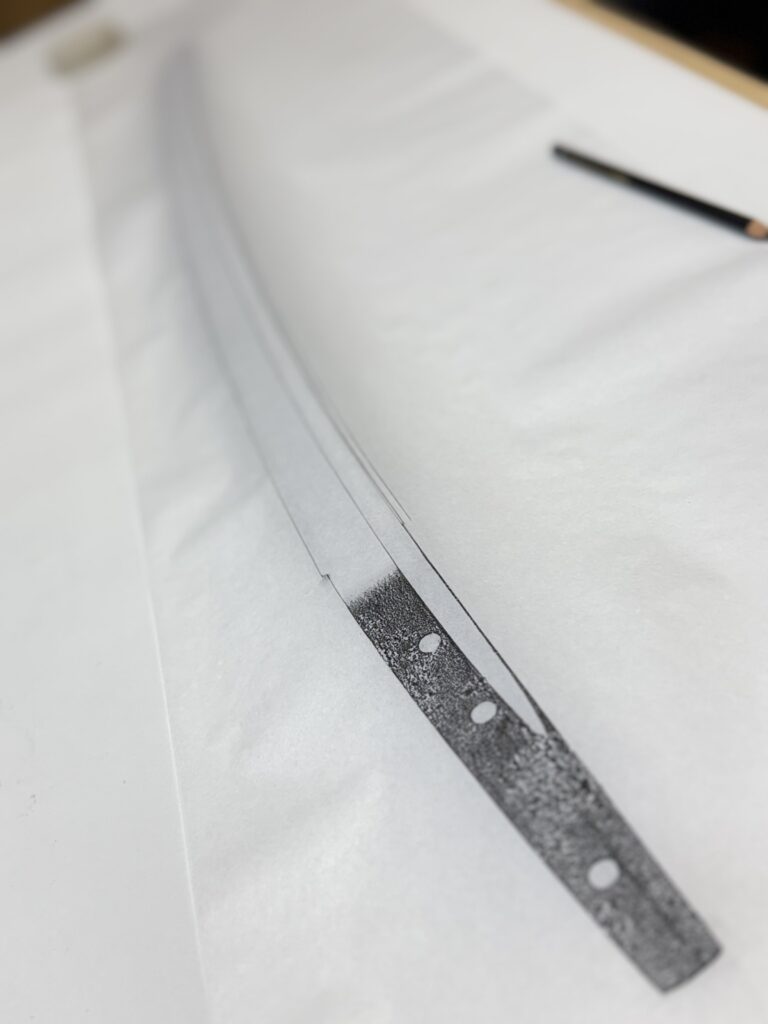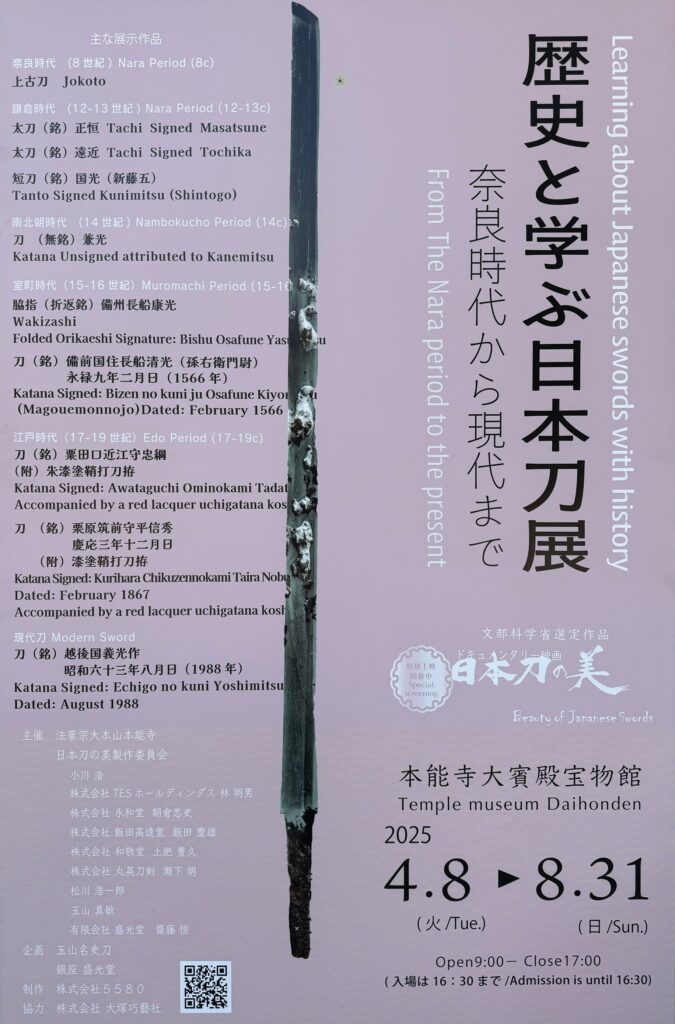本能寺大寶殿宝物館にて「歴史と学ぶ日本刀展」が始まりました。
上古刀から現代刀までの名刀が並びます。
刀装具では折紙付の名品や出土の倒卵形鐔も展示されています。
・上古刀 (奈良時代)
・太刀 銘 正恒(古備前) (鎌倉時代初期)
・太刀 銘 遠近 (鎌倉時代中期)
・短刀 銘 国光(新藤五) (鎌倉時代末期)
・刀 無銘 兼光 (南北朝時代)
・脇差 折返銘 備州長船康光 (室町時代初期)
・ 刀 銘 備前国住長船清光(孫右衛門尉)(室町時代末期)
永禄九年二月日(1566年)
・ 刀 銘 粟田口近江守忠綱(江戸時代中期)
(附)朱漆塗鞘打刀拵
・ 刀 銘 栗原筑前守平信秀(江戸時代末期)
慶応三年十二月日(1867年)
(附)漆塗鞘打刀拵
・ 刀 銘 越後国義光作 (現代)
昭和六十三年八月日(1988年)

また今回も新たに押形を多数展示して頂く事になりました。
以下押形展示リスト
・短刀 銘 定利(綾小路) (光山押形所載/鎌倉時代前期)
・短刀 朱銘 則国(粟田口)
本阿(花押) (鎌倉時代前期)
・短刀 銘 国吉(粟田口) (鎌倉時代中後期)
・短刀 銘 備州国分寺住人助国作
嘉暦二年正月日(1327年) (広島県重要文化財/鎌倉時代末期)
・短刀 銘 助弘(福岡一文字) (鎌倉時代末期)
・短刀 無銘 当麻 (鎌倉時代末期乃至南北朝時代)
・短刀 銘 備前国吉井吉則
応永二年三月日(1395年) (室町時代初期)
・短刀 銘 入鹿實次 (室町時代初期)
・短刀 銘 實可
入鹿 (室町時代前期)
・短刀 銘 信長 (浅古当麻) (室町時代前期)
・短刀 銘 入鹿住藤原實綱 (光山押形所載/室町時代中期)
・短刀 銘 月山貞一造(刻印)
明治三年季冬刳物同作 (1870年) (近代)
・短刀 銘 於東京高輪以獨逸鋼鉄 胤勝
明治三十六年五月(1903年) (近代)
・短刀 銘 元亨三年二月日 以余光鉄 備州長船住景光 鍋島景光ニ倣ㇷ源貞次
紀元二千六百一年八月日 彫同作(花押)(1941年)
(棟銘)為井内彦四郎氏作之 (現代)