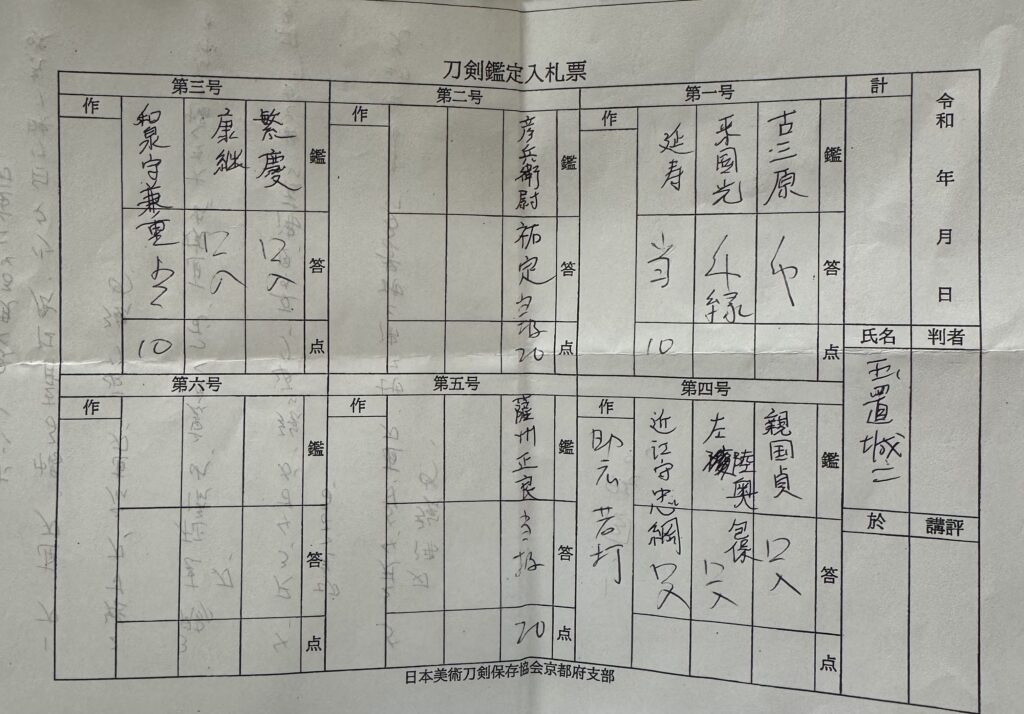延寿の帽子(1)
第67回頃までの延寿派重刀・特重指定品中(一部重文重美含む)、刀・太刀の帽子の調書。(無銘は伝含む)
無銘延寿
・焼き深く表は乱れごころ、裏は直ぐ調となり共に先小丸
・大丸ごころに返り浅い
・直ぐに大丸返り浅い
・直ぐに小丸先やや掃き掛け
・湾れ込み小丸・焼き詰め
・直ぐ調に小丸、先掃き掛けごころ
・直ぐに小丸
・焼きやや深く直ぐに先少し掃き掛け、大丸となり表焼き詰め、裏極短く返る
・直ぐに焼き詰め風
・直ぐに小丸やや長めに返る
・直ぐに大丸短く返り、先僅かに掃き掛け
・直ぐに先やや掃き掛けて丸く返る
・直ぐにやや掃き掛け、小さな食い違い風入り、先湯走りごころかかり、丸く極僅かに返る
・直ぐに先やや掃き掛けて、表は丸く返り、裏は小丸に返る
・直ぐにやや掃き掛けて丸く返る
・直ぐに表は丸、裏は小丸、共に掃き掛ける
・直ぐに小丸、先掃き掛け、やや長く返る
・表湾れこみごころに小丸、裏直ぐに丸
・直ぐに先小丸
・直ぐに丸く、先細かに掃き掛ける
・直ぐ調に先強く掃き掛け、大丸ごころにやや長く返る
・直ぐに丸く返り、先掃き掛ける
・直ぐに丸、表は尋常に返り、裏は浅く返る
・直ぐに小丸
・乱れ込先掃き掛けて僅かに返る
・直ぐに先小丸
・直ぐに小丸、先僅かに掃き掛ける
・直ぐに先小丸
・僅かに湾れ込、先小丸
・直ぐに先小丸、裏掃き掛け、二重刃となる
・直ぐに小丸、殆ど焼き詰めとなる
・直ぐに先大丸(押形では小丸になる)
・僅かに湾れ込、はきかけて表小丸、裏焼き詰め
・直ぐに小丸、僅かに返り掃き掛けごころがある。
・直ぐに小丸
・浅く湾れ先小丸
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸掃き掛けかかる
・直ぐに大丸
・直ぐに小丸、裏やや尖りごころとなり返りの下に小さく棟焼きかかる
・直ぐに丸く返る
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸掃き掛けかかる
・表直ぐに先たるんで小丸に返り、裏は直ぐに小丸
・直ぐに大丸ごころに先掃き掛ける
・直ぐに丸く返り、表先少しく掃き掛ける
・直ぐに大丸風に浅く返り先僅かに掃き掛ける
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸
・直ぐに先丸く、返りは極めて短い
・直ぐに小丸
・直ぐに大丸ごころ、返りやや寄り掃き掛ける(押形では小丸となる)
・直ぐに小丸、やや深く返り、先少しく掃き掛ける
・表は湾れごころに丸く返り、先沸え崩れて強く掃き掛け、裏直ぐに大丸に返り、掃き掛ける
・直ぐに大丸風、先僅かに掃き掛け、表は極めて浅く返る
・直ぐに小丸、僅かに掃き掛ける
・直ぐに丸く先細かに掃き掛ける
・直ぐに小丸に深く返り、裏先掃き掛ける
・僅かに立ち上がり、浅く湾れごころを帯、大丸風に浅く返る
・直ぐに大丸風に返り、先僅かに掃き掛ける
・直ぐに丸く浅く返り、二重刃風かかり、先掃き掛ける
・直ぐに小丸
・直ぐに大丸風に返り、先僅かに掃き掛ける
・直ぐに丸く返る
・直ぐに小丸
・大丸に先僅かに掃き掛けて返る
・直ぐに先丸く、極浅く返り掃き掛ける
・直ぐに丸く浅く返る
・先小丸に浅く返る
・直ぐに丸く返り先掃き掛け
・直ぐに丸く浅めに返り、先僅かに掃き掛け
・直ぐに小丸、裏大丸風
・直ぐに大丸、先少しく掃き掛け匂い口しまる
・直ぐに丸く、先掃き掛け
・僅かに乱れ、先小丸
・浅くたるんで大丸ごころに先僅かに掃き掛けて浅く返る
・浅く湾れ込、表は沸え崩れごころに裏は小丸に返り共に掃き掛ける
・直ぐに大丸風に先はきかけ、表浅めに返り、裏はやや深く返る
・直ぐに大丸ごころとなり、返り浅く、金筋入り、掃き掛ける
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸
・直ぐに細かに掃き掛けて焼き詰める
・直ぐに先掃き掛けて小丸に返る
・直ぐに小丸
・小丸に浅く返る
・表直ぐに丸、裏浅く湾れて小丸、共に僅かに掃き掛け
・直ぐに小丸
・食い違いごころあり、先丸く浅く返り、掃き掛けかかる
・浅く湾れごころに丸くやや浅く返り、先掃き掛け強く錵付く
・丸く浅く返る
・浅く湾れ込、先焼き詰めごころに僅かに返る
・直ぐに小丸、先掃き掛ける
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸
・直ぐに先丸く返る
・直ぐに小丸
・僅かに湾れ込小丸
・直ぐに先小丸尖りごころ
・直ぐに小丸、掃き掛ける
・直ぐに小丸
・直ぐに先掃き掛けて、丸く返る
・直ぐに丸く僅かに返る
・直ぐに小丸
在銘国村
・浅く湾れ込、表は二重刃風を見せ、共に先小丸に返る
・直ぐに先小丸
・直ぐに小丸に僅かに返る
額銘国村
・直ぐに大丸風にやや深く返り、先少しく掃き掛け
無銘国村
・直ぐ、先小さく掃き掛け大丸、短く返る
・直ぐに先大丸ごころに短く返る
・直ぐに先丸、やや掃き掛け
・やや湾れ込んで先小丸に短く返る
・直ぐに小丸
・湾れ込小丸、僅かに掃き掛け、裏二重刃かかる
・直ぐに大丸浅く返る
在銘国泰
・湾れ込先の丸み大きく返る
・直ぐに小丸
・浅く湾れ小丸
・表裏共二重刃がかり直ぐに丸く返る
無銘国泰
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸、掃き掛けかかる
・直ぐに表は焼き詰め、裏は丸く返る
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸
在銘国時
・直ぐに大丸風に浅く返る
・直ぐに小丸、表裏とも二重刃となる
・直ぐに小丸、僅かに尖りごころがある
・直ぐに小丸
・やや細く直ぐに小丸
・僅かに湾れごころに締まって先丸く返る
・表小さく乱れ、表直ぐ、共に先尖りごころに丸く浅く返り、掃き掛ける
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸、浅く返る
・少し立ち上がって表は浅く湾れ、裏は直ぐ、共に大丸風に返り、先僅かに掃き掛ける
・直ぐに小丸
・大丸に返る
・直ぐに小丸、返り短い
・大丸に土取りをし、掃き掛けかかり、裏は返り寄る
・やや弱く細く直ぐに小丸
・綺麗に小丸に返り締まり気味
・直ぐに小丸、表裏とも掃き掛けかかる
・盛んに掃きかけ火焔風
無銘国時
・直ぐ、先丸、二重刃状となり、表は尋常、裏は長く返る
・直ぐ、先丸風、長めに返る
・直ぐに先掃き掛け小丸に短く返る
・直ぐに大丸ごころ、先細かに少しく掃き掛け
・直ぐ、先小さく掃き掛け、大丸風
・浅く湾れて大丸風
・直ぐに小丸
・直ぐに丸くやや深く返り、表は食い違い刃、裏は二重刃風かかり、共に掃き掛け
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸
・直ぐに小丸風に僅かに返り、先掃き掛け
・直ぐに先小丸、僅かに返り、掃き掛けごころ
・先丸く返り僅かに掃き掛け
・表、小丸、裏中丸共に浅く返る
・直ぐに先小丸
・直ぐに小丸
在銘国資
・大丸ごころに返り浅い
・表は浅く湾れ、裏は直ぐ、共に焼き詰めて先盛んに掃きかけ、沸え強く付く
・直ぐに小丸
・直ぐに立ち、僅かに湾れて先小丸に浅く返る
無銘国資
・直ぐに盛んに掃き掛け、沸え強く付き、先小丸風に返る
・殆ど直ぐに焼き詰め
・直ぐに小丸、先僅かに掃き掛け、二重刃ごころがある
・直ぐに小丸、掃き掛けかかる
在銘国吉
・表僅かに乱れて先小丸、裏殆ど焼き詰めごころ
・直ぐに小丸
・湾れ込み小丸
・直ぐに小丸
・直ぐに先丸く、僅かに返る
・表直ぐに大丸風に僅かに返り、裏直ぐに焼き詰める
・小丸
・直ぐに丸く返り二重刃かかる
・直ぐに先小丸
無銘国吉
・直ぐに小丸、二重刃風かかり、先掃き掛ける
・直ぐ、先尖りごころに小丸、長めに返り、湯走りかかる
・直ぐに小丸
・直ぐに先丸く返る
・大丸ごころに先僅かにはきかけ、返り短い
在銘国信
・直ぐに表焼き詰め風、裏大丸風に浅く返る
・直ぐに焼き詰める
・直ぐに大丸
・直ぐに表大丸ごころに返り、裏は焼き詰め風
・表裏焼き深く直ぐにやや大丸気味に浅く返る
・極浅く湾れて小丸
無銘国信
・直ぐ調に焼き詰め、裏先小さく掃き掛ける
・浅く湾れて先尖り、強く沸え付き裏沸え崩れ、共に頻りに掃き掛け裏火焔となり二重刃かかる