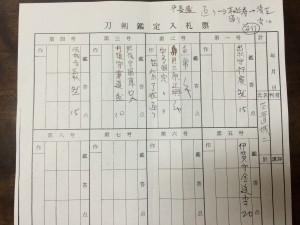京都支部例会 刀剣入札鑑定会
例会
一号 刀
肥前です。正広か行広。この二人の違いは分からない。
出羽守行広と入札。
二号 刀
反り浅。中切っ先。棒樋。少し鎬高め。直刃。少しほつれなど。
肌は少々粗め。映り気。帽子の先が眠くなり形判別不明(おそらく少し大きい)。
この手の出来は私の眼力では選択肢が多過ぎて非常に難しい。
おそらく大磨上無銘だが、もしかしたら茎尻に銘があるかも知れない。
兼常と入札。
三号 脇差(鎬造り)
少し反り、尋常な造りこみ。拳丁子だが中河内とは違うタイプの華やかさが有る。
この人では無いと思うが他の選択を見つけられず。
肥後守国康と入札。
四号 脇差(鎬造り)
反りが大変浅い。物打付近の刃線が特に直線的。直刃調の互の目。
法城寺正弘と入札。
五号 脇差(鎬造り)
直にかなり長く焼き出し、美濃風の互の目。三品帽子。
伊賀守金道と入札。
然
イヤ
国入り
然
当
多分二号は全部外す予感がする。
とりあえず選択肢をつぶして行く。
二号 貝三原正興と入札。
三号は消去法で残った丹後守兼道に入札。
然
イヤ
然
然
当
二号 宇多国宗と入札。
然
イヤ
然
然
当
二号は三札とも外しましたが、当たるまで入れてよいと言う事で、続ける。
筑紫了戒(通り)→平長盛(通り)→末延寿(通り)→清左(当)
一号 刀 銘 肥前國佐賀住正広 寛永十五年八月吉日
二号 刀 折り返し銘 波平行安
三号 脇差 銘 大和守吉道
四号 脇差 銘 但馬守法城寺橘貞國
五号 脇差 銘 大法師法橋来金道 万治元年十二月吉日
鑑賞刀として、京都府支部在籍の北川正忠刀匠、平成二十七年新作名刀展、優秀賞第一席入賞作品を拝見しました。
太刀 銘 北川正忠作之
刃長 二尺四寸一分 反り 約九分