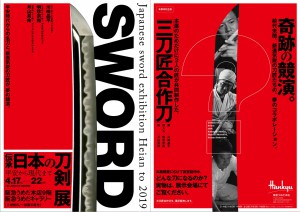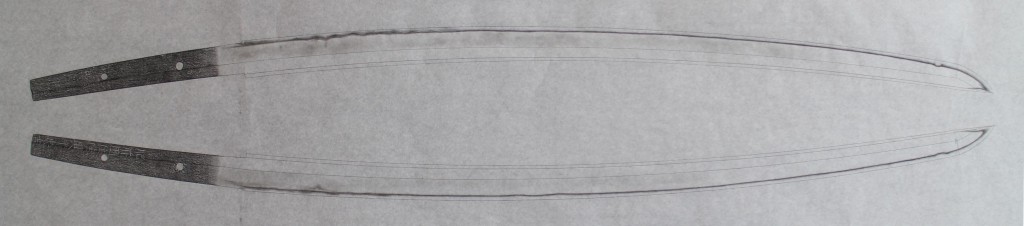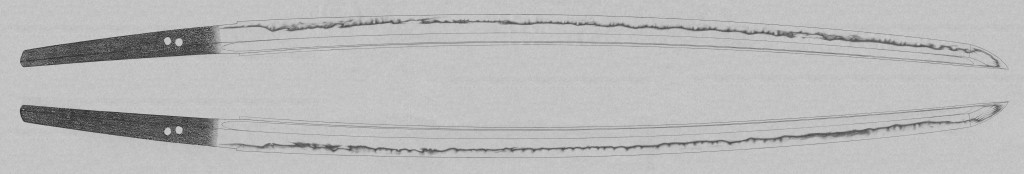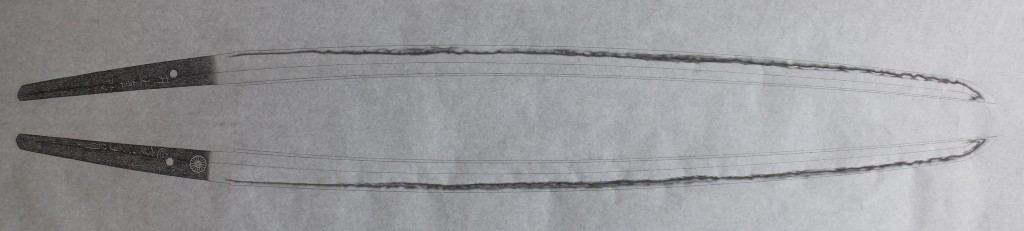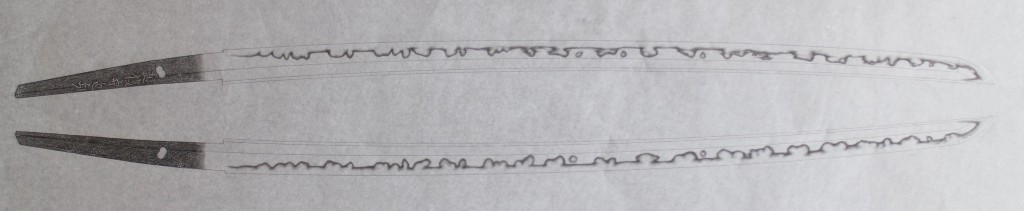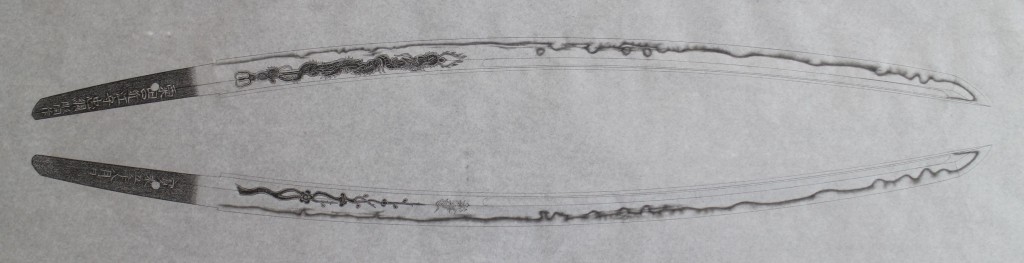続き
歳を取ったせいか、田舎の事をもう少し知りたくなり、十津川郷採訪録(全五巻)という本を買ってみました。
私の郷里十津川村は”秘境”と呼ばれる事があります。
現代では秘境といえば聞こえは良いですが、生活する人にとっては不便極まりない僻地です。
しかし外に出た人間としては、ずっと秘境であって欲しい気持ちもある訳ですが。。
十津川郷が長い間秘境として存在した一番の原因は道路事情の悪さです。
「十津川街道」によると、十津川郷の南端まで道路が開通したのは昭和34年だそうです。
電気が来たのは昭和20年代の中頃。
「十津川街道」の中で、私の実家の隣の人が、電気が来る以前の生活の事を「それまでは江戸時代の暮らしじゃぁ」と言っていますが、大袈裟ではなく本当にそれに近い暮らしだったのだと思います。
私も母から電気が来た日の事を聞いた事がありますが、本当に嬉しい出来事だったそうで。
今でも度々秘境として紹介される事のある村ですが、現在では道路事情がよくなり、十津川村の秘境度はかなり下がっています。
しかし道路が通る以前、昭和20年代までの十津川村の秘境度合いは、現代からは想像が出来ない、本当の秘境であったはずです。
母は小学一年から、朝家を出る前に藁でワラジを2枚編み、1枚を履き、1枚は帰りのために持って行ったそうです。
食料は「高山幽谷、僻遠多くは不毛の地にて食に乏しく土民ども雑穀木の実をくらい・・・」の通り、主食は雑穀。サツマイモは御馳走の部類。
「”瓜根のキゴ”(黄烏瓜の根から採るデンプン)を、えずきながら食べた」という話をよく聞かされました。
そんな親ですので、私も小学2、3年の頃、コマ回しの紐をなくし、買って欲しいと母に頼んだのですが、「自分で綯(な)いなさい」といわれ細い麻紐を綯ってコマ紐を作ったのを覚えています(私もワラジの作り方は教わっていて、遊びでビニールの荷造り紐を綯ってワラジを作って履いたりしていました)。
でもねぇ、硬い麻紐じゃぁコマは上手く回らんのですよ。。