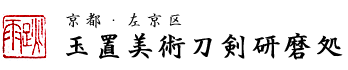大太刀、無銘 伝金房(本能寺蔵)
21回目。
室町時代の大和物に金房一派があります。
この派の詳細は不明ですが、手掻系といわれています。
作風に大和色は薄く、末備前や末関、平高田などに似る作を多く見ます。
この太刀は刃長三尺四寸六分と長大です(茎先を切断しています)が、重刀指定の金房の作に類似の品が数点あり、種別はいずれも薙刀です。
本太刀も種別を薙刀にと思いましたが少し気になり、大太刀を多数所蔵する日光二荒山神社の「二荒山神社男体山頂鎮座1230年記念 宝物館開館50周年記念 宝刀譜」(平成24年)を確認をしました。
宝刀譜にはこの太刀と同形状の物を多数所収(寸はもっと長大な物が多い)、それらは全て大太刀と記され、また小川盛弘先生の解説に「長巻の柄が付けられた大太刀」との一文があり、やはり本刀は大太刀とすべきかと思います。【長刀(なががたな)とする場合もあるようです】
長巻の名称が出て来ましたので、薙刀と長巻について少し。
「長巻直し」「薙刀直し」という名称がありますが、 愛刀家の間ではこの区分が曖昧で、協会でも数十年前までは用語が統一されていなかったようです。
重要刀剣指定品には、薙刀形状の造り込で茎を切り詰めて刀に直した物が多数あります(横手の有るものと無い物両方を含みます)。
第1回指定品~60回辺りまでを確認したところ、第26回頃までは、同じ形状でも、「長巻直し」と「薙刀直し」の名称が混在していました。しかしその頃を境に「長巻直し」の名称は消え、全て「薙刀直し」に統一されています。
過去、刀剣美術誌上で、長巻と薙刀の違いについての論考が発表された事もありましたが、結論を明確にはしていませんでした(1987年刀剣美術誌第368号、「長巻と薙刀の相違点」辻本直男)。
しかし二荒山神社の宝刀譜では小川盛弘先生が「長巻=拵え名称」との見解を示されている通り、現在ではその様に考えられています。
また最近では京都国立博物館で開催された「京のかたな展」図録巻尾の用語集にも以下の通り記されています。(この用語集は単に過去用語の使いまわしはせず、今回の図録用に検討し収録されています)
【薙刀(なぎなた)】長柄武器の一つ。長大な棒状の柄(え)に刀身の茎を差し込んで固定する。長巻との分別は刀身部の形状ではなく、拵えによる。
【長巻(ながまき)】長柄武器の一つ。片刃で、長大な柄(つか)に刀身の茎を差し込んで固定する。薙刀との違いは刀身部の形状ではなく、拵えによる。
最後に、余計ややこしくなるかも知れませんが、一応書きますと。。
・薙刀状の刀身は横手の有無に関係なく全て「薙刀」。
・薙刀を刀に直した物は横手の有無等関係なく全て薙刀直し(「長巻直し」との言葉は現在は使用しない)
・薙刀拵入り薙刀は刀身と拵を合わせて「薙刀」。
・長巻拵入り薙刀は刀身のみをいう場合「薙刀」、拵は「長巻(長巻拵)」。
・長巻(長巻拵)に刀身(薙刀及び大太刀或いは長刀(なががたな))が入ったものは刀身と拵を合わせて「長巻」。
※長巻拵えとは、長い柄を細縄や革で巻いたもの。
※刀身は通常の刀形状で、茎が薙刀の様に長い造り込みの物を現在協会では長刀(なががたな)と呼称しています。
本能寺